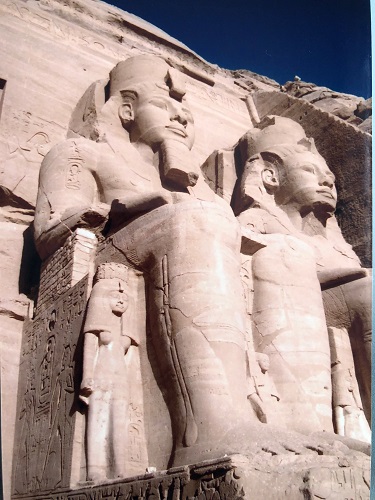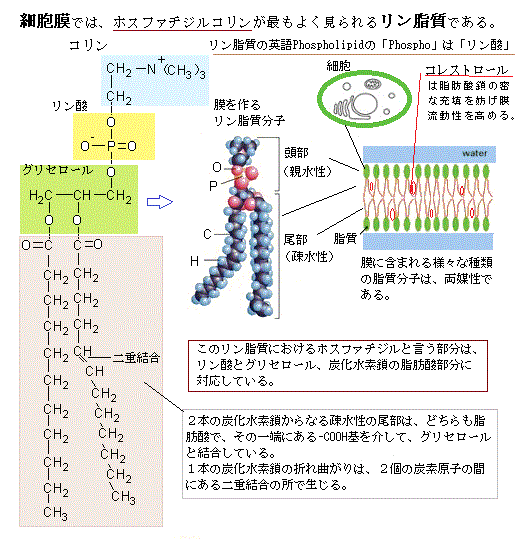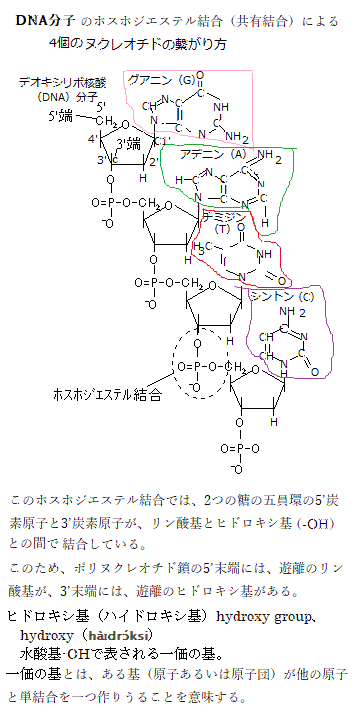| デモクリトスの原子論 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DNA DNAが遺伝物質 生物進化と光合成 葉緑素とATP 植物の葉の機能 植物の色素 葉緑体と光合成 花粉の形成と受精 ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応 植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1) 遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝 減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学 イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸 生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物 陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応 根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖 フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学 ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン 元素の周期表 デモクリトスの原子論 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1)時代背景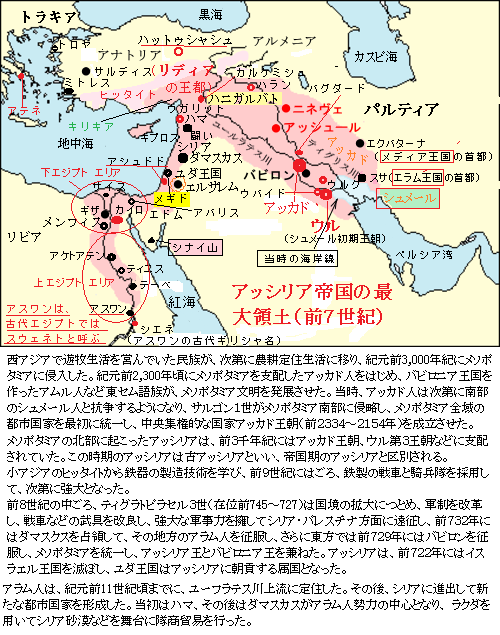 現代の私たちが知る限りにおいて、最初に体系化された物理学は、アリストテレスにより極めて良質に創始された。『物理』と言う学問分野の名称自体が、アリストテレスの著作のタイトルに由来する。 現代の私たちが知る限りにおいて、最初に体系化された物理学は、アリストテレスにより極めて良質に創始された。『物理』と言う学問分野の名称自体が、アリストテレスの著作のタイトルに由来する。アリストテレスは17歳の時、プラトンが作った哲学学園アカデメイアに入学した。その時、プラトンは63歳、その弟子になる。その類稀なる才能は卓越し、「学校の精神」と評された。 アリストテレスの物理学は、流体の中の物体や、重力と摩擦を受けている物体の運動を、適切かつ正確に描写している。 「なによりもまず、大地と空を区別しなければならない。空では、すべてが水晶のような物質からできており、それらが周期的かつ永続的に大地の周りを回っている。大地は、同一の中心を共有する球体の中心に位置し、大地もまた球形である。 地上では、力による運動と自然運動を区別しなければならない。力による運動は圧力(押す力)に由来し、その圧力が尽きた時に運動は止まる。自然運動は鉛直方向に発生する。上と下のどちらに動くかは物質ごとに異なる。あらゆる物質は、自身にとっての『自然な場所』、つまり、常にそこに戻ってくる水平面を持っている。 土は一番低い所に、水は土の上に、空気は水の上に、火は空気の上に、それぞれ『自然な場所』を持っている。石を持ち上げ、そのあと手を離したら、石は自然運動によって下に向かって落ちていく。これは、石が自分の水平方向へ戻ろうとした結果である。一方で、水中の気泡や空気中の炎は、やはり自然な場所を目指して上に向かって昇っていく」 古代地中海世界では、地中海が重要な交通要路であったため、地中海の沿岸部は発達したが、内陸部は山間部が殆どで、しかも地中海性気候に属すので、夏は暑く乾燥し、冬は少雨で、その上、大河や肥沃の平野がなく、河川による水運や陸上交通は発達しなかった。
アラム人は、フェニキア人やヘブライ人と並ぶ、セム語族の民族で、BC1200年頃から西アジアのシリアのあたりに定住し、内陸部の陸上交易に活躍した。彼らの使用したアラム語と、彼らが造りだしたアラム文字は、ユーラシア大陸の内部にまで交易活動とともに伝えられ、広がっていった。 ダマスクスはアラム人が建設した都市である。BC11世紀ころ、アラム人はユーフラテス川およびハブル川流域(トルコ南東部の丘陵地帯からシリア領内に入りユーフラテス川に注ぐ大きな支流)を占拠していくつもの王国を作った。その後、シリアにも進出して都市国家を建設した。当初はハマ、やがてダマスカスがアラム人の本拠となった。彼らは統一国家を作ることなく、都市内外での交易活動に専念し、シリア砂漠などを舞台にしたラクダによる隊商貿易で活躍した。さらに交易網を拡大し、古代オリエント世界に商業語としての古代アラム語を定着させた。やがて、その勢力は、アッシリア帝国の西漸を妨げる最大の障害となった。 紀元前6世紀、人類史上、極めて重大な思想上の革命が、ミレトスMiletusで成し遂げられた。エーゲ海をはさんだギリシア本土の対岸、アナトリア半島西海岸(今のトルコのアイドゥン県バラト近郊)のメンデレス川河口付近にあったギリシア人の植民都市である。青銅器時代から人が住んでいた。タレスなどミレトス学派を生んだことで有名である。 青銅器時代の定義は、地域によって違いはあるが、もともと利器の材質に基づいた命名である。石器時代の後の、鉄器時代に先行した時代、つまり鉄の冶金術がまだ知られていない、青銅で鋳造された時代である。 青銅器時代とは、本来、青銅製の利器その他の器具の製造、使用が行われた時期を言う。主要な利器その他の利器とは、鋭い兵器や武具、実用の鋭利な刃物などのことである。器具一般ではない。祭祀具・副葬品・宝器・儀器などのように宗教上の目的から、また権威の象徴として青銅の利器が作られていても、例えば、クレタ島のミノス文化の双頭斧double-axeは、青銅製の祭祀具として有名であるが、それは青銅器時代と呼ぶ指標にはならない。日本の弥生時代の平形銅剣や広鋒銅鉾(ひろさきどうほこ)なども典型的な儀器であって、これらに基づいてミノス文化時代同様、弥生時代を青銅器時代とは呼ばない。 文明の利器の最たるもの兵器や武具と、器具・装身具などの製作に青銅が基本的な材料として用いられた時代、人類史では、都市と都市国家や政府組織の成立、畜力を利用した車の出現、文字の発明と国際交易・市場経済の定着がみられる時代であり、未開から文明への画期的な変換点あった時代とみられる。 青銅は、銅90%とスズ10%を基準とする合金である。スズの主要鉱石である錫石(すずいし)の産地は限定されているうえに、この鉱石を溶錬してスズを分離、採取することには、かなりの技術を要する。一方、銅は自然銅の形で発見されるから、当初は銅が利器や装身具に用いられた。スズが産出しないか、あるいは入手困難な地域では利器などにはもっぱら銅が用いられた。 今日なお青銅器時代の意義が高く評価されるのは、先史文化を考える分類体系として、画期的な特異性が認められるからである。BC3,000年からBC2,000年ごろメソポタミアに始まり、インドではインダス文明期以降、中国では、殷・周の時代である。日本では、弥生時代に大陸から青銅器と鉄器が同時にもたらされたため、この時代は設定されていない。エジプトなどの地域では、銅製品は出現するが、錫の入手が困難なため青銅器時代に入れなかった。 古代の西アジアや中国では、鉄使用の初期の頃、隕鉄(いんてつ)を利用した。隕石である隕鉄が、そこかしこ大量に散らばっていたわけではないため、入手しやすい膨大な埋蔵量を誇る鉄鉱石(酸化鉄)が利用可能になるまで、長い間、鉄製品は得難い貴重品であった。 イラク、ウル出土の短剣は10.9%がニッケルの隕鉄でBC2,500年頃のもの、トルコのアナトリア高原、アラジャヒュユクの遺跡から発掘された剣は、BC2,300年頃のもの、柄と鞘が黄金、刀身が鉄製だった。シリアのラス・シャムラの神殿から発見されたBC1,500年頃の鉄斧は、2.25%のニッケルを含む隕鉄だという。その現代のラス・シャムラにあった古代都市国家ウガリットは、フェニキア人が築いた都市国家で地中海を臨む高台にあった。西アジアと地中海世界との接点となる国際的な港湾都市として発展し、BC1,450年頃~BC 1,200年頃にかけて全盛期を迎えた。ここの遺跡から発見された粘土板の文書には、アルファベットの原型となったウガリット文字が使われている。 都市国家ウガリットはBC1200年ごろ、「海の民」の侵攻を受けて滅亡し、その後廃墟となった。「海の民」は、東地中海上で活動した系統不明の民族で、その軍事力の大きさや内容も解明されないままであるが、この時代、アナトリアのヒッタイトやミケーネ文明を衰退に追いこみ、エジプト新王国にも侵入するなど、一時期、西アジアに壊滅的な打撃を与えた。 ヒッタイト王ハットゥシリ1世は、BC1,680年、ハットゥシャシュ(現在のボガズキョイ,アナトリア高原のほぼ中央部にある)を首都として王国を建設した。BC1,595年頃、ムルシリ1世率いるヒッタイト古王国が、バビロン第1王朝期最後のサムス・ディタナ率いる古バビロニアを滅ぼし、メソポタミアにカッシート王朝を成立させた。ヒッタイトは、青銅器が主流の時代に、最初の鉄器文化を築いたとされる。高度な製鉄技術は、強靭な鉄製兵備を充実させ、遂には、メソポタミアまでも征服した。そのヒッタイトの滅亡により、独占していた鉄器製造技術が、西アジアから東地中海一帯へ拡散され、青銅器時代から鉄器時代へと移行したと見られている。 「海の民」は、北方のギリシア人の諸王国を襲い、その後、エーゲ海を渡りキプロスからアナトリアのヒッタイトの海沿いの重要な拠点を次々に攻め落とし、シリアやパレスチナへ、その一方、リビア方面からエジプト新王国を侵掠した。 「海の民」は、凌辱略奪し、火を放って破壊するが、侵入地を支配搾取することなく、夥しい残虐と破壊の跡を残して去っていた。 鉄とニッケルの合金からなる隕鉄を鍛造した鉄製の利器は、小アジアやエジプト、メソポタミアで広く作られていた。中国の中原でも、BC14 世紀頃の鉄製兵器 で、商代中期、北京市平谷県劉家溝墓より出土した隕鉄製鉄刃銅鉞(てつじんどうえつ)がある。しかし、隕石の数が限られていたため、隕鉄の製品は普及しなかった。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
2)ミレトス学派
現代のミレトスは海に接していないが、これはメンデレス川の堆積によって湾が埋まってしまったためであり、古代においては港湾都市であった。 タレス(BC624年頃~546年)は、イオニア地方のミレトスからほど近いサモス島の生まれだが、ソクラテスの孫弟子に当たるディオゲネス(BC412年~BC323年)によれば、およそ現在のレバノンの領域、フェニキア人(ギリシア人は、東方オリエントから主に通商を目的として西方に来た人々を「フェニキア人」と呼んだ)の名門テリダイの家系と言う。西洋哲学史において、古代ギリシア時代の記録として残る最古の自然哲学者であり、イオニアに発したミレトス学派の始祖と見られている。また、ギリシア七賢人の一人とされる。BC5世紀のギリシア・アテネの歴史家ヘロドトス(生没年不詳)によれば、その知識を用いて日食を予言したといわれている。これは天文学上の計算からBC585年5月28日の日食と考えられている。また地に落ちた影と自分の身長とを比較して、ピラミッドの高さを測定したとも伝えられている。 彼の活動したイオニアは小アジアのエーゲ海沿岸に位置する。ホメロスの口承詩『イーリアス』と『オデュッセイア』は、主にイオニア方言で語られている。イオニアは地理的に東方と西方文化が交流する十字路であるため、ギリシアはもとより、エジプトやバビロンから数学や自然科学などの先端的知識が集積していた。そうした文化的基盤がタレス・アナクシマンドロス・アナクシメネスなどミレトス学派を台頭させた。 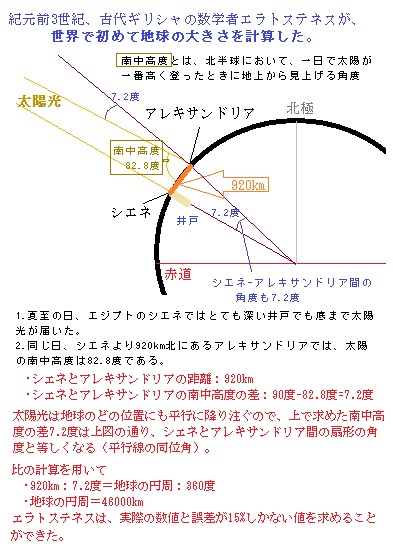 紀元前6世紀初めのミレトスで、タレスとその弟子、アナクシマンドロス・ヘカタイオス・アナクシメネスと彼らが形成する学派のメンバー達によって、 紀元前6世紀初めのミレトスで、タレスとその弟子、アナクシマンドロス・ヘカタイオス・アナクシメネスと彼らが形成する学派のメンバー達によって、「神話や精霊を引き合いに出すことなく、事物の性質それ自体の中で答えを探求する」、 「とりわけ、批判的な思考を正しく用いる。それにより自らの視点を絶えず修正する」、 「師の思索に立脚しながらも、弟子は時にそれを否定し、批判し、より優れていると思えるものを生む哲学的思考や科学的思考が目覚ましい発展には不可欠である」と、 ミレトスの人々がそのことの重要性に気付き尊重した。以来、人間の知識の幅は目覚ましい勢いで広がり、更に深まった。 ヘカタイオス(BC550?~BC475?)はミレトス出身、ギリシア最古の歴史家で最古の散文家である。更に 政治家としてイオニア植民市の反乱にも関与した。広く旅行し、地図も含む世界地誌『世界周遊』と歴史的著作『系譜』を著し、ヘロドトスの先駆者として大きな影響を及ぼした。 「ヘカタイオスの世界地図」は、ヘロドトスによれば、その地図は青銅板に彫られており、ペルシア人の支配に抵抗してイオニアのギリシア人植民市が反乱した(BC499~BC494)際に、ミレトスのアリスタゴラスによりスパルタへ運ばれたと言う。 その青銅板からヘカタイオスは、バビロニア人と同じく、「世界は平たい円盤状をなす」ものと考えていたと見られている。OCEANOS(オケアノス)と書く海洋に囲まれ、北が上となり地中海によって、上部のEUROPA(エオローバ)と、下部のASIA(アジア)に別れ、東の端にインドがある。アフリカもトルコも中近東もASIAに含まれている。 アリストテレス(BC384‐322)は地球球体説を主張する。根拠は、「地上のあらゆるものは圧縮・集中によって球を形成するまで中心に向かおうとする傾向を持つ」、「南へ向かう旅行家は、南方の星座が地平線より上に上るのが分かる」、「月食時に月面に影が差す大地は円い」などの観察結果からである。更にアリストテレスに由来する知識として、ヨーロッパ人たちの住む世界は、赤道を挟む熱帯の北側にある温帯で、灼熱の熱帯と極寒の寒帯は無人境である。地球は球形であり、熱帯と南北の温帯と寒帯という5つの領域を持ち、南半球には未知の大陸が存在すると認識していた。 古代ギリシアの数学者、特に数学と天文学の分野で後世に残る大きな業績を残したエラトステネスEratosthenes(BC 275年‐194年)が、地球の大きさを測定し、現在では地球の円周は約4万km、その1割超ほど過大な44500~46250kmkmと、古代としては驚くほど正確な結果を算出した。ただし、その測定値は出典ごとに違い1,500k超ほどの差がある。 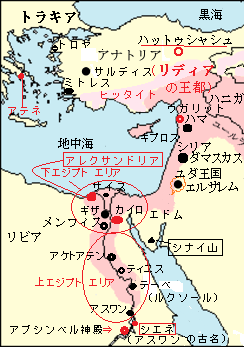 エラトステネスは、シエネ(現在のアスワン)とアレクサンドリアとの太陽の南中高度の違いから地球の全周長を求めた。当時、シエネはアレクサンドリアの真南にあたるナイル川上流にあると見られていた。しかも、アレクサンドリアとシエネの距離は、隊商が掛かる日数から算出されているため、精度は高くないはずが、その計算
結果は称賛に値する。 エラトステネスは、シエネ(現在のアスワン)とアレクサンドリアとの太陽の南中高度の違いから地球の全周長を求めた。当時、シエネはアレクサンドリアの真南にあたるナイル川上流にあると見られていた。しかも、アレクサンドリアとシエネの距離は、隊商が掛かる日数から算出されているため、精度は高くないはずが、その計算
結果は称賛に値する。(アスワンは、古代エジプトでは南の辺境の町、スウェネトSwenetと呼ばれた。スウェネトとは古代エジプトの言語で「交易」を意味する。シエネは、古代ギリシアの呼び方 ) ヘカタイオスの歴史書は、批判的な思考が核心を鋭く衝く文章からから始まる。「私はここに、自分にとって正しいと思えることを書いていく、と言うのも、ギリシア人の物語は、矛盾や当てにならない記述に満ちているように思えるから」。 伝説によれば、ヘラクレスはギリシアのマタパン岬(岬の先端にはギリシア神話でハーデースの住居とされる洞窟があり、洞窟の上の丘にはポセイドンを祭った神殿跡がある)から冥界に下ったと言う。ヘカタイオスは、マタパン岬を訪れたが、そこのどこにも地下通路や冥界の入り口は存在しないと確認した。その伝説は虚偽であったようだ。 アナクシマンドロス(B.C.610〜B.C.540頃)は、ほんの数年で世界に対する認識を深め構想を広げて見せた。地球は空に浮いており、地球の下側にも空が広がっている。雨水は大地から蒸発した水に由来する。地上に存在する物質の多様性は、唯一単純な構成成分の発現と理解できる。 アナクシマンドロスは、万物のアルケーarkhē(始源)は、タレスは「水」と断定したのに対して、「アペイロンapeiron(限定されないもの)だと言った。 タレスの「万物は水から生じている」という説では、 「そもそも火はどのようにして生まれたのか」 という問いには窮する。これは、「水」は限定的な物質であるため、“冷たい”や“湿っている”といった自然現象はうまく説明できても、それらに「相反」する“熱い”や“乾いている”といった現象はうまく説明できない。そうした制約を乗り越えるためには、アルケーは無限定な性質のものであるほうが望ましいので、アナクシマンドロスは、「アペイロン」を想定し、その「アペイロン」から様々な相反する性質が分かれ出て、多様な存在が生み出されると考えたのである。 アナクシマンドロスは、動物や植物は、環境の変化に対応するように進化する。人間は他の動物が進化した末に生まれたに違いない。アナクシマンドロスの構想には、現代人が共有する「世界を理解するための基本原理」、『進化と淘汰による自然選択』を論拠にしていた。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
3)ギニシアの都市国家
なお、ドーリア人は西北系方言のギリシア人であるのに対して、東方系のイオニア人が集住して成立したアテネは、他のポリスと同様、当初は王政であったが、ポリスの市民の中から騎士階層が育ち貴族となり、次第に王に代わりアルコン(執政官)として統治するという貴族政治に移行していった。 アテネの貴族は、ポリスの構成員の中で土地などの豊かな財産をもち、武具・馬具を常備する騎士としてポリスの領土拡大や防衛の主力戦力となった人々である。代表的なポリスであるアテネは、スパルタなどのドーリア人の攻撃と戦いながら、ポリスを形成する過程で、BC8世紀ごろまでに貴族が政権を独占するようになった。 BC683年には、貴族の中から選ばれた定員9人のアルコンArchon(執政官;ギリシア語で「統治者」)が、任期1年で、行政・軍事・祭祀・法律の制定などの権限を行使する貴族政治の最高権力機関となった。王権の中の国政の執行権が分与されたことを淵源とする。これがアテネの貴族の合議制による共和政体である。 筆頭アルコンはアルコン・エポニュオスArchon Eponyuosuと言われ、英語では「eponymous(əˈpɒnəməs;名祖の)」、つまり筆頭アルコンの名を「名祖(なおや)」として、その年を表記する。西暦の1年の途中からの1年任期なので、アテナイの歴史ではたとえば「ニコデモスのアルコンの年(BC483/2年)」と言われる。 アルコンは任期が終わると、その経験者が審査を経て終身会員(貴族制時代には任期10年)となり、アレオパゴスAreopagos会議(ローマの元老院に相当する)の終身会員となった。それは議場がアクロポリス西方の小さな丘アレオパゴス(アレスの丘Areios pagos)にあったことに由来する。アレスの丘は、残忍で血なまぐさい戦闘の神アレスAresが殺人のかどで神々に裁かれた場所とされており、この会議には神話に由来する権威があった。殺人・放火犯の裁判や役人の監督を職務とした。BC5世紀半ば以後、民主政の発展とともに権力を失った。 アテネの積極的な植民活動により、貨幣を使う広域的な地中海経済を発展させた。BC7世紀のアテネでは、ポリスの市民は4等級に分けられ、そのうち第3級の「農民級」、第4級の「労働者級」が平民と言われた。 これを背景にポリスの平民が台頭し、貴族と平民の抗争が激しくなっていった。平民はポリスの市民の一員として発言力を強め、貴族の寡頭支配に反発し、国制への参政権を求めるようになっていった。 貴族政は動揺しはじめ、BC632年には貴族のキュロンがクーデターで権力を掌握しようとしたが、平民たちの抵抗で失敗する。続いて、BC621年には、ドラコンの立法によって平民も成文法で守られることになり、BC594年のソロンの改革では負債の帳消しや債務奴隷の禁止の措置がなされ、財産をもつ平民の政治参加も実現した。アルコンも平民から選ばれるようになり、平民は貴族と対等な政治参加を実現させていった。このような平民の地位の向上を背景として、貴族と平民の双方に人気を得て独裁的な権力を握ったペイシストラトスが、BC6世紀中頃、僭主政を布き、民主政が危機に陥った。 ペイシストラトスは僭主となるとむしろ合法的に国事を執行した。しかしその支配がしっかり根を下ろす前に、政敵によって一時アテネを追われた。その後謀略をもって復帰したが、再び党派間の争いから亡命に追いやられた。だが亡命先トラキアのパンガイオン金山で産出される金銀で資金を蓄え、アルゴス人の傭兵を雇い、ナクソス島の僭主リュグダミスの援助を得て、エレトリアを足掛りとして、BC546年、マラトン近くの「パルレニスの戦い」で反対派貴族を倒し、アテナイ市を支配した。ペイシストラトスは、民衆の武器を取り上げてついに僭主政を実現した。 多くのポリスの王は、神話時代に遡る正統な血統を誇る。この本来の皇統とか王統の血筋によらず、実力により君主の座を簒奪し、身分を超えて君主となる者を僭主と呼び、その僭主による政治を僭主政治という。古代ギリシアにおける僭主は、基本的に貴族政をとるポリスにおいて、政治的な発言力を増してきた平民を支持基盤にし、貴族の合議制を抑えて独裁的権力を振るった。アテネに現れたペイシストラトスは、自らの勢力基盤であった小農民や商工業者を優遇し独裁的権力を維持し得たが、やがて、市民の自覚の高まりは、次第に僭主の独裁を許さず民主政を実現させようになる。 BC527年に死去したペイシストラトスには、二人の息子、ヒッパルコスとヒッピアスがいた。二人とも権力を継承したが、ヒッパルコスは同性愛のもつれからアリストゲイトンという男に殺されてしまった(BC514年)。ヒッピアスの方は残酷な暴君と化したため、BC510年、アテネ市民は蜂起し彼を追放した。ヒッピアスは、アケメネス朝ペルシアに亡命し、後のペルシア戦争では、ペルシア軍とともにギリシア侵攻に加わっている。 アテネ市民は僭主政治の愚昧さと弊害を知り、その出現を防止する必要性を認識した。 クレイステネスの改革 イサゴラスに率いられた上層貴族や最富裕層(多くの富裕層は都市部に住居を構え、しばしば遠隔の農地の管理に馬を駆って出掛けた)らによる貴族政治を維持しようとする寡頭派(平地党)と、貴族クレイステネス(父はアテナイ‶ギリシャ共和国の首都アテネの古名”の名門メガクレス、母は名門アルクメオン家出身のアガリステ)を支持する参政権を持つ商工業者や農民・労働者など、民主政を主張する民主派(海岸党)との争いが起こり、イサゴラスはスパルタ軍の支援を受けて一時権力を掌握した。クレイステネスは一旦、国外に亡命した。 イサゴラスは民会に提案する議案を準備する評議会を解散させようとしたが、評議会はそれを許さず反抗し、アクロポリスに逃げ込んだイサゴラスとスパルタ兵を二日にわたって包囲してついに撤退させ、亡命先からクレイステネスを呼び戻した。 クレイステネスは民衆の支持を支えに、その領袖として国政にあたった。クレイステネスはBC508年にアルコン(執政官)となると、ただちに改革を行い、僭主の復活を許さず、民主政を守るための画期的な制度改革を行なった。 今までのデモス Demosを改編し、「クレイステネスの改革」の要となる10部族制度を支える行政単位とした。 アテネの支配領域であるアッティカ全土を139のデモスに区画した。その自然村落を地理的基盤として再編成し、区民登録名簿を作成し、それぞれのデモスごとに区長を置いた。「クレイステネスの改革」は、この区民名簿に基づき18才以上の成人男子には、市民資格を与え民会への出席を認めた。ポリス市民の全体会議である民会とは別に、デモスごとに区民総会を開いて日常的な問題を処理した。やがてクレイステネスの時に設置された『五百人評議会』の議員を選出する母体となった。 『五百人評議会』は、民会の議決にかける前に議案を審議する日常的な任務があったため、やがて、実質的な常任執行委員会として行政を担当するようになる。実際、BC462年、エフィアルテスとペリクレス(母がクレイステネスの姪)の改革によって、貴族から構成されていたアレオパゴス会議の実権が剥奪され、『五百人評議会』が行政の最高機関となった。 古代アテネのデーモス Demos は、元来、「村落」を指すが、「クレイステネスの改革」により、民主政を支える基本単位とされたことから、「民衆」を意味するようになり、民主政Democracyという言葉が生まれ、現在のデモクラシーという言葉に繋がった。 また「クレイステネスの改革」、特に農民育成策は、彼らの実質的な地位の向上に繋がり、中小の土地所有農民による武器の入手が比較的容易になり、兜・胸甲(きょうこう)・すね当て・直刀・楯・投槍などの武器を自弁で所持するようになり、古代ギリシアの陸軍の中核を担う重装歩兵として国防の主力となった。その結果、貴族による政権独占は困難になり、アテネに重装歩兵民主政を確立させ、BC5世紀の民主政の発展を揺ぎ無いものにした。 「クレイステネスの改革」の中でも『陶片追放政策』は有名である。オストラコンという陶片を使って、市民による投票を行った。僭主になりそうな危険人物をオストラコンに記し、投票総数が6,000票以上に達すると、最多得票者は10年間、国外へ追放される。市民が積極的に軍事と政治に参加をしアテネはさらに飛躍した。 歴史家ヘロドトスは、「かくてアテナイは強大となっ たのであるが、イセゴリアisegoriaということが、あらゆる点において、いかに重要なものであるか、ということを実証したの であった」 と述べている。 イソノミア isonomia(等しい者の統治)とは、万人が等しく政治の営みを求めることができると言う意味であるから、その営みは、アテネのポリスにあっては、とりわけ一緒に集まり話し合うという営みなのである。故に、「イソノミア」を担保するためには、何よりも『言論の自由』が不可欠となる。『言論の自由』自体が、イセゴリア isegoria、つまり『市民が政治方針について自由に発言する平等な機会が与えられる』、アテネでは『民会ecclesiaで発言を望むものには、誰でも平等にそれを認める政治手法』と同義となる。
スミュルナ(「エーゲ海の真珠」と古来から称えられる港、現在は「イズミル」、付近にはエフェソスなどの古代遺跡)は、BC11世紀、イオニアギリシャ人によって、アナトリア西岸の重要な商業港を備える植民都市として建設された。ローマ時代には商業都市として栄え、ローマ帝国の解体後は、ビザンチン帝国が支配し、その後、オスマン帝国時代にも支配されてからも繁栄を維持している。その住民の多くはギリシア系であった。 第一次世界大戦でオスマン帝国は敗戦した。スミュルナはギリシアに割譲された。トルコ独立戦争時の1921年、ケマル・アタテュルク(トルコ共和国建国の父)の率いるトルコ軍が、サカルヤ河畔における戦闘(サカルヤの戦い)でギリシア軍に勝利した。 結果、ローザンヌ条約で全てのトルコ人およびムスリム以外の住民は、スミュルナから追放され、1930年、スミュルナはイズミル県としてトルコ共和国に編入された。これがその後のギリシア王制廃止の一因となった。 テーベ、またはテバイThebaiは、アテネの北西にあるギリシアのポリスの一つで、近接するせいかアテネへの対抗心が強い。同じアナトリアの東部海岸に諸都市を建設したアイオリス人とイオニア人でありながら、テーベは、アナトリアの植民都市を守るため、ペルシア戦争(BC500年~BC449年)ではむしろペルシア側に協力した。 アテネの民主政治化 ペリクレス(BC495頃~BC429年)は、ペルシア戦争の最中にのアテネの民主政を完成させた。BC443年~BC429年まで、選挙で将軍職(ストラテーゴス)に選出された後、連続して 15年間再任され続けた。 「ペリクレス時代」と呼ばれるアテネの全盛期を築いた。ペリクレスはアルコンではなかった。アルコンの任期は1年で再任は認められず、9人の合議制なので、民主的ではあったが、パルテノン神殿の建設のような長期的政策を実行するには不向きだった。専門職である将軍職は、クレイステネスの時に設置され、10人が民会で選挙で選ばれ、再任が可能だった。 ペルシア戦争は、アケメネス朝ペルシアとアテネを中心とするポリス連合軍の戦いであり、BC500年~BC449年の約50年間、4回に及ぶ。発端は、ペルシアが支配権を握ったイオニア地方のギリシア人植民市が、ペルシアの支配に反発しBC500年に起こした「イオニアの反乱」を、ペルシアのダレイオス1世(大王)が鎮圧したが、その際、援軍を送ったアテネなどのギリシアのポリスに対し、大遠征軍を派遣し帝国の版図拡大を図った。 BC480年8月、大軍を擁するペルシアとの戦い(第3次)では、ギリシャ中東部、カリモドロス山とマリアコス湾に挟まれた狭隘なテルモピュライの地峡に誘ったが、スパルタのレオニダス王も戦死するほどの玉砕(テルモピュライの戦い)をし、アテナイはペルシア軍に占領されて焼かれるなど、ギリシアの諸都市国家は最大の危機に陥った。 しかし、アテネを中心に都市国家の連合軍が、陸上ではサリッサ(4.0- 6.4mの非常に長い槍)を駆使する重装歩兵による密集部隊戦術で、海上戦ではアテネ海軍の三段櫂船(さんだんかいせん)の「衝角 」戦術で優位に戦い、ペルシア王アルタクセルクセス1世は、アナトリアへ逃れた。 ギリシアの三段櫂船の船員は、漕手170人、補欠漕手・水夫・戦闘員30人の200人、その漕手170人が三段に設営された板に腰かけて、合図に合わせて一斉に櫂を漕ぐ。アテネの三段櫂船は、最高で時速18kmは出たと言う。船首には青銅製の「衝角」をつけ、敵船に体当たりして船体を破壊する戦術が採られた。「衝角」には、二つの鑿のような青銅製の刃があり、ひとつは水上、他方は水中に入っている。衝角の2つの突出は、敵船に衝突して船腹に穴を穿って浸水させる武器と、水の抵抗を少なくし速度を上げる水切りと、両方の機能を持っていた。 ペルシア戦争のサラミスの海戦では、三段櫂船の戦術が大いな破壊力を発揮した。BC480年9月末、アテネの東側海域の沖合に近接するサラミス島付近でアテネ海軍が三段櫂船を駆使してペルシア海軍に勝利した。この三段櫂船の漕手には、武器や武具を持たないため、貧しい市民や無産市民に課せられた。ペルシア戦争の帰趨を決する重要なサラミスの海戦の勝利は、その三段櫂船の漕手の活躍があって初めて可能だった。これ以後、三段櫂船の漕ぎ手として活躍する多くの無産市民の発言力が高まり、アテネ民主政を支える民衆層の広がりとなり、アテネ都市国家の全盛期を迎えた。 アテネの没落 デロス同盟とは、エーゲ海周辺のギリシア諸都市国家が、ペルシア帝国軍の来襲にそなえて、BC478にアテネを盟主として結んだ軍事同盟で、最大時には200のポリスが参加した。各ポリスが一定の兵船を出して連合艦隊を編成し、それのできないポリスは一定の納入金を同盟の共同金庫に入れることにした。実際に艦隊を提供したのはアテネだけで、他のポリスは納入金を納めるだけであった。共同金庫はアポロン神殿のあるデロス島におかれ、同盟の会議もそこで開催された。 アテネ軍が中核になりペルシアの侵略を打破した功績により、デロス同盟の納入金の管理は10人のアテネ市民に任され、その執行権は初めからアテネが握っていた。BC454年には、金庫がデロス島からアテネに移された。その後、 BC449年に、デロス同盟とアケメネス朝ペルシアとの間で、ペルシア戦争終結を目的とした条約が批准された(カリアスの和約)。しかし、ペリクレスはデロス同盟を強引に継続させ、アテネはデロス同盟を通じて「アテネ帝国」と呼ばれるほどの専横を振るうようになった。 その一方、ペロポネソス半島内の諸都市国家は、スパルタを盟主とするペロポネソス同盟を、既にBC6世紀に結成しており、次第に両同盟の対立が深刻になり、ギリシアの二大ポリス、アテネとスパルタの関係が険悪化した。 デロス同盟の資金を当時の将軍職ペリクレスがアテネにパルテノン神殿(BC447年に建設が始まり、BC438年に完工、装飾等はBC431年まで行われた)を建てることにつぎ込んだ。当然、他のポリスの不満は高まった。このアテネの横暴に、既に、スパルタを中心に結成されていたペロポネソス同盟の諸都市国家が反発しBC431年の開戦となった。これが古代ギリシアを没落させる契機となるペロポネソス戦争(BC431年~BC404年)である。 戦争開始の翌年のBC430年、ペリクレスは戦争にそなえてアテネ人をアテナイに移住させた。市内の人口は過密となり不衛生、真夏の炎天下なれば疫病が蔓延し、神殿と言わず、路上と言わず死体が放置される状態となった。ペリクレスの二人の子供もペストに罹患し死亡、ついに自らも一年後のBC429年、ペロポネソス戦争の戦闘の最中、疫病に罹って死亡した。「アテネのペスト」とは、「悪疫」の意味で、いわゆるペストではなく、天然痘であるという説もある。 ペルシア戦争後、アテネはデロス同盟の盟主となり、ギリシア全域の覇権を握り海上帝国として西方の地中海にもその勢力を拡大しようとした。アテネの野望に反発したのが、シチリアのギリシア人の植民市シラクサで、スパルタと同盟して抵抗した。 本土でのスパルタ軍との戦いで劣勢に陥ったアテネは、直接、海軍を派遣してシラクサを攻略し、アテネの植民都市にすることで起死回生を図ろうとした。しかし、BC413年、ニキアスが指揮するアテネ海軍は、シラクサの攻囲戦で、シラクサとスパルタの連合軍に敗れた。アテネ海軍は全滅の危機に瀕し、撤退を決意しその準備に入った。いざ撤退となる8月27日の満月の夜に月食が始まった。アテネ軍衆の過半が、これを凶兆と見て出航中止を要請し、ニキアスら指揮官たちも出航をためらった。そればかりか逗留を長びかせた。 三段櫂船のような軍船には、乗員の寝場所がないため、夜間は海浜に引き揚げて乗員は陸上基地で炊事をし休息した。 シラクサ軍は、夜襲を掛け、アテネ海軍の船すべてを焼き払い、動きを封じた。上陸していたアテネの部隊は捕虜となって石切場に閉じこめられ、全員が餓死、ニキアスも捕らえられ処刑された。アテネは200隻以上の軍船、35,000人に及ぶ乗組員、4,000人のアテネ出身者を含む陸軍、および多くの資材と財貨を失い、ペロポネソス戦争の帰趨は決定した。 後世、アリストテレス(BC384‐BC322)は地球球体説を主張する時に、「月食時に月面に影が差す大地は円い」などの観察結果を述べている。 BC734年頃、ギリシアのペロポネソス地方にある都市コリントスの植民者たちがこの場所を発見し、低湿地帯を意味するシラコ Sirako と名づけた。土地が肥沃であり、また原住民たちは彼らに好意的であったため都市は発展し、地中海においてギリシア植民市のうちで最も繁栄する都市国家となった。 シチリアでのアテネの敗北を知ったイオニアのデロス同盟に加盟する諸都市が離脱すると、スパルタはイオニア諸都市のアケメネス朝ペルシア帝国からの保護を盟約し、一方、アテネに勝利するためペルシア帝国からの資金援助を受けた。その資金でスパルタは海軍を増強、次第に制海権を握ってアテネの穀物輸送ルートを抑えたため、BC404年にアテネは全面降伏した。スパルタはギリシアの覇権を握った。 アテネの海上帝国は崩壊し、デロス同盟も解体、ポリス世界の覇権はスパルタに移った。そのスパルタがペルシア帝国と同盟したため、ペルシアのギリシアへ干渉が再び強まった。 しかも、ギリシアに統一政権が生まれることを恐れたペルシア帝国は、一転してアテネ・テーベ・コリントなどに資金を援助し、スパルタとコリント戦争(BC395~BC387)を起こさせた。スパルタの専横を嫌い、アテネ・テーベ・コリントの三ポリスが同盟して戦った。三ポリス同盟側は一時勝利を収め、今度はアテネの復興を恐れたペルシア帝国がスパルタの要請を受けて仲介に乗り出し、いわゆる「大王の和約」で終結させた。その後ギリシアではテーベが、一時、台頭するが、全体として弱体化し、北方のマケドニアの支配を許すこととなる。 30年間に及ぶペロポネソス戦争は、スパルタの勝利に終わったが、両軍の戦いは、ギリシア本土とエーゲ海全域にわたり、さらにエーゲ海上から遠く西地中海のシチリア島まで及んでいる。 この戦争の長期化によりアテネ のポリス社会を支える市民が疲弊没落し、農地が荒廃し、ポリス民主政の社会基盤が崩れていった。そのため兵士の主体も市民による重装歩兵から、傭兵に変わった。特にアテネではBC430年ペストの大流行で人口が激減し 、クレタ諸島やバレアレス諸島(スペインの東の地中海上の島々)などから多数の傭兵を雇い入れることになった。それが衰退期に向かう契機となった。 古代においてバレアレス諸島は投石器を扱う優れた能力を有する傭兵の出身地として広く知られており、ガイウス・ユリウス・カエサルが自らの手で書き記した『ガリア戦記』に、「ガリアで歴戦中のカエサルが、バレアレス人の投石隊を傭兵として利用した」との記述がある。古代の地中海世界では、東のロードス島人や西のバレアレス諸島の人が、特に投石器の名手が多いことで知られ、諸 国の傭兵部隊に投石兵として配属されていた。 テーベの将軍エパメイノンダス ペロポネソス戦争後にスパルタが優勢になると、テーベに有能な将軍エパメイノンダスが現れ、その指導のもとでBC371年、南ボイオティアのレウクトラの平野での会戦「レウクトラの戦い」でスパルタを破り、ペロポネソス同盟軍を率いたスパルタ王クレオンブロトス1世を敗死させた。エパミノンダスの戦術は、左翼に見るからに重装備の歩兵部隊を縦隊で厚く密集させ、中央と右翼には機動性のある騎兵と軽装兵を、左翼よりも幾分後方に置く「斜線陣」を布いた。スパルタ王にエパミノンダスの雁行陣の弱点を突く攻撃を誘った。スパルタ軍は劣勢な右翼を突破口と見て集中して攻撃し深く侵入した。勢いのまま敵陣深く進撃するスパルタ軍が側面を晒すと、エパメイノンダスは、重装備の歩兵部隊を、すかさず、スパルタ軍の重装備歩兵部隊の弱点である後ろと右から 襲いかかり殲滅した。スパルタ王の遺体がそのまま野晒しになるのは耐えがたいとして、休戦協定を結んだ。 重装歩兵は(ラテン語ではホプリテス hoplitēs)は、世界各地で年代も様々に活躍していた。古代ギリシア世界の重装歩兵は、「ホプロンhoplon」と呼ばれる盾を持って戦ったことからホプリテス(複数形でホプリタイ)と呼ばれた。 重装歩兵は、頭部は兜、胸部から腹部は鎧、手は籠手、脚部は膝当て・脛当てなどで重装な防備を施していた。盾を左肩の力で保持し、露出した右半身は隣の歩兵の盾で保護した。この陣形は正面に対しては大きな防御力と破壊力を持ったが、機動力のある騎兵などによる側面・背面攻撃に弱点があった。そのため、時代が進むと中央に重装歩兵密集陣を展開し、その右側面に騎兵部隊を配置し、前方には軽装歩兵などによる散兵線を布いた。 ファランクスphalanxとは、会戦の際に用いられた重装歩兵による密集陣形である。BC2450年頃の古代メソポタミアの『禿げ鷹の碑Stele of the Vultures』(シュメールの都市遺跡ギルスで発見された。ルーヴル美術館蔵)に大盾と槍による密集陣形が描かれている。BC7世紀以後の古代ギリシアでは、鎧兜を着用した重装歩兵を重視するファランクスが布陣された。当時の地中海交易の発達により、富裕な市民層が育ち、アテネのような都市国家の市民は兵役の義務があったため甲冑が普及し、重装歩兵部隊を編成することを可能にした。 ボイオティア同盟軍(ボイオティアは、古代ギリシアの一地方で、アッティカの西北に位置、中心都市はテーベ)はペロポネソス半島へと侵攻した(アッティカは、アテネ周辺を指す地域名)。そこで、今まで侵攻されたことが一度もなかったスパルタの地ラコニアへと足を踏み入れ、スパルタに隷属していたメッセニアを解放し、スパルタの都市経済に大打撃を与えた。テーベが、新たなギリシアの覇者となった。さらに北方に進出しマケドニアと戦い、フィリッポス2世(アレクサンドロス大王の父)を人質にするなど、勢いがあった。 BC362年、ギリシア本土アルカディア高原の古代都市マンティネイアと結んだスパルタとアテナの連合軍と再び対立し、テーベを中心とするエヴィアやテッサリアなどのボイオティア同盟軍が会戦した『マンティネイアの戦い』で、エパメイノンダスは自ら突撃隊を率い敵を敗走させたが、自身は戦闘の最中に槍を受けて戦死した。この戦いでボイオティア同盟軍は勝利したものの、テーベは、エパメイノンダスをはじめとするダイファントスやイオライダスなど有能な将軍を失った。これ以降テーベはギリシアの覇権を維持できなくなり、衰退の道を歩むことになる。 マケドニアの台頭 当時のマケドニアの殆どは現在のギリシアに属する。BC4世紀後半には、テーベも他のポリスと同様に衰微し、逆に力を付けたマケドニアのフィリッポス2世がギリシア本土に侵攻する。テーベは、アテネなどと協力してそれに当たったが、BC338年、ボイオティア地方の東に広がるカイロネイア平原での会戦『カイロネイアの戦い』でアテネ・テーべ連合軍は大敗した。翌BC337年、スパルタを除いて支配下に入った全ポリス間で結成されるコリントス同盟の一員としてマケドニアの支配下に入った。コリントス同盟の加盟国は、都市国家の自治が認められ、相互不可侵の平和条約が締結させられた。マケドニアの実質的な軍事・外交上の主導権下に入った。ギリシア本土は、背後に マケドニア王国の圧倒的な軍事力があるため平和が保たれた。 マケドニアの国王フィリッポス2世(フィリップとも表記)の在位はBC359~BC336、その間、ギリシア北方の後進国であったマケドニアを強国に育てた。その少年時代、父アミュンタス3世死後の王位継承をめぐる争いに介入した将軍エパメイノンダスが率いるテーベに人質にされた。フィリッポスが有能と見込み、エパメイノンダスは彼を指導した。 この時代に、フィリッポスはファランクスphalanx(重装歩兵密集部隊戦術)や斜線陣などテーベ軍の陣形を学んだといわれている。斜線陣は、将軍エパメイノンダスが考案した、ファランクスの弱点をついた戦術である。レウクトラの戦で、スパルタのファランクスの弱点である右側に対応する自軍の左側に主戦力を配置し、スパルタの攻勢が戦力の弱いテーベの右側へ流れて行くに従い突撃を遅らせスパルタの攻撃を加速させ、深入りし過ぎた時、ファランクスの弱点であるスパルタの軍勢の右側と背後から崩していく戦法である。 フィリッポスは、祖国に帰り内紛を収めて即位すると、周辺諸部族との関係を強化しマケドニアを統一した。マケドニアは、ギリシア北方のドーリア人によって建国された文化的にも経済的にも遅れた辺境の後進国であった。マケドニア王家と近親者は、王位継承をめぐる骨肉の争いが絶えず、所領を持つ貴族達も私闘を繰り返していた。 全体的に山深い地形ながら、鉱物資源にも恵まれていた。フィリッポスは、パンガイオン金山から算出する金銀で富国強兵を図った。 エーゲ海北岸に接する平野部は、地中海性気候で温暖、しかもギリシアの大部分と異なり広く肥沃であるため、夏の乾燥に強いオリーブやブドウなどの果物や柑橘類などの栽培や牧羊が広く行われている。バルカンの山岳地帯に接する、主に西マケドニア地方の山岳部は、高山性の気候のため多くは季節ごとに移動する遊牧生活(羊や山羊)を行っていた。 歩兵部隊の強化は、マケドニア軍の重要課題であった。それまでは農民を一時的に徴用する民兵レベルのものであった。フィリッポスは、軍制の改革を行い、地方別に農民達を徴発し、サリッサで装備した常設の密集歩兵部隊に替え、軍団編成して厳しく軍事訓練をした。フィリッポスが編成した密集歩兵部隊は職業軍人といってもよいレベルになっていた。しかもマケドニアの住民に国家意識が目覚めた。その装備の特徴は、全長5~6mのサリッサであり、他のギリシアの重装歩兵の装備した槍よりも長かった。穂先も、出土品で見る限り、刃渡り60cmほどと長く、石突をつけることでバランスをとっていた。折れた際には、石突を武器にした。おそらく当初は貧しさ故に、胸当ても使わず、盾も小型の物を使っていたようだ。マケドニアの密集歩兵達は、楔形陣形を組んだままサリッサを水平に構えて突撃し、混戦となれば、フィリッポスの密集歩兵は剣も装着し、個々の接近戦にも強かった。 マケドニア軍の強みは、王の指揮系統は絶対であり、兵士達はその命令に応じて動くよう訓練されていた。 フィリッポスは、兵士達を集めて長期間にわたる訓練を行った。それにより密集隊形を組んだまま、様々な動きができるようになっていた。後に「カイロネイアの戦い」では敢えて後退し、追ってくるアテナイ軍の隊列が乱れてくると反転してこれを撃滅してる。 フィリッポスは、伝統的に個人技に優れていた騎兵戦力を増強し、貴族の若い子弟を集めて、当時、ギリシア世界では軽く見られていた騎兵部隊を編成し直した。フィリッポス2世に忠誠を誓った精鋭の騎兵部隊、マケドニア重騎兵「ヘタイロン」の誕生である。規律を身に付け、フィリッポスの命令を絶対として、楔形で敵陣に突進、その衝撃力と機動性を兼ね備えた勇猛な騎兵軍団となった。 フィリッポスは、テーベの希代の英雄エパメイノンダスから学んだ、ペルシア型の軽歩兵と騎兵の共同戦術や兵站の運搬、偵察の技術などを効果的に組み合わせる新たな戦術を創り上げていた。マケドニア軍は、戦術と戦略をわきまえた、完全に統制され兵士達であった。 フィリッポス2世がBC359年夏に即位した当時、マケドニア王国は周辺に様々な敵を抱えていた。まず、西のイリリア(イリュリア)は、BC4世紀にバルデュリス王が現れて、イリリア王国を強盛国に変えていた。バルデュリス率いるイリリアは、かつて兄のペルディッカス3世を4000人の兵士と共に敗死させ、余勢を駆ってマケドニアに侵攻し、 西部の上部マケドニアを占領していた。東のパイオニアは、バルカン半島に存在した民族の一つで領土を 窺っていた。さらにアテネは、長年にわたり、エーゲ海に流れるストリモナス川の東岸の台地アンフィポリスを奪取しようとして、かつてマケドニア王位を狙った王族アルガイオスを支援していた。 エーゲ海北岸のアンフィポリスは、トラキア、ヘレスポントス(ダーダネルス海峡)につながる交通上、戦略上の要所、またパンガイオン地区の金・銀の集散地であり、船材の積出し港として通商上重要視されていた。フィリッポス2世が占拠するBC357年まで、事実上独立を保持していた。 難敵イリリア王国に、編成されたばかりのマケドニア軍であったが、ヘタイロンの楔形突撃で前陣を破壊し、イリリア軍を敗走させた。領内のイリリア人を追い出し、マケドニアの国家としての自立はほぼ達成した。BC357年、フィリッポス2世がアンフィポリスを占領し、パンガイオン金山を含むトラキア地方を制圧、その後も、周辺地域へ兵を進め、次々に領土を拡大していった。わずか数年でマケドニアはギリシアにとって無視できない存在に成長していた。フィリッポス2世は、いよいよギリシア本土へと介入するチャンスを探り始めていた。 BC338年8月2日、テーべの北方に位置する、ボイオティア地方の都市カイロネイアの東に広がる平原で、ギリシアとマケドニア両軍の決戦が行われた(「カイロネイアの戦い」)。マケドニア軍の右翼はフィリッポスが指揮する近衛歩兵部隊、中央には密集歩兵部隊、左翼には、息子のアレクサンドロスが率いる騎兵部隊、総兵力は軽装兵を含めて34,000。アレクサンドロス18歳、初陣が正規軍同士の本格的な戦争であった。アレクサンドロスはマケドニア軍の精鋭、ヘタイロンを采配する。 対するギリシア軍は、フィリッポスに対抗する左翼にアテネ軍、中央にカイロネイアなどの同盟諸国の部隊、アレクサンドロスに向き合う右翼にはテーベを中心とするボイオティア軍が布陣した。軽装兵を含めた総兵力は36,400。とりわけ最右翼には、ギリシアで最強と謳われた精鋭歩兵部隊、テーベ軍の神聖隊がいた。ただ、アテネ軍を初めボイオティア軍の殆どは傭兵で、しかも連合軍の最大の欠点は、連携が取れていなかった。 戦闘は、まずフィリッポスが歩兵部隊をゆっくり後退させることから始まった。正面のアテネ軍がこれを追撃しようと突出する。中央のカイロネイア人部隊はアテネ軍との間隔を空けないようにと左へ移動し、右翼のボイオティア軍もこれに倣った。これに呼応するテーベの戦列の至る所に隙間が生じ、そこへアレクサンドロス率いるヘタイロンが突入、神聖隊の側面を突破し背後に回ることに成功した。ここでも、フィリップスの戦術眼と統率力が際立ち、アテネ軍が動揺して戦列が乱れたところで反転し、一気に破壊した。テーベの神聖隊も、苦戦となれば自ら軍勢の先頭となって突入するエパメイノンダスのような将軍もなく、それに従う兵士の忠誠心もなかった。カイロネイアの会戦は、マケドニア軍の圧倒的な勝利に終わった。 ギリシア軍は、数の優位を戦術に生かせずアテネ人だけで戦死者は1,000人以上、捕虜は2、000人にのぼった。テーベ人の共同墓地からは254人分の遺骨が発掘され、これらすべて神聖隊の戦死者と見られている。大多数の戦傷者や戦死者は、カイロネイアの平原に放置された。テーベ軍の神聖隊は、壊滅した。以後再結成されることはなかった。 後退戦術により敵の戦列の乱れを誘い、相手戦列に生じた隙間へ重装備した騎兵の楔形突入、これらはすべてフィリッポスの思い通り戦術であった。こうした戦法は、東方遠征でアレクサンドロスがそっくり採用することになる。 フィリッポス2世は、スパルタを除くギリシアのポリス連合であるコリントス同盟(ヘラス同盟)の盟主と成り、さらに東方のペルシア帝国遠征を構想していたらしいが、カイロネイアの勝利の2年後、BC336年、護衛官パウサニアスに短剣で胸を刺されて即死、 フィリッポス46歳であった。 パウサニアスは、逃走用に用意してあった馬に向かって走り出したが、護衛兵たちが追いつき槍で刺殺した。フィリッポス2世暗殺事件の真相は、古代マケドニア史の学術的問題となっている。フィリッポス2世の構想は子のアレクサンドロスが継承した。 1977年と1978年に、ギリシャの中央マケドニアのヴェルギナ(マケドニア王国の都アイガイとして栄えた)で王家の墳墓3基が発掘された。その第1墳墓から発掘された成人男性の脚の骨を分析した結果、膝の部分に大きな穴があき、骨が癒着して関節が動かなくなっている。古代の文献にフィリッポス2世がBC339年の戦いで負ったと書かれている傷と一致することが分かった。BC336年に暗殺される3年前、フィリッポス2世はスキタイ人(BC6世紀から黒海北岸の草原地帯を支配したイラン系騎馬民族)との戦いで得た戦利品の分配話がこじれた結果、トラキアのトリバリ人と争いになり、瀕死の重傷を負った。セネカ、プルタルコス、デモステネスなどが古代ギリシャの文献で記述した傷の厳密な位置とは異なっているものの、どの文献もフィリッポス2世がその傷が原因で脚が不自由になったとしている。 第2墳墓の副葬品のいくつかは、アレクサンドロス大王のものであった可能性を示していた。 第1墳墓に埋葬された3体の遺骨を分析した結果、遺骨は中年男性と、死亡時に18才くらいだったと推定される若い女性、そして性別の不明な新生児のものであった。この法医学的分析や、古代の文献に記されたフィリッポス2世と7人の妻のうちの最後の妻とその子どもの死亡時の年齢と一致した。 アレクサンドロス大王が謀ったなどの諸説があるが、フィリッポス2世は護衛官パウサニアスに暗殺され、王位を継いだのが当時20歳のアレクサンドロス大王であった。アレクサンドロス大王は王位継承の障害となるクレオパトラ=エウリュディケを自殺に追いやり、産まれたばかりであった子供を惨殺している。 ペロポネソス戦争後のギリシアの混乱に乗じてギリシア本土に侵攻した。 自ら従軍したペロポネソス戦争の史実を記述した、アテネ出身のトゥキュディデスの著書『歴史』には、 「マケドニア人達は歩兵で防御に当たろうとせず、上部マケド ニアの同盟国から得た騎兵を加えた騎兵隊を以て、隙をね らっては、 多勢で無勢のトラキア軍を襲撃した。馬術に優れ、胸当てをつけた彼らの攻撃に抗しうる者は無かった。トラキア人達は、多くの敵兵に囲ま れて、危機に陥ることが往々にしてあったので、この大群に対して命を賭すれば味方の人数が尽きると悟って手出しをしなくなった」 と述べられている。 アレクサンドロス大王(BC356年~BC323年) BC5世紀末、新たな都ペラは、バシレウス(ギリシア語の君主の称号)であったアルケラオス1世(BC413年~BC399年)によって建てられ、旧都アイガイ(ヴェルギナ)が遷都された。BC4世紀、ピリッポス2世や、アレクサンドロス3世はペラで生まれた。 BC342年、アリストテレスがマケドニアの王子アレクサンドロスの師傅となり、都ペラの近郊ミエザにあったニンフの神殿のところに学園が作られた。アリストテレス37歳、アレクサンドロス王子は13歳であった。アレクサンドロスはフリッポス2世の次男、兄が一人いたが、知的障害があったため、フィリッポスはアレクサンドロスに期待して、その教育には特に配慮した。その一環が有名なアリストテレスだが、同時に、プトレマイオス(BC367年~BC282年)やカサンドロス(BC358頃~BC297)など同世代の貴族の若者と一緒に勉強させた。 プトレマイオスは、マケドニア王国の貴族ラゴスの子で、アレクサンドロスの幼少時より「ヘタイロイ」の将校の一人であった。プトレマイオスは、アレクサンドロス3世の東征の際には将軍として従軍し、帝国内でも重要な地位にあった。 BC330年以降は、アレクサンドロス大王の側近護衛官の一人となっている。アレクサンドロスの死後はディアドコイ (ギリシア語で後継者たちを意味。アレクサンドロス大王の死後、帝国のために戦ったマケドニアの諸将に与えられた呼称)の一人としてエジプトを本拠にした。エジプトのヘレニズム国家プトレマイオス朝の初代ファラオとなる(在位:BC305年~BC282年)。ディアドコイの多くが暗殺や戦死、獄死といった非業の死を遂げる中で、プトレマイオスは天寿をまっとうした数少ないディアドコイの一人であった。内政において統治体制を確立し、外征においては領土を東地中海まで拡張するなどして、古代エジプトの繁栄を取り戻した。 BC336年、父王が暗殺されたため、マケドニアに20歳のアレクサンドロス3世が即位すると、テーベは反旗を翻した。翌BC335年、アレクサンドロス3世はテーベを急襲し、徹底的に破壊し都市は壊滅した 。テーベ人6,000を殺し、神官を除く全自由民を奴隷として売った。捕虜の数は3万にのぼった。 テーベは、BC 316年大王のディアドコイ の一人マケドニア王カサンドロスによって再建された。BC 197年ローマの支配下に置かれた。 BC334年に始まるマケドニアのアレクサンドロス大王の東方遠征軍は、ヘレスポントス(ダーダネルス海峡)を渡海して、ペルシア軍と小アジア(アナトリア)半島の北西端グラニコス川(現在名コジャバシュ川)で戦い勝利した。ここで壊滅させた騎兵隊は、ペルシアの精鋭部隊とも言うべき戦力であった。この勝利によって、小アジアのギリシア諸市の解放がほぼ達成された。 アケメネス朝ペルシアの最後の王ダレイオス3世が初めて出陣した来たBC333年のイッソスの戦いでも戦闘用馬車に乗っていながらダレイオス3世が突然逃げ出し、BC331年のアルベラの戦い(ガウガメラの戦い)でも決着がつかない前にまたしても逃亡、BC330年には都のペルセポリス(イランのファールス州;現在はシーラースの北の砂漠の中に遺跡として残る)は、アレクサンドロス大王によって焼き討ちされ廃墟となった。ダレイオス3世はエクバタナに逃れたが、次々と臣下が離反、最後はバクトリアのサトラップで、バクトリアの総督らに牛車に放り込まれ槍を投じられ、そのまま死ぬまで放置された。BC330年、アケメネス朝ペルシアは滅亡した。バクトリアは、BC255年頃~BC139年まで、現在のアフガニスタンの地域に入植させられたギリシア人が支配するヘレニズム諸国の一つとして存続する。 アレクサンドロス大王は過酷なゲリラ戦に苦しんだバックトリアとソグディアナを制圧した後、BC326年、インダス川を越えてパンジャブ地方に侵入したが、疲弊した兵士がそれ以上の進軍を拒んだ。大王もやむなくインダス河口付近のパタラから西進に転じる。BC323年、スサに帰還した。さらに西進し、地中海方面への遠征を考えていた。しかし、祝宴中に蚊に刺され熱病に掛かり、10日間熱にうなされ、そのまま6月17日に32歳で急逝した。その死因は諸説あるが、最近ではマラリアの中でも致死率が高い「熱帯熱マラリア」が有力とされている。ハマダラカが媒介するマラリアで、古来、旅先で命を落とす人が数多くいた。 アレクサンドロス大王は遺言を残す。「最強の者が帝国を継承せよ」。この遺言が発端となって、彼の部将達ディアドコイが覇権を争うことになる。それらの争いを、「ディアドコイ戦争」と呼ぶ。アレクサンドロス大王の築いた帝国は、アンティゴノス朝マケドニア、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプト のヘレニズム三王国に分裂し、一旦は安定をする。 ディアドコイの一人カサンドロス(BC358頃~BC297)は、アレクサンドロス大王死後、大王の遺児アレクサンドロス4世とその母ロクサネ(バクトリアの豪族の娘)を殺害し大王の家を断絶させ、マケドニアとギリシャの大半を領有した。 古代ギリシアの崩壊 BC338年、カイロネイアの戦いでアテネ・テーベ軍を破ったフィリッポス2世は、その年に全ギリシアのポリスに呼びかけ、コリント(コリントス)で会議を開催し、その議長としてポリス間の同盟を結成させた(コリント条約)。そのポリス間で結成させた同盟をコリント同盟と言う。コリントス同盟・ヘラス同盟・ヘレネス同盟などとも呼ばれる。マケドニアの覇権を認めないスパルタだけは、参加しなかった。 各ポリスは自由で独立した対等な権利が保障されたが、ポリス相互の抗争は一切禁止され、また政体の変更や私有財産・貸借関係の変更も禁止され、海賊行為はもとより禁止された。古代ギリシアがいかに荒んでいたかが知られる内容であった。それでもマケドニアは、実質的な軍事・外交上に齟齬が生じたため一端は退いた。 BC337年、マケドニアのフィリッポス2世はギリシア本土を征服し、スパルタ以外は支配下に入れた。ギリシアの各国のコリントス同盟も、新たな普遍的平和条約の枠組みを受け入れた。フィリッポスはこの条約により、各国代表からなる評議会を設置し、その機関を通してギリシアを統制した。 政体変革の禁止は、各都市国家の親マケドニア政権が続くことを狙い、負債の帳消しと土地の再分配の禁止は、フィリッポスに服従する上層市民の利益を擁護するものであった。つまり、加盟国の政治と社会の秩序を現状のまま固定するこの仕法は、半世紀にわたってギリシア人の都市国家が採用してきた国際関係の体系化であり、そのままギリシア支配統制の制度機構として利用した。 こうしてギリシアの軍事・外交の権限はすべてマケドニアのフィリッポス2世に握られ、事実上、前8世紀から続いたアテネ民主政の時代は終焉し、新たなヘレニズム期に移行していくこととなる。ただし、アテネなど諸ポリスは、未だ事実上独立国家として存続している。 このフィリッポスの巧みな外交戦略、練達な政治手法が、フィリッポスがBC336年に暗殺された突然の非常事態を、むしろ奇貨居くべしとし、子のアレクサンドロス3世が20歳で政権を継承することを可能にした。 翌BC335年に、有力ポリスの一つだったテーベがマケドニアからの離反をはかり、兵を挙げた。アレクサンドロスは一気にテーベを急襲して降伏させ、コリント同盟会議を開催してテーベの処遇を審議させ、徹底した破壊と領土の分配、住民を奴隷として売却することなど苛酷な決定をリードしている。 BC334年、アレクサンドロスは「コリントス同盟の全権将軍」という資格でギリシア同盟軍を動員し、東方遠征を開始した。その「ヘレニズムの大義」が、コリントス同盟の大義であるはずが、アレクサンドロスが東方遠征は、現実にはコリント同盟諸国には大きな負担がかかり不満が高まった。しばしばアケメネス朝ペルシアと結んで反アレクサンドロスの動きを策すが、その生前には決定的な離反に繋がらなかった。アレクサンドロスの東方遠征に動員されたギリシアの同盟諸国民には、根強い反マケドニア感情が渦巻き、アレクサンドロスもギリシア人部隊を信用できず、重用しなかった。 ギリシア諸国のうち唯一、マケドニアの覇権を認めなかったスパルタは、コリントス同盟にも加盟せず「光栄ある孤立」を守った。アレクサンドロスが東方遠征に出発する際にも、マケドニアはスパルタを攻撃しなかった。逆に、スパルタ王アギスがBC331年夏に反マケドニアの挙兵に踏みきった。ペルシアの支援を受ける一方でアテネにも同調を期待したようだ。兵力は歩兵2万、騎兵2千に達し、中にはイッソスの戦い(BC333年11月、アレクサンドロスの率いるマケドニアの東方遠征軍が、小アジアの東部に進み、ダレイオス3世の率いるペルシア帝国軍とイッソスで激突した)の戦場から離脱したギリシア人傭兵8千が含まれていたが、ギリシア人の傭兵はマケドニア軍から冷遇され、不満の方が強かった。当時、アケメネス朝ペルシアは、既にマケドニア軍に大敗し、ダレイオス3世は家族までも置き去りにして行方を絶っている。 イッソスの戦いは、BC333年11月に起こったアルゲアス朝マケドニア王国およびコリントス同盟の連合軍とアケメネス朝ペルシアの戦いである。この戦いはアレクサンドロス大王の東方遠征中に生じた戦いの中で2番目に大きな戦いであった。 ロドス島の出身のメムノン(BC380年~BC333年)は、ギリシア人でありながらアケメネス朝ペルシアのダレイオス3世に仕えた傭兵であった。開戦前、東方遠征を開始したアレクサンドロス3世の軍は強力だが遠征に疲れている、直接対決を避け、敵の食料補給を絶つための焦土作戦による弱体化をダレイオス3世に提案する。ペルシア側のヘレスポントス・フリュギア太守アルシテスの「我が国民の家に火を点けるなどとんでもない」、「ギリシア傭兵にとっては、戦争が長引くと報酬が多くなるからだろう」などと批判にされ、後方に配置され浮いた状態に置かれた。 前年のBC332年、マケドニアを発って東方遠征を開始したアレクサンドロスは、ダーダネルス海峡を越え小アジアに渡って、その東北部のグラニコス河の戦いで勝利した。ペルシア軍(主力はギリシア人傭兵部隊)との最初の本格的戦闘であった。『アレクサンドロス大王東征記』の著者は、アッリアノス、2世紀のローマのギリシア人の政治家、歴史家であるが、アレクサンドロス3世の東征研究の一級の史料として有名である。その著書によれば、このときアレクサンドロスは自ら長槍を取って先頭で戦い、あやうく命を落とすところであったと記されている。しかしながら、自ら馬を駆って突進し敵将ミトリダテスを投げ槍でしとめる、この時の騎乗する戦闘行動が傑出し、アレクサンドロスは味方将兵の信頼を得ると共に敵に対しては計り知れない恐怖心を与えることになった。メムノン麾下のギリシア人傭兵軍も敗走させ、イオニア地方から小アジア内部に侵入し、アナトリアの西部サルデス(サルディス)で勝利し、フリュギア地方(古代アナトリア中西部の地域名・王国名でもあった)の中心都市ゴルディオン(アナトリアを縦貫する主要道に沿う)に達した。遠征の当初の目的であった小アジアのギリシア諸市の解放は、ほぼ達成された。ギリシア軍は多大な戦利品を得た。 敗報を聞いたダレイオス3世は、「メムノンの言う通りにしていれば…」と後悔した。その後のメムノンは、小アジアでの劣勢を挽回するために軍勢の再編成に奔走しペルシア軍を立て直して、アレクサンドロス3世も迂闊に手は出せない状況を一時的に作り上げた。さらにギリシアへの反攻作戦すら計画したが、間もなくメムノンは病死した。 サルデスは、BC7世紀~6世紀のオリエント4国分立時代のリディア王国の首都であった。BC612年にアッシリア帝国が滅亡してオリエント世界が新バビロニア王国(メソポタミア地方のカルデア王国)、メディア王国(イラン高原)、エジプト末期王朝(第26王朝など)と、このリディア王国(小アジア)の四王国に分立した。サルデスは、アナトリアの最も西部のエーゲ海に面した地域、エフェリスなどのイオニア系植民都市を征服し、エーゲ海の都市と同盟を結び、その交易により巨富を築いた。BC6世紀中頃のクロイソス王(在位BC560~BC546)のころ全盛期となり、巨大なアルテミス神殿を建造した。しかし、東方のカッパドキアの領有を巡ってアケメネス朝ペルシアのキュロス2世と対立し、ギリシア中部のポーキス地方にあった都市国家の聖域デルフォイのアポロン神託にしたがって開戦したが、プテリア(ハットゥシャシュのあった地より黒海に近い地)の戦いで敗走,BC 546年頃キュロスに捕えられ,首都のサルデスも滅ぼされた。 イッソスは現在のトルコとシリアとの国境に近い平野、BC333年10月、アレクサンドロス自身が先陣を切って、ペルシア軍中央のダレイオス王に向かってと突進した。激戦の最中、またもやダレイオスは恐怖に駆られて戦場から逃走した。ペルシア人は自らの王が逃亡し、この戦いに負けたと知り、持ち場を離れて逃亡し始めた。マケドニアの騎兵は逃亡中のペルシア軍を追撃し、ばらばらに逃げ惑うペルシア軍を夜になるまで掃討し続けた。多くの古代の戦いと同様に、この戦いの後も、ギリシア人の追撃によるペルシアの虐殺が行われた。 オリエントとは西南アジアからエジプトに至る一帯の総称である。アレキサンダ-大王のペルシャ・エジプト・インドへ遠征結果、西方のギリシア文化と東方のオリエント文化双方が融合し、ヘレニズム文化が生まれた。文化の中心はギリシアから東方に移り、エジプトのアレキサンドリア、シリアのアンチオキア、小アジアのペルガモンなどが中心となった。インドのヘレニズム文化としてのガンダ-ラ美術は中国から朝鮮を経て日本に渡り、飛鳥文化を生んだ。 アレクサンドロスがギリシア防衛のために残しておいた代理統治者アンティパトロスは歩兵1万2千、騎兵1500にすぎず不利であったが、海上ではマケドニア海軍が帰順したフェニキアとキプロスの艦隊を加えて圧倒的に優勢だった。最大の焦点はアテネが反乱に参加するかどうかであったが、アテネはついにアギスの誘いに乗らなかった。コリントス同盟から離脱することは避けた。孤立したアギスの反乱は、BC330年、アンティパトロスによって鎮圧された。同BC330年、マケドニア・ギリシア連合軍4万がペロポネソス半島中部のメガロポリスでスパルタ軍と対決、スパルタ側の5,300が戦死、アギス自身も最期を遂げて反乱は終息した。 アレクサンドロスは古代フェニキアの都市マラトスに留まり直接指揮せず、海軍を派遣し、戦費を送っただけであったが反乱が鎮圧されたことで東方遠征を継続した。この反乱はアレクサンドロスのギリシア人に対する不信感を強めた。その後しばらくはギリシアでの反マケドニアの動きはなかった。 イッソス会戦後、古代フェニキア都市マラトスからーフラテス川中流域にも足を伸ばし、アレクサンドロスの渡河点に近いと思われるアサド湖付近を実地検分した。 アレクサンドロスがペルシア帝国を滅亡させた後も帰還することなく、「アジアの王」として君臨し、自ら神格化を進めると、コリントス同盟を通じてのギリシア支配は次第に空洞化が進んだ。征服地には各地に植民市アレクサンドリアを建設し、ギリシア人を入植させた。遠征後半はペルシア人など現地勢力との融合を図り、これらは東西融合政策と呼ばれるが、その実態はギリシア人の不満分子を離間させることにあった。 BC338年のマケドニアのギリシア支配から、アレクサンドロス大王の帝国が成立するBC323年、アレクサンドロス大王が急死すると、いわゆるディアドコイ(後継者たち)間の争いが始まり、複雑な混乱がほぼ終息すると、プトレマイオス朝エジプト・セレウコス朝シリア・アンティゴノス朝マケドニアの三国が建国される。この三国はいずれもギリシア人の統治者が治める国家なので、ヘレニズム三国という。アンティゴノス朝マケドニアでは、ギリシア的な統治が行われていたが、その一方では、東方のプトレマイオス朝エジプトとセレウコス朝シリアでは、いずれも専制的な統治が行われ、伝統的な神権政治と融合していった。 この三国のもとで、ギリシア文明とオリエント文明が融合して、いわゆるヘレニズム文化が形成されていく。アレクサンドロスが死んだことにより、ギリシアの反マケドニアの動きが強まったがディアドコイ戦争が展開される中、BC301年にコリント同盟は解消された。ギリシア本土のポリス経営と経済・軍事は衰えたが、アテネやスパルタは自治が許され、特にアテネは学問の中心としての活動は続いていた。しかし、次第に地中海世界の経済や文化の中心は、プトレマイオス朝の首都アレクサンドリアに移っていった。 なお、このヘレニズム時代と並行した時期に、西地中海地域にローマとカルタゴが台頭し、前3世紀のポエニ戦争で勝ったローマが、次いで前2~1世紀に次々とヘレニズム諸国を征服して、地中海世界を統一し、BC1世紀の末にローマ帝国を建設することとなる。 ポリビオスPolybius(BC203頃からBC120頃)は、ヘレニズム末期、ギリシアのペロポネソス半島の北部沿岸にあるアカイアに生まれた。当時のギリシアは北方のアンティゴノス朝マケドニア(BC306年~ BC168年)に対して、アテネ・コリントスやロードスなどのポリスや、ペロポネソス半島北部のアカイアAchaia地方のメガロポリスなどの12の弱小諸都市が結成したアカイア同盟などが連合して対立、抗争していた。 した。
第三マケドニア戦争では、ローマ軍がマケドニアを攻撃して戦争が勃発した。BC168年、ギリシアの北東部の海岸にあたる、マケドニア南部ピエリア地方の都市ピドナPydna(ピュドナ)の戦いでマケドニアに大勝した。ローマの将軍アエミリウス・パウルスは、マケドニア王ペルセウスの軍を追い詰め決定的に壊滅させマケドニア王国を滅亡させた。マケドニアは、ギリシア南部・トラキア・小アジアなどを失い、残りの領土は4つの共和国に分けられた後、ローマの属州とされた。ローマは「マケドニア支配からのギリシアの開放」を宣言し、ギリシア諸都市の自由独立を保障して、占領せずに撤退した。 ローマは莫大な戦利品を獲得したため、ローマ市民は以後、直接税を免除されることとなる。戦後の東地中海におけるローマの影響力は高まり、やがてはこの全域がローマ領となる。 なおこの間、BC202年のザマの戦いに敗れたハンニバルがカルタゴを離れ、セレウコス朝シリアに亡命し、ローマとの戦争を働きかけた。セレウコス朝のアンティオコス3世はその企てにのり、勢力を西方に拡大しようとした。それに対してBC192年、ローマはカトーCato(カルタゴ滅亡を主張したローマ共和政末期の政治家、軍人。大カトーと呼ばれ、曾孫の小カトーは、共和派としてカエサルに徹底して反対し殺された)が海軍を率いて遠征、セレウコス海軍を破り、またハンニバルの率いた海軍もロードス海軍に敗れた。 その後もハンニバルの抵抗は続いたが、ローマはBC188年にアパメアの和約でセレウコス朝と講和し、莫大な賠償金を課した。しかしこのときも征服地を領土化することなく、全軍を引き上げた。BC183年、ついにハンニバルは自殺し、その抵抗は終わった。 マケドニア戦争はBC167年のマケドニアの滅亡で終わったが、ギリシア本土にはなおも都市国家が存続し、アカイア同盟は維持されていた。アカイア同盟はマケドニア戦争ではローマを支援したが、都市の内部では富裕市民はローマとの同盟を望んだのに対して、下層市民の中に反ローマ感情が強まっていた。中継貿易で栄え、反ローマの中心となったコリントはBC146年にローマとの開戦に踏み切ったが大敗した。ローマはコリントを徹底的に破壊、マケドニアとギリシアを合わせて属州とした。この年、西地中海ではポエニ戦争が最終段階を迎え、カルタゴも破壊され、ローマの西地中海支配は完了した。 (ポエニ戦争は、BC264年のローマ軍によるシチリア島上陸から、BC146年のカルタゴ滅亡まで3度にわたり繰り広げられきた、共和政ローマとカルタゴとの間で西地中海の覇権を巡って争われた一連の戦争である。ポエニとは、ラテン語でフェニキア人を指す。カルタゴはフェニキア系国家であった。 豊かな穀倉地帯のシチリア島は西半分がカルタゴ領で、東半分がギリシア人勢力のシラクサが抑えていたが、北東にあるメッシーナはシラクサより離反したカンパニア人の傭兵部隊マメルティニが占領していた。シラクサの僭主ヒエロン2世は、マメルティニに対して攻撃を開始した。マメルティニはローマとカルタゴの両方に助けを求めたが、このことがポエニ戦争の直接の原因となった。翌BC263年にシラクサはローマと講和して同盟を結んだ。ローマはシチリア島の西部を中心として支配下に収め、BC227年にはローマは総督を置いて統治し、ローマの最初の属州とした。シチリア東部はシラクサの統治が認められていた。) マケドニア戦争の勝利とその後のギリシア諸都市の征服によって、ローマは巨額の賠償金や多数の奴隷だけでなく、ギリシアを属州として支配し、税を徴収することになった。 ローマが地中海全域を支配して「我らが海」とするのは、オクタウィアヌスのローマ海軍と、アントニウスとプトレマイオス朝エジプトのクレオパトラの連合軍が、ギリシア西北の地中海上でのアクティウム(アクティウムはギリシア本土の西岸、アンブラキコス湾の入口)の海戦でプトレマイオス朝エジプトを破るBC31年のことである。 ローマはアカイア同盟に対しては反ローマ派の主要人物を人質とすることを要求、ポリビオスもその中に含まれていた。ローマに抑留されたポリビオスは、軟禁生活中にヘロドトスの『歴史』、トゥキディデスの『戦史』などの歴史書を研究していた。偶然に執政官スキピオの知遇を得、そのギリシア語の教師となった。 ローマの将軍スキピオは、第2回ポエニ戦争でカルタゴ軍のハンニバルを破り、大スキピオと言われた。ローマはマケドニア戦争と並行して、親カルタゴ勢力を各個撃破した。このため、ハンニバルのカルタゴ軍はイ タリア半島で孤立する。ハンニバル軍は次第に補給に苦しみ、掠奪を重ねながら、なおも14年にわたり、イタリア半島を転戦したがローマを直接攻撃する戦力はなくなっていた。 将軍大スキピオは、イタリア半島でのカルタゴ軍との決戦を避け、その本拠を直接攻撃する。ローマ軍が北アフリカに上陸したため、ハンニバルは急きょ本国からの帰還要請を受け、カルタゴに戻った。BC202年、両軍はカルタゴの郊外で衝突(ザマの戦い)した。スキピオの巧みな戦術や、カルタゴ軍の内紛などからローマ軍の勝利となった。 カルタゴ軍の敗因は、その陸軍は市民兵ではなく傭兵を中心としていたことや、海軍は市民が参加したが、第1回ポエニ戦争で制海権を失ったことなどが大きな敗因となった。 その子が第3回ポエニ戦争でカルタゴを滅ぼし小スキピオと呼ばれた。将軍小スキピオ率いるローマ軍は、カルタゴを徹底して破壊、属州アフリカとして支配した。 小スキピオは、アエミリウス・パウルスの子で、大スキピオ (スキピオ・アフリカヌス ) の子のスキピオの養子となり、元老院で重視されていた名門貴族の一員になった。優れた軍人で、高潔で教養があり、ギリシア文化にも造詣深く、ギリシア文化人を招いてサークルを作り、歴史家ポリュビオスがその一人であった。 スキピオの知遇が切っ掛けになり、ギリシア人のポリビオスがローマで活躍することになる。その後彼はスキピオに従ってポエニ戦争に従軍した。小スキピオの厚遇もあって、それらの体験を通して、ローマの強大化した経緯を研究し、ヘロドトスの『歴史』やトゥキディデスの『戦史』などの歴史書を読みふけり、ギリシア語で書いた政体循環史観による大著「歴史」40巻を著して歴史家として名を遺すこととなった。 共和政ローマ時代、BC2世紀の歴史家ポリビオスがその著『歴史』のなかで展開した、一種の歴史理論によれば、ギリシア・ローマの歴史には、その政治形態において、君主政→暴君政→貴族政→寡頭政→民主政→衆愚政→君主政、という循環がみられるという。ポリビオスは歴史の中に一定の法則性を見い出し、それを政体循環史観と呼んだ。 ポリビオスの『歴史』は、ヘロドトスの『歴史』、トゥキディデスの『戦史』とともにギリシア語で書かれた歴史書の最も重要な著作であるが、失われてしまった部分が多く、全40巻中、完全な形で現存するのは第1巻から第5巻までに過ぎない。その執筆には歴史家の通念として貫かれる事実を正確に探求する歴史に対する姿勢である。 ポリビオスは政治秩序の本性が政体の循環であるとして「それによってさまざまの政体は変化し移行しまた出発点に戻る」と論じた。例えば寡頭制による専断や愚昧さを経験する人々がいる間は、平等主義や言論の自由を重要視する人々が民主制を支持するが、孫の世代になると自由と平等に「はきちがえ」が生じ衆愚を呼ぶ、やがて自由や平等の価値を大事にせず、暴力的な政体へと回帰すると言う。ポリビオスはこの観点からローマの繁栄もいずれは衰退に向かうと指摘し、時代が下るにつれ成長し栄え、やがて自然に下降していくことを見通しながら、歴史の叙述によってそれを明らかにしようと試みている。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
4)古代エジプト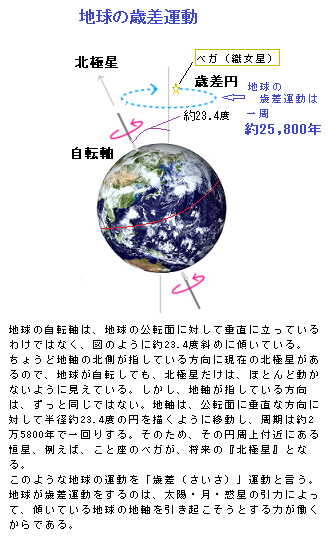 ミレトスは、クレタからアナトリアへ移住した人々を中心に、先住のカリアの人々も加わり、BC11世紀に創建された都市で、BC7世紀後半からBC6世紀にかけて、その最盛期を迎えた。カリア語Carian
languageは、鉄器時代のアナトリア半島南西部のカリアで使われていた古代語で、リュキア語と同様にインド・ヨーロッパ語族アナトリア語派に属する。カリアはリュキアの北西に位置し、ギリシア人の植民地であるイオニアと隣りあっていた。 ミレトスは、クレタからアナトリアへ移住した人々を中心に、先住のカリアの人々も加わり、BC11世紀に創建された都市で、BC7世紀後半からBC6世紀にかけて、その最盛期を迎えた。カリア語Carian
languageは、鉄器時代のアナトリア半島南西部のカリアで使われていた古代語で、リュキア語と同様にインド・ヨーロッパ語族アナトリア語派に属する。カリアはリュキアの北西に位置し、ギリシア人の植民地であるイオニアと隣りあっていた。リュキアはアナトリア南西部の地中海に面した一地方の古名、山が多く、南西の国境地帯は深い森林に覆われている。その西から北西にかけてカリア地方に接している。紀元前7世紀から紀元前3世紀にわたるカリアの碑文が残っている。 カリア本土のほかにギリシアにも碑文が残るが、エジプトのサイスからブヘン(現在はナセル湖の下に水没)にいたるナイル川沿いに170ほどの碑文が残る。その大半は短文の墓碑銘か奉納文である。ヘロドトスは、エジプト第26王朝の初代ファラオのプサメティコス1世(在位: BC663年~610年)は、イオニアとカリアの傭兵による軍事力を背景としていた、と記す。それを裏付けるように、エジプトの豊かなナイルの土壌と穀物豊饒の女神イシス像の土台には、カリア語で記したプサメティコス1世時代の碑文が残る。 エジプト第26王朝のファラオ、プサメティコス1世が在位する前の古代エジプト、 BC7世紀前半、既にオリエント世界最大の勢力となっていたアッシリアが、BC671年にエサルハドン王の下でエジプトに侵入した。第25王朝のヌビア人の王タハルカは戦いに敗れ根拠地であるヌビアへと追われアッシリアのエジプト支配が始まった。 エジプト 古代王国 サハラ砂漠は、南極を例外とすれば世界最大の砂漠、それが、9000年前から6000年前の「アフリカ湿潤期」には、なだらかな草原が広がり、アカシアの木など森林もまばらにあり、緑の大地が広がっていた。サハラ一帯には、多くの湖や川が散在し、多くの動物たち集まり、泳いでいる人々も居た。それを岩に描いた絵画が発見されている。 およそ25,800年周期で発生する地球の歳差運動によって地球の自転軸が回転して、5000年ほど前に降雨地域がサハラより南に移動したため、サハラが乾燥し始めた。そのサハラが砂漠化するのに僅か数百年程度しかかからなかった。 サハラに住んでいた人々は、砂漠化から生業を奪われ、海岸部や南へと移動して新たな定住社会を模索した。 リビアや地中海沿岸の各地から、またアフリカ内部からも、生活に必要な水を求めて、特に大三角州地帯などナイル河流域に人が集中しはじめるようになる。 エジプト 初期王朝時代 (第1~2王朝)(BC3000~2650頃) 上エジプトの農耕牧畜文化の発展の過程で、集落の膨張による階層化が進み、支配構造が分化していった。この流れが加速すると、集落間の競合による大集落の中小集落に対しての併合や収奪が激化した。やがて、大集落の都市化とそれを中核にする広域的な地域統合が始まり、王が誕生する。上エジプトでは、ヒエラコンポリスと、その北の勢力の中心がアビュドス(アビドス)、この2大都市に統合されていた。 この時代から上級支配者層の権力が強大になり、支配層は中小集落や従属者に対する威信財として舶来品やその模倣品を使った。エジプト国内には、金・銅・ざくろ石・水晶・アラバスターなど鉱物資源が豊富で、西アジアへの交易拠点となる港湾設備を、地中海により近い下エジプトに作った。この時期に下エジプトにも、独立した政治勢力があったようだが、ただ上エジプトからの植民地も置かれてあったので劣勢のようだ。 最終的に、ヒエラコンポリスとアビュドスの2大都市が地域統合を行い、アビュドスの王ナルメルが、初めてのエジプト統一王朝の初代の王になる。 ナルメル王のパレット(陶片)の裏面の中段には、上エジプトを象徴する白い冠(ヘジェト)を被っている王が武威を振るう姿を捉えている。棍棒を振り上げるナルメルに、膝を折り髪を鷲掴みにされている人物は下エジプトの人物のようだ。その右にあるヒエログリフは、「銛」と「オアシス」を表す。カイロから南西に130km離れたファイユーム・オアシスの支配者ではないか。ナイル川の支流が流れ込むエジプト最大の塩湖・カルーン湖の近くで、現在でも肥沃な農地と豊富な水に恵まれ、綿花や小麦などの集散地となっている。古王国時代から、既に半農半牧ないし半漁で定住が可能であったと考えられる。 この棍棒を手にして敵を打ち据える王の姿は、その後3000年にわたって繰り返し神殿などで描写される王のモチーフとなっている。ナルメル王の 目の前のヒエログリフ(聖刻文字)には、上エジプトの王ナルメルの化身ハヤブサ(ホルス神)が、下エジプトを象徴するパピルス(カミガヤツリ)の生えた人物を鼻フックすることによって、上エジプトの王が下エジプトを征服したことを表す。その背に生えるパピルスの花は、1000という数を表す。それが6本生えているので、6000人を捕虜にしたことを示す。 パピルスはエチオピアの河川流域が原産で、川や沼の縁の湿地に生える、高さが2~3mの背の高い水草。BC3000年頃、ナイル川デルタ地帯の浅瀬湿地帯で刈り取り、その繊維を紙の原料とした。古代エジプト文明で生まれたヒエログリフは、その紙に書き記された。メソポタミア文明での楔形文字は粘土版に彫るのでパピルスは用いなかった。paper の語源となった。 その下段には逃げ惑う二人の人物が描かれている。髪型から土着の民のようだ。それぞれの顔の左側に異なる絵文字が書かれている。左は「都市の周壁」、右はナイル川の西側に居たベルベル人の素朴な神殿と考えられる。ベルベル人は何千年も前からナイル川左岸で半農半牧や遊牧専従を生業としていた。モロッコのおよそ半数がベルベル人で、アルジェリア・チュニジア・リビア・エジプトにかけて広く分布するコーカソイド系住民である。元々、ネグロイド系との混血を重ねている。  BC3000頃、上エジプト出身のナルメル (メネス)が上下エジプトを統一し、初期王朝時代(BC3000~BC2686頃;第1~2王朝) の第1王朝を創始しファラオとなった。都を上下エジプトの境界に近いメンフィス(現在のミート・ラヒーナ村付近にあった)を国都として建設した。 2012年に、先王朝時代の王イリ・ホルがメンフィスを訪問していることを描写した碑文がシナイで発見された。イリ・ホルはナルメルよりも2代前の王である。ナルメルはこの都市の創設者ではなく、国都として再開発した初代の王である。 メンフィスは、古代の地中海の歴史を通じて重要な都市であり続けた。メンフィスはナイル川河口付近のデルタ地帯という戦略的要衝に形成された都市であり、各種の社会生活の拠点として栄えていた。メンフィスの主たる港であるペル・ネフェル(Peru-nefer)には数多くの工房・工場・倉庫が並び、王国全体に食料・商品、嗜好品を流通させていた。その黄金時代の間、メンフィスは市場・貿易・宗教の地域的中心地として繁栄した。 カイロの南にある現代の居住地であるミート・ラヒーナ、ダハシュール、アブシール、アブ・ゴラブ、そしてザウィト・エル・アリヤーンなど市街地全てが、メンフィスの行政区分の内部にあった。 マネトによって記録された伝説では、最初に上下エジプトを統一したファラオであるメネスがナイル川を堤防で迂回させ、ナイル川沿いの地にメンフィスを建設した。ギリシア人の歴史家ヘロドトスも同様の内容を残している。彼自身が残した記録によればヘロドトスはペルシア人の支配下にあったメンフィスに滞在しており、ペルシア人はナイル川の堤防に特に注意を払っているので、この都市は毎年のナイル川の洪水から守られているのだと記している。 メンフィスが統一エジプトの最初の首都であることは疑いないが、エジプトは恐らく互いに必要性に駆られて統一され、文化的な繋がりや貿易関係が強化されたのだとされている。王国統一以降も、下エジプトの文化は殆ど無傷のまま生き残り、歴史時代のエジプト文化に貢献している。ナルメルによる政治的支配は、下エジプトの文化の抹殺にまで及ばなかった。その背景には下エジプトの文化は、上エジプトより優れ、社会構造も進んでいたという。ナルメルのエジプト王国の統一は、単なる征服ではなかった。国都を下エジプトの境界に近いメンフィスに移し、下エジプトの経済的な優位性をナイル川に堤防を築きより発展させた。多くのエジプト学者達は、メネス王を歴史上実在が確認されているナルメルと同一人物であると考えている。 メンフィスは古王国時代を通じて首都であった。この都市は第6王朝の下で、創造と芸術の神プタハの信仰の中心として、都市の威信においても頂点に達していた。プタハ神殿を守るアラバスター(大理石に似て古代の方解石のものは硬度は3で硬い、白い半透明で縞目がある石)製のスフィンクスはこの都市のかつての権力と威信の記念碑となっている。 メンフィスはエジプト統一の第1王朝当時は、イネブ・ヘジュ(Aneb-Hetch、Ineb-Hedj)と呼ばれていた。「白い壁」という意味である。王宮が石灰岩の壁で囲まれていたからだと言う。現在のミート・ラヒーナにあるメンフィスの遺跡は新王国時代のもので、初期王朝時代の王都はその西にあるメンフィスのネクロポリスであったサッカラ北部にあった可能性が高い。このかつての首都の遺跡は、ギーザのピラミッド群と共に世界遺産として1979年から保存されている。 メンフィスは、最終的にナイル川のデルタ地帯で、地中海沿岸に形成された都市であるアレクサンドリアの発展によって、古代末期にその経済的重要性を喪失したために消滅したと考えられている。 ヒエラコンポリスのホルス神殿で発見されたナルメル王のパレットは「エジプト文明の始まり」を語る時には欠かせない特別有用な遺物の一つ、ヒエログリフhieroglyphsで描かれている。聖刻文字ともいう。ギリシア語の「聖なる」 hirosと「彫る」 glūphoがこの名称の由来である。絵文字の原形をほぼ完全にとどめる象形文字で、主に碑銘に用いられている。極めて具象的で、1字1字の構成は古代エジプトの伝統画法と完全に一致し、木面や石面に入念に浮彫りするため、壁画として併用された場合、その記録性とともに美的・装飾的効果に優れ、エジプトの遺跡では多く採用されている。石製・陶製・金属製などに彫られた生命・安定などを意味する文字は、護符にもなった。古代エジプト文字の一つヒエログリフは、その起源はBC3100年頃に遡り、AD4世紀末まで使用されていた。 19世紀のフランスの古代エジプト学教授ジャン=フランソワ・シャンポリオン(「古代エジプト学の父」)が、初めて解読に成功したヒエログリフは、象形文字と呼ばれるように絵が彫られるが、実際は、表意文字よりも表音文字の方が多い。表意文字の音を借りることもある。漢字で言う仮借の場合、表音文字では通常母音は無視され、子音だけが利用される。 『仮借』とは、ヒエログリフと同様、象形文字を起源とする漢字では、同音の漢字を借りて当て字とし、アジアを「亜細亜」と「音」で表記する。漢字の場合、むしろ象形が仮借され、元の本義に加えて偏などの部首がつけられ、形声文字になる方が多くなる。「羊」が「洋」に、「然」が「燃」に、「者」が「煮」になるなど様々で、日本の漢字の85%近くが形声文字である。より表現力が豊かになる。 材質はシルト岩、神殿への奉納用化粧板のため、63cm×42cmと大きく作られている。上下エジプトのシンボルを示すナルメルの姿が浮彫線刻されており、これによって、ナルメルが上下エジプトの統一者であることが知られる。 パレットの最上段の、裏表両面の絵は同一である。上に出張っている左右の図像、角が生えた人面はバト神とハトホル神の2神のようだ。両者とも先史時代から崇められていた雌牛の神である。その2つ彫刻は明らかに表現が異なり、左端の牛神は右端の牛神より小さい。パレット画は上位の者を、より大きく浮彫する。 多神教であった古代エジプトでは神の相互間で、神格に差がある。その神の間に四角い囲いはセレクと呼ばれ王宮を表している。この中のある図像が王名を表す。ヒエログリフ(聖刻文字)で王名が浮彫されている。 バト女神は、後にハトホル女神に吸収され、その一部となった。ハトホル女神は多数の「母なる女神」の集合体であり、もともとは一般名称だったとも考えられている。 ホルスHorusは、古代エジプトの天空神、王権の守護神であり、ハヤブサまたはハヤブサの頭をした人物として表現される。滑空するハヤブサの背景の天空、日月はその両眼とされ王を見守った。王国を統一する上エジプト王と結びつき、王はホルスの化身とされ、神王理念が形成された。パレット内の四角い囲いはセレクと呼ばれ王宮を表している。その中央に浮彫される、王名の先頭に必ず『ホルス』のヒエログリフ、その頭上にはハヤブサを頂く。王権の守護神で、自身もホルスの化身と考えたファラオは皆「生けるホルス」の称号を持つ。 古代エジプトには地方ごとに様々な神が存在し、力の強い地域の神が神話的権力を持つことがよくある。歴代のファラオの多くは、このホルスに憧れを抱いていた。死後は我こそがホルスになる存在だということを信じていた。 太陽神ラーの顔はハヤブサ、ハヤブサの頭を持った鳥頭人身の姿で描かれる。頭上には太陽を象徴した円盤を乗せている。これが神々の頂点に立つ。ここのハヤブサの頭をもつラー(ラーアトゥム)の子『ホルス』は、天空と太陽の神である。そのホルスの目が上部に描かれている。『左目は月の象徴』、右目は『ラーの目・太陽の象徴』とされている。 壁画に描かれたホルス=ファラオには、ハヤブサの上にラーの目が描かれた壁画となる。古代エジプトのファラオの多くは、我こそがホルスの化身、政治を司る神、死後は我こそがホルスとなると神権思想に立っていた。 古代エジプトの初期では、イシスではなくハトホル女神がホルス神の母親とされている。つまり「母性」こそがこの女神の最初の本質であった。やがて天神ヌトと地の神ゲブの娘イシスが、古代エジプト宗教の最高の女神となり、兄オシリスの妻となってホルスを生む。 有名なエジプト初期の王、ナルメル王のパレットには、ハヤブサ(ナルメル)の姿と、それを見守るように上部に描かれた牛(ハトホル女神)の顔が刻まれている。 2つの雌牛の神の間の図像は、典型的なヒエログリフ(聖刻文字)で、上がナマズ、下が大工道具のノミを表している。これらはそれぞれ「ナル」「メル」と読めるため、この王はナルメルと呼ばれる。 また、パレットとは化粧用のパレットで、縄に括られた二匹の豹の長い首が円を描いて交差する中央の窪みが化粧用の顔料を磨りつぶす所で、こちらがオモテ面ということになっている。上下エジプトの統一をモチーフにするよだが、対峙する豹の面構えは険悪だ。 その上の表面の2段目は、侵略するナルメル王の本営を浮彫している。一番大きく描かれているのがナルメルの額の前にナルメルのヒエログリフがある。裏面と同様の儀礼用の装いで、例の棍棒も左手に握っている。ただ冠が違い、下エジプトの王の象徴である赤冠被っている。赤い王冠が下エジプト、白い王冠が上エジプトの王冠であり、合わせた上下エジプト王冠が上下エジプト両国の王冠を示す。つまり、下エジプトの王として描かれている。その前方の右端には、2列に横たわる10体は、ナルメル軍が倒した下エジプトの首のない死体である。それぞれの股の間に斬られた首が置かれている。ナルメルの名は、ナマズ(ナル)と鑿(メル)の象形文字によって表される。慣習的にも「ナルメル」と呼ばれる。ナルメルは「荒れ狂うナマズ」という意味である。その本領が発揮された。決して平和裏に平定が行われたのではない ナルメルの前の豹柄の服を着た人物が、首からぶら下げているものは筆記用具だと言う。頭上のヒエログリフは、チェトあるいはチャティと読む。宰相を表す。その宰相の横で、4人が高々と掲げる旗竿は、右の2本は、ハヤブサがてっぺんに止まっているので王家のもので、左の2本は王に服属する上エジプトの大集落や部族の旗で、下エジプトへの侵掠を物語る。 この浮彫が古代エジプトの基本的な美術様式となる。二次元表現で首から頭部にかけては側面図にし、人体を正面図にする組み合わせで描く。また実際の身体上の大きさに関係なく「地位の高低」が人物の大きさで表現される。また場面ごとに段を区切り、人物像は地面を現す線の上に描かれるなど、その表現方法が既に初期王朝時代に確立した。 さらに表面の4段目では、王の化身である雄牛が、その角で町の周壁を壊し逃げ惑う人を踏みつけている。下エジプトの都市国家を、ナルメルが蹂躙する象徴的な構図である。古王国時代のエジプトの総人口は、約120万人、農村人口は114万人程度、平均的な集落の人口は450人くらいであったという。つまり都市部の人口は全体で6万人程度、都市の数と都市ごとの人口は少なかった。その少数の都市こそが文明の牽引役になっていた。 先王朝時代末に王を戴く都市、アビュドスやヒエラコンポリスなどが出現したが、古代エジプト研究者はこれらを「都市国家」と呼ばない。その未発達ままエジプトの領域国家が形成されたからである。 当時のエジプトの都市の人口も、同時代のメソポタミアなどの他地域や、その後のエジプトの他時代と比べてもかなり少なかった。先王朝時代黎明期のエジプトはいまだ人口が比較的少なくて、各地の都市が未発達のままであったため、貧弱な武器と装備と兵力で「領域国家」の形成が実現できた。これが、広いナイル河流域を支配する「領域国家」が早期に出現した要因であるという。 先王朝時代では、外敵を防ぐ周壁に頼る集落は今のところ発掘されず、初期王朝に入ってから初めて作られたエレファンティネが初見となる。メソポタミアの初期王朝時代では、複数の都市国家がそれぞれの民族意識を共有することで形成された。エジプトでは、初期王朝時代によって領域国家の建設で達成された。 パレスチナ(地中海東岸、東はヨルダンに接する「ヨルダン川西岸地区」と、西を地中海、南をエジプトに接する「ガザ地区」に分かれている)では、BC3500年頃から初期青銅器時代の文化が普及し、レヴァントで既に都市化が進行していた。意外にも、この地の初期青銅器時代から、南パレスチナにエジプト人が住み始めていた。エジプト製土器とパレスチナ製のエジプト様式の土器が共伴して出土している。それ以外にエジプトの王名が記された土器、エジプト様式の印章および印影を持つ粘土封、エジプト風の日乾レンガ建造物が発掘されている。南パレスチナの遺跡やシナイ半島の遺跡から、エジプトの王名を刻んだ土器やエジプト様式の円筒印章と印影をもつ封泥が出土するため、遅くとも第1王朝開闢頃にはエジプトの王たちの管轄下で、交易が組織的に行われていたという見解が優勢である。 ナルメル王治世の頃をピークとして、第1王朝前半ジェル王治世の頃にパレスチナにおけるエジプトの影響は急速に低下し、ほぼ同時にパレスチナの人口の一部が遊動化して、社会構造に大きな変化期が訪れた。その理由はわかっていない。一方、下ヌビアでエジプトと緊密な関係を保ちながら生活していたヌビアAグループ文化の人々は、ほぼ同じ頃にナイル河流域からほとんど姿を消した。 ナカダ文化は先王朝時代の中核となる文化であった。上エジプトでナカダ文化が現れたときは、まだ農耕牧畜文化の中で比較的平等に生活が営まれていた。古代エジプト史では、先王朝時代の後に初期王朝時代が来る。ナカダ文化は約千年続くが、定住がほとんど見られない状態から統一王国になるまでの時代区分でもある。やがて支配層の階層化が進んで、重層的に分化していった。 この流れが加速するその一方で、今度は集落間でも階層化が始まった。つまり大集落が中小集落を支配するようになった。大集落の都市化と地域統合が始まり、王が誕生した。やがて上エジプトでは、ヒエラコンポリスとアビュドス(アビドス)の2大都市に統合される。一方、下エジプトにはマアディ・ブト文化という、ナカダ文化と時期的に並行した文化が存在していたが、ナカダ文化と比べると階層化が進まず平等社会のままだった。 先王朝時代のナカダ文化期頃に、マアディ・ブト文化の生産性が高まる。土器や石器に次いで豊富に出土する、当該期 の石製容器には、ナイル川下流域および東部・西部砂漠から産出する多様な石材が用いられた。最も入念に石製容器が作られたのは王朝時代直前で、轆轤も回転砥石も使わず、薄く正確に成形し、ざくろ石を粉末にした金剛砂で磨き生地の美しさを出している。特にメソポタミアやエジプトには、専業の石細工師が製作していた。それ以前に、北メソポタミアでは大理石・方解石などの白色系の軟らかい石を加工して容器をつくる風習は新石器時代からあった。シュメール文明が形成されるころには、石製容器の製作を専業とする工人が都市のなかに現れる。シュメール人の都市国家は、BC3800年頃に突如としてこの地に現れ、そのメソポタミアでは、既に、BC3500年頃に轆轤が開発されていた。 南米も文化が芽生えてからでも数千年の歴史があるのに、インカ時代に入っても『轆轤』は発明されなかった。軸対称の陶器を粘土で成形するのに、轆轤は如何にも有効である。ガラスもまた発明されなかった。インカの末裔はガラスの鏡に驚き、その低コストを見抜けず、物々交換で大量の金を失った。 エジプトの石製容器は、BC3 千年紀初頭から、主として副葬用に製作され奢侈品あるいは 威信財が多かった。初期王朝時代という 統一国家が形成された時期と同じくして、石製容器の急増が、王墓および高官墓への副葬品と重なる。この文化はやがて、ナカダ文化に呑み込まれた。 上エジプトの南端はアスワンハイダムで有名なアスワン(シエネ)で、ここが第1急湍(きゅうたん;急流部)になっていて、その南はヌビアと呼ばれる。ナカダ文化と対応するこの地の文化が「ヌビアAグループ文化」と呼ばれている。Aグループ文化の生業は、農耕・牧畜・狩猟・採集・漁労を組み合わせたもので、おそらくエジプトと同じようなナイル河の沖積低地と増水を利用した穀物栽培が行われていたと推測される。栽培種と思われるエンマー小麦(小麦の中で最も古い品種、高栄養価)と大麦、豆類が出土している。ヌビアの沖積低地の幅が狭いため、エジプトほど規模の大きな沖積地農耕は行われていなかったようで、集落の規模も小さかった。 ヌビアは、エジプト南部からスーダン北部にかけてのナイル川流域、一般的にアスワンの第1急湍から南の第4急湍付近までを指す。金や木材の産地として、アフリカ奥地からの貢納品の中継地として、また多くの傭兵を供給地として、古代からエジプトにとって経済的にも軍事的にも重要な地域であった。下流のエジプト領の下ヌビア(古代名ワワト)と上流のスーダン領の上ヌビア(古代名クシュ。スーダン北部からエジプト南部にまたがるナイル川流域の地名)からなり、下流方向にあたるエジプト南部の下ヌビアにはアブ‐シンベルの神殿がある。 エレファンティネ島はナイル川の第1急湍を構成する無数の島や岩礁の1つであり、当該第1急湍の北端にあたる。古代エジプトの地理概念ではエレファンティネ島が上エジプトの南端であり、島の南端部には、主に新王国時代に建てられたクヌム神殿遺跡やナイロメーターの遺跡がある。 第一急流を越えてナイル川を遡るとそこは「ヌビア」と呼ばれる地域であった。下ヌビアの人々とエジプト人との関係について、第1王朝開闢前後から両者が敵対的になり、戦闘が起こったことが、ゲベル・シェイク・スレイマンの岩壁画やアハ王のラベルの記述から知られている。第1王朝初期に両者の国境地帯に位置するエレファンティネに城塞が築かれたことも、ヌビア人との敵対的関係を示唆する。 フェニキア人は、ユーフラテス川上流に定住し内陸交易を担ったアラム人(BC1200年頃から西アジアのシリアのあたりに定住し、統一国家を作ることなく、内陸部の陸上交易に活躍。ダマスクスはアラム人が建設した都市)とよく対比される。アラム人がラクダによってシリア砂漠などで隊商を組んで交易をしたのに対し、フェニキア人は航海に長じて海上交易で活躍した。フェニキア人の根拠地は、東地中海南岸、現在のレバノンあたりで、BC3000~BC2000年頃、地中海東岸中部にビブロス・ベイルート・シドン・ティルスなど多数の都市国家や植民市を建設した。フェニキア人は当時、根拠地のレバノン山脈全域に繁茂していたレバノン杉(現地に自生する樹木はスギではなくマツに近縁な種)を使って、地中海の交易活動に進出した。レバノン杉は、高さが40mほどにまで生育する。現在ではほんのわずかしか残っていない。レバノン杉は、フェニキア人のように交易に従事する人々が船材や建材にするため伐採した。さらにフェニキア人の特産品として、ミュレックスと呼ばれる貝から取れる赤紫色の染料(貝紫)を特産としていた。この染料で染めた織物も有力な商品となった。他にも、高度な技術を身につけた職人が作り出す象牙や貴金属、ガラス細工などがあり、フェニキア人がもたらす品物は垂涎の的となった。やがて、カルタゴなどいくつもの海外植民市を建設して、地中海沿岸各地を経て遠く北ヨーロッパやイギリス、さらに遠くサルガッソー海までも航海していた。フェニキア人は貿易と海運で地中海を席巻した。しかしBC3千年紀から北メソポタミアに起こり、BC9世紀~BC8世紀に、鉄製武器・戦車などの兵力で優位になり内陸で勃興してきたアッシリアに征服され、フェニキア地方(レバノン)の諸都市は政治的な独立を失っていった。 ナルメルが実在したという物証が多数ある一方で、現在のところ、メネスの名はマネトの王名表や伝承にしか登場していない。 マネトはエジプト人で地元の神官であったが、その時代のBC300年以降は、プトレマイオス朝(BC305年~BC30年)の時代であり、アレクサンドロス3世(大王)の死後、そのディアドコイ(後継者)となったラゴスの子プトレマイオス(1世)によって建国された。そのマケドニア人のプトレマイオス1世・2世に仕えたためギリシア語で著作を行った。また、エジプトの神官としてヒエログリフも解読できたようで、その能力が著作に生かされたとみられている。 当時、世界最大にして最重要な「アレクサンドリア図書館」は、ムセイオンmouseion(museum の語源だが、学堂として発展した)の付属機関であった。ローマ支配下でも存続したが5世紀初め、アレクサンドリアの総主教キュリロス自ら率いるキリスト教徒による学者の虐殺を伴う弾圧によって、サラピス寺院やアレクサンドリア図書館、他教の記念碑や神殿を破壊し尽した。マネトの著作も現存しておらず、断片部が引用される著述で伝わるだけである。 エドワード・ギボンの『ローマ帝国衰亡史』に、「四旬節のある日、総司教キュリロスと一団の修道士達が、馬車を馭して自分の教えている学園に向かっていたヒュパティアを馬車から引きずりおろし、教会に連れ込んだあと、彼女を裸にして、カキの貝殻で生きたまま彼女の肉を骨から削ぎ落として殺害した」と記している。キュリロスと修道士達は、アレクサンドリア市当局に金品を贈り、ヒュパティア殺害に関する公式の調査を中止させた。 ヒュパティアは、東ローマ時代のエジプトで活動したギリシャ系の数学者・天文学者・新プラトン主義哲学者であった。 「考えるあなたの権利を保有してください。なぜなら、まったく考えないことよりは誤ったことも考えてさえすれば良いのです」、「真実として迷信を教えることは、とても恐ろしいことです」という彼女の言動が、キリスト教徒を激怒させと言う。 彼女の著述は残されることはなかった。既に、370年代には、サラミス主教エピファニオスEpiphaniosの著書『バナリオン(ギリシア語で薬箱の意)』で異端と同様ギリシア哲学も攻撃するようになていた。エピファニオスは、403年に死去、その後、聖人の列に加えられた。 今日では、王名は発掘された碑文を解読して得られたものから使用されている。マネトの王名表の王の名や在位は、アビュドス(エジプト初期王朝時代の王の埋葬地)などに残され、19世紀に解読された碑文の王名表とは一致しない。しかし、マネトが残した王朝の区分は現在でも、そのまま使用されている。 ナルメルの妻は、下エジプトの王女ネイトホテプと考えられている。彼女の名が刻まれた碑文がナルメルの後継者であるホル・アハやジェルの墳墓から発見されていることから、彼女はホル・アハの母もしくは妻だったのではないかと見られている。 ナルメルの墳墓は、アビュドス地方のウンム・エル=カアブ(エジプトの第1王朝の王のネクロポリス;墓地)で発見された。ナルメル王の墓は比較的小規模なもので、2つの連結された玄室(棺を納める部屋)がある。第2代アハ王からは大規模化した。地上建造物は残っていないが、第3代ジェル王から基本構造が規格化し、玄室を低いマウンドで覆い、それを日乾レンガで直方形にして覆い、さらにそれより大きなマウンドで覆っている。 第1王朝8代の王たちの墓は見つかってはいるが、発見されているのは いずれも地下構造のみであり、初期王朝時代にはピラミッドの建造は無かった。最古のピラミッドは第3王朝の初代ジェセル王の王墓である。 BC1720頃 エジプトの政治的混乱に乗じてアジア系民族ヒクソスが、デルタ地域に第15王朝を樹立した。エジプト史上初の異民族王朝が開かれる。BC1565頃、エジプトから第15王朝のヒクソスを追放し、イアフメス王がテーベに第18王朝を樹立する『新王国時代』が始まる。古代エジプト文明の最盛期となる。メンフィスは、テーベ市の勃興と共に政治的中枢としての機能を失った。 BC664、プサメティコス1世、第26王朝を樹立し、都をサイスに置く。アッシリアがエジプトを征服した後、エジプトの管理を委ねられたサイスの王家による王朝(サイス朝)を指す。 BC525、アケメネス朝ペルシャ王カンビュセス2世がエジプト(エジプト第26王朝)を征服し、ペルシャ帝国によるエジプト支配による第27王朝が始まる。事実上アケメネス朝の属州(サトラペイア)であり、総督の居館はメンフィスに置かれた。アケメネス朝の君主たちも古代エジプトを征服した後にはファラオに即位している。 プトレマイオス朝エジプトは、BC304年、アレクサンドロス大王の部将で、ディアドコイ(後継者)の一人となったプトレマイオス1世が建国した。都はアレクサンドリアで、ヘレニズム文明の中心地として栄えたが、次第にギリシア的な要素は薄くなり、プトレマイオス家の王もギリシア人の王としてではなく、エジプト伝統のファラオとして君臨し、オリエント的な専制政治を行った。 アレクサンドリアはローマ帝国の統治下、最も重要なエジプトの都市であり続けた。メンフィスはフスタート(アラブ人の統治下となったエジプトにおいて、初めて首都となった都市)がAD641年に建設される頃には市街の大部分が放棄され、石材は周囲の集落で再利用された。それでも、12世紀頃まで堂々たる遺構が残されていたが、間もなく広大な敷地に建物の残骸と散乱した石が広がるだけの大地となった。 オシリス神は、「太陽の都市」ヘリオポリス( カイロの北東郊外にある古代エジプトの太陽神信仰の中心地、ギリシャ人によって名づけられた。ギリシャ語で「ヘリオスの町=太陽の町」という意味)の神殿の神学者が入念に作り上げたことで、神話の中心となった。太陽信仰の神殿が建てられ祭司団が形成されたのは、初期王朝時代第1王朝期の、BC2350年頃にさかのぼる。古代エジプト名はイウヌウ。 【亡き父オシリスが冥界を支配し、息子のホルスが現世を支配した】 新たな神話の創設により、エジプトの神聖王権が確立する。 ナイル川流域にBC3000頃、世界最初の統一国家が形成され、強大な王権を持つファラオのもとに、初期王朝時代・古王国時代・中王国時代・新王国時代の4期に分けられる王朝支配が続いた。 【古代エジプトのファラオにとって、死は新たな人生への始まりでもあった】。 中王国以前は、復活を許されていたのは「王達」だけで、死者となった王は、本来、現世に蘇ると信じられていた。死者の蘇り信仰が始まってから千年も経過するが、人々は、過去の誰も、蘇ってこないことに気がついた。戦乱の時代が続き、荒廃した国土を救うはずの王達が蘇らない。民衆も不満不信を抱くようになった。 エジプト神話において、死から復活するのは神々の王オシリスである。死することは、このオシリスと一体化することであり、一度死してからまた復活するというのは、オシリスの復活をなぞることであった。神話によれば、エジプトで最初のミイラはオシリス神、ミイラを作ったのはアヌビス神である。オシリスが復活したように、王たちもまた、蘇ることが出来るだろう…。ミイラには、そのような願いが込められていた。やがて、この神話になぞらえられ、蘇ることが出来るのは、王と、王に匹敵する権力を有した者達に拡大する。 初期王朝時代末期頃から中王国時代頃にかけ、マスタバMastabaと呼ぶ日干し煉瓦を台状に積み上げた長方形の大きな墳墓が古代エジプトで建設された。長方形を基本とし、大きなものは長さ60m、幅3mほどの規模があり、古い時代の基本的な貴人の墓の形体であった。マスタバとはアラビア語でベンチを意味し、その外見の特徴から呼ばれた。時代・身分・地方により形式や用材などは様々であるが、基本的に、地上の礼拝堂と地下の埋葬室の2つの部分よりなり、埋葬室は地下の玄室で、それを結ぶ深い竪坑または階段でできている。玄室の壁面には、主にファラオかその家族の日常生活などが、沈み彫り sunk reliefされ彩色が施され、それが古代エジプトで多用された技法で、背景部分を掘り下げないため、人物との段差が生じ背景から沈んで見える。 死後の世界も同様と考えるエジプトの死生観を反映し、最古のマスタバはサッカラ遺跡(メンフィスの住民がネクロポリスとして使用した場所)の初期王朝時代の2代目アハの王墓で、地上部分が広く食料などの貯蔵室となっている。後の墓では地下部分が拡張され貯蔵品はそこに納められた。死者の住居として家の機能や構造が備わり、いくつもの部屋が用意されたものもある。 大型のマスタバになるとトイレや召使の部屋、さらにはハレムなどが併設されているものもある。一部のマスタバには付属して船用の囲いが建設されている。死後に船旅を楽しむつもりか?新たに奴隷と兵士とレバノン杉の調達のため遠征の準備なのだろうか?王のマスタバの周囲には恐らくはその家臣と思われる人々の付随的な墓を伴うこともある。マスタバは後世まで盛んに造られた。ギーザやサッカラなどでは、貴族や重臣のマスタバが、生前の王に仕えていたときのようにピラミッドの周囲に整然と配置されている。それは殉死した人々なのだろうか? エジプト 古王国時代(第3~6王朝)(BC2650~2180頃) ①古王国時代第3王朝 古王国時代(BC2650~2180頃)の第3王朝にピラミッドの建造が始まる。その第3 王朝では階段状のピラミッドであった。 古王国時代第3王朝になると、この時代の王碑文などが数多く発見されるようにる。この考古学的史料で知られている第3王朝の最初のファラオと、マネトの記録や他の王名表の記録とは殆ど一致しない。考古学的に知られる最初のファラオはサナクトである。サナクトに関する史料は少なく即位の経緯や統治について詳しくはわかっていないが、彼はエジプト古王国時代(BC3000年~2650年頃)第2王朝のカセケムイの娘と結婚することでファラオとなるに相応しい地位を得た。 サナクトの王名は、シナイ半島の南シナイのワディ・マガラ地域の岩碑にレリーフされた破片が見つかっており、トリノ王名表にも存在することから実在は確実視されている。即位順が不明なため年代を特定できないが、トリノ王名表では18年の治世が記録されている。 シナイ半島でレリーフが出土したのも、先王朝までの王たちが、シナイ半島で採れる銅とトルコ石を確保するため遠征したためである。征服したシナイ半島の領地から採れる鉱石は、この王朝から始まるピラミッドなど大規模な建造を可能にした。 シナイ半島から見つかったレリーフの王は二重冠ではなく赤冠を身につけている。この王朝の王たちは下エジプトのメンフィス出身のためか、下エジプトの王権の象徴である赤冠をかぶるレリーフが出てくることが多い。 (『トリノ王名表Turin King List』とは、古代エジプトのファラオの名を記したパピルス文書である。新王国時代(第18~20王朝;BC1570年~1070年頃)第19王朝のラムセス2世の治世(BC13世紀)に制作されたと考えられている。イタリア・トリノのエジプト博物館で発見されたため『トリノ王名表』と呼ばれ、現在もトリノのエジプト博物館に保管されている。 パピルスの冒頭部分および末尾は散逸しており、その他にも欠損部が多く全貌は明らかになっていないものの、表には王の名前と在位年数が記されており、中には在位月数と日数まで詳細に記されている。他の記録には表れないような短命の王・小領主についても記述されている。その殆どは、BC3世紀の古代エジプトの歴史家・神官であるマネトが、ギリシア語で著述した歴史書『アイギュプティカAegyptiaca(エジプト誌)』と整合している。 マネトはBC300年頃のエジプト人で、プトレマイオス朝に仕えた神官だったと考えられている。エジプトの王朝の時代区分は、BC3世紀にエジプトの神官マネトによって著された『アイギュプティカ』に基づいている。彼はプトレマイオス2世によってエジプトの全王朝の歴史を書くように命じられ、当時の神殿に残されていた記録と王の名簿を調査して、現在のエジプト史学者にまで参照される史書を作成した。その著書は現存しておらず、引用によって断片的に内容が知られているのみである。 19世紀になってエジプトの古代のヒエログリフやヒエラティックhieratic(神官文字;ヒエログリフを簡略化した行書体で、主として行政文書・書簡・文学作品に使用された)が解読されるまでは、ヘロドトスとマネトが古代エジプトのほぼ唯一の史料だった。ヘロドトスは第26王朝のことを詳しく記している。 現在、王名は発掘された碑文を解読して得られたものが使用されている。マネトの王名表の王の名や在位は、アビュドスなどに残された碑文の王名表とは一致しないが、マネトが残した王朝の区分は、現代でも、そのまま使用されている) その次のファラオがジェセルである。マネトの記録した王統はあまり正確ではないが、そのトソルトロス(マネトとは、ジェセルZoserをギリシア名のソルトロスTosorthrosと記した)に関する記述は明らかにジェセルと重なる。ジェセルは第3王朝では、最も功績が大きいファラオであり、側近のイムヘテプは有能な高官であった。イムホテプは、太陽信仰の本山であるヘリオポリスの上級祭司であったときに、ジョセル王に登用された。 階段ピラミッドの出現は、王がヘリオポリスの太陽信仰を王家の公式信仰として採用したことを示す。ピラミッドは王にとって太陽神により近づく階段であった。 ジョセル王には、ナイルの渇水によってエジプトが飢饉に瀕した時、アスワンのエレファンティネ島の守護神であり、ナイル水源の神クヌムのために祭事を営み、危機を乗り越えた。毎年夏になると水源付近に降る雨のお陰でナイル川は氾濫しし、水がひければ肥沃な大地となる。ただ、数年に一度の頻度で起きる、渇水による旱魃が極めて甚大な被害をエジプトに及ぼした。古代エジプトの時代、ナイルの象徴的な水源は国の南端のエレファンティネとされていた。領土の一部をクヌム神に捧げたという碑文が遺る。 (ナイル川は、ヴィクトリア湖を主な源流とする約5,760kmの大河であるが、ヴィクトリア湖には多数の河川が流入するが、その一方でヴィクトリア湖からの流出する河川はナイル川1つだけである。ヴィクトリア湖は、ケニア・ウガンダ・タンザニアに囲まれたアフリカ最大68,800 km2ある湖である) 初期王朝時代(第1~2王朝;BC3000年~BC 2650年頃)の王たちの発見されている墓は、いずれも地下に埋葬する構造のみであり、初期王朝時代にはピラミッドの建造は無かったようだ。ジェセルの時代になると、初期王朝時代以来王達が追求してきた王権の確立が現実のものとなり、まさに神たるファラオに相応しい地位と経済力を手に入れつつあった。それを示す偉大な記念碑が、サッカラ(メンフィスのネクロポリス)に建てられた。最古のピラミッドは、古王国時代(第3~6王朝;BC2650年~BC 2180年頃)の第3王朝の初代ジェセル王の高さ約62mの6段の階段ピラミッドである。底面は長方形で、東西は125m、南北は109mある。地下28mの所には地下室が掘ってあり、玄室や回廊がある。元神官の博学な高官イムホテプに命じてサッカラ造らせた。それが史上初のピラミッドとも言われるジェセル王のピラミッドである。この独特の墓形式を設計したのもイムヘテプであった。 ジェセル王に仕えたこの賢人は、紀元前27世紀中頃に最初のピラミッドを建設した人物で、新王国時代以降からは、書記の「守護聖人」として崇拝され、紀元前7世紀には学者と医者の守護神として、ついに神格化されるまでになった。その姿は、しばしば書記の姿で表される。 生前のイムヘテプの肖像は、今のところ存在しない。墳墓も未だに確認されていない。カイロのエジプト博物館に収蔵されている第3王朝時代のジェセル王の彫像の台座の銘文に、王の助言者イムヘテプの名が記されており、「下エジプト王の大法官、上エジプトの王に仕える者、偉大なる領地の長、高官(パト)の長、偉大なる預言者(ヘリオポリスの大神官)、彫刻師と石工の長」などの称号が列挙されている。 ジェセル王の時代になると、エジプト初期王朝時代以来の王権がようやく確立し、そのエジプト最初の繁栄期の首都は、一貫してメンフィスに置かれた。古王国時代には中央政権が安定し、ピラミッドでわかるように、強力な王権が成立していた。まさに神たる王に相応しい地位を王は現実に手に入れつつあった。それを示す偉大な記念碑が、サッカラに建てられた史上初のピラミッドと言われるジェセル王の階段ピラミッドである。ピラミッドの建設は古王国時代の極めて重要な特徴の一つである。一般的にマスタバと呼ばれる大型の墳墓から次第に階段ピラミッドが発達し、やがて種々の改良がなされ、第4王朝には四角錐の直線のラインを持った真正ピラミッドが誕生した。 マヤ(メキシコの南東部、グアテマラ、ベリーズなどいわゆるマヤ地域、BC900年ごろからいくつもの大都市が盛衰を繰り返す。1546年にスペインがこの地方を完全に制圧した)・トルテカ(メキシコのトルテカ帝国は、 7世紀頃〜12世紀頃)・アステカ(1428年頃~1521年までの約95年間北米のメキシコ中央部で栄えた)といったアメリカ大陸では、最も多くの階段ピラミッドが造られいた。 ジェセルの死後後継者となったセケムケト王(在位;BC 2565年頃~BC 2559年頃)以降も、ピラミッドの建造が継承されていった。しかし、セケムケトについての史料はいずれも乏しく、詳細な生涯像が浮かばない。マネトによればジェセル(トソルトルス)の後には6人のファラオによる157年の治世があったことになっている。 セケムケトの統治の痕跡は未完成ピラミッドやシナイ半島で見つかったレリーフなどがあるが、具体的な姿として形を成すまでには至っていない。 あの未完成ピラミッドも、サッカラに建設された。治世が短かったためか、マスタバ状のまま造りかけのピラミッドの中には石棺が安置されていた。その中に王の遺体は存在しなかった。セケムケトのピラミッドは外見からすればほぼ完成しているので、石棺を運び込んだものの、ピラミッドが完成しなかったため王の遺体を安置できなかったようだ。ピラミッド複合施設は造りかけのまま放棄されている。 第3王朝のカーバー王はセケムケトの後継者であり、セケムケトとジェセレトネブティ Djeseretnebti の間の息子だと考えられている。名前ジェセレット・ネブティまたはジェセレット・アンク・ネブティは、第3王朝の王のピラミッドの下の地下ギャラリーで見つかった象牙の布のラベルに表示されていた。一般的なnebti-crestと書かれているが、その人がエジプトの王族であったのか、それとも固有名であったのかを識別できるような個人的な肩書きがない。おそらく「二人の女性(女神)のために生きている高貴な方」として、セケムケト王の妻を尊崇しているようだ。 The Nebty name (also called the Two-Ladies-name) was one of the "great five names" used by Egyptian pharaohs. ネブティ名が、「二人の女性名」と呼ばれるが、元はエジプトのファラオが使用する「偉大な5つの名前」の1つ、しかも最も古い王室のタイトルの一つであった。現代的に「二人の女性名」と直訳するのは、エジプト語のネスティnbtjの単純な訳語から派生したに過ぎない。 「crest」は「王室の紋章」と理解され、女神ネクベットとウアジェトの2神をペアの神として神聖化する宗教的な表現であり、その王室の紋章は、上下エジプトを統一するエジプト国家の王を意味する。 白いハゲワシからなるネクベットは、古代エジプトの女王の称号Mwt-niswt(「王の母」)で表現される「王の天の母」として崇拝された。ウアジェトのコブラは「王の額に天のダイアデムdiadem(王が身に着ける装飾されたヘッドバンド)としてはめられるヘビの装飾像」として崇拝され、ファラオを取る勇気のある人に火を吐くと信じられている。ウアジェトを非常に人気があり、すでに初期の王朝時代には、いくつかの神々が額にウラエウスuraeus(蛇形記章)を身に着けているように描かれている。 ウラエウスは、エジプトに棲息するアスプコブラが鎌首を持ち上げた様子を様式化したもので、古代エジプトの主権・王権・神性の象徴である。その蛇形記章が女神ウアジェトの象徴である。ウアジェトはエジプト神話の中でも最古の神の1つで、コブラとして描かれることが多い。ナイル川デルタ地帯の守護神とされ、やがて下エジプト全域の守護神とされた。そのためファラオが頭部に蛇形記章をつけるようになった。当初はウアジェトの神像を頭につけたり、頭を取り巻く冠を被ったりしていたが、その後も常に冠の装飾の一部として使われ続けられている。蛇形記章をつけていることはファラオであることと同義であり、それはウアジェトの庇護と領土の支配権を表していた。BC3千年紀のエジプト古王国時代から既にこの伝統が存在していた。ウアジェトと関連の深い女神やウアジェトの特定の面を表す女神にも、蛇形記章を身につけた姿で表現されている。 エジプト全土統一に際して、上エジプトの守護神で白いハゲワシの姿で描かれるネクベトやウアジェトを表す蛇形記章と共にファラオの王冠に付加されることにより、ファラオが上下エジプトの支配者であることを示した。それぞれの信仰が深かったため、それらを習合することができないまま、2柱の女神を「2人の貴婦人 The Two Ladies」と呼び、統一エジプトの共同守護神として崇めた。 ネプティの名前でThe Two Ladiesを崇め、各ファラオは、2人の女神の指導と保護の下で自分自身が存在することを示し、したがって、エジプト全体の支配者として自分自身を正当化する。上と下のエジプトがBC3000年頃に統一されたとき、ウアジェトとネクベトの描写は、ファラオの宮廷では「二人の女神」と非公式認識されていた。 カーバーは、ギザの2km南方ザウィト・エル・アリヤンにある層状ビラミッドの建設発注者だと考えられている。これは未完成のピラミッドで、当初、約42~45mの高さにする予定だったが、20mまでしか建設されなかった。また、ファラオの名が残っているカーバー統治時代の記念碑が11個遺っている。 2015年4月22日、エジプトのマムドゥーフ・ダマティ考古相が、エジプト北部ミヌーフィーヤ県のクウェイスナで、カーバーの霊廟が発見されたと発表した。 この王は『トリノ王名表』に「消去」として記載されており、これは彼の治世下で王朝上の問題が起こったか、この表を作成した書記官が、その古代の記録を完全に判読できなかったことを示唆している。またカーバーは実は第3王朝最後のファラオであり、フニと同一人物であるという見解もある。 やがて「カーバーの霊廟」は、我々に何を語ってくれるのだろうか? 第3王朝最後のファラオのフニは24年間の治世でありながら、その統治の実態を知る史料は殆どない。彼はメイドゥムにピラミッドを建設した。メイドゥムはナイル川西岸のベニースエイフ県にある。北にあたるメンフィスのアブ・ロワシュという街まで、約100km離れている。メンフィスはナイル川河口付近のデルタ地帯という戦略的要衝に形成された都市であり、メンフィスの主たる港であるペル・ネフェル(Peru-nefer)には数多くの工房・工場・倉庫が建ち並び、王国全体に食料や商品を供給していた。その黄金時代の間、メンフィスは商業・貿易・宗教の地域的中心地として繁栄した。メイドゥムから北のメンフィスまでの約100kmの間に有名なピミッドが多数点在している。 メンフィスは、やがて同じナイル川のデルタ地帯で、しかも、地中海沿岸に形成された都市アレクサンドリアの発展によって、古代末期にその経済的重要性を喪失したために、現在はミート・ラヒーナ近郊にある野外博物館「首都の遺跡」として一般公開されている。 メイドゥムにある「崩れピラミッド」がフニ王のものとされている。フニが造った7段の階段式ピラミッドの上に、息子のスネフェルが、もっと大きなピラミッドにするため、1段を追加し、最後に階段部分を石積みで充填し、仕上げに表面をトゥラ産石灰岩(殆どが方解石の粒子だけからできている。きれいな模様があるものは「大理石」と称し、装飾石材として利用される)の化粧石でくまなく覆い、古代エジプト史上初めて建てられた真正ピラミッドのはずだった。作業が終盤に入った時、表面の化粧石と階段部分を埋めた石積みが崩れ始め建設作業は中断した。 「崩れピラミッド」まま現在に至る。そのため葬祭殿に刻印がない。「崩れピラミッド」周辺には、葬祭殿やナイル川の河岸に建つ流域神殿とそれをつなぐ参道など、古王国時代(BC2686頃~BC2181頃)の一般的な葬送施設をすべて備えた、現存する最古のピラミッド複合体でもある。 第3王朝最後の王フニの跡を継いだ第4王朝(BC2613年頃~BC 2494年頃)最初の王スネフルが、真正ピラミッドを完成させた。 ②古王国時代第4王朝 行政組織が整備された古王国時代には、各地にピラミッドが建設された。ピラミッドは単独の建造物ではなく、通常はピラミッド複合体pyramid complexと呼ばれる神殿や倉などの施設が付属し、建造した王の死後も葬祭は継続して行われた。しかも、神事は時代を追うごとに重要視される傾向があった。 古王国時代のピラミッドは、現世にあっては神の化身として地上を治め、死後は神々の一員となるファラオのために、その必要となる王の遺骸および副葬品を祭儀の場に捧げる巨大な死後の居住空間であった。ピラミッド本体のほか葬祭殿、砂漠の縁にある運河沿いに建てられた河岸神殿、あるいはナイル河畔の河岸神殿と葬祭殿を廊下で結んでつなぐ周壁や参道、時には儀式用の船を舫う舟坑などの施設で構成される。舟坑はすでに第1王朝王墓からも出土されている。元々は葬儀用の舟が利用する実用的な装置であったが、1954年クフ王の大ピラミッド南側に発見され復元された例から鑑みて、やがて葬儀用の舟が、太陽神信仰との結びつき、死後太陽神となったファラオが天を航海するための「太陽舟」として重要な役割を担う、とされた。
マスタバは、アラビア語でベンチと言う意、地下の墓室の地上に、一般に日干し煉瓦で石積みされた長方形で台状の墓である。先王朝時代末期から、特に古王国時代全般にかけて多数あり、しかも後世まで盛んに造られた。ギザやサッカラなどでは、貴族や重臣のマスタバが、生前の王に仕えていた時の様子で、ピラミッドの周囲に整然と配置されている。典型的な構造は、地上の礼拝堂と地下の埋葬室の二つの施設からなり、埋葬室は地下の玄室とそれを結ぶ竪坑または階段を備える。 フニの息子と下級の王妃メルサンク1世の息子であると見られるスネフェルが、エジプト第4王朝の初代ファラオとされている。またフニと別の王妃との間の娘、ヘテプヘレス1世はスネフェルの正妃であると考えられている。フニの死によってエジプト第3王朝は終了した。 スネフェル王は、エジプト古王国第4王朝の初代ファラオで、クフ王の父にあたる。世界遺産となった赤いピラミッドのほか、屈折ピラミッドなど多くのピラミッドを建造した。その治世については殆ど不明であるが、彼の後の王たちが巨大なピラミッドをいくつも建造していることから、政治的には安定し経済的にも豊かであったようだ。 第4王朝の初代ファラオ・スネフェル(在位BC2613年頃~2589年頃)は、BC2610年頃「ヌビア遠征から7000人の捕虜と20万頭の家畜、またエジプト東部のシナイ半島(紅海とアカバ湾に挟まれた三角形)方面への外征も記録されており、多数のベドウィン(砂漠の住人を指す、普通アラブの遊牧民族)を連れ帰って来た」という。エジプト王国の歴史を通して 、南方のヌビアから、主に兵士や召使・建築労働者として、移住者が多く流れ込んでいた。エジプトでは既に良質な木材は国外からの調達に頼り、スネフェルはレバノンから40隻の船でヒマラヤスギを買って来ている。スネフェルは、交易と戦争などの目的のためシナイ・ヌビア・リビュア(北西アフリカのナイル川より西側の地区)で船を建造させた。王権は最盛期を迎えていた。 スネフェル王は、崩れピラミッドなど多くのピラミッドを造営した。その一つは方錐形で後のピラミッドと同じ形のものが作れた。壁面が二等辺三角形になっており、これがスネフェルが最後に造った最初の真正ピラミッドとも言われている。カイロの南約40kmのナイル川西岸ダハシュールにあったネクロポリスに建造した「赤いピラミッド」で、その呼称の由来は、表面の花崗岩が赤く見えるからである。当初、ピラミッドは化粧石で覆われていたはずが、化粧石が持ち去られてしまったため、花崗岩が露出したことによる。方錐形は太陽光線を具象化したもので、太陽神信仰と関係がある。 スネフェルが最初に手がけたのは、カイロの南約100kmにメイドゥーム(メンフィスに近いナイル川西岸)にある父フニのもので、階段状のピラミッドであるが、一般的な葬送施設をすべて備えた方錐型の真正ピラミッドとしては初めて造られた。だが、その建造が終盤に入った時、表面の化粧石と階段部分を埋めた石積みが崩れ始め造営は中止された。葬祭殿に刻印が施されていないまま、崩壊により、ピラミッドは現在の状態となった。 その後、すぐそばに自分のピラミッドも造った。さらにダハシュールに屈折ピラミッドと赤いピラミッドを作った。屈折ピラミッドは、高さ約105m、その下部の傾斜は約54度21分、高さ49.07mから約43度21分と傾斜が緩やかになる 。メイドゥーム近くのセイラにある小さな崩れピラミッドもスネフェルが作ったと考えられている。クフ王の父であるスネフェルの造ったピラミッドはどれもクフのギザの大ピラミッドよりも小さいが、スネフェルがピラミッド建設に使った石の総体積は、歴代ファラオの中で最大である。 スネフェルが一代で、真正ピラミッドを完成させた。その模索の過程がたどれるのも古代エジプトのヒエログリフがあればこそであった。 スネフェル王の屈折ピラミッドは、メンフィスの上流ダハシュールにあり、スネフェル王が建てた赤いピラミッドも近くにある。有名なエジプトのピラミッドは、「メンフィスとその墓地遺跡 – ギザからダハシュールまでのピラミッド地帯」という名称で世界遺産に登録されている。カイロはナイル川東岸であるが、その上流の西岸に、北からギザ・メンフィス・サッカラ・ダハシュール・マズグーナ・リシュト・メイドゥムと南へ並ぶ、その周辺遺跡の見どころはやはり「ギザの三大ピラミッド」である。クフ王のピラミッド・カフラー王のピラミッド・メンカウラー王のピラミッドを指す。また、ジェゼル王の階段ピラミッド・ペピ1世のピラミッド・メルエンラー1世のピラミッド・スネフェル王の赤いピラミッド・スネフェル王の屈折ピラミッドと、数々のピラミッドがこの世界遺産に含まれている。 赤いピラミッドの呼称の由来は、表面の花崗岩が赤く見えることからそう呼ばれる。ピラミッドの大きさは、高さが104m、エジプトのピラミッドの中では、クフ王とカフラー王のピラミッドに次いで3番目の大きさになる。壁面が二等辺三角形になっており、これが最初の真正ピラミッドとも言われている。 スネフェル王の屈折ピラミッドは、その赤いピラミッドの近くにある。屈折ピラミッドは、高さは105m、底辺は189m、その傾斜が途中で変わっており、上部は43度、下部は54度となっているため、その独特な外観から名付けられた。傾斜が変化している理由には、「勾配が急すぎて危険であるため変更した」、「工事中に王が病に倒れたため、急いで完成しようと高さを低くした」などの他、諸説ある。 スネフェル王のピラミッドを中心に、その周辺遺跡は、約3,000年間にわたり大小様々な墓が作られてきた巨大な「死者の町」と言われている。メイドゥムの崩れピラミッドは、ピラミッドのコア部分が見られ、その建造方法を研究する上でも貴重なピラミッドと言われている。その周辺には王族の墓である長方形の巨大な墓『マスタバ墓』が複数発見されている。それらは、スネフェル王の息子たち、つまりクフ王の兄弟たちの墓であると確認されている。 その頂点にあるのがギザの三大ピラミッドである。BC2550頃に20年前後かけてクフ王が第1(大)ピラミッドが造営された。クフ王のピラミッド・カフラー王のピラミッド・メンカウラー王のピラミッド、この時代のピラミッドが、規模・技術ともに最高水準を示す。メンカウラー王のピラミッドの造営の頃から、第4王朝の王権が衰退し始める。 ③古王国時代第6王朝 古王国時代第6王朝のペピ2世(BC2216~2153年)、90年以上の治世のため、晩年には王権が弱体化した。古代エジプトの歴代王の中で最も長く生きた王の一人とされる。6歳ほどの年齢で王位に就き 、その後、60年以上在位している。同じくらい在位していたのは在位67年のラメセス2世Rameses Ⅱ (在位BC1290~BC1224年頃、エジプト新王国の第19王朝の王。トトメス3世と並ぶエジプト史上有名な英主)などごく限られている。この時代は、既にプントとの交易が普通に行われていたようだ。 プントとはエジプトの南、今のソマリア(正式名称プントランド・ソマリア国)あたりをさす。またピグミー族をとらえ、幼いペピ2世に献上した貴族ハルクフの名前も記録に出てくる。 エジプトには、ピグミー族がモデルとされる陽気な神ベスが存在する。 治世64年目の初めには亡くなっていたと推定されている。長寿だと余り長く治世が続くため後継者が先に亡くなっているなど、次の王が立つときに騒乱が起こりやすい。記録に残っている数は僅かだが、子供たちが父の存命中に死去している。 イシス女神が子供のホルスを抱くときの伝統的なポーズで作られたペピ2世と母アンケネスメリラーの像が見つかっている。この像には、聖なる蛇ウラエウス(王家の守護として帽子や冠の飾り、または首飾りなどによく表されている、コブラ姿の女神。彼女は翼を持ち、凶暴な毒蛇と化すが、味方につけるとこの上なく心強い、実際のコブラの属性を反映させている。)も登場している。古代エジプト世界における。聖なる母イシスと王を象徴ホルスとの神話の原型は、既に完成されていたようだ。彼の没後、王国は急速に衰え、第一中間期(BC2180年頃~BC2040年頃、第7~11王朝))と呼ぶ混乱の時代を迎える。その実態は、古王国のファラオの後継者争いがあったとしても、自然環境が壊滅的に破壊されたため、再建不全に陥ていたことによる。それでなくとも、毎年定期的に氾濫し、肥沃な大地をもたらすと理想的に語られていたナイル川は、数年に一度の頻度で、氾濫時の水位が低くいため、不作を招いていた。 「王の母」 古代エジプトでは女性の地位は総じて高く、そのため王妃に与えられる称号がいくつもある。いちばん最初の称号が「王の母」である。王妃は神聖な王の血統を繋ぎ、次代のファラオを産むことが期待される。「王の母」になることで神性となり権力が振るえる。 時代が下ると「偉大なる王の妻」など称号の種類が増えてくる。それだけ王妃の役割が重要になり、その評価が高まってきたからである。 「王の母」の代表格が王妃ヘテプヘレスである。古王国時代の第4王朝、初代のスネフェル王(カイロの南方にあるダハシュールの屈折ピラミットが有名)の王妃であった。第3王朝の最後の王フニの娘で、「神の娘」という称号を得て、王家の正統な血をひき、スネフェルの結婚により、前王朝から次の王朝へと王家の血を引き継ぐとして二つの王家を統合する役割を果たした。 スネフェル王は、BC2610頃ヌビアやシナイ半島に遠征して、レバノンより杉材(船材・建材)やシナイ半島のトルコ石を輸入し、王権は最盛期を迎え、やがて莫大な遺産を遺した。 古王国時代のBC2550頃、クフ王は第1(大)ピラミッドを造営する。ヘテプヘレスはそのピラミッドを建てたクフ王の母である。カフラー王やシェプセスカフ王の祖母である。彼女の称号には「王の母」、「二つの地の王の母」、「ホルスの従者」、「神の娘」などがある。 息子がファラオになったことで、ヘテプヘレスは「王の母」の称号を得た。ギザで発見された彼女の墓から多数の副葬品が発見されており、その1つの輿にはヒエログリフで「支配者の指導者」と刻んである。ヘテプヘレスは支配者であるクフ王の指導者だったということである。 エジプト 第一中間期(BC2180年頃~BC2040年頃、第7~11王朝) エジプト第6王朝のペピ2世の死後社会が混乱した時期、中東全域で長期に及ぶ乾燥化が始まっていた。古王国時代末期の気候の大変動による乾燥化により、ナイル川の水位が著しく低下し川の氾濫も勢いを弱めると、数十年に及ぶ旱魃による深刻な飢饉が起き、長年に渡る社会の荒廃を一層助長することになった。 第1中間期を通して食糧難が民衆と支配者層を苦しめた。このような中で、古王国後の第7王朝~11王朝は次々と破綻した。これが150年は続いた古王国崩壊後の暗黒時代である。 これは地球規模に及び、メソポタミアではアッカド王国が滅亡したのもこの気候変動が原因のようだ。アッカドはメソポタミア南部のユーフラテス下流で、バビロニアの北よりの地域名で、現在のイラクの中部に当たる。BC2300年、メソポタミア全域の都市国家を最初に統一し領域国家を建設した。アッカド王朝は11代約180年続いたが次第に衰退し、BC2150年頃、バビロニアの東北から興ったグティ人の侵略を受けて滅亡した。グティ人は約125年間、アッカドの地を支配したが、やがてメソポタミアでは,シュメール人が独立を回復、ウルを拠点にウル第3王朝が出現する。 グリーンランドの氷床やアンデス山脈の氷河から採取されたコアの調査により、BC2200年頃に、どこか北方で火山が大爆発し、大量の火山灰が世界的規模で降り注いだことがわかっている。これによりヨーロッパでは寒冷化、中東では乾燥化が激しくなった。、 日本列島の縄文時代の中期は、農耕などの進捗による大集落化と、祭祀文化の開花により大繁栄期を迎えるが、BC2200年頃の突然の寒冷化で、日本列島を縦走する中央高原一帯に壊滅的な打撃を与えた。 同じ時期にエルニーニョ現象が発生し、アフリカからインド洋に吹いていた季節風が非常に弱まり、エチオピア高原に旱魃をもたらした。 1971年、第9王朝の第3ノモスの君主アンクティフィーの墓の碑文が発見された。そこには、エジプト南部が壊滅的な飢饉に見舞われ、飢えた人々が我が子を食べるに至ったとの、ショッキングな記述があった。 エジプトのナイル川流域に潅漑農業が行われると村落を基盤とした小国家が形成される。それをノモスと言う。古代エジプトの人々とって、ノモスは行政単位であると共に祭礼・土木・水利などを管理する地域共同体であった。上エジプトに22、下エジプトに20、合計42のノモスがあった。古代エジプト第3王朝初代ファラオのジェセル王のピラミッドに、ノモス名とノモスの長官ノマルコスnomarchosの称号があり、今のところノモスの存在を示す最も古い史料となる。ノモスの長官ノマルコスは、日本語では一般的に州侯と訳す。3000年にもわたる歴史の中で、その位置付けや権限、及び定義は変化している。そのため、個々のノモスの内政や実態は、殆ど解明されていない。 エル・マンスーラはデルタに存在した古王国の大都市であった。古王国崩壊以降の土器が発見されてない。デルタにあった他の集落跡でも同様である。デルタには古王国には27も集落跡があった。古王国崩壊直後にはたったの4つに激減していた。16世紀初めにエジプトを掌握したオスマン帝国がデルタ支配の重点都市としたため一段と繁栄した。 ファイユーム地方のカールーン湖で数ヵ所ボーリング調査をしたところ、この湖が古王国時代が崩壊する時期の数10年のあいだ干上がっていたことが分かった。 1996年、下エジプトのナイル・デルタで、古王国時代末期の9000体に及ぶ骸骨が発掘された。 第1中間期初頭の気候変動は、王朝を支える官吏や神官にも大きな打撃となった。彼らは、創造神によって定められた宇宙の秩序の体現者たる王に仕えて秩序の維持に貢献すれば、現世における成功が与えられるという信念を古くより持っていた。しかし第1中間期に入り、もはや旧来のような安定した地位の維持や俸給、供物の確保が不可能となり、彼らの価値観も変容を迫られた。 神の定めた正義の下に秩序を確立する最高責任者は王であった。 更に王は秩序を維持する義務を負うが、王によって統治される人々にも秩序の実現を要求する権利があり、むしろ自ら進んで要求しなければならないという主張も成立した。更に王が死去した後、千年を超えているが、王の復活が見られない。神聖王権に疑念が生じた。 ペピ2世の長期政権の間に、エジプト古王国の中央集権体制は瓦解していた。第6王朝の数名の短命王の後に第7王朝が樹立したとあるが、殆ど史料が残らない。エジプト第8王朝も第7王朝時代から続く混乱の中で短命王が続き、短期間のうちに終焉を迎えた。 第8王朝のカカラー王が建設した小さなピラミッドがサッカラの南から発見され、内部からピラミッド・テキスト(主に古王国時代、故王の復活と永生のため、葬儀や供養の儀式の際に誦された呪文の集成が墓室壁面に刻まれた。ピラミッドごとに呪文に異同がある。)も発見されている。BC2160年頃~BC2130年頃、ヘウト・ネンネス(ヘラクレオポリス)は上エジプト第20県(ナルト・ケンテト)の首都であり、ここに拠点を置く州侯は統一王朝の弱体化につれて次第に強大化した。 メンフィスを拠点とした伝統的な統一国家が崩壊する中で自立勢力となったヘウト・ネンネス(古代エジプト語:Hwt-nen-nesu)侯の政権を指して第9王朝と呼ぶ。 ヘラクレオポリスの王朝のヘウト・ネンネス侯は、成立以来30年余りの治世の後、BC2130年頃~紀元前2040年頃?、ヘウト・ネンネスを拠点にエジプト全域に勢力を拡大した。第9王朝から第10王朝へと交代したとされる。その間、具体的な経緯などまったく分かっていない。現代のエジプト学者は多くの場合、第9、第10王朝を一まとめに扱っている。 エジプト第9王朝に続いて上エジプト北部地方を支配したが、第10王朝への交代の具体的な経緯などは分かっていない。現代のエジプト学者は多くの場合、第9、第10王朝を一まとめに扱っている。マネトがこれを二つの王朝に分けた理由も不明である。 当時テーベを拠点とした第11王朝は著しく強大化し、第10王朝との対立が深まっていた。第10王朝と第11王朝の国境は当初上エジプト第8県のアビュドスの北にあったが、第11王朝との国境紛争が頻繁に発生していた。こうした状況下、第10王朝は上エジプトの州侯に対しても広範な自治を認めてその協力を仰いだ。
自立した地方豪族の群雄割拠で古王国が衰退した後、第1中間期(第7~11王朝)の分裂期を経てBC2040年頃、上エジプトのテーベ州侯であったメンチュヘテプ2世がエジプトを再統一した。これが中王国時代(BC2040~1785年頃)の第11王朝であった。中王国は約250年ほど続いたが、メンチュヘテプ2世の死後間もなく、第11王朝の宰相アメンエムハト(アメンエムハト1世)が、王位を簒奪し第12王朝を開いた。 中王国のアメンエムハト3世は、BC1800年頃、ファイユーム地方の大規模な灌漑事業を完成させる。中王国時代の黄金期を迎えた。アメンエムハト2世の治世から始まった開拓事業を、先代の父王センウセレト3世から引き継ぎ、アメンエムハト3世の時代にも事業継続され、ようやく完成された。 ファイユーム・オアシスの北西にあった古代の淡水湖・モエリス湖は、カイロの南西80km付近にあった。「モエリス」とは「大きな運河」という意味である。面積は1,270km2~1,700km2、淡水魚のテラピア漁が行われていた。 厚く沈殿した泥のためにナイル川がファイユーム窪地に溢れ込み、その大部分が洪水で溢れた水が溜まる湖であった。ナイル川からこの自然の湖へと通じる水路を拡幅して運河とした。このプロジェクトをアメンエムハト3世が完成させた。この運河により、ナイル川の洪水を制御し、乾期にはナイル川の水量を保ち周辺地域ファイユームの灌漑用水とした。古代エジプトの第12王朝のファラオ達が、ファイユームにできた自然湖の余剰の水を溜めておいて乾期に利用する貯水池として使用していた。 現在では、僅か202km2の塩水湖のカールーン湖として残する。 アメンエムハト2世は、王センウセレト1世の治世42年目に父王の共同統治者に任命され、その治世中、湿地帯が広がるファイユーム地方が、大幅な食料増産が可能な新たな広大な農地の開発が期待できるとし、長大なな堤防を築き、その水路をより広く深く掘削し、ナイル川からの水の流入を調節し、灌漑用水ばかりか運河とし水運に利用した。 アメンエムハト3世の時代に完成し農業生産は飛躍的に増大した。王国の経済成長もピークに達し、中王国時代最盛期の王となった。 父王が南のヌビアでの対外政策に力を注いだのに対して、アメンエムハト3世の関心は主に北のシナイ半島の南海岸にあるセラビト・エル・カジムやワジ・マガレで、その目的はトルコ石の鉱山開発に向けられた。またアスワンの南東の東部砂漠内にあるワディ・ハンママート(ワディは涸れ谷の意)でアメシスト(紫水晶)を採掘している。 シリアからナイル第3急湍までの多数の建造物や碑文から、アメンエムハト3世が偉大な王であると考えられている。外征が多かったようで、碑文の90%以上が国外で発見されている。 BC2000年紀(1000年代)は、オリエント全体で民族移動が激しくなった時期である。第12王朝のアメンエムハト3世(在位BC1842頃~BC1797)の死後、非王族である可能性が高いアメンエムハト4世(BC1798~BC1786)が跡を継いだ。その治世については殆ど知られていない。その後女王セベクネフェルが即位した。非王族の後継とその後の女王即位という事態は後継者争いあったことが想定できる。セベクネフェルは、アメンエムハト4世とは直接的な血の繋がりがないので、アメンエムハト3世の娘と推測される。碑文の定型句も女性形になっており、「ラーに愛でられし雌鷹」とある。 1941年、セベクネフェル女王の像とともに発見された王の像には「ヘテプイブラー・アアムサホルネジュヘルアンテフ」という名が書かれてあった。「アアムサホルネジュヘルアンテフ」は女王の執事長であった人物の名である。この王の王名を記した王笏は、北シリアのエブラからも出土している。「アアムサ」は、古代エジプト語でアジア人の息子という意味なので、外来系の人物ではないかと推測されている。BC1782年、女王セベクネフェルが死去。大家令であったヘテプイブラー・アアムサホルネジュヘルアンテフが一時王位を簒奪した。 間もなく彼の政権は終わり、セベクヘテプ1世が王位についた。 それが中王国時代の終焉であった。 第2中間期(第13~17王朝)(BC1785~BC1542年) エジプト第12王朝をの国家制度は、セベクヘテプ1世によってそのままエジプト第13王朝に継承される。次の13王朝から17王朝までを第2中間期と呼ぶ。 13王朝の王達は12王朝の王達の命名規則を踏襲している。第13王朝の初期は、第12王朝と繋がりがあるため王都も同じである。 実際、王統は血縁関係で続いている。この第13王朝は、極めて弱体化あるためか、王の記録はあまり残っていない。 マネトの記録によれば、第13王朝にはテーベ(古代エジプト語:ネウト)出身の60人の王がいたとされ、ようやくトリノ王名表には36人の王が記録されている。それで 明らかになるのが、第13王朝の王達の平均在位が数年程度であったことである。 第13王朝の政府機構は、王位を異常なほど短期間に置くことで王朝を存続させた。エジプト第13王朝は、宰相を中心として官吏が国家を運営する王朝へと変化していた。 王自体、政府機関の一員に過ぎず、つまり中王国時代のエジプトに大いなる繁栄をもたらした偉大な功績のあるアメンエムハト3世の系統であるため、王国統合の象徴的として実権を与えず利用していたようだ。官吏による放漫な国家運営が維持できたのも、地方自体が疲弊し、さらに周辺から押し寄せる他民族に侵入され、地方は壊滅状態であったため反旗を翻すこともできなかったのだろう。 当時のエジプトは、シリア・パレスチナ地方からの異民族の移動により、メソポタミア地方からの民族的文化と融合していた。シリア地方のバアル神が崇拝されていた痕跡も残されている。 バアル神は、カナンで信仰された神、嵐と雷雨や山岳の神で、慈雨により豊饒をもたらすとされ神、旧約聖書ではユダヤ教と対立し、ユダヤ人を誘惑する異教の神として書かれる。唯一神ヤハウェ(文語訳で「エホバ」)のライバルとして敵視されるバアルだが、ヤハウェ自体が天候神であるバアルの影響を大いに受けており、バアルに捧げられた讃歌が名前だけ挿げ替えられてヤハウェのものにされ、バアルが撃破した原初の大蛇ロタンがレヴィアタン(旧約聖書に登場する海の怪物、悪魔)の原型と見られるなど神性の流用がなされている。 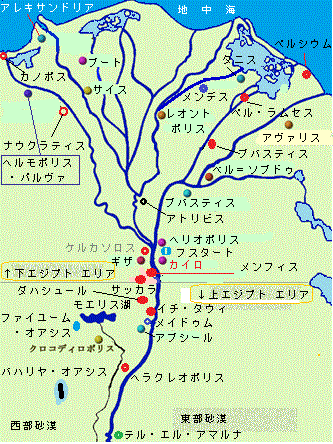 BC1720年頃、エジプト国内の政治的混乱に乗じて、アジア系民族ヒクソスが支配権を確立し、東デルタのアヴァリスAvaris(古代エジプトの都市。ナイルデルタ地帯の北東部にあった。テルエルダバアTal al-Dabaa付近)を王都として、第15王朝を樹立した。エジプト史上初の異民族王朝が開かれた。エジプトの文化を受け入れ、王もファラオを称したので、エジプトの王朝に加えられている。王国の支配地域はパレスティナからエジプト全土に及ぶが、直接統治したのはデルタ地方のみで、各地に分立する地方領主に宗主権を行使する間接統治であった。
ヒクソスは、 東方からエジプトに侵入した異民族で、シリア地方にいたセム系種族アモリ人を中心として、いくつかの民族が雑じり合っていた。デルタ東部の国境の防備が手薄となったのに乗じて、異民族がアジアより侵入し、デルタ東部を中心に定着し、傭兵として実力を蓄え、クーデタにより第15王朝を開いた。 BC1720年頃、エジプト国内の政治的混乱に乗じて、アジア系民族ヒクソスが支配権を確立し、東デルタのアヴァリスAvaris(古代エジプトの都市。ナイルデルタ地帯の北東部にあった。テルエルダバアTal al-Dabaa付近)を王都として、第15王朝を樹立した。エジプト史上初の異民族王朝が開かれた。エジプトの文化を受け入れ、王もファラオを称したので、エジプトの王朝に加えられている。王国の支配地域はパレスティナからエジプト全土に及ぶが、直接統治したのはデルタ地方のみで、各地に分立する地方領主に宗主権を行使する間接統治であった。
ヒクソスは、 東方からエジプトに侵入した異民族で、シリア地方にいたセム系種族アモリ人を中心として、いくつかの民族が雑じり合っていた。デルタ東部の国境の防備が手薄となったのに乗じて、異民族がアジアより侵入し、デルタ東部を中心に定着し、傭兵として実力を蓄え、クーデタにより第15王朝を開いた。彼らは馬と戦車、それに鉄をエジプトに伝えた。しかしヒクソスに関係のある遺跡は、その後エジプト人達にすべて破壊尽くされ遺っていない。 BC1680頃、別のヒクソスのグループが下エジプトを占領し、第16王朝を開く。第15王朝ヒクソスの反主流派で、デルタ地帯でアヴァリス政権と並立し、また対立していた数多くの都市国家レベルの弱小支配者たちの集合体である。エジプトの王とまでは自称していなかったようだ。 BC1650頃、既にナイル川中流域のテーベの地方貴族が第17王朝を興し、ヒクソスと対抗する勢力となっていた。王朝初期は現状維持に努めていた。アヴァリスに本拠を置くヒクソスの宗主権を認めながら争いは避けていたようである。北にはヒクソス、南にはヌビアという南北双方に懸案を抱えながらも三国鼎立状態を維持していた。 第17王朝にとって、北部のアヴァリスをヒクソスの第15王朝が制してから、地中海からの交易もままならず、南部ではヌビアが台頭していた。セケンエンラー2世の時代に、最終的にはヒクソスを追放し、ヌビアも制圧し悲願のエジプト人による全土統一を成し遂げようと第15王朝との戦争に突入した。第15王朝のアペピ1世がセケンエンラー2世に「テーベのカバの鳴き声がうるさくて眠れないのでカバを何とかして欲しい」という手紙で揶揄されたことが切っ掛けとなって、 BC 1570年頃、セケンエンラー2世はヒクソス王アペピ1世を攻撃した。惨敗であった。セケンエンラー2世は乱戦の中で戦死した。1881年、テーベ近郊のデイル・エル・バハリにある「ロイヤル・カシェ(王家の隠し場所)」で、セケンエンラー2世のものと思われる苦悶の形相のミイラが発見された。ミイラの頭部には、複数の敵による5ヵ所もの致命傷があった。 エジプト 新王国時代(第18~20王朝) (BC1567~BC1085頃) その子のイアフメス1世がファラオとなるが、幼少であったため、セケンエンラー・タア2世の王妃にして母のイアフヘテプ1世が摂政を務めていたと考えられている。イアフメス1世はBC1565頃に第18王朝を創始し、ヒクソスとの戦いを再開、BC1542年にヒクソスの都アヴァリスを占領し、国土再統一を達成した。ここからエジプト新王国時代最初の第18王朝が、都をテーベに置き始まる。 先代までにアビュドスを含む中部エジプトまで領地を回復できていたため、即位直後にメンフィスを取り戻しているが、その後、ヒクソス王朝の首都アヴァリスを陥落させるまでには6年を要した。近年の発掘調査により、住居遺構・生活用品・碑文史料などの出土といっためざましい成果があり、アヴァリスは既に中王国時代から、政治・軍事・宗教の一大センターであったようだ。運河沿いに開けた商業都市の市場には、エジプト人はもとより、アジア人・リビア人・ヌビア人など数多くの商人達で賑わっていた。 日干し煉瓦の建造物であった要塞は、極めて堅固で、イアフメス1世は10回の遠征と3度の総攻撃を行なったとされている。エジプト全土の統一は、イアフメス王治世10年目のことだった。 ヒクソスはエジプトから追われ、パレスティナに逃れたが、3年後に最後の拠点シャルヘンも陥落し、滅亡した。BC16世紀の初期には、既にテーベを中心として独立運動が起っており、王国を回復したエジプト人達はヒクソスの記念碑や記録をすべて破壊してしまった。全てのヒクソス人が、エジプトから追放されたわけではない。支配者層を除く一般人や、混血した人々はそのまま留まり続け、アヴァリスは第19王朝になっても「アペピの居城」や「アジア人の地」といった名前で呼ばれていた。 初めは、ヒクソスを追ってパレスチナ地方にまで軍を進め、やがてシリア地方から南はヌビアのナイル川の第4急湍(現スーダンのメロウェダムの南のメロウェのあたり)までを支配する史上最大の版図を領有し、オリエント世界に覇を唱えた。ヌビア植民地に総督府が置かれたのもこの王の時代で、何度かの反乱が起きたこともあり、ブヘン(現在はナセル湖の下に水没)の砦を中心として監視のための軍が置かれるようになった。総督には「クシュの王子」の肩書きが与えられるようになった。エジプトの再統一による国力増大によって数々の大規模建築が遺された。 テーベの王が全土を領有したことにより、この時代はラーではなく、テーベの守護神であるアメン神が最高位の扱いになった。王妃はイアフメス・ネフェルトイリで「アメン神の正妻」の称号を持つ。守護神であるアメンに仕える王族の女性の神官の称号「アメンの神妻」という地位が作られたのは新王国時代だ。イアフメスの王妃、イアフメス・ネフェルトイリがその初代であった。後に神格化され、これ以降アメン神は神々の中でも特別に尊崇される。 (アメン神は、羊の姿をなぞる、二本の羽飾りを頭にのせた男性の姿が基本。男根を勃起させた生殖と豊穣の神ミンの姿から造形された。そのためテーベの守護神で豊穣の神であった。名前は「隠す」を意味する動詞「imin」に由来、「隠されたる者」を意味する。元々、大気中に存在する「見えない神」のイメージもあり、大気や雲に関わる神でもあった。 ナイル川の東岸にあるテーベで信仰されていた地方神であったが、この地の王族がヒクソスと呼ばれる異民族国家を撃退したことから、戦勝をもたらした神として称揚された。新王国時代の王達が、ヌビアやシリア方面にも進出すると、アメンは敵国に対する勝利や領土拡大をもたらす国家神として尊崇された。 ヘブライ語のアーメンは「本当に」「然り」という意味で、無関係。 )  アメンヘテプ1世は、少年期終わり頃に父イアフメス1世を亡くし、母である王妃イアフメス・ネフェルトイリが摂政として後見することでファラオとして即位を果たした。息子のアメンヘテプ1世(BC1525~BC1504年)と母の2人がテーベの主、守護者として君臨した。王妃は優秀な執政官で、人々の信頼を勝ち得ていたようだ。王妃は息子とともに、波乱の第2中間期後の不安定な政治・経済・宗教を建て直し、エジプト統一の基本体制を確立した。二人の死後、彼らを祀る様々な神殿が建立されるようになり、そのうちのいくつかがテーベ地方で発掘されている。
二人は、とりわけテーベの王室のネクロポリスにあった職人の村、デル・エル=メディーナの住民に特別に厚く崇拝され、守護神とみなされていた。デル・エル=メディーナの遺跡とベルナール・ブリュイエールは、テーベ山中にある砂漠の小さな谷の窪みにある。この遺跡は、新王国時代の王家の谷や王妃の谷の墓の造営に従事した職人たちの居住地と墓地だった。 アメンヘテプ1世は、少年期終わり頃に父イアフメス1世を亡くし、母である王妃イアフメス・ネフェルトイリが摂政として後見することでファラオとして即位を果たした。息子のアメンヘテプ1世(BC1525~BC1504年)と母の2人がテーベの主、守護者として君臨した。王妃は優秀な執政官で、人々の信頼を勝ち得ていたようだ。王妃は息子とともに、波乱の第2中間期後の不安定な政治・経済・宗教を建て直し、エジプト統一の基本体制を確立した。二人の死後、彼らを祀る様々な神殿が建立されるようになり、そのうちのいくつかがテーベ地方で発掘されている。
二人は、とりわけテーベの王室のネクロポリスにあった職人の村、デル・エル=メディーナの住民に特別に厚く崇拝され、守護神とみなされていた。デル・エル=メディーナの遺跡とベルナール・ブリュイエールは、テーベ山中にある砂漠の小さな谷の窪みにある。この遺跡は、新王国時代の王家の谷や王妃の谷の墓の造営に従事した職人たちの居住地と墓地だった。アメンヘテプ1世のアメン神への信仰が深く、テーベ(現ルクソール)のナイル川東岸にアメン神を祀るカルナック神殿を建設した。カルナック大神殿は、ルクソール神殿(カルナック神殿の副殿。カルナック神殿とは、スフィンクスが並ぶ約3kmの参道でつながっていた)とともに、テーベの町の中心を形作る重要な建造物だ。この時代特有の、墓と神殿を切り離す形式を最初に考案したのは、この王だとされている。 カルナック神殿は、地方神であるアメン神の神殿として造られていた。地方神だったアメン神が太陽神ラーと結合し、国家の最高神に変貌すると、歴代の王も神殿や像の寄進を繰り返すようになった。小さな地方神殿は、未完成ながら高さ43mというエジプトで最大の第一塔門や、巨大な柱が並ぶ大列柱室、そしてトトメス1世とその娘のハトシェプスト女王の巨大なオベリスクなど巨大な建造物群となり、今ではエジプト最大の神殿となっている。第二塔門に二枚の羽根の冠をかぶるアメン神が浮彫りされている。 古代エジプトのオベリスクは、初期の頃では太陽神殿の入口の両側に2本ペアで建設された。言わば太陽神と共に王の権威を示すモニュメントmonumentであった。新王国時代に、それまではテーベの守護神で豊穣の神であったアメン神が太陽神であるラーと一体化してから、カルナックのアメン大神殿のように神殿の入口にもオベリスクが建てられるようになった。カルナック神殿は花崗岩で築かれ、現在もその姿を残している。ファラオの宮殿は日干し煉瓦で造られたため、今日では殆ど遺っていない。 この時代は、父王の時代と同じく、内政を諸侯に任せて分業する形式がとられていた。内治においては官僚制度を整備し、軍事面では父イアフメスが戦争に苦しんだことから、軍制military systemを全面的に改革したのち、前王の時代に引き続き、北方シリア、南方ヌビアへの遠征し、ヌビアを平定した。彼の作り上げた戦闘集団としてのエジプトの軍隊と優秀な官僚制度は新王国繁栄の礎となり、内政が安定していれば遠征に専念できる。 自分の王権を絶対化させるための政治取引として、先王イアフメス1世の娘・自分の妹の娘婿のトトメス1世を自らの後継と定めた王位を盤石にした。アメンヘテプ1世の父王イアフメス王が、エジプト中王国以来栄えていたナイル川中流域の都市テーベの守護神として崇められていたが、それでもテーベ南方の地方神で過ぎなかったアメン神を、古来の太陽神ラーと一体化して、アメン=ラー信仰(アメン=ラー)が起こした。イアフメス1世の息子アメンヘテプ1世は、神聖権威を身にまとう王権の体制を布くため、そのアメン神を国家の最高神に変貌させ、ファラオを「アメンの子」と認識させた。ファラオ達はそれを誇示するため、自分の名前に神々の名を入れていく。例えばアメンホテプは「アメン神を崇める者」という意味、トトメスは「月の神であるトト神に作り出された者」という意味である。 アメン神の信仰は基本的には多神教で、いろいろな神が存在していたが、アメン神が主神の座に就いた。イアフメス王の後継アメンヘテプ1世はヌビアを平定し、カルナック神殿を造営した。多数の神官が組織されて、新王国の歴代ファラオは、盛んにシリアやパレスティナに出兵するが、その際、戦勝を祈願して、テーベのアメン神殿に戦利品や征服地の租税など多額の寄進を誓った。やがてアメン神殿を管理するアメン神官団は、莫大な財産を背景に発言権を増し政治に介入するようになると、王位継承などにも干渉し、神官の勢力は王朝の政治を左右するほどになった。 エジプトの最盛期を迎えるアメンヘテプ3世の治世下(BC1391~BC1353年)に、偉大な王妃イアフメス・ネフェルトイリは、息子のアメンヘテプ1世とともに神格化された。 彼のミイラは現在、カイロのエジプト考古学博物館で展示されている。首に花輪をかけ、ミイラマスクをつけた状態で展示されている。棺に入り込んだハチがミイラと一緒に見つかっており、「昆虫ミイラ」とされている。 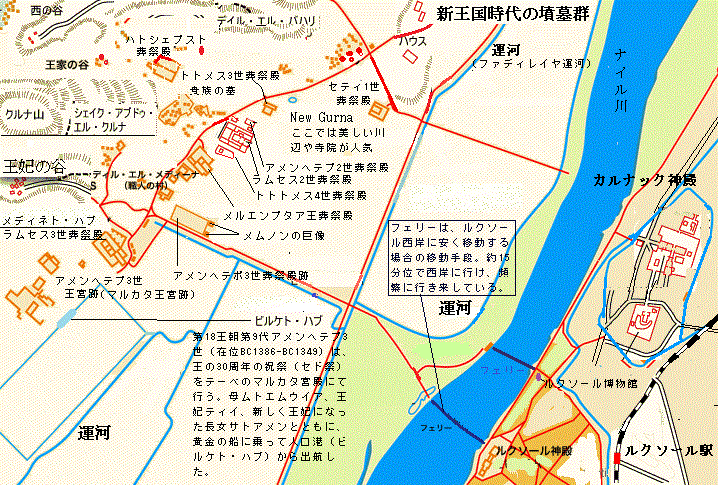 ハトシェプスト女王 2007年6月27日、エジプト政府はカイロ市内で記者会見し、1903年にルクソールの「王家の谷」の墓の1つから発見された女性の2体のミイラのうちの1体が、古代エジプト新王国時代第18王朝のハトシェプストHatshepsut女王と特定されたと発表した。 CTスキャナー撮影により3D画像を作成し、2体のうち1体の身体的特徴がハトシェプスト女王の子孫のものと結びついた。さらに、歯が収められていた箱には女王の名前が刻まれており、CTスキャナーで撮影したところ、箱の歯はミイラの臼歯が抜けた隙間と1mmの狂いもなく一致した。もう1つの棺から見つかった女性のミイラは身元が特定できなかった。 愛と美と豊穣と幸運のハトホル女神は、ウシの耳や角、そして独特の髪型で表現されている。同じ表現が王妃の像でも見られることがある。独特の巻き髪は、ハトホル女神の典型的な髪型の1つであるが、王妃がその独特の巻き髪をすることで、ハトホル女神の神性を借りて、人を超えた存在として権威を高める。古代エジプトの中でも、新王国時代の第18王朝は特に王妃が活躍した時代である。本来ファラオには男性しかなれない。女性のファラオが登場したのもこの時代で、男装の女王として登場する。 ハトシェプストは、BC1500年頃から活躍した。古代エジプトでは、王位継承の条件として、王家の血筋が極めて重要であった。ハトシェプストの父トトメス1世は、主流でない王族であり、軍人出身であった。第18王朝を樹立したイアフメス王の王女と結婚して王位に即いた。二人の間に生まれたハトシェプストは、母から王家の血筋を受け継いだ。 トトメス1世の跡を継いだトトメス2世は側室の生んだ王子であった。正妻の娘であるハトシェプストと結婚することで、王家の血筋を継いで行ける。ハトシェプストが大きな力を得たのも、新王国時代創建の第18王朝初代のイアフメス王直系の孫であったからである ハトシェプストの夫トトメス2世は、治世間もなく、死去した。側室が生んだ王子トトメス3世 はまだ幼く、このような場合の伝統に従って、王妃ハトシェプストがトトメス3世の共同統治者として国を治めた。ハトシェプストは当初から実権を握っており、数年後には「ファラオ」を名乗るようになる。ハトシェプストは夫の死後、ファラオの妻ではなく、「アメン神の妻」という称号を好んで使うようになった。 ハトシェプストは、碑文では自分が女性であることを隠していない。名前の下には、女性であることを示すヒエログリフが殆どの場合ついている。その治世の初期に赤色花崗岩でつくられた座像を見ると、体つきは明らかに女性だが、王権のシンボルである聖蛇ウラエウスのついた縞模様のネメス頭巾(額に長方形の布を当て、耳を出す形で頭を覆い、折りたたんだ布で両肩に垂れ飾りを形作る)をかぶっている。神殿の浮き彫りでは、足首までの長さの伝統的な女性の衣服を身にまとっているものや、足を大きく広げて、堂々たるファラオのポーズをとっているものなどがある。 本来ファラオには男性しかなれない。それで男装、つまり本来の正しいファラオの姿形となることで、自分の権威を高めようとした。女性のファラオは、余りにも異例のことであった。やがて、男性の装いの方が統治しやすいと考えたのか、完全に男のファラオとして自分を描かせるようになった。この頃の彫像や浮き彫りには、ファラオの頭巾をかぶり、付け髭をし、短いキルトの両端を前で交差させるシェンジュウトと呼ばれる腰布をまとい、女性であることを示す特徴を殆ど隠している。 葬祭殿のレリーフには、自分の王位継承は神の意思によるものだという銘文を刻ませている。また、父のトトメス1世が自分を跡継ぎにすることを望んだばかりか、王位継承の儀式も見届けたとの作り話も浮彫りしている。その浮彫りでは、偉大な神アメンがトトメス1世の姿を借りて、ハトシェプストの母親の前に現れ、牡羊の頭をもつ創造の神クヌム(轆轤を回して粘土で人間をつくる神)に、「私のために、あらゆる神々よりもすぐれた娘をつくるのだ」と命じたと伝えとぃる。 ハトシェプストは、男性のファラオのように、戦争で勇ましく戦うことはできい。それで内政に優れた手腕を発揮した。ハトシェプストは交易を進め、中でもナイル川上流深くプント(現在のエチオピアやエリトリア周辺)にまで交易使節団を派遣した。ハトシェプスト女王葬祭殿のレリーフには、香木などの贅沢品が運び込む様子が描かれている。 互いに使節団を派遣し合い、それぞれの産物を交換するという事業を、研究者は「ロイヤル・ギフトの交換」と呼んでいる。この国による大規模交易は、外交に優れた効果を及ぼした。この時期の地中海・西アジア地域は、各地で密接なつながりが生じ「グローバル」な世界へと発展していった。ハトシェプストによる「ロイヤル・ギフトの交換」が推進した交易が、その先駆けとなったと評価されている。 また、女王の治世下、シナイ半島では金の採掘が行われ、国内のいたるところで大規模な建築事業が推進された。偉大な神アメンを祀った広大なカルナック神殿には、花崗岩のオベリスクを4本建立した。数あるオベリスクの中でも、屈指の壮麗さを誇るものとなった。シナイ半島からナイル川上流域のヌビア地方まで、数々の神殿を修復し、新たに造営もした。ハトシェプスト女王が残した建築のうち、最高傑作として名高いのが、現在のルクソールの西岸、王家の谷の東側の断崖を背に建てられているアル=ディール・アル=バハリにある葬祭殿である。 葬祭殿は、モダンな3階建ての建造物で、各階に広いテラスが設けられている。2階のテラスの左端はハトホル女神の礼拝所となっている。その隣には女王が派遣したプント国との交易を描いたレリーフが遺っている。ハトホル女神礼拝所には、牛の耳を持つハトホル女神の顔を刻んだハトホル柱や、ハトホル女神の象徴である牝牛のレリーフなどが色も鮮やかに遺っている。牛の姿をしたハトホル女神の乳を飲むハトシェプスト女王のレリーフもある。 断崖を背にして築かれた葬祭殿は、美しさと迫力を兼ね備えた見事な景観となっている。 背後の断崖の向こう側は、新王国時代の歴代の墓が造営されている「王家の谷」である。ハトシェプストも王として、王家の谷に大規模な墓を造営した。 ハトシェプストは、王都テーベの都市レイアウトを完成させるなど、第18王朝繁栄の基礎を築いた。 彼女の死後、女王の像は息子トトメス3世によって徹底的に破壊され、王名表からも名前が削られた。女王になる前の像は遺されているので、女王としてのハトシェプストの痕跡だけを隠滅させた。 2階のテラスに向かって右端はアヌビス神の礼拝所。そして、3階には女王の墓に続くとも言われる至聖所がある。庶子のトトメス3世が単独の王になった時に、葬祭殿の女王のハトシェプストの浮き彫りや像のほぼすべてが、神殿や記念碑から削りとられている。彼女の彫像は打ち砕かれ、穴に投げこまれていた。 カルナック神殿では、ハトシェプストの浮き彫りや、カルトゥーシュと呼ばれる枠で囲んだ紋章が削りとられ、オベリスクに刻まれた銘文は、周りに石を積み上げて隠されていた。そのおかげで、偶然にも現代まできれいな状態で保存された。 葬祭殿では、ハトシェプストを王妃として描いた浮き彫りは破壊をまぬがれたものの、ファラオとして描いたものは、一つ残らず削りとられた。破壊は念入りかつ計画的になされたようだ。 「感情に駆られた命令とは思えません。政治的な決断でしょう」と、1961年から葬祭殿を調査してきたポーランドの調査隊の責任者ズビグニエフ・サフランスキーの見解である。 1960年代の発掘調査で、ファラオとしてのハトシェプストの事跡が抹消され始めたのは、彼女の死後少なくとも20年たってからであることが明らかになった。これで、継母にいじめられた息子が憎悪に駆られて復讐したとする解釈は覆された。 今では、トトメス3世は、息子のアメンヘテプ2世が他の親族との跡目争いに勝って自分の跡を継げるよう、息子の王位継承権の正統性を強調する必要があったためと考えられている。こうした解釈により、ハトシェプストの評価も変わり、権力欲の強い冷酷な女ではなく、すぐれた為政者と見られるようになった。 2005年、エジプト考古庁長官のザヒ・ハワスは、研究チームを率いて、ハトシェプストのミイラ探しを始めた。調査の過程で、有力視されたのがKV60a号と呼ばれるミイラであった。このミイラは1903年にハワード・カーターが発見した王家の谷のKV60と言う小さな墓から見つかった2体のミイラの1つであった。ハワード・カーターは、イギリスのケンジントン生まれのエジプト考古学者で、1922年、「世紀の発見」と高く評価されるツタンカーメン王の墓を発見した。その発掘が契機になり、古代エジプト史の研究を加速化させ、エジプト史に新たな歴史観を提示するなど画期的な成果に繋がった。 王家の谷の比較的下位にあるKV60号墓でミイラが安置されていた。それは、100年以上も前に発見されたミイラであった。KV60a号は長年、棺にも入れられずに墓に放置されていた。頭巾も着けず、宝石・黄金のサンダルや指輪もなく、ツタンカーメン王のミイラを飾っていたような数々の財宝も一切なく、無残にもうち捨てられ朽ち果てていた。 今ではこのミイラは、エジプト博物館に2室ある「王家のミイラ室」の1室に納められ、そのケースの銘板にはアラビア語と英語で、「ハトシェプスト女王」と書かれている。その遺体はようやく、血縁者であるエジプト新王国時代のファラオ達とともに、この部屋に安置された。 21年間に及ぶエジプトの統治であれば、当然、後世に自分の事績を誇りたかったハトシェプストだったが、その事跡が消し去られたばかりか、遺体も長く置き去りにされていた。 ハトシェプストの死は、トトメス3世による謀殺が疑われていたが、そのミイラの調査により、癌を患い、また虫歯と糖尿病に悩む太り気味の女性であった。 トトメス3世 トトメス3世は、義母ハトシェプストが亡くなり、単独の王になると対外遠征を積極化した。長年、トトメス3世は、ハトシェプストの政治を補佐したに過ぎず、大半の時間を軍隊で過ごしたため、高い軍事的能力を身につけていた。トトメス3世の治世33年の間で第8回のアジア遠征が最大の規模で行われた。BC15世紀、トトメス3世率いるエジプト軍とカデシュ王率いるカナン連合軍(カデシュ・メギドなどのレバントの都市国家群がミタンニ王国と連合)がハラブ(アレッポ)付近で遭遇し戦闘が行われた。トトメス3世はこれに勝利し、メギドの都市に敗走させ、そのメギドを7ヵ月にわたり攻囲し開城させた。 更にユーフラテス川を超えて前進し、シリアからミタンニ軍を駆逐した。ファラオと共に従軍した書記により複合弓(特に木製、竹製の材料に、動物の骨・角や腱、鉄や銅の金属板など複数の材料を張り合わせ、その射程と破壊力を向上させた弓)の使用や死者数など、ヒエログリフで描かれた歴史上最古の記録が遺る戦いとなった。カルナック神殿の外壁のレリーフがそれである。 メギドの戦いでの大勝は、パレスチナでのエジプト軍の優位性を決定的なものとした。「カナン」と言う地名自体、古代エジプト王朝の州の名称として使われたのが初見とみられる。その領域は、地中海を西の境界とし、北は南レバノンのハマト、東はヨルダン渓谷、そして南は死海からガザまでを含む。シュメール人の都市マリのBC18世紀頃の残骸の中で発見された文書に、都市国家相互間のゆるい連合域として記されている。 アジア遠征によってシリア支配を確立したトトメス3世は南方に軍を転じ、スーダン北部にあたるナイル川第4急湍のナバタ地方(クシュの首都ナパタ、ナイル川の屈曲部沿いに高さ98mの小山ゲベル・バルカルがある)までを征服し、エジプト史上空前の領土を獲得するに至った。ヌビアを第二瀑布を境に下ヌビア(ワワト)と上ヌビア(クシュ)に分割し、それぞれに副総督が置かれてヌビア総督(南のヌビアの王子)を補佐する体制が築かれた。古代エジプト史上最大の版図から大量の富が流入し、エジプトは空前の繁栄を謳歌した。 トトメス3世は、ヌビアとアジアへの軍事遠征によりエジプトの領土を最大にする。第9代のファラオ・アメンヘテプ3世(在位期間BC1388~1351年頃まで,約38年に及ぶ)の治世は、古代エジプトが文化的、経済的に最も繁栄した時期であり、エジプトの領土は依然として最大規模を誇っていた。アメンヘテプ3世は、財政規模を拡大させると、マルカタ王宮やアメンヘテプ3世葬祭神殿など、エジプト各地で大規模な建築活動を数多く行っている。 トトメス3世からアメンヘテプ3世までの時代が、エジプトが広くオリエント全域にその権勢を揮った「帝国時代」とも呼ばれる極盛期となった。首都テーベには異国の人が往来し、各地の産物が集った。 早稲田大学古代エジプト調査隊は、1974年1月、ルクソール西岸のマルカタ南遺跡のコム・アル=サマック(魚の丘)で、アメンヘテプ3世の彩色階段を発見した。そのルクソール西岸のネクロポリスには、アメンヘテプ3世時代の岩窟墓がある。その西岸の王家の谷は東谷と西谷があり、東谷にはトトメス3世王墓・ツタンカーメン(トゥトアンクアメン)王墓・ラムセス2世王墓など、新王国時代の王墓を含む埋葬施設がある。アメンヘテプ3世王墓は、王家の谷の入口から西側に入る西谷にあり、アイ王墓(王族だが、アメンホテプ3世の時代からの古参の臣、ツタンカーメンの治世ではアメン大神官の地位にあった)などもある。アメンヘテプ3世王墓の規模は、第18王朝の中で最大である。その王墓に描かれた壁画は、緻密で色鮮やか、古代エジプト史の中でも最高水準にある。王の副葬品には、王妃ティイのものと考えられる黄色ファイアンス製シャブティ片(副葬品として埋葬されたミイラ本人を象った小像、死後必要な労働を死者の代わりに行う)、アメンヘテプ3世の青色ファイアンス製ブレスレット片とシャブティ片など、王の重要な遺物が多数出土した。 アメンヘテプ3世の王妃ティイは、のレリーフがテーベ西岸のウセルハト墓で出土した(ブリュッセル・ベルギー王立美術歴史博物館蔵)。ティイは王族ではなかった。新王国時代で最初の平民出身の王妃であった。アメンヘテプ3世の父親であったトトメス4世もまた、王族出身ではないネフェルトイリを正妃としている。新王国時代は、王族の女性と結婚することが慣例であった。トトメス4世やアメンヘテプ3世のように王族以外から正妃を選ぶのは極めて異例のものであった。 そんな伝統的な王の婚姻慣習を破ってまでも、王族出身ではない女性と結婚できたのも、専制王として絶対的な権勢を有していたからである。 ウィーン美術史美術館が蔵する王妃ティイとの結婚に際して作られた「アメンヘテプ3世の記念スカラベ」には、王妃ティイの両親の名前が刻まれている。それによると、ティイの父親はイウヤ、母親はチュウヤTjuyu(チュイア、トゥイウ)という名である。イウヤは中部エジプトのアクミム(アフミーム;水の便が良く商業中継都市として発展し,織物業が盛ん)出身の有力者であり、アメンヘテプ3世は、イウヤの娘と結婚することで強力な王権を築くことができた。イウヤとチュウヤは、王家の谷に彼らの墓を築く特権を得ていた。その墓は、1905年にイギリス人考古学者のキベルJ. E. Quibellにより発見され、墓内部からは非常に保存状態の良いミイラ・マスクをつけた二人のミイラや多数の副葬品が発見されている。 イウヤのミイラは、古代エジプトの死体防腐処置技術の粋を尽くして作られている。イウヤとその妻チュウヤは、死亡時50~60歳だったとみられる。夫イウヤ同様、チュウヤは埋葬設備の碑銘から身元が判明した。彼女の名前に加え、王の着付け係、アメン神の歌姫、ミン神のハーレムを取り仕切る婦人といった肩書がヒエログリフで記されていた。 イウヤとチュウヤは王族ではないが、社会の上流層の一員であった。彼らの娘ティイは、エジプト史屈指の強力なファラオ・アメンへテプ3世と結婚した。ツタンカーメンの父はおそらくティイとアメンヘテプ3世の息子アメンヘテプ4世(アクエンアテン)で、母は外国から来た王妃とされるキヤである。だが、他のファラオと同様、アクエンアテンには複数の妻がいた。その1人がネフェルティティで、ツタンカーメンにとっては継母にあたる。その継母ネフェルティティとアクエンアテンの間には6人の娘が生まれた。ツタンカーメンはその1人、つまり異母きょうだいのアンケセナーメンと結婚した。このため、ツタンカーメンとその妻のどちらにとっても、イウヤとチュウヤは曾祖父母なのだ。 イウヤとチュウヤが亡くなったとき、近親の王族たちは2人が最も上等な地に、第18・19王朝の王族が眠る広大な墓地「王家の谷」に埋葬した。1905年に発見されたイウヤとトゥヤの墓は、KV46と呼ばれている。イウヤとチュウヤの亡骸は、現存するミイラの中でも圧倒的に保存状態がよい。ミイラ作りには時間と費用がかかるが、防腐処置師たちはいくらでも使えたようだ。 ネフェルティティの名の大意は、「美しい・者(NeFeR-T-)が訪れた(iTi)」となる。ネフェルティティの正体は、エジプトにやってきたミタンニ(BC15世紀、メソポタミアの北方の山岳地帯を支配したミタンニ人が建てたメソポタミア北部の王国)という国の王女タドゥキパ、という説がある。ベルリン国立博物館が所蔵するアケタートン (現テル・エル・アマルナ) で発見されたその美しい胸像が特に有名である。6人の娘を産み、そのうち2人はエジプトの女王となった。ドイツの発見者が「石こうに色を付けた王女の胸像だ」と騙して持ち出した。エジプトは返還を迫っている。 (スカラベは、古代エジプト人が神聖視した甲虫の一種、または甲虫を象ったエジプトの宝石彫刻。この虫の名は、古代エジプト語の1つケペレル語では「生成」の意味することから、天地創造の太陽神ケペラのシンボルとして崇拝され、多くの護符や装身具、王名や貴人の名を刻んで印章などにして着用する風習があった。) アメンヘテプ4世(アクエンアテン)と太陽神アテン 湖の造営に関する「アメンヘテプ3世の記念スカラベ」は大英博物館が蔵している。アメンヘテプ3世の治世11年に、王妃ティイの出身地であるアクミム近郊のジャルカという町に、長さが1.9㎞、幅が0.36㎞の巨大な人造湖を2週間ほどで完成させたことが記されている。王は、この湖の完成の式典で「輝くアテン」という名の船に乗ったことが記されている。アマルナ時代に唯一神として崇拝されたアテンの名前が使われていたことは、非常に興味深い。この太陽神アテンを唯一神とする宗教改革を断行したアメンヘテプ4世は、アメンヘテプ3世と王妃ティイの息子である。王妃ティイは、王太后になっていた。アメンヘテプ4世は、王の治世4年に中部エジプトに位置するテル・アル=アマルナの地を公式訪問する。この公式訪問には、王妃ネフェルトイティとともに、母であるティイも同行していた。 アメン神官は政治にも大きな影響を与える程強大になり、しかも驕慢になり堕落していた。アメンホテプ4世はそれまでの神々を否定し、アテン神が唯一の神であると、宗教改革を打ち出した。アメンホテプ4世として即位してから5年後、、テーベから280キロ程離れた現在のアマルナに遷都し、新しい王宮の建設が決定された。新首都は「太陽円盤の地平を意味」するアケトアテンと名づけられた。王は自らの名前を「アクエンアテン(アテンに愛されし者, アテンに仕える者)」と改名し、アテン神を唯一神とし、伝統的な美術様式にはとらわれない「アマルナ様式」という新しい美術様式を育てた。新王国・第18王朝時代の大きな変革期となるアマルナ時代の誕生に、王太后ティイは重要な役割を演じたと考えられる。 古い体制を払拭すべく改革を半ば強引に進めて行く。この宗教改革の最大の目的は力を持ちすぎた神官たちを抑え、王の権威を再復興することにある。テーベのカルナック神殿を中心とするアメンの神官団の台頭が著しかった。寄進によって多くの土地が神殿の所領とされ、ファイユームに至る各地方の財政さえも管轄下に置かれた。その為にアテン以外の神々を否定した。アテン神は、太陽を模す円系から無数の手が出ている絵で描かれる。太陽神の力は、日中の太陽を通じて、太陽からの恵みとして表現される。人々はアテン神から、身分・地位・貧富などに関わらず平等に恩寵が受けられると説く。 『全てはアテンから生まれ、アテンに還る。すなわちアテンが全てである。』と説き、偶像崇拝を否定した。偶像崇拝の意味するところは、アテン神以前の神々は人型であったり動物型であったり、何かに宿る形で存在していた。しかしアテン神の本性は、太陽が空を明るくし、大地を温め、植物を成長させる力そのものであるとした。 アクエンアテンはアテン神を拝礼する為に神殿は要らない、アテン神は太陽そのもの、誰もがどこからでも拝礼できるとした。神殿の管理人である神官は不要とした。 ちなみに、都であるアケトアテンにはアテン神殿があった。ここに仕える神官はファラオにより新たに募集され、旧体制の排除が進められた。 エジプトでは、王が、神と人間の仲介役を担っていたが、アクエンアテンの統治下では、王と王妃がこの役割を担うことになる。王夫婦はかつて無いほど精力的にこの役割を果たした。太陽はアテン神の姿を取らず、実在感が希薄な単なる太陽円盤として表現された。地上における神の唯一の具現者は王夫婦となった。従って、宗教的図像では、王と王妃だけが太陽光線を浴びている。この彫像の銘文にも、太陽と王および王妃の深い関係を示した内容が刻まれ、王の後ろには 「地平線に君臨する太陽よ、アテン神の円盤から発する日光となって地平線で喜び輝く太陽よ、永遠に生き続けよ。上エジプトと下エジプトの王、ネフェルケペルウラー・ウアエンラー(アクエンアテン王)よ、永遠に生き続けよ」と記してあり、王妃の後ろには、同様の神の名に続いて「偉大なる王妃ネフェルネフェルアテン・ネフェルトイティ王妃よ、永遠に生き続けよ」と書かれている。 アマルナ発掘では、私人の住居から、王と王妃を描いたステラ(石碑)や彫像など、記念の小品がいくつか発見された。アテン神の太陽円盤の地上で、唯一生きた姿として描かれる王夫婦が崇拝され、多くの家庭には(偶像崇拝を否定した)王夫婦を祀るための小祭壇があった。この彫像らは、持ち運びやすく場所を取られず、日常の安寧を願う対象であったと思われる。背面支持板に書かれた一連の聖なる称号から、彫像の制作年代が特定できる。このような称号はアメンヘテプ4世(アクエンアテン)の統治下9年目以降からしか見かけられない。BC1345年から王の亡くなった年のBC1337年までのごく短い期間に制作されたと言える。 この時期の芸術品は都があった場所の地名をとり、アマルナ芸術と呼ばれる。有名なのが、ベルリンの博物館にあるネフェルティティ像(アクエンアテンの正妃)で写実的で実に美しい。容貌も人間味に溢れたている。かつてのファラオは自身を神格化する事が優先され、容姿は伝統的で画一的である。写実性に欠けていた。しかしアマルナ芸術は伝統に囚われない自然主義で、ありのままの美しさを表現する。宗教的思想ばかりでなく芸術や庶民生活に新風を巻き起こした。先代のファラオが築いた莫大な財産を元手に、改革は急激に進められた。 それが余りにも急進過ぎたため、神官たちの反発を買う。加えて、疫病の突発的な猛威により衰退を余儀なくされた。またアクエンアテン王は戦いが嫌いで、他国の侵略に対して、アテン神に祈れば乗り切れると説いたと言う。実際、祈るだけでは解決できず、軍人達にも不満が広がり、結局、アクエンアテン王の死をもって改革が途絶し、アマルナ(古代エジプトではアケトアテン )が終焉を迎える事となった。死後、アクエンアテンは異端の王と嫌気され、都や神殿は取り壊され、別の神殿の建材として再利用され、ほぼ残っていない。歴代のファラオの名が連なるリストからも消され、歴史から抹消された。あの大発見がされるまでは… その後ファラオは9歳の少年王、息子のトゥートゥ・アンク・アメン(ツタンカーメン)に引き継がれていく。実際はトゥートゥ・アンク・アメンの前の2年間、スメンクカーラーという人物がファラオになっている。 マディーナト・グラーブ遺跡 王妃ティイの名前が、アメンヘテプ3世の名前と並んで記されている作品が数多く遺されている。へラクレオポリス地域は、現在のエジプトの首都カイロから約120km 南の ナイル川西岸の一帯を占める地域で、古代の行政区分では上エジプト第20ノモスにあたる。ノモス行政の中心地は、王朝時代を通じてへラクレオポリス・マグナ(現;イフナーシア・アルニマディーナ)にある。テー べやメンフィスといった中心都市以外では、最も豊富な考古学資料を提供してくれる。ここのファイユーム地域には、、新王国時代・第18王朝のトトメス3 世治世下に建設された都市、マディーナト・グラーブ遺跡がある。この王宮複合体は、第20王朝のラムセス5世治世下(在位:BC1145年~ BC1141年;天然痘により在位期間4年で死去)まで存続していた。 このファイユーム地域遺跡は、ナイル川から遠く離れているため、地域的な方位を川の流路に求めることはできない。北東から南西方向に直線的に伸ぴる、緑地と砂漠の境界が地域的な方位を決めているようだ。王宮周辺には居住域が広がり、その周辺に墓域が展開している。墳墓を時代別に見ると、活動が 盛んであった新王国時代に属するものが最も多く、しかもこの時代には土坑墓 だけでなく王宮や周辺地区の経営に携わった人々の竪穴墓shaft tombや、 日乾煉瓦造 の礼拝堂を備えた大型墓も多数造営されている。 発掘された王宮に属する建物の大部分は、王家の女性達が暮らした新王国時代の「ハーレム(後宮)」があった。グラーブ遺跡は、湖と豊かな自然が満喫できるファイユーム・オアシスへの入口にあった。第18王朝時代のトトメス3世により造営が始まり、その後、新王国時代(第18~20王朝)を通じて利用されていた。ただ、トトメス3世がグラーブに滞在したのは1年のうちの僅かな期間だったと推測されいる。 王が不在の間、ハーレム(後宮)の女性達は、機織りなどの仕事を担当していた。ハーレム(後宮)は王室の工房でもあった。生産されていた、薄くて白い亜麻布(あまぬの;リネンlinen、アマ科の一年草・亜麻の繊維を原料とした織物の総称。広義で麻繊維に含まれ、麻特有のカラッとした風合いがある)は、当時は貴重で高価なものであった。出土した碑文から、「機織りの長」という称号を持つ女性がいたことが知られる。このグラーブでは、紡錘車や糸玉など、亜麻布生産に関連する用具が多数出土している。ガラス容器も香油などを入れるため意匠をこらし、粘土などで作った芯には、ガラス棒が巻きつけられていた。表面の文様も、溶けた色ガラスの棒を巻き付けて、固まる前に引っ掻いて作り出されている。高級オイルや香油はエーゲ海地域、最も品質の高いと言われるクレタ島などで生産され、「鐙壺(あぶみつぼ);鐙は馬具の一つ、騎乗者の足を乗せる部分が袋状になっているもの、壺の把手がそれに似ていた」に入れられて、エジプトへ輸出されていた。 グラーブの墓から出土したファイアンス容器などは、「ハーレム」で暮らした高貴な女性達も使った高価な品々であった。エジプトの職人は、多くの「鐙壺っぽい」高級な彩色陶器を作っていた。ファイアンス容器は、繊細な淡黄色の土の上に錫釉をかけた陶磁器を指す。酸化スズを添加することで絵付けに適した白い釉薬が考案され、古代の陶芸は大きく発展することになった。 このマディーナト・グラーブ遺跡から、ティイの名を刻した供物台が発見されている。これはティイがアメンヘテプ3世のために副葬品として用意したものである。しかも、王妃ティイの名前が、アメンヘテプ3世の名前と並んで記されている作品が数多く遺されている。第18王朝時代の絶頂期の王アメンヘテプ3世の補佐役として、王妃ティイは、常に夫の傍らにいて重要な役割を果たしていたようだ。 王の死後は、息子のアメンヘテプ4世とともにアマルナ王宮に移り住んだ。ティイの孫にあたるツタンカーメン王墓からは、彼女の髪の毛が発見されている。ティイの遺体は再びテーベに戻されたと推測される。「高齢の婦人the elder Lady」と呼ばれる髪の長い女性のミイラが、ティイのものではないかとされている。 第 18王朝はイアフメス王以下 14人の王が統治した。 トトメス3世の時代には6000人、アメンホテプ2世は10万人の奴隷を連れ帰った。ラムセス2世の時代には神殿に仕える奴隷だけで113,433名が記録されている。奴隷として連れてこられた人々の大半はエジプトに定住する道を選んだようだ。 ナイル川は全長 6695kmに及ぶ世界最長の大河、毎年夏季にゆるやかな大氾濫をよび起こし、流域一帯を肥沃な大地に変える。溜池や灌漑を怠らなければ、年2回の収穫が可能な豊かな大農業地帯である。他の地中海沿岸と比べれば自ずとわかる掛け替えのない大地が広がっている。このエジプトに入って来た多くの形跡はあっても大規模に脱出した記録がないのも不思議ではない。 巨石を組み上げて高さ約150mのピラミッドを造るには膨大な労働力が必要だ。建設に携わった人々の大半は、無理やり働かせられる奴隷ではなく、むしろ優良なエジプト国民であった。それでも、奴隷同然に扱われる低報酬の労働者だったのだろうか。かつては、痩せさらばえた身なりの人々が、鞭に打たれながら荷船から巨石を降ろして木そりに載せ、ピラミッドまで引いていく過酷な労働で消耗すれば使い捨てにされるイメージがあった。 近年、ギザの大ピラミッド近くの古代都市「ヘイト・エル=グラブ」と、同時代に栄えた紅海の港「ワディ・エル=ジャルフ」での発掘調査などにより、古代エジプトのクフ王など歴代の王の大ピラミッドを築いた人々は精鋭の労働者集団であり、遠く離れた地域から食料や生活用品、建築資材を船で運ぶ交易の担い手であったことがわかってきた。しかも、高度な計算技術と管理能力を兼ね備えた者達を、組織的にを育てる社会的インフラが整備されていたようだ。 その巨大な建造費用を消費するピラミッドや神殿建設に不可欠だった多大過ぎる程の労働力を継続的に組織化し、その財源となる地中海沿岸を広域的に展開する交易網を充実させ、長期にわたってエジプトに莫大な富をもたらし、何世紀にも及ぶエジプトの繁栄を支え続けることができる集団が育っていた。 古代の「ヘイト・エル=グラブ」は、クフ王のピラミッドの南東約1kmの場所にある。今はナイル川から離れているが、ピラミッド建設当時はナイル川に面した港町であった。発掘により、その港町は予想よりもはるかに立派で、周到な都市計画のもとで設計・建設されていた。 労働者の居住区画は、通りの両側に細長い建物が立ち並び、それぞれの建物には炉床と労働者40人分の寝床、監督官用と思われる別室が1つ設けられていた。 遺跡の一角から、パンを焼くのに使われた壺などが出土しており、そこはパン焼き場だったと考えられている。そのパン焼き場の南には大きな建物があり、おそらく食堂であろう。その隣には穀物貯蔵庫と思われる建物群や家畜を飼っていたと思われる囲いの壁があった。 ここの住民は6000人程で、その時代では極めて恵まれた環境であった。ピラミッド建設の長く辛い1日の労働を終え、食事をしに町に戻り、焼きたてパンと羊の肉や乳などを頼み、翌日に備え今夜のメニューとして大勢の仲間が集い談笑しながら食べた。 王妃の谷(ネフェルタリ女王の墓)
ネフェルタリは、第19王朝時代の第3代目のファラオ、ラムセス2世(在位;BC1290年頃~BC 1224年頃)の最初の正妃(第一王妃)、神后(God's Wife)の称号を持ち、この称号によって多くの富を授けられたとされる。 (ヒッタイト王国を建国し、BC1680年~BC1650年頃に統治したラバルナ1世の妃タワナアンナの名がそのまま第一后妃の称号となった。タワナアンナは妃の称号ではあるが、既に独立した身分となり、夫である王が亡くなり皇太后になった後も、そのタワナアンナが生きているかぎりタワナアンナの交代はなく、死ぬまでの身分として保障される。よって、王が交代をしても生きている限り、次の王の妃はタワナアンナの称号・身分を手にすることはできない。例外はほとんどなかった) ネフェルタリはラムセス2世の数多い(100人以上の)妃の中で最も有名な妻、メリトアモンをはじめ5人の息子と娘を儲けたが、若くして世を去った。ネフェルタリが埋葬された王妃墓-QV66は王妃の谷の中でも壮麗なものであり、ラムセス2世が彼女を特別な存在として扱っていたことが窺える。 ネフェルタリが13歳の時に当時15歳、父セティ1世から王位を継承する前のラムセス2世と結婚した。二人はは同年代だった。ラムセス2世の統治期間は、古代エジプト王朝で2番目の長さとなる、67年間であった。古代エジプト王朝で史上最長の統治をするファラオは、第6王朝のペピ2世(BC2216~2153年)で、在位期間は94年間と治世が長いため、晩年には王権が弱体化した。古代エジプトの歴代王の中で最も長く生きた王の一人とされる。 ネフェルタリも便宜上の結婚や政略結婚であり、そしてラムセスの長男アメンヘルケプシェフが生まれると、彼女は同時期に妃となったイシス・ネフェルトよりも早く、最初の正妃になったとされる。彼女の死後、イシス・ネフェルトが正妃となった(イシス・ネフェルトが先に亡くなり、ネフェルタリと一緒に正妃になったの説もある。 ) ネフェルタリの出自については、彼女は「国王の娘」の称号を持っていないので、王族出身ではなく、エジプト貴族の一員であったらしいということ以外殆ど不明である。 彼女は、ネフェルタリ・メリ・エン・ムトとも呼ばれる。意味は「愛らしき者、ムトに寵愛されし者」。ムトはアメンの妻であたる女神である。ネフェルタリはラムセス2世の即位前、彼が15歳の王子であったときに結婚したが、ラムセス2世の8人の正妃のなかでも、上エジプトにおいてもっとも重要な妃の地位にあったと考えられている。ラムセス2世は、最愛の妻を「そなたがため、太陽の燿く者」と呼んだ。王妃の谷のなかにあって、もっとも壮麗なのが彼女の王妃墓-QV66である。他のファラオの妃と違い、ネフェルタリを描く壁画では、ラムセス2世と同等の大きさで描かれている。ラムセス2世の寵愛の深さが偲ばれる。 2016年ネフェルタリの足の骨と認定された骨が見つかり調査の結果、彼女の身長は165cm、その推定死亡年齢は40~60歳くらいとか、その時代の平均寿命は30歳前後と考えられている。2人の間に生まれた息子がファラオになれなかったのは、90歳と長い生きした父より早く死んだためでしようか。 ネファエルタリの墓は、1904年に発見されたが、1950年代に保存状態が悪くなったとして閉鎖された。2016年11月から観光誘致のために再び公開されるようになりました。保護のために1回の見学時間は10分間、また1日150名の限定入場といった制限があります。 アブ・シンベル小神殿の柱に、彼女の美しさについて、語られた記録が残されている。アブ・シンベル神殿は、エジプト最南部とスーダンとの国境近くを流れるナイル川流域にあるヌビア遺跡群の1つである。古代都市アスワンを中心にアブ・シンベルからフィラエ島(旧アギルキア島)までの間に点在するヌビア遺跡群であるが、王国の墓地群やアブ・シンベル神殿、アマダ神殿などの建築物があるが、中でもBC13世紀に建造された巨大なアブ・シンベル大神殿が有名である。 歴代ファラオの中でもヒーロー的存在、父王の死後、約25歳の時に即位したラムセス2世の治世は、エジプト人の誇りとなっている。アブ・シンベル神殿は、そのラムセス2世によりBC1250年頃に造られ大小2つの神殿からなる。大神殿の内部は、エジプトの太陽神ラー、小神殿は、豊穣・幸運・愛・美を司る女神ハトホルを祀り、太陽神、守護神などの神々の石像やレリーフなどの美しさに目を奪われる。砂岩をくり貫いた岩窟神殿で、大神殿入口にある、4体のラムセス2世の座像が印象的である!青年から壮年期の時系列順になっている。だが、左から二番目の像が地震で損壊したままになっている。 「世界遺産」という理念を確立させた大事な遺跡でもある。1960年代、ナイル川にアスワン・ハイダムの建設計画がもち上がり、ヌビア遺跡群が水没する可能性が出てきた。この危機に、エジプトとスーダンの政府はユネスコに、ヌビア遺跡救済を要請した。これが契機となり、世界中の人々の協力により、遺跡は高台へと移設され、水没をまぬがれた。1972年にユネスコ総会で採択されたのが『世界遺産条約』だった。 アブ・シンベル小神殿は、王妃ネフェルタリのために建てられた見られているので、ラムセス2世にとってネフェルタリは、ハトホルの『天空の女主人、・生命の貴婦人・ラーの瞳・トルコ石の貴婦人』などの称号が与えられる価値ある存在だったようだ。 ネフェルタリは比較的早いうちに亡くなっているが、ラムセス2世は彼女の墓の玄室を、溢れんばかりの美しい壁画で満たした。「かの人は死によって、余の魂をはるか遠くに奪い去った」。 ネフェルタリの墓の壁画は、王家の谷にあるファラオの墓を含めても、最高傑作と言える。実は見学料金がかなり高い、2018年2月時点で、王妃の谷にあるネフェルタリの墓の見学には、王妃の谷(80ポンド)とネフェルタリの墓(1000ポンド)が必要で、1ポンド=6円で換算すると6480円と高額になる。ツタンカーメンの墓の見学となると、王家の墓三つ(160ポンド)を含むとツタンカーメンの墓(200ポンド)を合わせると、2160円になる。 かつて、ネフェルタリの墓は塩で覆われ、バクテリアや菌類による損傷が酷かった。1986年から1992年までゲティ研究所とエジプト考古最高評議会が共同でこの墓の修復を行った。元エジプト元考古相のザヒ・ハワスの話として、この修復プロジェクトを開始したときゲティ研究所とエジプト考古最高評議会は、この墓は公開せず、高額の入場料を支払った少数の人が入れるようにすることに合意したと言う。 モーゼが、虐げられたと言うユダヤ人を率いてエジプトから脱出することや、当時のエジプトに在住するイスラエルの民に関する記録などは、その時代の歴史史料に一切痕跡を留めていない。あるのは、旧約聖書にあるユダヤ人の「出エジプト記」だけである。モーゼの紅海の奇蹟でも、そのルートは聖書の記述自体に矛盾があって、場所の特定すら不可能とされている。 エジプトから逃れるためにモーゼに率いられて「出エジプト」を行い、その途中のシナイ山で十戒を授かった「シナイ契約」とがユダヤ教成立の重要な伝承となっているが、モーセは聖書外資料にはまったく現れず、シナイ山の位置も特定できていない。その後、数十年にわたりシナイ半島の荒野をさまよった後に、モーゼの使用人であったヨシュアが指導者となり、ジェリコ(エリコ)の戦いに勝利してカナーン(パレスチナ地方の古名)を征服し、イスラエルの12部族にくじ引きで定住地を与えたという。 しかし、エリコの発掘の結果、その城壁は青銅器時代のBC2300年頃の頃であり、ヨシュアの頃は既に人が住める地域ではなかったようだ。多民族が争闘を繰り返す最中にあって、長い定住の過程を理想化したフィクションと見られている。 BC1900年頃に再び町が建設され、町の領域は初期の壁の外にも拡大し、さらに外側により高い周壁が建設された。BC1560年頃にヒクソスの侵入にあい、大火災に見舞われて廃墟となった。 エリコは海抜260m、死海から続く低地の地溝帯、ヨルダン大峡谷帯にある。エルサレムの丘に降った雨が地中に浸み込み、低地のエリコの町で湧き出すため温暖で泉が豊富、ヨルダン渓谷の常緑のオアシスと呼ばれている。 メソポタミア文明 文明が発達すれば、自然と車輪が発明されるわけではない。マヤ文明にもアステカ文明、さらにインカ文明など、新大陸の社会には車輪の痕跡が存在しない。その移動と運搬は、人の足と獣の背に頼っていた。すべての動きは緩慢で、経済活動は小規模で不活発のままであった。 車輪は、四大文明の中のメソポタミア文明で出現した。メソポタミアでは、荷車・馬車・2輪戦車などを開発した。最古の車輪の実物資料は、円盤形の車輪Disk Wheelである。これは、3 枚の板材を切り出し、それを 合わせて円になるように仕上げた、三枚の板材からなる合成車輪である。このような円盤形の合成車輪は、ウル(Ur)・キシュ(Kish)・スサ(Susa)から出土してい る。車軸の両端にこの車輪を付けるだけで、物の移動は相当に楽になっている。古代のメソポタミアの経済や社会に様々なイノベーションを起きた。車輪と荷車の開発と同時に、野生ロバが家畜化され、橇(そり)や荷車の牽引に利用されはじめた。メソポタミアの土地は川の氾濫のおかげで肥沃な大地はあるものの、資源が非常に少なく、金属資源や木材・石材といった基本的な資源に乏しく、都市と市民の生活の維持に必要な物資は他の地域から輸入しなければならなかった。ウルク期の前の時代、シュメール文明の直前のウバイド期の後半に南メソポタミアと他の地域をつなぐ物流網は既に出来上がっていた。ウバイド文化の担い手が、南メソポタミアに植民して灌漑農耕を始めた。 メソポタミア南部にあった古代都市ウル出土のスタンダードのパネルにモザイクされた戦車、ウルク (Uruk)出土の粘土版に描かれた絵文字などもある。カファージャ出土レリーフやアジェムホユック出土青銅製車輪模型からは、既に車輪と車軸が発明されていたことが判明している。 車輪は元々は轆轤として使われていた。轆轤がいつ発明されたかははっきりしていない。車輪の発明は同じくメソポタミアでBC3500年頃に誕生した轆轤の動きにヒントを得たものと考えられていた。コーカサス北部から車輪が、ポーランドでは車輪を描いた土器が発掘されており、これらはともにBC3500年頃のものと推定されている。車輪の誕生は一つの土地ではなく、時を前後して複数の地で発明されたという可能性が高い。轆轤は青銅器時代に広く使用されるようになった。初期の轆轤は手や足で直接、轆轤を回転させながら壺や食器を形作った。 メソポタミアで都市国家文明を最初に生み出し、高度な文明を営んだシュメール人の民族系統は不明だが、約5000年も前の壁画に車輪付の乗り物を描いていた。車輪の歴史は驚くほど古く、そして時代が経つにつれ、次第にエジプト・インド・黄河流域の社会に伝わっていった。最初はコロに使う丸太を輪切りにし、心棒を付けた程度だった。それが板を組み合わせた円板型、軽量化のためにスポークspokeつき車輪へと発展した。 ティグリス・ユーフラテス川流域(メソポタミア地方南部)に、都市国家キシュ、ウル、ウルク、ラガシュなどを建国したシュメール人は、、メソポタミア文明の基盤を構築した人々である。自らのことを「ウンサンギガ」と呼んでいたようで、その後シュメール文明を征服してこの地に栄えたアッカド人達(アッカド帝国)が、その地域を「シュメール(葦の多い地域という意味)」と呼び、そこの先住者を「シュメール人(Sumerians)」と呼んだ。 シュメール人の都市国家は、BC3800年頃に突如としてこの地に現れ、そこから一気にメソポタミア文明が開花し、目覚ましい発展を遂げた。美術・数学・天文学・建築・宗教などに加えて、行政機構や軍事の発展、文字や文学の発明などをもたらし、非常に高度な都市国家を形成した。また、シュメール人の都市国家は、ジッグラトと呼ばれる7層の塔の神殿(聖塔)を囲むようにして栄えたのが特徴で持っていた。特にバビロンでは国家神マルドゥクに関する儀礼がジッグラトの前で行われた。メソポタミアは沖積平野であるため石材はなく、泥を固めた日干し煉瓦を積み上げ、アスファルトを接着剤として建設した。 シュメール人の残した都市遺跡として最大のものがウルクで、ウルクは城壁に囲まれ、行政機関のセンターとなる遺跡があり、約230ヘクタールの居住地をもっていた。ウルク (Uruk) 期 のBC3800年頃は、「都市化」・「工芸の専業化」・「身分の階層化」といった一連のプロセスを経て、都市化がより機能化するウルク中期・後期に突如l出土する大量生産された小型の粗製鉢が現れる。「容量の規格化」と、階層化した集落内で「強制的な労働」があり、行政機関による「生産管理」が行われていた。後期には公共建築物や一般住居の他に、街路や排水管などの整備が目立つ。 ウルクに次いで繁栄したウルの遺跡からは王墓が発見された。都市遺跡は、他に20ヵ所ほどが知られているが、破壊盗掘されている。このように、非常に高度な文明を築いたシュメール人であるが、その民族的な起源は不明で、BC4000年紀前半にメソポタミア南部に移動してきたと考えられている。メソポタミア地方南部の平野部に、キシュ・ウル・ウルク・ラガシュなどの最初の都市国家群を形成し、麦類やナツメヤシの栽培、牛や羊、山羊や豚などの飼育を行った。 BC2000年初頭、メソポタミアがアムル人およびバビロニア人に支配されると、シュメール人は徐々に文化的アイデンティティを失ない、民族として消滅するのも速かった。シュメール人の歴史、言語、技術に関する知識は全て、またシュメールの名さえも、だんだんと忘れ去られていった。シュメール文化は19世紀になるまで歴史の闇に閉ざされていた。 「ジッグラト」は、ギリシアのオリンポスと同様、外敵から都市国家を守護する神を祀り、あわせて見晴台ともなった。バベルとはアッカド語では「神の門」を表す。一方聖書『創世記』によると、ヘブライ語のの語根バーラルbalal(ごちゃ混ぜ、混乱)と結びつけている。 バビロニア各地に33基の聖塔(ジッグラト)のあったが、首都バビロンの聖塔はシュメール人が着工し未完であったものを、アッシリア帝国滅亡後の4国分立時代、新バビロニア王国第2代の王ネブカドネザル2世が、BC7世紀、巨大な聖塔を完成させた。それが旧約聖書の「バベルの塔」の原型であると考えられている。「バベルの塔」という表現は聖書には見られず、「街とその塔(the city and its tower)」、単に「街(the city)」と表現される。 新バビロニア王国は、古バビロニアのハンムラビ王時代以来の繁栄を享受した。またバビロン市内に国家神であるマルドゥク神殿などの神殿が多数設けられた。ネブカドネザル2世は、BC586年に、西方のパレスチナのヘブライ人(ユダヤ人)のユダ王国を滅ぼし、多数のユダヤ人を首都バビロンに連行した。これが「バビロン捕囚」である。約50年の捕囚後、新バビロニアがアケメネス朝ペルシアのキュロス2世によって滅ぼされたBC538年にようやく解放された。パレスティナの地に戻ることが許された。 ヒクソスは、エジプトに侵入したアジア系民族で、エジプトに騎馬と戦車をもたらし、BC1650年に第15王朝を建て、エジプト新王国によってBC1542年にエジプトから追われるまで約1世紀間、エジプトを支配した。 ヒクソスとは「異国(出身の)支配者たち」を意味するヘカウ・カスウトに由来する言葉で、BC2000年紀の前半にヒッタイトやミタンニなどのインド=ヨーロッパ語族の民族移動が西アジアに及んだ頃、それに押される形でアジア系の民族がエジプトに侵入してきたのがヒクソスと思われる。彼らは武力に優れ、エジプトに騎馬と戦車を持ち込んだとされている。一時的に支配したが、その実態は判らないことが多い。 中王国時代に傭兵としてシリアからつれてこられた人々であった可能性もある。 ヒクソス支配がもたらしたもの ヒクソスのエジプト支配によって、エジプトはオリエント世界での孤立が終わり、広い西アジアの国際社会と関わりを持つこととなった。またヒクソスの軍事力、とくに騎馬と戦車の技術が持ち込まれた。戦車とは戦闘用の二輪馬車のことで、これ以後エジプトの各王朝でも採り入れられていく。それ以外にも複合弓、青銅製の刀、鎧などもあった。 しかし、ヒクソスがもたらしたものは武器と軍事技術以外にはほとんどなく、信仰ではパレスティナの地方神であったバアルをエジプトの神セトと同一視して崇拝し、王名をみるとキアンとかアペピなどアジア風であるが、いずれもファラオを称し、遺品には王名をエジプト伝統のカルトゥーシュ(隅を丸めた枠)で囲まれている。 彼らはエジプト中王国が衰え、第2中間期という分裂期となった時期に、エジプトに侵入し、アヴァリス(現在のテル=エル=ダバア)に都を築き、シリア・パレスティナからエジプトにまたがる地域を支配した。ヒクソスはエジプト史上、最初の異民族支配による王朝であったが、エジプトの文化を採り入れ、王もファラオを称したので、エジプトの王朝として加えられ、第15王朝(ヒクソス王朝とも云う)、第16王朝といわれた。 ナイル川中流にはテーベを都にしてエジプト人の第17王朝がすでにあったが、ヒクソスの宗主権を認めながら軍事技術を学び、BC1570年ごろにはセケンエンラー2世はヒクソス王アピペと戦った。最初の戦いでは敗れたが、その子のアアフメス1世はBC1552年に第18王朝を創始し(エジプト新王国とする)、ヒクソスとの戦いを再開、BC1542年にヒクソスの都アヴァリスを占領し、国土再統一を達成した。ヒクソスはエジプトから追われ、パレスティナに逃れたが、3年後に最後の拠点シャルヘンも陥落し、滅亡した。 ヒクソスの王アピペは、テーベの王セケンエンラーに次のような手紙を送った。 「町の東の沼からカバを追い払うようにさせよ。それらが昼も夜も私の眠りを妨げるのだ。鳴き声が町の人々の耳を患わせるのだ」。 セケンエンラーには謎のような手紙の意味に気づいた。カバはアピペ王の支配を快く思っていないエジプト人を指しており、セケンエンラーに彼らを始末しろと言っているのだ。しかし同時にエジプトではカバは悪の象徴でもあり、カバを狩るとはこの世の秩序を保つ王の神聖な義務とされていた。もしセケンエンラーがカバ狩りを行えば、自分が正当な王だと宣言することになる。困ったセケンエンラーは名案がなく、家臣を集めて会議を開いたが・・・ これは後の第19王朝の時代の物語の断片で、結末は知られていない。ところが近年、テーベの近くの「王のミイラの隠し場所」からセケンエンラーのものと思われるミイラが発見された。彼は戦死したらしく、その頭部には致命傷となったと思われる傷が残っていた。その傷痕は明らかにエジプト製の武器ではなく、ヒクソスの都アヴァリスとされる遺跡から出土する青銅製の斧によるものだった。つまり、セケンエンラー王(ヒクソスから見れば地方の君主)はヒクソス王アピペの挑発に乗って戦いに踏み切ったが、戦死してしまったという、物語の後半を示していると考えられる。 ただ、パレスチナの遊牧民が豊かなエジプトに移住し、BC 3千~BC2千年紀の古代東方一帯の文書に、傭兵として、債務奴隷身分に陥った下僕として、定住民を侵害する遊牧的下層民として、ハピルもしくはハビルと呼ばれた、その身分状況と対応させている。ヘブライ人は、ギリシア語のヘブライオスhebraiosによる呼称で、、「進みゆく」「越えてゆく」などの意味をもつ動詞イブルから転じて、「(ユーフラテス)川の向こうから来た者」を意味する。本来、川を渡って来た東方の遊牧民集団を呼んだ。 エジプトに移住してきた様々な人種や民族の多数の遺物が、エジプトの歴史を物語る。古代エジプト人は、最初期からアフリカ内陸部と、地中海沿岸や西アジアの人種が混血した結果、誕生している。そして歴史を通して、様々な段階で、多くの移住者を受け入れてきた。BC1,800年平民叙事詩「シヌヘの物語」に語られるように、エジプト人は国を離れたがらなかった。現在のエジプトは、アフリカ人でも、アジア人でもなく、白人でも黒人でもない、いわば「地中海人」とでも言うべき状態にある。 エジプト南部アスワンあたりからスーダンのハルツームにかけてのナイル川流域は、古代から「ヌビア(黄金)」と呼ばれていた。中石器時代に、この地域の南部に主として漁労とカバ猟を営む黒色人種が住んでいた。ヌビア地方には、肌が黒く縮れた髪を持ち、エジプト人やアラブ人とは異なる風貌を持つヌビア人たちが古代から住み、商人や奴隷、傭兵の姿で、多くの遺跡のレリーフに描かれている。ヌビア人は木の枝と泥で造った小屋に住み、土器を作り、抜歯の慣習があった。 新石器時代のBC 3900年頃、ハルツーム周辺にエジプトから農耕文明が入ってきた。その後、白人系牧畜民が南下し、牛・山羊・羊などの牧畜と、乳とバターの利用が伝えられた。 野生の牛は、人が近づいても攻撃す様子を見せなければ警戒しない。しかも、気候が乾燥していれば水源から離れようとしない。そのため、狩猟採集民による牧牛は、遅くともBC5500年頃には生業となっていた。この当時、サハラ砂漠の南縁の部分に当たるサヘル地帯の岩の壁面に、牧畜の風景の絵が描かれ始めている。 半乾燥草原から灌木の茂るサバナへの移行地帯にあたり比較的湿潤で、地中海沿岸諸国と西アフリカのあいだのサハラ縦断交易が先史時代から活発な交易の行われていた。主に西アフリカについて用いられるが、スーダンやアフリカの角の諸地域を含める場合も多い。歴史的に「スーダン」と呼ばれた地域が中核的な役割を果たしていた。灌漑施設が殆ど普及していないため、雨水に頼るその日暮らしも危ういレベル、その後は深刻な砂漠化やサハラ交易の衰退などの問題に直面している。 牛はその肉を食べるばかりでなく、血と乳を飲食するために飼われていた。特に、遊牧民にとっての牛は「歩く貯蔵庫」と言われるほどの貴重な財産であった。先王朝時代、ナカダ文化Ⅰ期~Ⅱ期前半(BC4000~3650年) 、一般の農民には、農作業などをする役畜であった。王家の領地では、牛を飼う施設を設けて飼育していた。 BC3150年頃、上エジプトのナルメル王が下エジプトを征服し、上下エジプトを統一してエジプト第1王朝を開いたとされる。ナルメルは上下エジプトのファラオとして確認される最古の王である。 BC8世紀には70年に渡って3人のヌビアの王が、黒いファラオとしてエジプトを治める、第25王朝を築いた。 アッシリアのエジプト支配当時、ナイルデルタ地帯の西寄りに位置する古代エジプトの都市サイス(現サエルハガル)を支配していたネコ1世(ネカウ1世)と、その息子プサメティコス1世(プサムテク1世)はアッシリアによってエジプトの管理を任され、それぞれ「サイスの王」、「アトリビスの王」という地位を承認されていた。 一方敗れた第25王朝ではタハルカの後継者タヌトアメンが体制を建て直し、紀元前664年に失地回復を目指して北上した。ネコ1世はアッシリアに服属する王としてタヌトアメンと戦い、敗れて殺されたと見られる。 ヘロドトスの『歴史』よれば、プサメティコス1世もアッシリアへの亡命を余儀なくされたと記す。しかしアッシリア王アッシュールバニパルの再度の遠征により、同年中にタヌトアメンの軍勢が撃破され、第25王朝が終了する。タヌトアメンは、その後、エジプトへの復帰を諦め、首都の位置を、ナパタから、さらに南のナイル川中流域メロエ(現スーダンの首都・ハルツームの北東)へ遷都した。メロエでは、エジプト文化をアレンジしながら継承する「メロエ文化」が花開き、黒いピラミッド群とヒエログリア(象形文字)に似た独自の「メロエ文字」も作られる。この文字の形こそ、エジプトのヒエログリフに似ているものの発音自体は古ヌビア語を基底にしている。残念ながら、未だ解読されていない。 プサメティコス1世は、サイスを首都とする第 26王朝 (サイス朝 )の王の地位を保証された。プサメティコス1世と下エジプトの支配者達との戦いは、アッシリアの宗主権下において行われたものであり、反アッシリア勢力の一掃と言う思惑もあったが、プサメティコス1世の下エジプト(メンフィス以北のナイルデルタ、アレクサンドリアからポートサイドにかけ、東西240km広がる世界最大級の三角州、肥沃な土壌である)における支配が確立された。その後、プサメティコス1世は上エジプト(現在のカイロ南部からアスワンあたりまでを指す)のテーベ(現ルクソール)に対しても自らの権威を承認させることに成功した。 メンフィスは、BC3世紀の古代エジプトの歴史家マネトによる古代ギリシア語で記された伝承によれば、この都市はメネス王によって建設されたと言う。さらに伝承にれば、メネスは、BC3000年~BC2850年の間に、初めて上下エジプトを1つの王国に統一し、第1王朝を創始した人物とされている。メンフィスが王都となったのは、ナイル川河口付近のデルタ三角州地帯という戦略的要衝に形成された都市であり、各種の社会生活の拠点として栄えていた。メンフィスの主たる港であるペル・ネフェル(Peru-nefer)には数多くの工房、工場、倉庫が存在し、王国全体に食料や商品を流通させていた。その黄金時代の間、メンフィスは商業、貿易、宗教の地域的中心地として繁栄した。 国内における支配を確立したプサメティコス1世は、古王国・中王国の行政制度を手本とした内政改革に取り掛かった。崩壊した国を侵略者から救い出し、古代エジプトに黄金時代をもたらしたプサメティコス1世の権威は絶対で、美術品にもその嗜好が強く影響し、古王国や中王国風の様式を手本とした復古的な美術様式が形成された。こうした動きは「サイス・ルネサンス」と呼ばれた。 そしてオリエントにおけるアッシリアの勢力が縮小に転じたことによって、紀元前653年頃までにはその宗主権下から離脱した。そしてシリア方面への勢力拡大を図った。ヘロドトスの記録によれば、プサメティコス1世はアシュドド(現イスラエル南西部、地中海に臨む港湾都市)を29年間かけて陥落させたと記す。
アッシュールバニパル王は、アッシリア史上最後の偉大な征服者であった。古代オリエントの研究には彼が残した図書館の史料が大きく貢献した。 ティグリス川上流にあったアッシリア帝国の都ニネヴェに、アッシュールバニパル王が王立図書館を建設した。世界最古の図書館とされている。メソポタミアとエジプトを統合し、広く西アジアを支配したアッシリアは、帝国内の産業や経済を掌握するために、王立図書館を情報センターとしても活用し、諸々の情報を、粘土板に楔形文字で刻印し記録保存した。 1,894年、フランスの外交官ボッタが発掘に成功し、大量に出土した楔形文字から、帝国最後の王センナケリブ王の王宮であったことがわかった。その遺跡からアッシュールバニパル王が建設した図書館跡も出土し、3万にもおよぶ楔形文字が刻印された粘土板が見つかった。アッシュールバニパルの図書館は、古代世界の中で最大規模であった。アッシュールバニパル王の個人的図書館思われがちだが、薬学・詩・地理学・科学・魔術などの写本や文献が多数保存されていた。 王は読み書きする程の知性を兼ね備えていた。ライオン狩りのレリーフなどにも腰にペンを携える姿が描かれている。 アッシリア帝国は、ペルシャ・バビロン・シリア・エジプトまで拡大していた。アッシュールバニパル王が図書館に残した楔形文字記録には、王室の記録・年代記・神話・宗教文書・契約書などであるが、そればかりでなく王室による許可書・法令・手紙・行政文書などが含まれていた。 BC609年、アッシリア帝国が滅亡してから廃墟となり、長い間その存在が確認さないままであった。それらはすぐに大英博物館に送られ、アッシュール学の学者たちによって懸命な解読作業が行われた。それから「アッシリア学」といわれる分野が発展していく。古代では最大規模であるアッシュールバニパルの図書館は、古代オリエントの研究に大きく貢献した。 アッシュールバニパル王の後半生については、記録が殆ど残っておらず、退位や死去の年など謎に包まれている。記された最後の文書には、BC638年、アッシュールバニパル王が宮殿で祈る様子や、過去の偉業について述べられていた。退位または死亡はBC631年頃ではないかとされている。この頃から、アッシリアが急激に崩壊の一途を辿っている。アッシュールバニパル王の息子、シン・シャル・イシュクンは、アッシリア王が王族・家臣・王族と次々と王位をめぐって交代する混乱の最中に暗殺され、アッシリア最後の正当な王として生涯を終えた。 首都ニネヴェ(古代メソポタミア北部にあった)では盗難が横行し、あげくの果て放火により蕩尽した。アッシュールバニパル王の図書館も焼失した。ただ、楔形文字が刻まれていたのは粘土板、燃えたおかげで長期保存され今日に至った。 当時のアッシリアの東方領域では、イラン高原を中心としたメディアが勢力を伸ばし、一方では、その西方のユーフラテス川沿岸では、BC625年頃、新バビロニア南部のカルデアの属州総督だったナボポラッサルがアッシリアから自立した。新バビロニア帝国初代の王(在位BC626~605)となり、ユーフラテス川沿いのバビロンBabylon(バグダードの南方約90kmの地点)で建国した。南部諸属州を奪い、次々と王宮や神殿を建設し、帝国隆盛の基盤とした。BC616年までには、ナボポラッサルはバビロニア地方の全域を支配下に収めた。 (カルデアは、古代のバビロニア南部の地域名で、メソポタミア南部全域を指す。本来のカルデアは、ユーフラテス川とチグリス川の2つの川の堆積物によってメソポタミア南東端に形成された、長さ約400マイル、幅およそ100マイルに広がる広大な平原であった) プサメティコス1世はこの事態に際しても、かつての支配者アッシリアの戦力に賭けた。BC616年にはシリアへ出兵して新バビロニア軍と干戈を交えた。 バビロニアの王ナボポラッサルとメディア国のキュアクサレス王は、BC614年、同盟を結んだ。ナボポラッサルは、アッシュールを包囲するメディア軍を支援するため、軍を率いて進んだが、バビロニア軍が到着する前にアッシュールは陥落していた。アッシリアは、既に王国としての体をなしていなかった。 首都ニネヴェを初めとする中心地帯は容易に制圧された。 王家のアッシュール・ウバリト2世がハラン(聖書名ハルラン)に逃れ再起を図った。ハランは、キリキア(トルコ南部の地中海に面した地域、地中海の向こうはキプロス)とアッシリア、アナトリアとバビロンを結ぶ四通八達した通商路であった。王族の一人アッシュール・ウバリト2世(B.C.612~609)は、ハランという所を拠点にしてバビロンのナボポラッサルと戦う。そのアッシリヤを支援するためにエジプトのネコ2世(ネカウ2世)が出征した。 BC610年にプサメティコス1世が没すると、息子のネコ2世が王位を継承する。依然としてアッシリアへの支援が続き、シリアへの再度の出兵に踏み切った。この時、ユダの王ヨシヤ(B.C.639~609)はエジプト軍の動きを阻止しようと、メギドで戦う。エジプト軍はこのメギドでの戦いでかなりの痛手を受けたが、ユダ王ヨシヤを討ち死にさせ、そのままユーフラテス川の手前のカルケミシュでアッシュール・ウバリト2世と合流した。カルケミシュはハランの西、ユーフラテス川を渡る最大の浅瀬で、そこでバビロン軍と戦って敗北を喫した。この時、アッシリヤの最後の王族アッシュール・ウバリト2世も殺され、1400~1500年間続いてきたアッシリヤ帝国は、B.C.609年に完全に歴史から消えた。 ユダ王ヨシヤ(在位;BC640~609年)は、旧約聖書「列王記」などに登場する。そのヨシヤは、8歳頃に即位し、その後31年間エルサレムを治めた。そのヨシヤ王の治世に、それまで服属していたアッシリアの衰退により一時独立を回復した。ヨシヤ王は、ユダヤ教の徹底した宗教改革を通して宗教的ナショナリズムを高め、それを国家再建の原動力とした。 この改革の発端は、BC622年、ヨシヤ王の治世18年、改修中の神殿から1つの「律法の書」が、大祭司ヒルキヤにより発見されたことによる。ヒルキヤはヨシヤ王にこの書物を見せた。2人の女預言者フルダにこれが失われた律法の書であるかを確認を求めた。フルダは、これこそが本来の律法の書であると告げた。王は民衆の前でこの書を読み上げて、神と民の契約の更新と告げ、以後の儀式はこの書に従い行われることを宣言した。また聖所における偶像崇拝を排除し、異教の神々の祭壇や祭具類などが破壊させ、主の礼拝所をエルサレムに集中させた。 このユダ王ヨシヤが、新バビロニアに対抗するため、アッシリアの援軍とした参戦するエジプトの王ネコ2世とメギドで戦い、エジプト軍の矢を受けて死亡した(メギドの戦い)。 ヨシヤの死後、一度はヨシヤの子ヨアハズが即位したが、戦の帰りに立ち寄ったネコ2世はヨアハズを廃位してヨアハズの兄弟エホヤキムを新しい王にした。 ヨシヤの死によりその改革の殆どが無に帰した。しかも、ユダ王国の独立は再び失われ、エジプトに金銀を納めさせられる従属国となった。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 5)デモクリトスの原子論 ミレトスは、市民が自分たちの法律を、自分たちで討議し制定するために市民会議が招集された歴史上初めての土地である。 BC7世紀半ばに、小アジアでカリア(現在のトルコのアイドゥン県、ムーラ県一帯に相当する。ドーリア人やイオニア人が、そのカリアCaria西部に入植し、そこにギリシアの都市国家を形成した)と対立していたイオニア人の12都市で形成されたのが「イオニア同盟Ionian League」で、その同盟都市の代表者が集まった会議が、ポセイドンの聖地「パンイオニウム」で開かれた。「イオニア同盟」に加盟する都市は12で、北から順に、ポカイア(現フォチャ)・クラゾメナイ・エリュトライ・テオスTeos・レベドス・コロポン・エフェソス・プリエネ・ミュウス・ミレトス(現アイドゥン)・サモス島のサモス・キオス島のキオスである。 ヘロドトス(BC5世紀のギリシャの歴史家)の『歴史』にその記述がある。 「さてパンイオニオンを共有するこれらイオニア人であるが、我々の知る限り世界中で彼らほど気候風土に恵まれたところに町を作っている者は他にはいない。イオニアより北方の地域も南方も、一方は寒気と多湿に悩まされ、他方は高温と乾燥に苦しむからである。 これらのイオニア人の話している言葉は同一のものではなく、4つの方言に分かれている・・・・」 「パンイオニオンはミュカレ山の北斜面にある聖域で、イオニア人が共同して『ヘリケのポセイドン』に捧げたものである。ミュカレは大陸から西方サモス島に向かって伸びている岬で、イオニア人たちは例の町々からここに集まり、パンイオニア(全イオニア祭)の名で呼んでいる祭りを祝うのである」 ミュカレ山」というのは現在のディレキ半島にあり、岩山の小高い丘の崖面に多くの灌木が散見されるのが印象的である。その半島の先端が海上に浮かぶサモス島に近接する。現在ではミュカレ山はトルコ領であるが、一衣帯水のサモス島はギリシア領である。 議論を重ねて叡智を集めることで、同盟都市相互間にとって雨過天晴を招く英断が積み重なる一方、乱雑に猛威を振るう自然の摂理に不問を貫く神々に、問う無駄を重ねることよりも、むしろ素直に自然界の原理を、この時代の人々は克明に研究し解明しようとした。 哲学philosophyのラテン語「philosophia」には、「知を愛する」という意味が込められている。sophia(智)をphilein(愛する)を原義とする。西周(にしあまね)は、「賢哲」を愛し希求する意味で「希哲学」の訳語を造語したが、後に「哲学」に改めた。 「哲」とは、会意兼形声文字(折+口)、「才」は、「ばらばらになった草・木の象形」と、「斤(おの、まさかり)」 は「曲がった柄の先に刃をつけた手斧の象形」、「折」とは「斧で草・木をバラバラに する」のことから、「才知明にして物の道理をよく知る」を意味する。それに「口」の象形が加わり形声合意文字となる。つまり、それを本義とする「口」にすれば「才知明なれば、その言もまた明なり」と言う漢字 「哲」が成り立つ。 「賢哲」とは「物事の道理に通じていること」であれば「叡智」を養う必要がある。古代ギリシアの哲学者デモクリストは、臆見や迷妄に惑わされず、しかも対象を絞ることなく、真理をただひたすら追求し続けた。19世紀前半まで「哲学」とは、世界や自然界、そして人間をも対象にする知識・知恵・原理を探究する学問一般であった。近代になると、次第に個別の諸科学が分化独立すると、「哲学」とはニーチェやアルベール・カミュ、そしてサルトルのような生の哲学、実存主義など世界・人生の根本原理を追及する学問となった。 ミレトスは、哲学・自然科学・地理学・歴史学などの揺籃の地となるほどに成長した。地中海のみならず、西欧の近代科学や哲学の根本原理が、BC6世紀のミレトス人の頭脳の中で育まれ、さらなる文明の画期的発展に貢献するはずであった。やがて臆見や迷妄により排除されるようになる。 BC6世紀の半ばにアケメネス朝ペルシア帝国(BC550年~330年)が侵略し、ミレトスはその支配下に入った。 貿易活動が制限されことなどへの不満が強まり、BC500年に、イオニアで反乱が起こり、ペルシアからの離反に踏み切った。BC 499年にペルシア軍の攻撃が始まり、反乱側は、ギリシア本土のアテネなどの支援を受け入れたが、BC 494年、ラデー沖の海戦(「ラデー」というのはミレトスの沖にあった島、現在では長年の堆積により内陸になっている)に敗れて一気に没落し、しかも、ペルシア帝国の鎮圧は仮借なく徹底的に破壊された。ミレトスの市民の大多数は奴隷となった。ペルシア帝国は、そのイオニアの反乱を支援したことを理由に、ギリシアの諸都市を征服する行動を開始した。それがペルシア戦争へと発展する。 しかし20年後、ギリシア人はペルシアの脅威を退け、ミレトスを見事に甦らせた。人口は再び回復し、市場と交易の中心都市として栄えた。ミレトス人の商流と物流に関わる知性と精神が広くギリシアに普及し、その合理的な思念が磨かれる流れるの中で、多くの科学と哲学の学派が創立されていった。 レウキッポスLeukipposは、『大宇宙系』と言う書物を著したとされている。伝承によれば紀元前450年、ミレトスからトラキアのアブデラへ船で渡っている。アリストテレスは、原子論atomismの創始者としている。 レウキッポスは、デモクリトス(BC470年頃~370年頃)の師であり、共に原子論の理論を編み上げた。レウキッポスのグループは、あらゆる時代の思想に甚大な影響を及ぼしている。二人の著書は散逸し、両者の思想は明確には区別できていない。 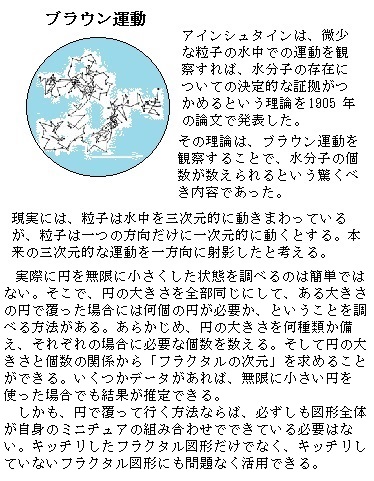 原子論者、自然哲学者として知られるデモクリトスは、知のあらゆる分野において70篇もの著書があった。いずれも散逸しているが、その断片に、人間の魂やその生き方、倫理や社会について言及している部分が多い。デモクリトスは人間の魂の働きもまた原子の働きによると見事に洞察している。魂は魂原子の群魂があり、その形態、配列、向きは変化する。ならば、人間の資質は生まれつき変わらないと考えられていたそれまでの人間観に対して、教育によって資質も変わっていくと言及する。 原子論者、自然哲学者として知られるデモクリトスは、知のあらゆる分野において70篇もの著書があった。いずれも散逸しているが、その断片に、人間の魂やその生き方、倫理や社会について言及している部分が多い。デモクリトスは人間の魂の働きもまた原子の働きによると見事に洞察している。魂は魂原子の群魂があり、その形態、配列、向きは変化する。ならば、人間の資質は生まれつき変わらないと考えられていたそれまでの人間観に対して、教育によって資質も変わっていくと言及する。現代の生物学でも、遺伝子の発現は環境や生育方法の影響を受けるとしている。「生まれborn」ばかりでなく「育てるbring up」も重要視されている。 古代の人々の多くは、それを読んで深く感銘した。当時の知識層の間でも、彼は偉人として尊敬されていた。セネカLucius Annaeus Seneca(BC1年頃~AD65年)は『自然論集』で、デモクリトスを「あらゆる古代人の中で、もっとも鋭敏な知性を備えた人物」と評した。 皇帝ネロの家庭教師も勤めたこともあるストア派哲学者「セネカ」の思想はストア派に属し、古代ギリシアのゼノン(BC335年頃~263年頃)が創始した哲学の学派で、当時のギリシア哲学を代表する学派であった。地中海を支配する中心がローマに移ると、ストア派はローマでも盛んになり、セネカが活躍した。ストア派の原則は「自然に従うこと」、つまり、宇宙の大原則に身をゆだね、神的な自然への服従を実践する生き方により、不安や欲望を取り除くことを理想とした。後にキリスト教の教義にも取り入れられ、西洋人に大きな影響を与えた。 キケロ Mrcus Tullius Cicero (BC106~BC43年)は、ローマ共和政の末期の「内乱の1世紀」時代の政治家でかつ雄弁家・文章家・哲学者として著名であった。属州の徴税請負人などになって経済力をつけてきた新興勢力である地方の騎士(エクイテスequites)の家柄に生まれ、ローマに遊学し、修辞学・哲学・法律を学び、弁護士として頭角を現した。さらにアテネ、小アジア、ロードス島に行き、ギリシア哲学を学びギリシア語文献をラテン語に訳すなど、素養を積んだ。ヘロドトスを「歴史の父」と呼んでローマに紹介したのもキケロであった。騎士階級出身の共和派の政治家としても活躍したが、カエサル暗殺後にカエサルの後継者に座ろうとするマルクス・アントニウスと対立し、BC43年、暗殺された。ラテン語の名文家として知られ多くの著作を残した。 そのキケロが「いったい誰と、あのデモクリトスと比較できようか?天賦の知性のみならず、魂もまた偉大であったあのデモクリトスと」と評価している。 (騎士/エクイテスは、古代ローマ共和制時代末期に登場した。従来の貴族・新貴族からなる元老院議員層に対し、徴税請負人などとなって富を蓄えた新興富裕層を騎士といった。彼らは、共和政末期には民会を拠点とする平民派の支持基盤となり、元老院を拠点とした閥族派と対立する。彼らの存在は、AD1世紀の内乱の過程で重要性を増し、初代皇帝アウグストゥス以来のローマ帝国の皇帝による統治も騎士階級を支持基盤として強化され、彼らから役人や軍人に登用される者が多かった) 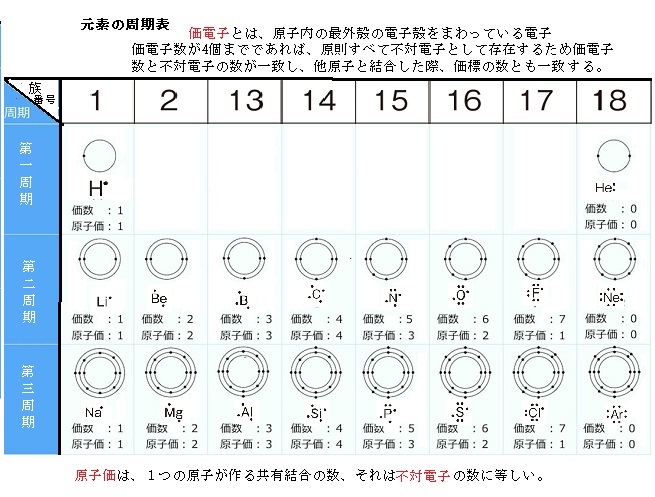 デモクリトスは、原子と原子が結びつく時、微視的スケールで起こる重要なことは、原子の形、全体の構造における原子の配置、原子の結び方だけであると言う。20数個のアルファベットが様々に組み合わさり、悲劇や喜劇、滑稽譚や壮大な叙事詩が作り出されるように、基本的な原子が様々に結びつくことによって、限りない多様性を備える世界が生まれると見事に看破する。 デモクリトスは、原子と原子が結びつく時、微視的スケールで起こる重要なことは、原子の形、全体の構造における原子の配置、原子の結び方だけであると言う。20数個のアルファベットが様々に組み合わさり、悲劇や喜劇、滑稽譚や壮大な叙事詩が作り出されるように、基本的な原子が様々に結びつくことによって、限りない多様性を備える世界が生まれると見事に看破する。つまり、原子間の結合でアミノ酸分子が生まれ、その分子同士の結合が重なれば、タンパク質などの巨大分子が形成される。 デモクリトスは「この途方もない原子の舞踊には、いかなる目的や意図を伴わない。私達は自然界に存在する他の事物と同様に、果てしなく続く原子が演じる舞踊の帰結である。それは偶然に結びついた結果とも言える。自然は種々の形態と構造を試し続ける。人間も動物も、果てしない淘汰の流れの中で、自然の気まぐれの選択によって発生した存在である。 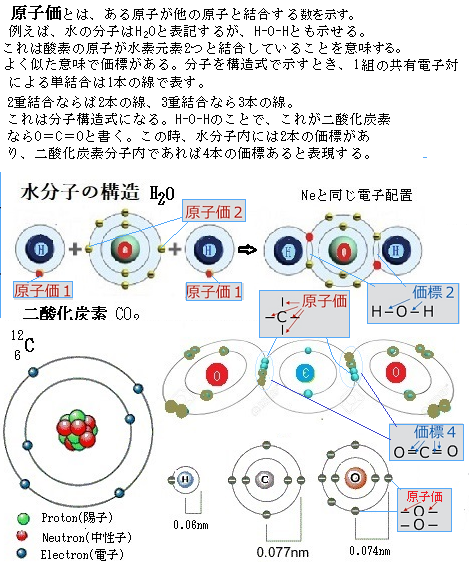 私達の生は、原子の組み合わせにより、私達の思考は微小な原子に由来する。私達の夢は原子が生み出したものであり、私達の希望や感情は、原子の組み合わせによって構成される言語の中に書き込まれている。私達の見ている光とは原子であり、私達の視野に映る像は原子によってもたらされる。海も街も星も原子からできている」。 私達の生は、原子の組み合わせにより、私達の思考は微小な原子に由来する。私達の夢は原子が生み出したものであり、私達の希望や感情は、原子の組み合わせによって構成される言語の中に書き込まれている。私達の見ている光とは原子であり、私達の視野に映る像は原子によってもたらされる。海も街も星も原子からできている」。信じられないほど透徹した洞察である。たった100個くらいの元素が織りなす宇宙空間であることも想定内に入れていたようだ。しかも光の「粒子性」をも看破している。 デモクリトスの偉大な着想は果てしない。想像力を働かせ、車輪が摩滅したり衣服が乾いたりするのも、極めて微少な木や水の粒子がゆっくり失われたためとする一方、その思考力は量子重力理論の骨格まで達する。 「宇宙全体は、終わりのない空っぽな空間、その中を無数の原子が行き交っている。その空間は無限であり、高低の区別も、中心も周縁も存在しない。原子は形の他にいかなる性質も持たない。重さも、色も、味わいも、原子自体無縁である」、「甘さと言う感覚があり、苦さと言う感覚があり、暑さと言う感覚、寒さと言う感覚、そして色彩をめぐる感覚がある。しかし、実体は、原子同士が織りなす空間の働きに負う」。 一神教の思想が猛威を振るった数百年に、デモクリトスの透徹した唯物的な自然主義は完全に忘失された。というより意図的に破棄された。 ローマ帝国末期の皇帝テオシドシウス帝(在位379~395年)は、もとは属州ヒスパニア(スペイン)出身の軍人であった。378年に皇帝ヴァレンスが西ゴート人とのアドリアノープルの戦いで敗死したために、急遽、軍隊司令官の一人だったテオドシウスが指名されて皇帝となった。マクシムスが西の皇帝を称したのに対し、テオドシウスは東の皇帝としてコンスタンティノープルを拠点とし、388年にはマクシムスの軍を破り、帝国を統一し再建した。 AD390~391年、勅命を発し、アタナシウスの教義を補強した三位一体説を正統教義として確認した。さらに392年、異教徒禁止令を出し、アタナシウス派キリスト教を事実上の帝国の唯一の国教とする。これによって三位一体説のキリスト教信仰がローマ帝国と結びついて権威ある国家宗教とされることとなった。 以後、古代の思想を考究する学派は次々と閉鎖され、キリスト教思想が受け入れない文書はことごとく破棄された。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 6)ルクレティウス ギリシア哲学は、天文学や物理学のみならず、幾何学や論理学・自然学をも含む学問や学究的部門の総称である。「哲学(ピロソピアphilosophía)」および「哲学者(ピロソポスphilosophos)」という言葉を最初に用いたのはピタゴラスと言われるが、「哲学者」を含めた「知者(ソポスSophos)」は「ソフィスト(sophistés)」とも呼ばれ、詩人もこれに含まれた。
ティトゥス・ルクレティウス・カルスTitus Lucretius Carus(BC99年頃~BC55年)は、デモクリトスの孫弟子にあたるエピクロスの哲学を信奉した。エピクロスの唯物的哲学の影響を受けたローマの詩人哲学者ルクレティウスの現存する唯一の長詩『事物の本質について』、それはカトリック教会からの災厄を免れ、漸く現代にまで残った文章である。 エピクロス哲学は、科学よりも倫理学に傾斜し偏っておりその思想にはデミクリトスほどの深みは無いが、時折、デモクリトスの原子論を表面的な仕法でパラフレーズしている。それでも、エピクロスの自然観は、デモクリトスから受け継いだとは言え、ルクレティウスは、デモクリトスの原子論的自然観を詳述した科学書として現在無二の史料的価値を持つばかりである。ルクレティウスの現存する唯一の6巻7400行からなる長詩は、一切の現象を因果関係において捉え、原子と空間から成る世界の自然法則を説明して現実の生を楽しむことを教えた。この雄大な長詩は古代の哲学の圧巻である。 エピクロスの宇宙論的説明を詩の形式で解説する。説明の付かない自然現象を見て恐怖を感じ、そこに神々の干渉を見ることから人間の不幸が始まったと断じる。死によってすべては消滅するとの立場から、死後の罰への恐怖 から人間を解き放とうとした。 自然に対すエピクロスの見方は、偉大なデモクリトスから受け継いだもの、エピクロスの思想やデモクリトスの原子論を、ルクレティウスは詩句の中で展開している。一神教が、実は個人的なえごが支配する 暗黒の数世紀に及んだ知的災厄から、かの深遠な思想の極一部が救出された。原子論に立脚する広大な世界観が、ルクレティウスを驚嘆させ、原子を、海を、自然を、空を美しいく知的に歌わせた。哲学の問い、科学的な観念、明晰な議論が、人間が形成する物質は、星や海を形作る物質と変わらない、と教えてくれる。その事を知り得た時、事物の単一性に対する深遠な感動が、美しい詩節となり 『わたしはこれから、自然のいかなる力が働き、太陽の運行や月の漂泊を司っているかを説明しよう。空と大地の間に伸びる自らの行路を、太陽や月が自らの意思で移動しているなどと考えないで済むように。または、太陽や月が、なんらかの神慮によって回転しているなどと考えないで済むように…・』 『わたしたちの誰しもが、天の種子から生まれてきた。誰しもが、同じ父親を持っている。わたしたちの母なる大地は、澄んだ雨粒を身に付けて、光り輝く果実や、繁茂する木々や、人間や、あらゆる世代の野生の獣を、活力に満ちた土から生み出した。そして、それらすべてを養うために、大地はわたくしたちに食物を与えた。おかげでわたしたちは、甘美な生活を送り、子孫を残すことができる…・』 ルクレティウスの詩では、わたくしたちに困難な事柄を要求したり罰を与えたりする、気まぐれな拗けた神など存在しない。それだから平常心が保っていける。ルクレティウスは、避けがたき死をも晴れやかに受け入れられる。あらゆる悪を消し去る死に対して、恐怖を抱く必要はない。信仰と無知は同義語であり、理性は闇を照らす光となる。 『事物の本質について』の発見は、ルネサンス期のイタリア、そしてヨーロッパに甚大な影響を与えた。その残響は、ガリレオ・ケプラー・ベーコン・マキャヴェッリなど、様々な書き手の言葉のうちに共鳴している。 ルネサンス(仏: Renaissanc)は「再生」「復活」を意味するフランス語である。一義的には、古典古代(ギリシア、ローマ)の文化を復興させようとする文化運動であり、14世紀にイタリアで始まり、やがて西欧各国に広まった(文化運動としてのルネサンス)。また、これらの時代(14世紀~16世紀)を指すこともある(時代区分としてのルネサンス)。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
7)デモクリトスと現代物理学 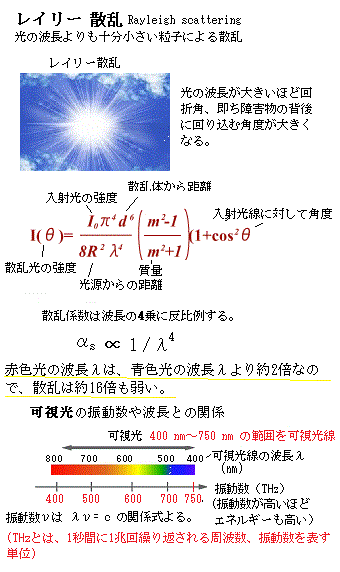 『そもそも高温の物体は振動する。それにより電子が振動すると、光が生じ周囲に広がる。電子の固有振動数は、物質中における電子の状態により様々に変わるが、その固有振動数と一致する光を受け取ると、電子はその固有振動数で振動を始める(共振、または共鳴と言う)。 『そもそも高温の物体は振動する。それにより電子が振動すると、光が生じ周囲に広がる。電子の固有振動数は、物質中における電子の状態により様々に変わるが、その固有振動数と一致する光を受け取ると、電子はその固有振動数で振動を始める(共振、または共鳴と言う)。 光を含む電磁波の種類は多く、物質に与える影響は様々であるが、すべてが電子や極性分子を振動させることができる。ただし物質の固有振動数も様々なため、その振動数に一致した電磁波が来た時だけ振動する。 例えば、電磁波の中でも振動数が大きい(波長が短い)紫外線やX線、ガンマ線は、大きなエネルギーを持っているので、分子中の電子を弾き飛ばして化学結合を壊したり、電気的に中性な原子の電子を弾き飛ばして、電荷を持ったイオンにしたりする。 振動数が大きい電磁波が細胞の中のDNAにぶつかると、DNA分子中の電子を弾き飛ばし切断するなど傷を負わせ、それが蓄積されると細胞の癌化を招く。 分子中の電子は、通常、特に固く結合しているため固有振動数が大きく、非常に速く振動している。そのため振動数の大きな電磁波でないと電子を弾き飛ばせない。 電子の固有振動数も、電子が物質中で、どのくらいの強さで結合しているかで決まる。例えば、金属中の自由電子free electron(物質内で特定の原子間の結合に束縛されず自由に動き回れる電子)は結びつきが弱く金属内を自由に行き来する。自由電子は金属結晶などには豊富に含まれるため電気をよく通す導体となり、ゴムなどは自由電子を含まれないため絶縁体(不導体)となる。 そのため金属は、電磁波のどんな振動数でも電子は共振する。ただし余り振動数が大きい紫外線くらいになると電子は自由に動けなくなる。』 次に引用するのは、ルクレティウスの詩『事物の本質について』の一節で、デモクリトスの原子論が現代にも通じることを証明する極めて重要な内容である。 『わたしたちの目の前に、明白な証拠がある。小さな穴から暗い部屋の中に差し込む太陽の光を、注意深く観察してみよう。すると、光の線に沿って、極めて小さな物体が運動したり衝突したりする様子が見て取れるだろう。これらの物体は互いにぶつかり合い、絶えず近づいたり遠ざかったりしている。このことから、物体は互いにぶつかり合い、絶えず近づいたり遠ざかったりしている。このことから、原子が空間の中でどのように運動するかを推定できる(中略)。 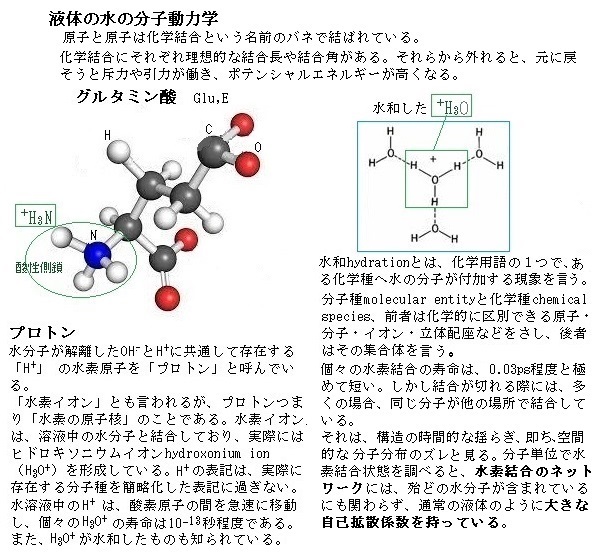 注意して欲しい。あなたの今は、太陽光線のなかで浮遊して衝突する微粒子を見ている。この光景は、わたしたちには知覚できない目に見えない物質が、微粒子の運動の原因であることを示している。事実、微粒子は頻繁に進路を変えたり後退したりする。ある時はここに、あるにはそこに、ある時は上に、ある時は下に、微粒子はあらゆる方向へ進もうとする。 注意して欲しい。あなたの今は、太陽光線のなかで浮遊して衝突する微粒子を見ている。この光景は、わたしたちには知覚できない目に見えない物質が、微粒子の運動の原因であることを示している。事実、微粒子は頻繁に進路を変えたり後退したりする。ある時はここに、あるにはそこに、ある時は上に、ある時は下に、微粒子はあらゆる方向へ進もうとする。このようなことが起こるのは、原子が自律的に運動するからである。小さな物体は原子に衝突し、この衝突が小さな物体の運動を決定づける(中略)。 こうして、光線の中で動いているところをわたしたちが見ている事物の運動が、原子から生み出される。それは、原子との衝突のほかには明確な原因をもたない、奇妙な運動である。』 イギリスのスコットランドの植物学者ロバート・ブラウンは、1828年に水面上に浮かべた花粉が破裂して中から出てきた微粒子が、ひとりでに不規則に動き回ることを発見した。花粉から出た1μm(10−6m=10−3 mm)くらいの粒子を顕微鏡で観察すると、ピコピコと激しく動き回っているのが見出された。彼は当初、これを生物特有の性質と考えたが、その後、ガラスや岩石のかけらなど無機物でもこの運動が観察され、しかも時間がたっても一向に衰えないことが分かった。これはブラウン運動Brownian motionと呼ばれるようになり、19世紀の科学界で大きく取り上げられた。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
8)カトリック教会は、ルクレティウスの著作を読むことを禁じた
ルネサンスとはラテン語で「再生」を意味する。14世紀のイタリアに始まり、15世紀に最も盛んとなった。その意義は、封建的特権・農奴制の廃止と、神中心の世界観の束縛から人間性の自由・解放と個性の尊重という近代社会へ向かう理念を確立したこと、にある。その根底には、この文化運動がギリシアやローマの「古典文化」を復興・再生させたことが大きく影響した。 『事物の本性について』の内容が、無神論に帰結する原子論を見事に展開する内容であるため、ルクレティウスを公然と評価することは、15世紀のイタリアでは大いに危険であった。 古典的名著『君主論』の作者として知られるマキァヴェッリは1,469年、フィレンツェに生まれる。29歳の時、フィレンツェ共和国政府の第二書記官に就任し、共和国政府の外交使節として、大いに活躍する。 しかし、14世紀末、メディチ銀行は、ローマ教皇庁の徴税事務や資金輸送を請け負い、そのローマ支店長が教皇庁の財務管理を任されるなどして、1420年までには、ローマ・ナポリ・ガエータ・ヴェネツィアなどに支店網を設けるまで事業を拡大した。有力者となったメディチ家は、フィレンツェ市政にも関与し、共和制の下で政権を掌握し、寡頭政治の形態を強めた。 メディチ家の政権が誕生するにおよんで、マキァヴェッリは官職を追われ、フィレンツェ郊外の山荘にひきこもり、不遇のうちに多くの著作を書き続けた。 マキァヴェッリもまた、1513年のカトリック教会の第5ラテラン公会議(ローマのラテラノLaterano宮殿を中心に開かれた5回の教会会議)で異端とされたアヴェロエス哲学およびエピクロス哲学に連なるルクレティウスの著述に言及することはなかった。 公会議主義Conciliarism(こうかいぎしゅぎ)は、カトリック教会の全教区の枢機卿・司教・神学者などを集めて、教会の教義や規則などの重要事項についておこなう最高会議で、神学者たちが支持する思想的枠組みを作り、13世紀に絶頂期に達した教皇権に対する抑止力として期待された公会議を幾度か開いた。これに対して、教会会議は、各地域の大司教や司教を中心に、教区の司祭や修道院長などが行なう会議である。カトリックの世界全体の会議を「公会議」、地域的な教会の会議を「宗教会議、教会会議」と分けている面も見られる。 マキァヴェッリ自身がルクレティウスの『事物の本性について』 全文を筆写し、余白に注釈を書き込んだという事実がなければ、マキァヴェッリへのルクレティウスの影響を証明するのは困難だったかもしれない。マキァヴェッリがルクレティウスを筆写した時期は、1498年に書記局に入局する以前の、比較的早い時期だった推定されている。この写本がバチカン図書館で「発見」され、ベルテッリとガエタによって筆写者がマキァヴェッリであると確定されたのは、20世紀半ば過ぎであった。 カトリック教会は、ルクレティウスの思想が広まるのを阻止しようと何度も会議で決議された。1526年12月、フィレンツェで開催された教会会議では、教育機関でルクレティウスを読むことを禁じた。1551年のトリエント公会議では、ルクレティウスの著作をキリスト教世界から追放することを決定した。 その一方では、第5ラテラン公会議などでは、周囲の期待に反して、結果的に有意義な内容を伴う議論が行われず、カトリック教会は自己改革のチャンスを逸し、宗教改革運動を招くことになった。 ローマ教皇は、教皇領という莫大な財産を背景に、そこから得られた富や、十分の一税、あるいは信者の寄付、そして後には免罪符による収入などにより、巨大なローマ教会の建物の中で贅沢な暮らしながら、破門をちらつかせながら国王よりも強い世俗的な権力もって、ヨーロッパを牛耳るほどの政治権力を行使しいた。 アレクサンデル6世(在位1492~1503年)はルネサンス期を代表するローマ教皇であり、また最も悪名の高いローマ教皇であった。出身はスペイン。当時は教皇に選出されると、教皇領の統治者としての富をもち、一族を教皇庁の要職につけたり、高位の聖職者に任命したり、はたまたイタリアの各領主と取引をして領主の地位を与えたり、恣意的に権力を揮ってきた。 教皇に子供がいるのが不思議だが、しかも愛人の子と言われている、アレクサンデル6世の息子のチェーザレ=ボルジアをヴァレンチノワ公に仕立て、娘のルクレツィアはフェラーラ公などに嫁がせなど世俗的権勢を行使していた。またフランス王シャルル8世をイタリアに引き入れ、1494年からのイタリア戦争の発端をつくるなど、その権力の行使に余念がなかった。 アレクサンドル6世による教皇庁の乱脈は、さすがに教会批判を呼び起こし、ルネサンスの全盛期であったフィレンツェではドミニコ会の聖職者サヴォナローラによる急進的な政治と教会の改革が行われたが、アレクサンドル6世はそれを異端であると断じて破門し、焚刑に処した。 サヴォナローラもまた、1494年~98年までフィレンツェの実権を握ると、「虚飾の焚刑」と称して美術作品を焼き払うなど厳しい神政政治を行い、最後は民衆の支持を失い自滅した。 カトリック教会は、救われたい人間の自由意志が救済のプロセスに重要な役割を果たすとする「自由意志説」に基づき、教会へ行う施しや聖堂の改修など、教会の活動を補助するために金銭を出すことが救済への近道として奨励した。 1515年に、メディチ家出身のローマ教皇レオ10世の名の下に売りだされた贖宥状(しょくゆうじょう)は、イタリアの聖ピエトロ大聖堂の建設費を集めるという名目で、ドイツにて売りに出されたもので、実際の発行者はドイツ宗教界の最高位であるマインツ大司教、販売の実務を担うのはドミニコ修道会だった。 ローマ教皇レオ10世は、メディチ家の一員として飽くなき権力欲と、貪欲な富への欲求を持ち続けた人物であった。 この贖宥状に対してザクセン選帝侯領の神学者マルティン・ルターが、1517年に異議を唱えたことが宗教改革の発端となった。 選帝侯とは、神聖ローマ帝国皇帝の選出権を持つ、有力な7つの諸侯をいう。宗教改革期のザクセン選帝侯フリードリヒ3世は、賢公とも称えられ、16世紀に始まったプロテスタント運動は、ザクセン選帝侯の保護下で推進されることになる。1502年にヴィッテンベルク大学を創設し、1508年にアウグスティノ会(私有財産を認めていない修道会で、修道士が托鉢を行い、善意の施しによって生活して衣服以外には一切の財産をもたなかった)の修道士マルティン・ルターを同大学の哲学教授に任命した。 1517年10月31日、ルターは95ヵ条の論題を教会の扉に張り付け、贖宥状の販売などのローマ・カトリック教会の慣行を批判し、いわゆる宗教改革を始めた。フリードリヒ3世は、ルターの宗教改革を支持し、保護した。1521年、ヴォルムス帝国議会(ドイツのヴォルムスで開催された神聖ローマ帝国の帝国議会、ルターはここで異端として教会から破門された)で国外追放となったルターをかくまい、ヴァルトブルク城で保護した。その後もルター派諸侯として領内の宗教改革を進めた。 当時ドイツの庶民の思いは、「なぜ教皇さまはあれほどお金持ちなのに、自分のお金で大聖堂を建てないのだろう」と言うものもであった。 中性キリスト教原理主義に一掃された『真実の世界観』が、自分が生きている現実の世界とは余りにもかけ離れていることを再認識されるようになったヨーロッパの人々は、現実を直視し観察する古代ギリシア人の卓越した研究成果に目覚めたのだ。その多くの人々は、ルクレティウスの自然主義・合理主義・無神論・物質主義が再認識され、現実の世界を支配する教会政治の専横と、聖職者でありながら論理的な正当性が欠けていることに苛立つようになった。 新約聖書で語られるイエス・キリストが、再降臨した時に、中性キリスト教原理主義者や現代のローマ教皇はどう振舞うのか。イエス・キリストを目前にして、ただ「時代が変わったのです」と弁解できるのであろうか?悲しいかな偉大なイエス・キリストとの出会いを想定していないようだ。 詩人ルクレティウスは、デモクリトスの物理学に「あらゆる大地は知へと開かれている。なぜなら徳を備えた魂にとっては、この宇宙が祖国であるから」と、深遠で美しい言葉を添えた。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
9)キリスト教に排除されたデモクリトスの著作
ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは『博物誌』の中で、ミレトスは黒海やマルマラ海沿岸に90もの植民地を作ったと記す。ギリシア語のアルファベットも、BC800年頃にこのミレトスで作られっと考えられている。 この小アジアのエーゲ海に面したイオニア地方に造られたギリシア人の港湾都市は、早くから中継貿易と市場取引が活発で、それにより培われた先進的な合理的思考故にギリシア哲学がこの地で発祥した。 前6世紀前半、この都市出身のタレスやレウキッポス(デモクリトスの師として原子論を創始)などが、万物の生成の元(アルケーarkhē)を探求することは自然な思考の流れで、その叡智を極めようとする研究過程で体系化した理論を総称してイオニア自然哲学といい、後のアテネのソクラテスやプラトン、アリストテレスなどのギリシア哲学の源流となった。 リディア Lydia は、BC7紀~BC546年、インド=ヨーロッパ語族系統の王国で都はサルデス(サルディス)にあった。BC612年にアッシリア帝国が滅亡して、オリエント世界が新バビロニア王国(メソポタミア地方)、メディア王国(イラン高原)、エジプト第26王朝末期およびこのリディア王国(アナトリア)の4王国に分立した時代、その最も西部のエーゲ海に面した地域を支配していた。 タレスと同時代のリディア王国は、東の大国メディア王国とハリュス河あたりで境を接していた。東部アナトリア高地を源流に、黒海に注ぐハリュス河は、底が浅いので船舶の航行には適さなかった。タレスは、ハリュス河の流れを変えることで、橋を渡さずにクロイソス王(在位BC560~BC546)の軍隊が渡河できるようにした。 BC585年に、メディア王国がリディアを攻撃したが、突然起こった日食に不吉を感じて両国は和平し、ハリュス河を国境と定めた。この戦いの時に、タレスは、日食が起こることを予言してみごとに的中させたという。 AD2世紀に、クラウディオス・プトレマイオスが著した天文学書「アルマゲストAlmagest」では、ギリシア天文学の通説である「天動説」を集大成している。プトレマイオスは、ギリシアの天文学者・数学者・地理学者で、127~141年にアレクサンドリアで天体観測をしていたという事実以外、なぜか?その履歴全てが分からないままとなっている。 ギリシャ天文学の集大成として、以後、教科書的存在となる「アルマゲスト」は、、ギリシャ語では『マテマティケー・シンタクシス(数学的集成)』という書名であった。中世にアラビア語訳されたとき『大著述』と呼ばれるようになり、それが12世紀に北イタリアのクレモナCremonaのゲラルドによりラテン語に翻訳されて『アルマゲスト』となった。以後、この書名で普及し、中世を通じて最も権威ある天文学書となる。 (ゲラルドGherardoは、12世紀にギリシアやアラビアの第一級の自然科学文献を、アラビア語からラテン訳した最大の翻訳者。ユークリッド・アルキメデス・プトレマイオス・アリストテレス・フワーリズミー、イブン・シーナー、イブン・アルハイサムなど87種にのぼる文献を翻訳した。ギリシアやアラビアの科学の大いなる遺産の上に、ようやく西欧科学の独自な活動が開始され、『科学革命』を起こし新たな西欧科学の知的基盤が作られていく)。 ゲラルドによりラテン語に翻訳されて『アルマゲスト』となり、この書名が一般的になった。中世を通じて最も権威ある天文学書となった。 15世紀のドイツの天文学者ヨハン・ミュラーJohann Muller(1436-1476)が著した『アルマゲスト』向けの『ヨハネス・レギオモンタヌスによる要約』によってはじめて十分に理解されるようになり、ヨーロッパの天文学がギリシャの水準に立ち戻り、近世への道が開けるきっかけとなった。ヨハン・ミュラーは、生地ケーニヒスベルク(王の山の意)をラテンに訳して、それを自らの名乗りとしてレギオモンタヌスRegiomontanusと称した。彼はプトレマイオスの数学や天文学の熱烈な信奏者で、「アルマゲスト」をラテン語に訳して抜粋し、その一方、彼自身の分かり易い注釈を加えて出版した。これが『ヨハネス・レギオモンタヌスによる要約』である。 「アルマゲスト」には、新バビロニアの祖ナボナッサル王(ナボナザール王;BC747-734)が即位したBC747以降の日食などの天文現象の観測記録が年代順に遺されていたため、それが記されいる。「アルマゲスト」が参照した年代順の王の一覧は、『プトレマイオスの王名表Canon of Kings』と呼ばれ、古代の年代を参照するための最も重要な基礎資料の1つとなり援用され続けられた。 プトレマイオスのナボナッサルが即位したBC747を起点として始まる「紀年法」は、世界最古の「紀年法」と言われている。「王名表」の「紀年法」は、アレクサンドリアのギリシア人天文学者に引き継がれ、BC331年~BC305年までマケドニア王国の王、BC304年からBC30年までプトレマイオス朝の王、そしてローマ帝国、また皇帝はいなかったが東ローマ帝国に引き継がれた。このリストは、コンスタンチノープルが陥落する1453年まで引き継がれた。 プトレマイオスは、次の月食を「アルマゲスト」のなかで実際に取り上げている。このなかで前半の記録はバビロニアからのデータである。もしこれらのデータがなければ、プトレマイオスが計算して「蝕」を予測することは難しかったであろう。 ドイツの天文学者ヨハン・ミュラーJohann Muller(1436-1476)が著した『要約』によってはじめて十分に理解されるようになり、ヨーロッパの天文学がギリシャの水準に立ち戻り、近世への道が開けるきっかけとなった。 エクリプス eclipseは、「日食」や「月食」など天文現象における「蝕」を意味する英語である。エクリプス (食) が起きるのは、地球と月が太陽と一列になった時で、 一方の天体が太陽による影を他方の天体に落とす時である。英語 やギリシア語でエクリプスを用語として共通に使うのは、日食・月食が相互に関連しているからである。古代バビロニア時代、天文学に携わる人々には、日食・月食の周期(サロス周期)は、知られていた。 アッシリアはチグリス川の上流で古くから勢力を保っていたが、BC8世紀頃より急速に領土を拡大した。エサルハドン王(BC680-669)からアッシュルバニパル王(BC668-627)の時代には、王は各地に占星術師を派遣し、頻繁に天変とその解析を報告させ記録させていた。 しかし、日食の予想は難しく、日食が有るか無いかの王の詰問に「日食の予想は月食の予想のようにはいかない」と返答していることがタブレット(粘土版)に刻まれている。 この頃の王への報告に記録されている日食は、 ☀日食 ☀BC679年 6月17日 ☀BC669年 5月27日 ☀BC657年 4月15日 ☀BC651年 6月7日 BC11世紀よりメソポタミアへ侵入したカルデア人は、BC626年に新バビロニア王国(カルディア王国)として独立し、その後メディアと連合して、BC612年にアッシリアのニネベを陥落させた。しかしカルデア王国は長くは続かずBC539年にはペルシアの攻撃で滅亡し、その後のメソポタミアはペルシアの領国になった。 メソポタミアの関連のタブレット(粘土版)の中には「食テーブル」と呼ばれる、その頃の日食や月食の日付や起きた位置などをリストにしたものがある。 現在見つかっているものは、BC475からBC457年までの日食のリスト。 また月食についてもBC417からBC381迄の月食のリストやBC175からBC152迄の月食のリストが見つかっている。 この時代、既にメソポタミアの数理天文学は高いレベルに達していたようだ。 前6世紀中頃のクロイソス王のリディア王国は、エーゲ海に面した領国であったため交易が盛んで、商工業が発達した。BC7世紀には、ヘルムス川の砂金で世界最初の貨幣(リディア王の紋章であるライオンの絵柄の「エレクトラム硬貨」)を作り使用した。この頃、全盛期となり、エーゲ海に面したエフェソスを支配して、巨大なアルテミス神殿を建造した。 しかし、東方のカッパドキアの領有を巡ってアケメネス朝ペルシアのキュロス2世と対立し、ギリシアのパルナッソス山の西南麓にある聖域デルフォイにあるアポロン神殿でアポロン神託を得て開戦したが叶えられず、BC546年にキュロス2世に攻撃され、その王クロイソスは首都サルデスで捕らえられ滅ぼされた。 ヘカタイオス(BC550年頃~BC476年頃、ギリシアで最初の歴史家)は、BC6世紀頃、富裕な家に生まれた。ペルシアやエジプトを旅して、「世界周遊記」などを著した。旅した後、生まれ故郷のミレトスに定住した。高い地位に就き、神話学や歴史の本の執筆に専念した。当時、BC5世紀前半は、アケメネス朝ペルシア帝国とギリシア都市国家連合間の長期にわたるペルシア戦争が始まる頃であった。ヘカタイオスは、ペルシアに対するイオニアの反乱の無謀を説いたが入れられなかった。 タレスは万物の根源(アルケー)は水であるとした。またエジプトに行ってピラミッドの高さを測定し、BC585年5月28日に小アジアで起こった日蝕を予言した。 当時から賢人として尊敬を集めていた。その一方で、オリーブの収穫が豊作になることを予想して、冬の間にミレトスとキオス島にある全てのオリーブの圧搾機械を借り切っていた。案の定、豊作になり、収穫の時、多くの人がタレスに圧搾機の貸し出しを注文したため、莫大な利益を得た。その『叡智』には商才も含まれる。 タレスはエジプトに出掛けてピラミッドの高さを測定した方法は、自分の影が自分の陰と同じ長さなる時に、ピラミッドの陰の長さを測定した。 タレスが、本当に、日食を予言したとすれば、バビロニアの祭司たちが、宗教的目的のために、少なくともBC721年以来蓄積してきた天文学の知識を利用したと見られる。バビロニア人は、BC6世紀には、黄道(太陽の周囲を公転する地球の軌道)と白道(月が27.32日かけて地球の周りを公転することにより天球上を動く道)を確定していたようだ。日食とは、月が太陽の前を横切るために、月によって太陽の一部(または全部)が隠される現象、月と太陽の重なり方によって、中心食と部分日食に分類される。中心食とは、月と太陽が完全に重なる日食のことで、それ以外を部分日食と呼ぶ。 この時期、ギリシアの知識人たちは度々、リュディアのサルディス(現;トルコ共和国マニサ県サルト)を訪れていた。サルディスは、ヘルムス渓谷の中流に位置し、トモロス山(ボズ山)の山裾の険しく高い尾根にアクロポリスを築いていた。 メソポタミアや西アナトリアを通る『王の道』の終点に位置し、軍道ばかりでなく、更にエーゲ海沿岸に通じる重要な街道の途上にあった。アクロポリスの眼下には、ヘルムス川(ゲディズ川)の支流周辺に広がる肥沃な扇状地があった。しかも砂金を含む沖積土である。タレスはサルディスでバビロニアの日食の記録に接していたかもしれない。 古来、ギリシアでは「七賢人」を、尊敬を込めて挙げている。その七賢人の七人は必ずしも一定しないが、イオニアのタレスだけは、「最初の哲学者」として必ず挙げられる。タレスの著作は一切遺されていないが、ヘロドトスやアリストテレスなどの著述の中に引用されている。 ミレトスは古代ギリシアにとって重要な都市であった。都市の繁栄もBC494年にミレトス艦隊がペルシアに敗れて都市が完全に破壊されたため衰退した。ヒッポダモスは、BC5世紀頃に活動したミレトス生まれのギリシア人で、史上に遺る最初の都市計画家とされている。ヒッポダモスはアテネ人達の古代ギリシア諸都市の無計画さを嫌い、整然と統制された都市計画を実現させた。ヒッポダモスが手がけたとされる都市では、いずれも機能的な構成を基本とし、その格子状パターンは、後にヒッポダモス方式と呼ばれた。格子状プランは、当時の中心都市アテネなどにはなかったことだが、イオニアではBC7世紀から既に使われていることが知られている。ヒッタイトやアッシリア、バビロニアなどの都市計画に織り込まれていた。ミレトスの新都市の建設は、BC479年頃開始された。B.C.474年に、再建されると、東地中海やエーゲ海の沿岸都市に再び影響力を及ぼした 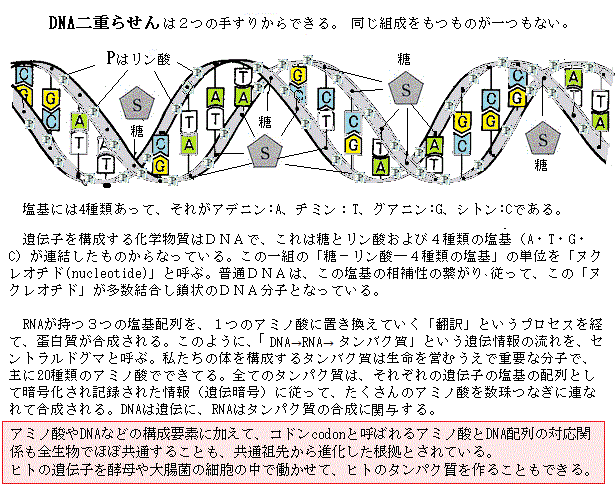 BC5世紀、都市を再び手中にしたペルシア人を、BC334年にアレキサンダー大王が駆逐したが、ミレトス市民は大王の支配下に入るのを歓迎しなかったと言う。大王の死後は王の部将アックロスのベルガモン王国の支配下に入り、BC200年にはローマ帝国の領土に包括された。 BC5世紀、都市を再び手中にしたペルシア人を、BC334年にアレキサンダー大王が駆逐したが、ミレトス市民は大王の支配下に入るのを歓迎しなかったと言う。大王の死後は王の部将アックロスのベルガモン王国の支配下に入り、BC200年にはローマ帝国の領土に包括された。アウグストスとハドリアヌスの時代にミレトスには多くの建造物が建てられた。 ミレトス遺跡の「市場の門」は、泉と議事堂の間、式典の通りの突き当たりに立つ壮麗な門で南アゴラに属する。 2階建ての記念門は円柱や彫像に装飾された3ヵ所の入り口がある幅29mの造りであった。現在、東ベルリンのベルガモン博物館に保存されている。 式典の通りの突き当たり、議事堂の北側に位置する広さ196×164mの市場である。面積32,000㎡の古代世界で最大の規模で、未だごく一部が発掘されただけである。三方にそれぞれ1ケ所ずつ門があり、2つの身廊nave(キリスト教聖堂内部のような、中央の細長い広間の部分。入り口から主祭壇に向かう中央通路のうちの翼廊に至るまでの部分を指す)の付いたドーリア式柱廊に囲まれていた。東柱廊の後方には78の店が並んでいた様である。B.C.3世紀に造られ、最終的に整ったのは、約BC2世紀頃と考えられている。
オスマン帝国は、ミレトスを重要な水陸交通の港湾都市として利用したが、港が沈泥で塞がれた時、ミレトスを見限った。現在、ミレトス都市の遺跡は海から約10km奥にある。現在ではトルコ共和国領に属し、既に廃墟となって久しい遺跡として残されている。 この古代の東地中海世界では、ギリシア語が3000年以上前から、インド = ヨーロッパ語系の日常言語として、さらには、公式記録や外交文書の言語として、重要な役割を果たしてきた。そのギリシア人と、古代イタリア人が活躍する。 デモクリトス(BC470年頃~370年頃)は、トラキア(ギリシア北方)のアブデラの出身、生年はBC470年頃で、ソクラテス(BC469年頃~BC399年)とは同時代であるが、交流はなかった。デモクリトスの全著作の散逸は、古代文明の崩壊の後に起こった。 一神教のキリスト教の世俗的な権威を維持するためには、デモクリトスの合理的かつ唯物論的な哲学は、キリスト教の脅威となる文書としてことごとく破棄された。プラトンとアリストテレスは、異教徒であったが魂の不死を信じていたため教会に容認され、むしろ古代文明の崩壊後の西欧思想は、アリストテレスを基礎に体系化された、とも言える。 キリスト教は、コンスタンティヌス帝の313年にミラノ勅令で公認され、ローマ帝国内に広く浸透していた。同時に、様々な教義が生まれたため、その統一の必要が生じた。ローマ時代のエジプトの、アレクサンドリアの司教であったアタナシウスは、イエスは神の子であり本質において神性を持つと主張し、イエスは神そのものではなく父なる神に従属するとして、その神性を否定するアリウス派と深刻な対立関係にあった。 アリウス(250頃~336)は、アレクサンドリア教会の長老であった。アリウスは、キリストは父なる神に、他の被造物と同じく無より造られたもので、神と同質ではないと人間性を強調した。キリストの本性は、神聖ではあっても、神の本性とは異質のものである、したがって神に従属しなければならない。と主張した。 324年、自らキリスト教徒であることを宣言したコンスタンティヌス帝によって、325年、小アジアのニケーア公会議に約300人の司教が召集され、協議の末、アタナシウス派が正統な教義とされた。 会議はアリウス派に反発するアタナシウス派との間で2ヵ月間にわたる議論がなされ、その結果、中間派も含めてアタナシウス派が大勢を占め、イエスの神性を認めるアタナシウス派が正統、アリウス派は異端とされ、ローマ領からの追放が決定された。300人の司教のうち反対は5人だった。 しかし、会議の後、コンスタンティヌス帝がアリウス派に寛容となり、両派の抗争は再燃した。アタナシウスは、定見のない帝と厳しく対立するようになった。 アリウス自身は、335年にコンスタンティヌス大帝によって追放処分が解除されている。ニケーア公会議ではアリウスの説を否定されたが、教父エウセビオなど、アリウス支持派はまだ宮廷で大きな力を維持していた。 大帝自身も次第にアリウス派の考えを認めるようになり、ついに追放処分を解除した。アリウス派は、コンスタンティヌス帝の晩年には、コンスタンティノープルのローマ帝国宮廷の中ではむしろ優勢となっていた。337年、大帝が死の床で洗礼を受けたが、その洗礼を施したのもエウセビオスだった。このようにコンスタンティヌスの時に、アタナシウス派が正統として確立したわけではなく、次のコンスタンティウス2世の時には逆にアタナシウスが追放されている。アタナシウス派が正式に正統とされるのは、381年のコンスタンティノープル公会議においてである。 コンスタンティヌス帝の死後、皇帝位は再び分裂し、キリスト教公認も一時期撤回されるなど混乱が生じた。アタナシウスの神とイエス双方に神性を認める考えに、さらに聖霊を加えて、その三者それぞれに際立った特徴があるが、実体において一体であるとする三位一体説が教義として確立した。 ローマ帝国末期のテオドシウス帝(在位379~395年)は381年に第1コンスタンティノープル公会議を召集し、アタナシウスの教義を補強した三位一体説を正統教義として確認した。 テオドシウス帝は390年、ギリシャ北東部・エーゲ海北岸の港湾都市テサロニケで暴動を起こした住民7,000人を殺害した。繋駕車(けいがしゃ:二輪の戦車)競走で市民の花形騎手が、同性愛の禁令を犯したかどで逮捕がされ、それに怒った市民が無条件即時釈放を要求して暴動を起こした。釈放を拒否したゴート人の総督とその幕僚たちに対する、蛮族出身者への差別意識も重なり、テサロニケのキリスト教徒が暴徒化して惨殺した。八つ裂きにした死体を勝利のしるしとして示威しながら市街で暴走した。報告を受けたテオドシウス1世は、「同胞と戦って血を流して、お前たちを守ってくれている蛮族出身将兵を殺すとは何事か!」と激怒し、徹底的鎮圧と暴徒の無差別殺戮を命じ、市民7,000人余りを虐殺した。ミラノ司教アンブロシウスは、皇帝がその罪を懺悔しなければ聖餐式を許さないと申し渡した。 聖餐とはイエス・キリストの最後の晩餐に由来するキリスト教の儀式で、その「主の晩餐」の語はいずれの教派でも使われる。新約聖書には、イエスが引き渡される前に、弟子たちと最後の食事を共にし、自分の記念としてこの食事を行うよう命じたことが記されている。既に1世紀終り頃には、信徒はパンとぶどう酒をキリストの肉と血そのものと見なし、「復活の主」の臨在を確信しながら、愛餐を共にしていた。復活のキリストの再臨を熱望しつつ持たれた彼らのその食事の中で、やがて厳密な意味での聖餐が祝われるようになった。伝統的なキリスト教において、聖餐の式は神による人間の罪からの救いを成就する式であり、イエスの死と復活を思い、そこにイエスの現存を確信し、信仰者と神、信仰者同士の絆を深めるものであった。 やむなくテオドシウスはアンブロシウスに従ってミラノの教会で懺悔し、その結果が、キリスト教国教化につながる。さらに392年、異教徒禁止令を出し、アタナシウス派キリスト教を事実上の国教とする措置をとった。多神教世界から一神教世界への大転換の時代であった。これによって三位一体説のキリスト教信仰がローマ帝国と結びついて権威ある国家宗教とされることとなった。アリウス派は、テオドシウス1世 以後勢力を失った。 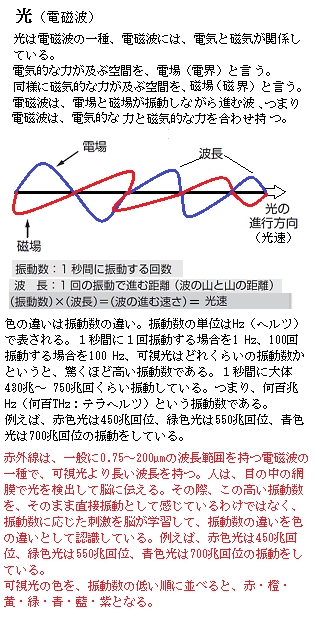 一神教の教義が猛威を振るった数百年間に、デモクリトスなど叡智を考究する学派は次々と閉鎖され、公認されたキリスト教の思想と相容れないデモクリトス文書全てが散逸した。 一神教の教義が猛威を振るった数百年間に、デモクリトスなど叡智を考究する学派は次々と閉鎖され、公認されたキリスト教の思想と相容れないデモクリトス文書全てが散逸した。3世紀頃のギリシアの哲学史家、ディオゲネス・ラエルティオスの著書「哲学において著名な人々の生涯およびその学説」では、全部で82人の哲学者をとり上げている。そのディオゲネス・ラエルティオスが伝えるデモクリトスの著作は『大宇宙系』『小宇宙系』『天体について』『自然について』『光線について』『明朗闊達さについて』『農業について』『種・植物・果実をもたらす諸原因』『動物を生み出す諸原因』『幾何学について』『医学について』『暦法』『法律論集』『戦術論』『大洋の航海』『バビロンの聖典について』『律動と調和について』『歌曲の美しさについて』『病から生じる熱および咳について』『ピタゴラス』『ホメロ スについて』など70篇と膨大である。その対象は、科学・自然哲学・倫理学・数学・音楽・医学・文学など多岐にわたる、まさに百科全書的とも言える著述家であった。そのどれ一つ残されていない。 530年頃活躍した古代末期の新プラトン派の哲学者シンプリキオスは、プラトンとアリストテレスを対比しつつアリストテレスの『範疇論』『自然学』『天体論』『霊魂論』についてすぐれた注釈を著わした。特に『自然学』の注釈はソクラテス以前の哲学者の断片的記述を多数含む点で貴重な資料である。しかしながら、デモクリトスに関してはその原文の引用が全くない。既に6世紀頃にはデモクリトスの著作全部が破棄されていたようだ。 宗教的迷信については、デモクリトスの著作からの引用断片において明確な記述は見られないが、やはり確たる根拠のないものと見なしていたと考えられる。実際、デモクリトスの自然学の枠内では神々ですら原子の集合体であり、そのような神々であれば有限の存在であり、原子の運動を統御するどころか、あくまでも世界の秩序の一部分であるにすぎないと見ていた。 「ある人々は、死すれば心身共に解体してしまうことも知らず、しかしも人生で犯した悪行を意識して、戦慄と恐怖のうちに生の時間を辛苦して歩む。 死後の時間についての嘘の物語を作りながら…」 デモクリトスは死後の生命の存続を「まやかし」と断じた。これは、ギリシア思想史上、初めて明確に生命の永続性を否定した画期的な記述であった。原子論者のデモクリトスにとって、死とは、原子からなる魂と身体の結合体が解体離散することであれば、死後に感覚や意識が存続することはもはやありえない。死の事実について無知であれば、この世での自らの悪行に良心の呵責に戦き、死後に待ち構えている恐ろしい劫罰を予期して、不安と恐怖に苛まれつつ生き続ける。それは魂にとっての動揺である。デモクリトスからすれば、心穏やかに生きられることのない彼らの「生」は、「生」と呼ぶ価値すらないである。 鋭い観察眼を持っていたデモクリトスだったが、その晩期には盲目になった。 「生涯の終わり近くなって盲目となったデモクリトスは、『魂の目』で見るものは肉体の目で見るものより真実の姿に近く、より美しいと言っている。彼はついに断食して自ら命を 絶つことにした。ところが、祭の最中に息を引き取ることになりそうだとわかると、妹が祭を楽しめなくなるからと言って、焼きたてのパンのにおいを嗅いで命を延ばしたと伝えられている。」(スレンドラ・ヴィーマ『ゆかいな理科年表』) 当時、三位一体説のキリスト教信仰が跋扈していれば、デモクリストの著書は受け入れられるはずもなかった。 エピクロスEpikouros(BC341年頃~BC271年頃)は快楽主義で知られる古代ギリシアのエピクロス学派の始祖である。サモス島出身のギリシアの哲学者で、BC307年頃、後に「エピクロスの園」と呼ばれるアテネ郊外に庭園を手に入れた。「エピクロスの園」で展開されたエピクロス学派は庭園学派と呼ばれる。親兄弟の他に大勢の弟子たちが集まり、親密な共同生活を送った。召使の奴隷にも哲学を学ばせたことが記録に残っている。エピクロスが71歳で没したあとは、弟子が庭園を引き継いだ。 その学徒はエピクロス学派(英語でepicurean)と呼ばれることになる。ここで研究・教育・著述に専念し、300巻を著したと伝えられるが、その殆どは失われ、現存するのは弟子たちに宛てた3通の手紙と教説と箴言(しんげん)の断片のみである。 原子論者のデモクリトスは、物体が見えるのは、その物体から原子が流れ出て、それによって物体の像が大気に判でも押したように現れ、それが伝わって眼に入って視覚が生じるのであると説く。デモクリトスは、物体の像をエイドラ(eidola)と呼ぶ。 エピクロスは、デモクリトスの原子論を受け継ぎ、自然界の事物は原子から構成されている合成物であるが、合成物の表面からは絶えずエイドラ eidolaが流出している。それは多くの原子からなる言わばフィルムのようなものであるがそれが感覚器官の内にあって同じく原子からなる魂を刺激することによって感覚が成立すると言う。 死や死後の懲罰の不安と苦しみから人間を解放せよ。苦を避け、隠れて生きよ!それも平静不動ataraxia(ætəˈɹæksiə)の境地を得るかぎりにおいてである。エピクロスの哲学は国事や世間の煩わしさから遠ざかり、心の平安を大切に生きることを説き、その生き方を意味する「隠れて生きよ」という言葉がよく知られている。後世誤解されたような単純な快楽主義ではない。 エピクロスの「快楽」とは、「苦痛や心配から解放された心の平穏としての幸福」だったが、快楽を人生の最高善と説いたことが誤解され、16世紀には彼にちなんで「美食家(epicure)」や「食道楽(epicurism)」という語が生まれた。そのため「epicurean」は今日、エピクロス学派の哲学者ばかりでなく、「快楽主義者」「美食家」をも意味するようになる。 エピクロスは「デモクリトス」の原子論を思想の基底とする、原子論的唯物論や原子論的自然観を展開した。霊魂は死によって消滅する。また感覚を徳や幸福の基準とする。この思想の上に快楽主義が築かれている。 エピクロスは弟子への手紙に次のように書いている。 「快楽が人生の目的であると我々が言う場合、その快楽とは、一部の人たちが無知であったり誤解したりして考えているような、放蕩や享楽のなかにある快楽のことではない。身体に苦痛のないことと、魂に動揺がないことに他ならない」 エピクロスは、アタラクシアの追及とともに、「死」の恐怖を克服することも唯物論の立場で説く。死とは、生の構成要素であるアトムへ解体することであり、解体されたものは感覚を持たず、感覚を持たないものは人間にとってなにものでもないと説く。 「死は我々にとって何ものでもないと考えることに慣れるようにしたまえ。というのは、善いことや悪いことはすべて感覚に属することであるが、死とはまさにその感覚が失われることだからである。」 「死は、もろもろの災厄のなかでも最も恐ろしいものとされているが、実は、我々にとっては何ものでもない。なぜなら、我々が生きて存在している時には、死は我々のところには無いし、死が実際に我々のところにやってきた時には、我々はもはや存在していないからである。」 「私が存在する時には、死は存在せず、死が存在する時には、私はもはや存在しない」 「epicureanエピキュリアン(快楽主義者)」の言葉の語源となったエピクロスの快楽主義は、死への真相を知ることで、死の恐怖を克服し、平静不動ataraxiaの境地に達することで『生』を全うする。エピクロスの倫理思想は、近代以降の哲学者や思想家に大きな影響を与え続けた。 目次へ |
||||||||||||||||||||||||||||||
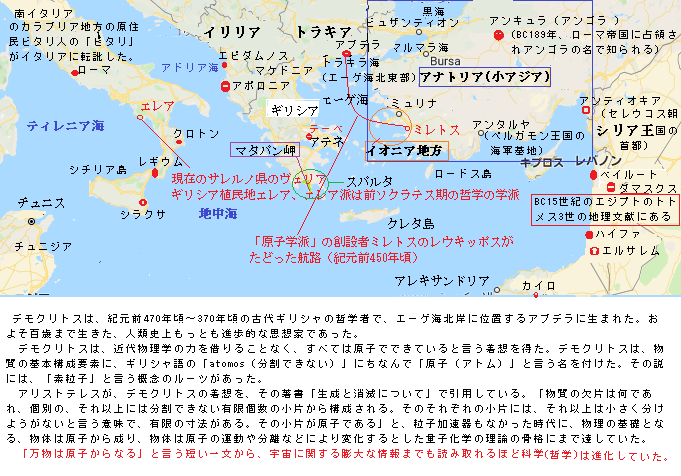












 ギザの
ギザの