| Top 車山高原 車山高原お知らせ 車山ブログ
|
|
| 目次 |
| 1)中王国時代,第12王朝 |
| 2)第2中間期, 第13王朝 |
1)中王国時代,第12王朝
古王国時代(BC2650年頃~BC2180年年頃)、最期の第6王朝のファラオ・ペピ2世の治世は90年以上続いたため、晩年には王権が弱体化した。BC2184年頃、ペピ2世が100歳を迎えて死去した。この時期、旱魃により治安の悪化がみられ、エジプト各地の州侯が自立傾向を示す。世界的に社会が混乱した時代で、中東全域で長期に及ぶ乾燥化が始まり、エジプトでは、その第1中間期(BC2180年頃~BC2040年頃)を通して食糧難が民衆と支配層を苦しめた。やがてテーベの第11王朝第4代ファラオ・メンチュヘテプ2世によるエジプト統一により、第1中間期は終焉し、二度目の隆盛期である中王国時代が始まる。
 |
| プント国は、エジプトの南東にあった。イエメン・ソマリア・ジブチ・エリトリア・スーダンなどの一部を含む領域。古王国時代, BC前26世紀、エジプト第4王朝のクフ王の時代、プント国から黄金がもたらされたとある。BC25世紀の第5王朝サフラ王は、没薬(モツヤクジュ)・白金・香料などを入手するためプントの国へ船団を派遣した。 BC1950年頃、第1中間期第11王朝のメンチュヘテプ3世は、エジプトから紅海までのワディ・ハンママートの陸路を整備した。 |
メソポタミア地域では、大規模な気候変動から、大地の乾燥が拡大し、ユーフラテス川の水位は1.6m低下した。南メソポタミア一帯では、人口の減少が見受けられ、50年後には、アッカド帝国自体が干ばつで滅亡する。北大西洋循環は驚くほど急激に減速し、数年の内に、これまで地中海の湿った空気をメソポタミアに運び続けていた偏西風が弱まった。各地に大旱魃が訪れ、破局が始まった。
同じ時期にエルニーニョ現象が発生し、アフリカからインド洋に吹いていた季節風が非常に弱まり、エチオピア高原に干魃をもたらした。ナイル川の水量は減少し、川の氾濫も勢いを弱めると深刻な飢饉となり、長年に渡りエジプト文明を荒廃させた)
メンチュヘテプ2世のエジプト再統一によって各地の採石場から良質な建材が入手が可能となり、エジプトで再び古王国時代のような大規模建築が始まった。テーベの職人に加えて、全土から職人たちが集められ、建築事業や芸術が振興された。特に、建築に画期的な変化をもたらした。テーベ対岸(ナイル西岸)に築くメンチュヘテプ2世の巨大な葬祭殿は、エジプトの分裂の時代が終わり、再び強大な国家となったことをその巨大さが証明する。
古代エジプト第11王朝の第5代ファラオ・メンチュヘテプ3世は、父メンチュヘテプ2世の治政が50年と長期であったため、その息子のメンチュヘテプ3世が、即位した時には既にかなりの高齢であった。統治期間は12年であったが、父王の統一事業によって国力が充実していたため、神殿や祠堂など多くの神殿建造の石材を得るため、上エジプトのワディ・ハンママートにある石灰岩の採掘場へ遠征もしている。BC1950年頃には、プントへ遠征隊を派遣し金・香料・コクタン・象牙など資材を調達するほど安定した治世であった。
第6代ファラオ・メンチュヘテプ4世は、第11王朝の最後の王であるが、サッカラやアビュドスで発見されている王名表ではメンチュヘテプ3世が第11王朝最後の王とされている。また別の記録ではメンチュヘテプ3世の後に7年間の空位期間があったとされている。このように、後世の公的記録の多くでメンチュヘテプ4世の存在は抹殺されていた。彼の存在を示す同時代の遺物もなく、メンチュヘテプ4世の名が記された史料は 、第12王朝のアメンエムハト1世の時代に作られた容器の破片が出土しているだけである。その一方、ワディ・ハンママートに残された碑文から、第11王朝の宰相兼上エジプト総督が「アメンエムハト」であったことが知られる。
テーベは約1000年にわたりエジプトの政治の中心となり、その守護神アメンも王朝神・国家神として神々の王の地位を保ち続けてきた。第11王朝は中央集権国家体制の再建に急なあまり、第1中間期に成長した世襲貴族や地方豪族の反発をかってクーデタで倒された。
 |
| ナイル川は、赤道下のビクトリア湖など湖沼高地から北流し、北緯31°付近で地中海に流入する世界最長の河川である。その最下流のエジプトは、流下してくる水を利用する。 年間降水量は極めて少なく、地中海に面するアレクサンドリアで約200mm、カイロで約25mm、南部のアスワンではわずか1mm程度、水資源のほぼ全量をナイル川に依存している。 ナイル川の洪水で氾濫した水をそのまま利用するのではなく、その灌漑は、古代から水路を造り、この洪水を堤防で囲んだ耕地(ベイスン)に導入して、2か月程、1.5m程の深さに湛水させ、ナイル川の洪水が引くと排水してコムギなどを播種した。これはベイスン灌漑と呼ぶ。 この洪水の長期湛水が、古代エジプト文明から5千年にわたりエジプトの農業を支えてきた。 乾燥地農業に宿命的に伴う耕地への集積塩類が毎年の湛水によって洗い流され、洪水に含まれる肥沃なエチオピアの流亡土壌が、毎年、耕地に堆積され、無肥料でも高い生産性が維持できた。 一方首都カイロから北へ車で4時間以上かかるナイル川の最下流域カフルシェイク県のナイル川の支流を使った運河の終点に行くと、底を掘り返して盛った土手が白い塩で覆われている。農業用水や地下水には塩分が溶け込んでいるので、灌漑した農地の地表からの蒸発量が多いと、塩が残る。ここのようなナイル川デルタの下流では、その水量が作物栽培に十分でない。農地からの排水を農業用水に再利用するため、さらに塩分濃度が高まる。 元々ナイル川は定期的な洪水により、それを利用した伝統的な灌漑が流域に肥沃な土をもたらした。1970年完成のアスワンハイダムにより洪水がなくなった。土は塩類の蓄積で疲弊し、肥料を大量に投入しなければならなくなった。 |
アメンエムハト1世は、BC1990年頃の即位直後に軍隊を率いて反対派の諸侯やヌビア人などの対立勢力を鎮圧し、古王国時代の首都メンフィスの南に「二つの土地の征服者」と言う意味を持つ、新たな都イチ・タウィ(現;ファイユーム県ラフーン)を建設し、前王朝が都とした南のテーベから北のファイユームへ王都を移転した。
新王朝は、地方有力豪族の多くを州知事に任命し、貢租の一部を自由裁量処分する権利や私兵の保有など支持勢力である世襲貴族の既存の特権を尊重したが、同時に、中央集権国家の実現を目指した。州知事間の衝突や特定の州知事の勢力拡大を防ぐため、地方行政単位であるノモス(州)の境界の確定と、同時に灌漑水路網の用水権を王家が保持することを明確化し、更に裁判官の任命権を確保した。
王に忠実な官僚を養成するため、第1中間期に形成された都市居住の工人層や王に直属する小土地保有民(庶民)の子弟に対し教育を奨励し、文字の習得や測量など教育制度の整備を行った。
王権の新たな経済基盤とするためファイユームの開発に着手した。そのため首都をテーベからファイユーム盆地に近いイチ・タウイに移すなど将来の中央集権化の実現へ向けて布石を打った。
治世20年目には改革の一貫として、古代エジプト史上で初めて共同統治の制度を導入し、王位継承の安定化を図った。共同統治者となった息子センウセレト1世は国境線の維持や領土の拡大など、主に軍制の統括にあたった。この息子と共同統治の政権形態が、クーデターを企てにくいものにし第12王朝を安定させていった。
アメンエムハト1世は治世30年目に衛兵によって暗殺された。当時、リビアへ遠征中であったセンウセレト1世は、父王暗殺の知らせを受けて、直ちに軍隊を残し少数の側近のみを率い急ぎ首都に帰還した。果断に混乱を収拾して、王位を得ようとした別の王子を殺害し、単独の統治者となった。これにより、共同統治者の存在が王位簒奪の防止に有効であることが実例で示され、以後第12王朝では父王が王子を共同統治者に据えることが制度化される。
アメンエムハト1世の方針は、王の暗殺にもかかわらずセンウセルト1世以下の諸王によって受け継がれ、第5代センウセルト3世の行政改革の断行により完全な中央集権化に成功する。
父王センウセレト2世はその治世中、各州を治める州侯たちに寛容な政策を行ったため、その息子のセンウセレト3世が即位した時、州侯達の権力は再び王権と拮抗するまでになっていた。センウセレト3世は、王位を不動にする新たな国家制度の構築を試みた。全国土を北、南、最南の三つに分割し、それぞれに高官会議を設置して州侯の専横を阻んだ。その結果、州侯の権力は大幅に抑えられ、内政は安定した。
完成度の高い政府組織が整うと、センウセレト3世は対外政策に力を注ぐ。資源豊富な採掘地を確保するため、ヌビア遠征を断続的に行った。その一貫として第一急湍に掘られていた運河の拡張工事も行っている。ある碑文には、センウセレト1世は150の彫像と60のスフィンクスの製作に必要な石材を確保するため、17,000人の遠征隊を東部砂漠の中央にあるワディ・ハンママートに送ったとある。ワディ・ハンママートは、エジプトの東部沙漠にある、岩山地帯に刻まれた長いワディ(涸谷)で、古代にも、ナイル流域部から紅海沿岸に到るルートとして用いられた。
現在は、ケーナ県の小さな町クィフト近傍を経由して、エル-バハール・エル-アフマル県方面に到る舗装された地方道が敷設されている。ナイル流域と紅海沿岸部を結ぶこの道路の交通量は多い。
古代エジプト王朝では、ワディ・ハンママートは、まず石材の石切り場として、次に、紅海沿岸部で金や銅鉱石を採掘し、ナイル川で舟運するルートとして、さらに紅海経由のシナイ半島交易ルートとして重視された。ワディ・ハンママートを経由する交易路のナイル川の拠点は、上エジプトの第5ノモスのハラウィの都コプトス(ゲブトゥ)であった。コプトスが第5ノモスの都に定められたのは、先王朝時代(BC3000年頃~BC 2650年頃)と思われる。ハラウィ自体は初期王朝時代第1王朝時代に遡る。都コプトスがハラウィの中心都市になったのは、おそらく先王朝時代からと思われる。
センウセレト1世は、BC1950年頃ヌビアのブーヘンに要塞を築き、第3急湍まで進出している。
息子のアメンエムハト2世(在位;BC 1929年頃~BC 1895年頃)は、その治世中、ナイル中部の湿地帯が広がるファイユーム地方が農耕・牧畜・漁業などの適地と知り、この地方へ水を送るための大規模な灌漑工事を行った。灌漑を効率化するために従来使用されていた運河がより広く深く掘削し、堤防を築くことでナイル川からの水の流入を防ぐ計画であった。
完成するのは、アメンエムハト3世(第12王朝の第6代ファラオ;在位,BC1853年頃~BC1806年頃)の時代であるが、現在でも豊富な水に恵まれた穀倉地帯として貢献する肥沃な農地が広がる。その水を分配していた水車が観光名所にもなっている。ファイユーム・オアシスを臨むファイユーム県の県都となり、近隣で取れた綿花や小麦などの集散地として、また、カイロからの交通の便もよいためナイル河谷(かこく)から鉄道も通じている。
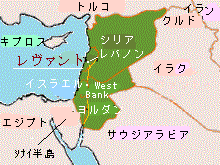 |
| レヴァントとは、東部地中海沿岸地方の歴史的な名称で、歴史学では、シリア・レバノン・ヨルダン・イスラエル(およびパレスチナ自治区)を含む。先史時代・古代・中世にかけて通常これらの地域を指す。 肥沃な三日月地帯の西半分にあたるレヴァントのシリアのテル・アブ・フレイラ遺跡では、BC11050年頃のライムギを生産する最古級の農耕跡が発見されている。 |
センウセレト2世(第12王朝の4代ファラオ)は、父王アメンエムハト2世の治世32年目に共同統治者として即位した。その治世中、アメンエムハト1世の代以降、政治権力を弱められていた各地の州侯とも友好関係を築き国政を安定させている。ファイユームの農地開発や建築事業など国内の統治に力を入れ平穏な時代が続いた。
中王国時代のファラオたちは、このファユームの地を好み、中王国時代に建設された小ぶりのピラミッドのいくつかは、ファユームのユーセフ運河に近い、景観の良い場所に築かれた。そのピラミッドは、古王国時代のギザの大ピラミッドとは比べるべくもないが…
ファユーム開発を促進したセンウセレト2世のピラミッドは、ファユーム盆地への入り口にあたるアル=ラフーンの砂漠に造られた。
ユーセフ運河の完成によってナイル川の水がファユームの盆地に導かれ、カルン湖は増水期、自由水面でナイル川と繋がり、その水位は盆地の標高18mとほぼ一致する。
ユーセフ運河によって従来は砂漠であったナイル沿いの土地に水が引かれ、ファユームの中央にあるカルン湖がナイルの水で満たされ、ファユームは肥沃な穀倉地帯となり、やがて中王国時代の拠点として繁栄を極める。
センウセレト2世のピラミッドはアル=ラフーンに造られた。イングランドのエジプト学者のフリンダーズ・ピートリーはその近くで、ピラミッド建設に携わった労働者の村ヘテプ・センウセレト(センウセレトは満足する)を発見している。そこは、現在のカフーンに在り、残されている遺物などからして、突然放棄された形跡がある。そのために、医療や会計など多くの生活パピルスが遺され、貴重な史料になっている。そのパピルス文書から、BC19世紀初頭には、既に労働者や職人たちの中にはエジプト人だけでなく、外国系の多くの民族が多数在住していたことが判明した。
1896年初頭、フリンダーズ・ピートリーらはルクソールの神殿群の一画を発掘した。その神殿複合施設はアメンホテプ3世の建てた神殿の北に位置している。元々その神殿はそこら中に散らばっている石に、アメンホテプ3世の名が刻まれていたため、アメンホテプ3世の建てたものとされていた。しかし、ピートリーは1人のファラオが隣接して2つも神殿を建てるとは思わなかった。発掘を開始して間もなく、ピートリーはその疑問の解答を探り当てた。メルエンプタハ本人の像や2つの素晴らしい石碑が見つかった。どちらもアメンホテプ3世の神殿で使われていた石像の裏面を使ったもので、元の像の顔が裏面にあった。この神殿はラムセス2世の息子メルエンプタハが、隣のアメンホテプ3世の神殿に使われていた石を使って建てたものだった。
アメンエムハト1世の国政の方針は、王の暗殺にもかかわらずセンウセルト1世以下の諸王によって受け継がれ、センウセレト2世の息子センウセレト3世(第12王朝の第5代ファラオ、在位;BC1878年頃~BC1840年頃)は、行政改革の断行により完全な中央集権化に成功する。対外交易も活発化し、ビュブロス・クレタ・プント・シナイ半島やワーディー・ハンマーマートにしばしば通商のための遠征隊を派遣し、王権の経済基盤を強化した。
第1中間期に比較的安定した時代を迎えるのは、第10王朝のケティ3世の治世である。ケティ3世が王太子メリカラーに与えた教訓であると伝えられる文書が現在し、『メリカラー王への教訓』と呼ばれている。かなりの部分が現存している。最もまとまって現存するのは第18王朝時代のものと見られる写本である。主要なテキストはサンクトペテルブルクのエルミタージュ美術館が保管している。かなりの欠損があるが、他所で発見されている断片もあり、ある程度復元されている。実際にケティ3世が表したものかどうかについては確実とはいえないが、第10王朝時代に作成された文書であると見られ評価は高い。その一節に
「貴族の子弟と素姓卑しき者とを分け隔てして はならない。能力によって、人々を取り立てるべきである」とある。中王国第12王朝期でも、新統一国家の行政機構を支える役人を庶民層からも人材を発掘する必要があった。 しかし、それでも人材の不足は否めなかった。中王国時代末期から第2中間期(BC1785年頃~BC1570年頃)にかけて、主に特殊技能者の獲得を目指して、かなり活発 な奴隷貿易が行われたようだ。第2中間期の異民族ヒクソスの王朝を滅亡させた新王国の時代に入ると、エジプトは積極的な対外進出策を推進する。征服は征服を生んで古 代エジプトの奴隷制は最盛期を迎えるのである。 ヘロドトスは、エジプトのファラオが、オリエントやヨーロッパから住民を連れ帰って、奴隷にしたと書いている。
古代エジプトファラオたちは、貴重な通商ルートを、掠奪型の遊牧民族の襲撃から守るために、ヌビアへ何度も出撃した。BC1850年頃、ヌビアやパレスチナに向けて軍事遠征を行う。遠征はいずれも成功を納め、新たな交易ルートが開拓された。センウセレト3世は、国境線を押し広げ歴代の王たちの誰よりも広大な領土を獲得した。遠征で得られた富の多くは国内の建築事業に充てられた。カルナックの北にあるメダムードにメンチュ神に捧げる大神殿を建立した。特に、ダハシュール(ファユーム・オアシスの北東、ナイル川西岸の砂漠にある王家のネクロポリス)に建造されたセンウセレト3世のピラミッドは底辺が107mという、第12王朝で最大規模のものとなった。
アメンエムハト3世は、父王センウセレト3世の時代に達成した中王国時代最盛期の王となった。第12王朝は、長年、湿地帯が広がるファイユーム地方の大規模な干拓を国家事業として引継いで来たが、アメンエムハト3世の時代に漸く完成した。ファイユーム地方の湖に流れ込むナイルの水をせき止める灌漑事業と運河の開削が主で、これにより農業生産は飛躍的に増大し、ナイル川までの水運が発達しエジプトの経済成長はピークに達した。
父王センウセレト3世が南のヌビアでの対外政策に力を注いだのに対して、アメンエムハト3世は主に北のシナイ半島で銅やマラカイトmalachite(孔雀石;銅の一次鉱床の周辺などに分布する銅化合物が濃集して形成された二次鉱物)、そしてシナイ半島南海岸のターコイズturquoise(トルコ石)の鉱山開発に向けられた。その結果、シナイ半島の50ヵ所以上の場所で治世中に記された碑文が発見されている。途切れなく遠征が繰り返されていたことが知られる。アメンエムハト3世の碑文は、シナイ半島のものを含め、その90パーセント以上が国外から見つかっており、反対にエジプト本国から出土しているものは非常に少ない。碑文には、当時の活発な対外遠征の模様が語られている。
アメンエムハト3世は、上エジプトのセムナSemnaに防衛拠点となる要塞をいくつも築きヌビア領土の完全な支配を確立した。セムナは、スーダンの北部州に属する同国最北の町ワディハルファの南方約 70km、ナイル川東岸にある。ナイル川もここで上流になると川幅が狭く急湍(第2急湍)となり、川底には花崗岩が露出し航行が不能となる。
アメンエムハト3世はヌビアへ進出し、この地の両岸に城塞を築いて南方防備の拠点とした。川に面した花崗岩の崖面には、第 12と13王朝時代の刻銘と増水の際の水位が刻まれている。エジプトとヌビアの国境ヌビアの地方神デドゥンは、中王国時代以前から崇拝され、やがて外国起源の神がエジプトの神となる唯一事例となった。第3王朝から第5王朝の間に編集されたと考えられ古王国時代に遡る聖典『ピラミッド・テキスト』では、地方神デドゥンに対して「ヌビアを支配するもの」、また、香料・香木が南方から輸入されることから「神々のために香を焚くもの」という形容辞が用いられる。
ユーセフ運河を完成させたアメンエムハト3世は、都をファユーム盆地に移そうと試みたようである。ユーセフ運河は、ファユームから直線距離にして 200kmほど上流のジャウティ(現;アシュート市)の辺りでナイルから分流している。地形に沿うように小さく曲がりながら 徐々にナイルから離れ、ラフンという村落の近くでファユームに入る谷を抜け、最後はカルン湖に流れ込む。その湖を見下ろす丘陵地のハワラにピラミッドを建設している。ハワラのピラミッドは、底辺部の1辺の長さ100m、高さ58m。外側を覆っていた石灰岩の化粧石は、ローマ時代には既に持ち去られている。現在は、日乾レンガ(泥レンガ)がうずたかく積まれた小山のような状態である。ダハシュールにあるアメンエムハト3世のもう一つの黒のピラミッドも、同様に、日乾レンガで出来ている。
内部は、盗掘を防ぐ、複雑な造りであったが、結局、破られ、金銀・財宝は盗まれてしまった。ピラミッド内部は、水が侵食していて、入ることが出来ない。考古学者フリンダーズ・ピートリーが、発掘に従事した。潜りながらで大変な発掘だった述懐している。玄室には王と王女の棺があった。
なお、ユーセフ運河は、中エジプト地方のナイル左岸では、流域の渓谷の幅が広がるにつれ、ナイルの川筋に概ね併走するように多数の水路が掘削されている。これらの水路は各地域に灌漑用水と生活用水を供給している。
ギリシアの歴史家ヘロドトスが記した『歴史』によれば、アメンエムハト3世のピラミッドの南側には、かつてギリシア人たちがラビリントスLabyrinthos(迷宮)に譬えた葬祭殿が建造されていたらしい。ラビリントスには24の中庭があり、部屋数は1500室にも及んだと言う。その半分は地下にあり、その部分はまだ発掘されていない。地上部分は地上の柱の一部を除き、殆ど遺存していない。
跡を継いだアメンエムハト4世によってしばらくの間は平和が保たれた。ただ、アメンエムハト3世と4世が親子関係にあったのかどうかははっきりしない。アメンエムハト4世が息子でなければ、アメンエムハト3世の娘セベクネフェルと結婚していたはずだが、それを証明する史料がない。
トリノ王名表では、アメンエムハト4世の治世は9年3ヶ月と4日続いたと記録されている。アメンエムハト4世が没すと、第12王朝の繁栄は急速に衰え、建造物も文字史料も極端に乏しくなる。その短い治世期間中は、大きな出来事もなく、比較的平和であった。
第12王朝の男系の王はここで終了する。いったん、アメンエムハト3世の娘セベクネフェルが即位する。しかしながら、セベクネフェルについて書かれた記録は殆どなく、統治の実態はよく分かっていない。その後、第13王朝は、アメンエムハト4世の息子たちによって引き継がれる。おそらく、セベクネフェル自身はアメンエムハト3世の娘であるから、アメンエムハト4世とは異母兄妹の可能性がある。
セベクネフェルの死をもって第12王朝は終焉をする。新たに第13王朝が創始された。 第13王朝は第12王朝からスムーズに継承された王朝と考えられている。実態が明らかでない多数の王が継承する政権であるが、そのほぼ全期間、国家は安定しており中央政府の権威は全土に及んでいた。
その理由として第12王朝時代に長年にわたって作り上げられ、12王朝の第5代ファラオ・センウセルト3世(BC1878年頃 ~BC1841年頃)によって完成されていた官僚機構が、第13王朝時代にも正常に機能していたからだ。中王国の官僚組織は極めて完成度が高かく、王権が弱体化しても事実上の統括者であった宰相を中心に国家を運営することが可能であった。実際、宰相をはじめ高位の高官は世襲され、職務の継承は安定していた。エジプトの統一はその後も維持されるが、前王朝が築いた繁栄は急速に失われ、文字史料も建造物も極端に少なくなる。
目次へ
第12王朝を継ぐ第13王朝の王達は明らかに同一の家系に属していないし、数多くの明瞭でない出自の王達がいる。第13王朝の歴代王と即位順は完全には復元されていない。主な史料として、王の数を60人とマネト(プトレマイオス朝に仕えたエジプト人の神官であればヒエログリフも解読できたとみられる。BC3世紀の古代エジプトの歴史家)は記し、少なくとも36人の王を上げているが、破損が著しい『トリノ王名表Turin King List』の記録であれば完全な復元には限界がある。
(『トリノ王名表』とは、古代エジプトの王(ファラオ)の名を記したパピルス文書で、古代エジプト第19王朝のラムセス2世の治世(BC13世紀)に制作されたと考えられている。イタリア共和国ピエモンテ州にある都市トリノのエジプト博物館で発見されたため『トリノ王名表』と呼ばれる。現在もトリノのエジプト博物館に保管されている)
第13王朝末期のセベクヘテプ4世の代に、下エジプトのクソイス(アヴァリス)出身とされる政権が、ナイル川デルタ地帯あるいはそのごく一部の狭い範囲を支配下において第13王朝の統制から離れ、エジプトの統一は失われていた。一般に第14王朝としてまとめられているアジア人の地方政権が自立してエジプトの統一は崩壊した。この第14王朝に関連する史料は極めて少ないため、果たして国家としての呈をなしていたかも分かっていなかった。そのため第13王朝がいつの時点で終わったのかも不明である。
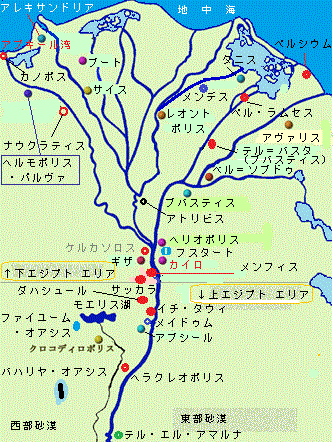 |
| クソイスは今日のサカと見られていたが、近年の発掘調査で第15王朝の首都であるアヴァリスにヒクソスよりも前の時代から大規模な宮殿が存在し、その同じ場所から非エジプト的な宗教様式を持った彫像が出土したこともあって、現在、第14王朝はアヴァリスを中心にした政権と見ている。 アヴァリスは後にヒクソス人王朝の首都となる町で、テル・エル・ダバア遺跡として遺る。第14王朝は第13王朝と併存した王朝で、第12王朝時代からナイル下流のデルタ地帯に住み着いていたカナン人を中心にした多民族集団が、下エジプト東部と接するパレスチナの領域をも支配していたようだ。 第14王朝のネヘシの治世下のBC1705年頃以降、デルタ地域に50年程度続く飢饉と疫病に見舞われた痕跡が遺っていた。これらの災厄が第13王朝にも打撃を与え、王権が弱体化し、多数の王が短期間で交代する第2中間期の政治情勢を混沌とさせる一因となり、ひいては第15王朝の急激な台頭を招いた。 |
マネトの記録によれば第14王朝には76人のクソイスの王がいたと記すが、トリノ王名表に記録されている王の中の何人かは第14王朝の王であると考えられている。それは、第13王朝の支配から脱し、独自の統治を行っていた小国の支配者たちである。そのうちの多くは都市単位の限られた統治権であった。軍事力は、装備も含めて極めて貧弱であった。
クソイスの王ついての史料は殆ど遺されていない。王とされている人々が果たして本当に同一の勢力か、同一の王族かを判断する史料が少なすぎる。そのため終焉の時期もはっきりしない。
第14王朝はデルタ東部の都市アヴァリス(現在のテル・エル=ダバア遺跡)を王都に成立したとされる。1970年代よりテル・エル=ダバア遺跡の発掘調査が始められた。この調査より、この地域にレヴァント系の居住区が登場したのは第12王朝末期からだった。第13王朝に入ると更にその地域は拡大し、中央政府はレヴァント系の人々を高官にも任用していた。
第15王朝のヒクソス時代になると、その直前から、既に居住域はより一層、拡大し続けていた。レヴァント系のコミュニティーが多数派を占める。 またこの頃から、それまで比較的規模的格差がなかったが、複数の部屋をもつ強固な造りの大型家屋が出現し、小さな家屋はその周囲に配置されている。つまり、第14王朝の高官たちを中核にして、レヴァント系の人々の中に社会的身分差が生じていた。その間に大きな政変があったようだ。
この第2中間期前期の異常な政治情勢が、下エジプトのデルタ地域東部に、さらなるアジア系民族ヒクソスHyksosが、エジプトの政治的混乱に乗じてBC1720頃、第14王朝の王都アヴァリスに第15王朝を樹立した。
BC1705年頃以降、デルタ地域が長期の飢饉と疫病に見舞われた痕跡が発見されている。これらの災厄は第13王朝に打撃を与え、王権が弱体化した。多数の王が短期間で交代するような安定しない第14王朝が、その時代に並立できた大きな要因であった。
メンフィスより南部の近郊にあった第13王朝の王都イチ・タウィが、第15王朝成立直後に征服された可能性は低いが、第13王朝の最後は、状況や時期も不明のままである。第14王朝の終わりの時期は、第14王朝と第15王朝の王都が同じアヴァリスだから、王朝の交代があったことになる。
1つ明らかであるのはこの時代には下エジプトで「アジア人」の勢力が増大していたことである。彼らアジア人は少なくても第1中間期以来、傭兵や奴隷、そして時には外敵としてエジプトに侵入して捕囚となり王宮や神殿の奴隷となっていた。彼らはエジプト人の歴史叙述では「侵入者」と見なされるが、実際には中王国時代にはアジア系の高官が輩出しており、その人的交流も相当活発であった。つまり、ヒクソスの第15王朝が成立するよりも前に、高い地位と権力を持つアジア系の人物が少なからず活躍していた。またヒクソスによって建設されたという記録の残るアヴァリス市は、既に第12王朝時代には存在していたことが確認されており、実際の起源はさらに遡る公算が高い。
第12王朝後期頃に南西に新しい居住区が形成された。この新しい居住区は旧来のエジプト居住区と異なり、住居の配置・構造が北シリアのそれと類似しており、シリア・パレスチナ地方の文化的影響を受けている。この住居跡に付随する墓地からはシリア・パレスチナ地方の武器が発見されており、この都市に多数のアジア系外国人の傭兵が居住していたことがわかった。第12王朝末期頃の墓地からは現物の2倍の大きさを持つ人間の石製坐像が発見されているが、その独特の髪型と黄色く塗装された皮膚の表現などから、この像はアジア系の高官を表現したものと見られている。
第13王朝時代の葬制に、より顕著なシリア・パレスチナの風習が見られる。この時代のアジア系の人物と思われる墓では、頭を北に顔を東に向けるという伝統的なエジプトの埋葬法とは異なり、死者の頭を南にして顔を東に向けるという埋葬法が取られている。また墓にはシリア・パレスチナ風にロバが副葬されている。加えて、メソポタミア地方と共通の習慣が見られた。
カナン地域を中心に各所で崇められた嵐と慈雨の神バアルが崇拝されていた痕跡も残されている。このバアル神はエジプト神話における戦争の神セトと関連付けられ、第14王朝時代にはセト神がアヴァリスの主神となった。このセト神はヒクソスが崇拝した神であり、何らかの関連があるのは確実であると思われる。この時代には恐らくアジア系と見られる王も登場しているようだ。
ヒクソス時代の遺跡が発見されている。その物質文化はレヴァントの文化とエジプトの文化の特徴が混合している。神殿の建築や土器、金属加工製品の形式などはシリア・パレスチナ地方のそれと類似しているが同一ではない。行われていたロバの犠牲などの儀式は、パレスチナ地方でも見られる。
 |
 |
 |
ヒクソスとクレタ文化圏の間に交流があったことが明らかとなった。特にアヴァリスで発見された壁画は、単なる模倣というよりはクレタ文化圏の人々がこの時期のエジプトに移住していたことを示していると見られている。
一方、クレタ島のクノッソス城塞遺跡では、第15王朝第3代の王キアンのカルトゥーシュを記したアラバスター製水差しの蓋が出土した。アラバスターは、大理石の一種で、大理石よりも軟らかく加工がし易いため、エジプトでは古来より広く彫像・香油瓶・壺など、幅広く美術や工芸品に使われた。命名は、エジプトの地名アラバストロンAlabastronにちなむとされる。歴代のエジプト王朝は、乳白色のアラバスターを原材に、独特の石製容器を生み出した。特に王家のためには水晶やラピスラズリなどの貴石も使われた。青銅器時代には、クレタ島のミノス文明がエジプトの石製容器を模作し、交易品としてエーゲ海一帯に広めた。アジア系民族ヒクソスがナイルデルタ地帯に第15王朝を樹立し、商業都市アヴァリスに宮殿を構え、逸早く東地中海沿岸やレヴァントとの交易の重要性に着目していた。また、中王国時代の赤色花崗岩製のスフィンクス像の肩に、キアン王のカルトゥーシュが落書きされていた。
第15王朝第4代のアペピ1世の治世は約40年と歴代で最も長く、その在位期間、テーベの第17王朝からの攻撃が執拗に続いた。しかしアペピ1世はアヴァリスを守りきった。その後継者アペピ2世が即位すると、あれほどの圧倒的な強さをみせた軍事力も色あせ、第17王朝からの攻撃にひたすら耐えるだけで王朝は疲弊しきった。第15王朝の終焉が、即ち新王国時代の到来を告げるものとなった。
ヒクソスは、エジプト第2中間期以降に、古代エジプトに移動してきた人々で、多くはシリア・パレスチナ地方をルーツとする雑多な民族集団であった。ヒクソスと言う呼称は「異国の支配者達」を意味する。古代エジプト語で、「ヘカウ・カスウト」とは、そのギリシア語に由来する。「ヘカウ・カスウト」は、元来は字義通り外国人の首長、特にアジア人のそれを指す言葉として使用されていた。これが、エジプトを支配する異民族の呼称となった。実際にエジプトを支配するようになった異民族達が「ヘカウ・カスウト」の語を一種の尊称として使用するようになっていた。
古代エジプト人の記録に加えて、戦車と長弓にして複合弓といった「新兵器」の使用や、上記のようなシリア・パレスチナ地方に起源を持つと考えられる習俗、人名などによって、ヒクソスとは強力な 軍事力でエジプトを征服した異民族政権であったという見解が多い。
トリノ王名表によれば6人のヒクソス王が108年間在位したと書かれている。マネトの記録には、第15王朝の王も6人とされており、通常「ヒクソス」「ヒクソス政権」などと表現した場合、第15王朝を指す。
ヒクソスの権力掌握の過程を語る史料は、マネトによる記録しかなく、ヒクソス関係の後代の史料は全て、外国人による侵略と解する偏見が強調され酷く歪曲されている。マネトが『エジプト史』で著述するヒクソスは、野蛮な侵略者と見なした。それが古代エジプトの伝統的な歴史認識であった。
マネトが、BC280年頃、カイロ北東郊外のヘルモポリスHermopolis(現在;アシュムーナイン)の古文書を用いて、ギリシア語で『エジプト史』3巻を著した。その「ヒクソス」の項目に、
「トゥティマイオスの代に、原因は不明であるが、疾風の神がわれわれを打ちのめした。そして、不意に東方から、正体不明の闖入者が威風堂々とわが国土に侵入して来た。彼らは、圧倒的な勢力を以て、それを簒奪し、国土の首長たちを征服し、町々を無残に焼き払い、神々の神殿を大地に倒壊した。また、同胞に対する扱いは、ことごとく残忍をきわめ、殺されたり、妻子を奴隷にされたりした。最後に彼等は、サリティスという名の王を1人、指名した。彼は、メンフィスに拠って上下エジプトに貢納を課し、最重要地点には守備隊を常駐させた」とある。
ヒクソス(BC1782年頃~BC1570年頃)は 古代エジプトに登場したシリア・パレスチナ地方に起源を持つ雑多な人々の集団である。馬と戦車と長弓を駆使する戦法で、エジプト第2中間期にナイルデルタ地帯にヒクソス政権を築いた。
特にエジプト第15王朝(BC1663年~BC1555年頃)はヒクソス政権と呼ばれたが、既にBC1680頃には、別のヒクソスのグループが下エジプトを占領し、第16王朝を開いている。
BC1650年頃、テーベの地方貴族がエジプト第2中間期に第17王朝を興し、ヒクソスと対抗する勢力となる。第17王朝ファラオ、セケネンラーSeqenenre 2世は、先代の王セナクトエンラー・イアフメスとその王妃テティシェリの息子だったと言われる。第18王朝の初代ファラオ、イアフメス1世の父は、第17王朝のセケンエンラー 2世、第17王朝最期のファラオ・カーメスは兄もしくは叔父である。
第19王朝時代に成立した『アポフィスとセケンエンラーの争い』という説話によれば、第15王朝のアペピ(アポフィス)王は「テーベの神殿で飼われているカバの鳴き声がうるさくて王の眠りを妨げるので殺すように」という殆ど言いがかりのような要請を送っている。エジプトではカバは悪の象徴でもあり、カバを狩るとはこの世の秩序を保つ王の神聖な義務とされていた。その使者をセケンエンラー(タア)は丁重に迎え入れ、アペピApepiに二心無きことを誓ったという。これが完全な史実とは考え難いが、テーベの統治者に過ぎないセケンエンラーは、即位した当初は先代の王たちの方針通り、第15王朝ヒクソスに臣従するしかなかった。
ヒクソスの王たちの中では珍しく、アペピ王の記録は少なからず残っている。トリノ王名表によれば、40年間エジプトを統治した。第15王朝アペピの時代は、主にデルタ地帯の東部からパレスチナまでの地域を直轄領として支配し、それ以外の地域では土着の支配者たちに、アペピ王に貢物や労働税を納めさせていたようだ。アペピ王の治世の間は、ヒクソスによるエジプトの支配体制が最も盤石だった時代であった。考古学的にも、エジプト人による第17王朝が治めていたテーベ周辺の地域でも、ヒクソスによる建築活動の痕跡があり、アペピの名を記した印章は遠くヌビアでも発見されている。
アペピの治世の半ば頃まで、テーベの王国との関係は概ね良好であった。やがて、平穏な時代が続いたことで第17王朝は徐々に力をつけ、アペピの治世の後半には第15王朝の支配を脅かすようになったと考えられる。セケンエンラーは、異民族支配の打破を大義名分として、ヒクソスの権威に反旗を翻し戦いを挑む。 デイル・エル・バラスに巨大な周壁に囲まれた宮殿を、近くの山腹には軍事基地を築いた。その遺跡が発掘されている。
さらに考古学的発見によってセケンエンラーが、実際に第15王朝に対して戦いを挑んだことが確実となった。15王朝と第17王朝の戦いは長く激しいものであったが、第15王朝は第17王朝に対して勝利を収め、セケンエンラー2世を敗死させた。第17王朝は、一時逼塞した。
ハトシェプスト女王の葬祭殿を見下ろすデイル・エル・バハリDeir el-Bahriでセケンエンラー王のミイラが発見されているが、彼のミイラは頭部右側面に3か所、眉間に1か所、左頬に1か所、合計5か所の戦傷を負っている。そのうち4か所は斧、残り1か所は槍によるものであった。死亡推定年齢は40歳前後、身長170cm。戦いの最中の戦死のため遺体の回収に手間取ったらしく、既に腐敗が始まっていた。戦場で急いで防腐処理が施されたせいか、ミイラの保存状態が相当悪く、姿勢も真っ直ぐに矯正されていない。極めて無残なミイラであった。
1881年の夏、ドイツ人考古学者エミール・ブルクシュÉmile Brugschは、エジプト人初の考古学者アハマド・パシャ・カルマを連れて、デイル・エル・バハリ南西の岩壁「ロイヤル・カシェ」に向かった。
デイル・エル・バハリは、ルクソールの対岸、ナイル川西岸に位置する。葬祭殿と墓の複合体がある。意味は『北の修道院The Northern Monastery』、かつてコプト正教会の教会として使われていたためである。
最初に、第11王朝のメントゥホテプ2世葬祭殿がBC15世紀に建設された。その後、第18王朝の間に、アメンホテプ1世とハトシェプスト女王の葬祭殿が築かれた。
トトメス3世(ハトシェプスは継母)の葬祭殿は 、後の第20王朝時代の地すべりで深刻な被害を受けた後、そのまま放置されたため、この複合体については詳らかでない。1961年に発掘された。
トトメス3世の神殿の南にある崖の隠れた凹みの墓には、王家の谷から運ばれてきた40体もの王室のミイラの隠し場所「ロイヤル・カシェ」がある。更なる冒涜や略奪を防ぐために、ミイラは第21王朝の僧侶によってここに安置された。
ブルクシュが墓に赴いた時のことを、ガストン・マスペロは次のように記した。
『岩壁の斜面に深さ12m、幅2mの穴が掘られていた。穴の底には西側に入口があって、その先は幅1.4m、高さ80cmの通路につながっている。
本来は木の扉があったが、いまはもう存在しない・・・7.5m進んだところで、通廊は突然、北に曲がり、さらに60mほど続く・通廊の幅はたえず変わる。
2mの場所もあれば、1.3mしかないところもある。
半分ぐらい進んだ所に荒削りの階段が4段あり、明らかに深くなっているのがわかる。
右側には、深さ3mくらいの未完成なニッチのようなものがあり、トンネルのさらなる方向転換が考えられてたことを示している。
突きあたりは、長さ8mほどの変形した長方形のような部屋があった。
中には木棺、ミイラ、副葬品が所狭しと置かれている。
ネシコンスという名前が記された白と黄色の棺が入口から60cmも離れていない所に置かれ、通廊からの出入りを塞いでいる。その少し奥には、第17王朝時代に典型的な大型の棺がある。セケンエンラー・タア2世 (セケンエンラー)のものだ。さらにヘヌウトタウイ王妃とセティ1世の棺もあった』
セケンエンラーのミイラは、場所は移動されたが自分の元の棺に入っていた。
王の戦死という事態を受けて第17王朝は第15王朝とクサエを境界とする協定を結んで一時講和した。しかしセケンエンラーの跡をついで第17王朝の最後のファラオ王となった息子のカーメス(BC1573年頃 ~BC1570年頃)は再戦を強く望んだ。彼と大臣達との間で行われた会議の様子を記した同時代の文書によれば、カーメスは大臣達を前に熱弁を奮って戦いの必要性を説いた。
「アヴァリスに1首長が居る、クシュにも他の首長が居る。余はアジア人とヌビア人の同盟と、このエジプトに割拠せるすべての輩の渦中にある。
(中略)人々は、アジア人の奴役(どえき)のために疲弊し、安らぐこともできない。余は彼と戦い、彼の腹を引き裂いてみせる。それが、エジプト人の救済とアジア人の殲滅となり、余の願いに叶う」
これに対し大臣達は穏健な共存の利を献策したが、カーメス王の不興を買った。カーメスは対ヒクソスの軍事行動を再開した。初戦で第15王朝側の有力諸侯であったヘルモポリス(現;アシュムーナイン)侯テティを破り、勢いに乗じて西部砂漠のバハリヤ・オアシスも占領した。そこで第15王朝がヌビアのクシュ侯へ送った使者を捕らえ、南北から挟撃される事態を防いだ。
その後もカーメスは直属の水軍を率いてナイルを北上し、各地の軍団を合流させつつ第15王朝の領域に快進撃を続けた。ヒクソス領の奥深くまで侵攻し、一時は第15王朝のアヴァリスを包囲するが、攻めきれず略奪した後撤兵した。
 |
| カルナック神殿はエジプトの南部、ルクソールにある神殿。BC1565頃、イアフメス王がエジプトからヒクソスを追放し、テーベに新王国時代第18王朝を樹立した。ルクソールは、テーベと呼ばれ、「百門の都」と称えられた。カルナック神殿はルクソール市内のナイル川東岸に位置しており、歴代のファラオが篤い信仰を寄せて寄進を続け、この結果増改築が重ねられて規模が拡張され、巨大な古代宗教の複合施設となった。東西540m、南北600mの周壁に囲まれた壮大な神域を持ち、世界最大の神殿と言われている。 |
BC1565年頃、イアフメス王がエジプトからヒクソスを追放した。ヒクソスと協力関係にあった南のヌビア(クシュ王国)も制圧し(ヌビア総督府が置かれ、総督は「クシュの王子」と呼ばれた)、悲願であったエジプトの再統一を果たす。
カムディKhamudiは、第15王朝の第5代ファラオ、トリノ王名表に記載されており、ヒクソス王朝最後の王である。パレスチナのエリコからスカラベ印章が見つかっている他、ビブロス(レバノンの首都ベイルートの北方約30kmにある地中海沿岸の都市、古代フェニキア人の都市として栄えた)からも彼のものと思われる印章が出土している。カムディの治世の半ば頃に、カーメスの後を継いだイアフメス1世が解放戦争を再開し、その攻勢に押されたヒクソスの勢力は急速に弱体化した。BC1565年頃、首都のアヴァリスが陥落し、第15王朝はエジプトから放逐された。
カムディは、パレスチナに逃れたが、ヒクソスの支配地域はシャルヘンを中心にネゲヴ砂漠地方に僅かに残るのみになっていた。そのシャルヘンも陥落したとされる。カムディがこの時に殺されたのか、あるいは既に死去していたのかは不明だが、シャルヘンの陥落をもって第15王朝は滅亡し、ヒクソスの支配は終焉を迎えた。
悲願であった古代エジプトが再統一され、テーベが首都になった。カルナックの神殿は大小様々神殿や祠などが集まった巨大な複合体である。その中心的な存在がアメン大神殿である。カルナック神殿やアメン大神殿における主な建設工事は、第18王朝(BC1565年頃~BC 1310年頃)のうちに行われた。
エジプトの権威の復興を図り、アテン神殿を破壊した、第18王朝のホルエムヘブが建てた第2塔門を入ると、第19王朝セティ1世が建てた大列柱室がる。名前の通りの巨大で太い134本の石柱が林立している。レリーフがくっきりと残っているほか、わずかに塗料痕があり、かつてはレリーフを含めて華やかに彩られていたことが伺われる。以後増築を重ねて極めて複雑な構成になっている。
(ヨルダン川西岸地区は、ヨルダンとイスラエルの間にあり、パレスチナ自治区の一部を形成するヨルダン川より西部の地域を言う。欧米などでは単にウェストバンクWest Bankと呼ぶことが多い)
目次へ
