
| Top 車山高原 車山の山菜 車山日記 車山ブログ 車山高原の野鳥 車山の紅葉 車山のすすき | |
| ☆早春のスミレ ☆車山高原の笹 ☆車山高原のシジュウカラ ☆諏訪の植生 ☆諏訪に生息する哺乳類 ☆諏訪の狐 ☆車山高原の狐 |

|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イングランドの自然科学アイザック・ニュートン (1643-1727年、ニュートン力学の確立や微積分法の発見)の万有引力の法則は、全ての物体はその質量と距離に応じて互いに引き合う力「引力」を持っているという法則から、地球上の物体にも地球の引力が働くことを示した。万有引力はニュートンによる「重力」の解釈でもあった。
その引力の大きさは質量に比例し、距離の2乗に反比例する。
質量Mの物体と質量mの物体が、離れる距離rであれば、2つの物体の間に働く力の大きさFg(F1とF2)の計算式は
Fg=F1=F2= Gm1m2/r2
(ただ、万有引力定数(重力定数)Gの測定は、重力が極めて微弱な力であるため精緻な測定が極めて困難となり、未だ定まってはいない。近年の実験では1つの値に集約されるどころか逆に分散し、ひとたび公式に決定された値であっても、その不確かさがしばしば指摘されている。
必要な検出器で感度を測定する際には、低周波側が地球の地面振動により、中周波数が、鏡の熱振動により、そして高周波側が、レーザー光線による安定したものを変化させる「光の量子性」が影響する。これらの障害が低減されれば、より高感な精度が期待できる。
重力理論と量子力学を統合する「量子重力」の分野でなら見つかる可能性が高いと期待されている。
Gは2018年の科学技術データ委員会の推奨値は
G=6.67430(15)×10-11m3kg-1s-2 ☆ 最後の括弧内の数値は、その桁を単位とした数値が「標準不確かさ」を示す。)
アインシュタインの特殊相対性理論によれば、速さの上限は、真空中における光速の値は 299,792,458 m/s(約30万km/s)と定義されている。
ニュートンは、「万有引力は、どんなに距離がはなれていても一瞬で伝わる」と考えていた。光速を超えられるのだろうか?
光は電磁波である。電波や赤外線、可視光、紫外線、X線、ガンマ線など、そのすべてが波長だけが異なる光の粒子である。
イギリス・スコットランドの理論物理学者ジェームズ・マクスウェル(1831年- 1879年)は、電気と磁気の理論「電磁気学」の創始者である。1864年、電磁気学の方程式(マクスウェル方程式)から電磁波の存在を予言した論文を、王立協会から発表した。電磁波の速さが秒速約30万kmであることを導き出し、可視光が電磁波の一種であるとした。つまり、電磁波は物質の振動ではなく、真空中でも伝わって行ける「電場(電界)」と「磁場(磁界)」が連動して振動しながら空間を伝播していく波の作用である、と解析した。「マクスウェル方程式」は、光の屈折や反射などを含めた光のあらゆる物理現象を記述する基礎方程式となった。この式があったからこそ、アインシュタインの相対性理論も生まれたとまで言われている。
波長λ×振動数ν=光速c
波長と振動数の積は常に一定なので、波長と振動数はお互いに反比例する。波長が短い、つまり振動数が高い方が、エネルギーも高い。
波長が短かいほど、電磁波のエネルギーは高く、周波数(1秒間に繰り返されるこの波の数)も増えていく。
また、電磁波は波と粒子の性質を合わせ持ち、電磁波の量子は光子と呼ばれる。
「電場」とは、電荷を持った電子などの素粒子やイオン化した原子(原子が電子を失う、または得ることにより電荷を持ったものをイオンといい、このうち炭素より重い元素のイオンを重イオンと呼ぶ。)などの荷電粒子(電気量とともに質量をもつ粒子)を置くと、正と負の電荷が引き合ったり、反対に正と正、負と負が反発しあったりするクーロン力が発生する領域を言う。また磁場中でこういった粒子が運動することで進行方向とは直角方向に生じる力を受けたりする。
「磁場」とは、磁石のもつ磁極に対して力を及ぼすような領域を言う。動いている荷電粒子は、磁場からも力を受け振動する。荷電粒子が振動すれば電磁波が発生する。
また電子レンジは「マグネトロン」と呼ばれる電子管から周波数2.45ギガヘルツの電磁波(波長が短いのでマイクロ波と喚ぶ。ただし、振動数が高いためエネルギーも高い)が放出される。このマイクロ波と食材が含む水の分子によって、電子レンジによる調理が可能になる。高い周波数の電磁波の波は、急激な振動となるため、水分子はその振動の急激な動きに合わせられなくなり、その結果、水分子の極性を揃える動きに少し遅れる傾向が現れる。この遅れが、水の分子などを振動させ、摩擦熱を生じさせる。この摩擦熱が食品全体に広がり加熱される。つまり、電磁波の波の動き(エネルギー)に対して抵抗力が生じ、電磁波のエネルギーが水中で熱に変わり、食材が加熱される。
(電気陰性度の高い方の酸素原子は、水素の電子を引き付けるため、酸素の周りの領域は、2つの水素原子の領域よりも負電荷を帯びる。これにより、両方の水素原子の負電荷の電子が、酸素原子の同じ側に引き付けられるため、水素原子の領域は両方とも正電荷を帯びる。これにより、共有結合する水分子は各水素側の正電荷と酸素側の負電荷により極性を持つことになる。ただし、水分子としては10個の陽子と10個の電子で形成されるので正味の電荷は0である。)
目次へ.

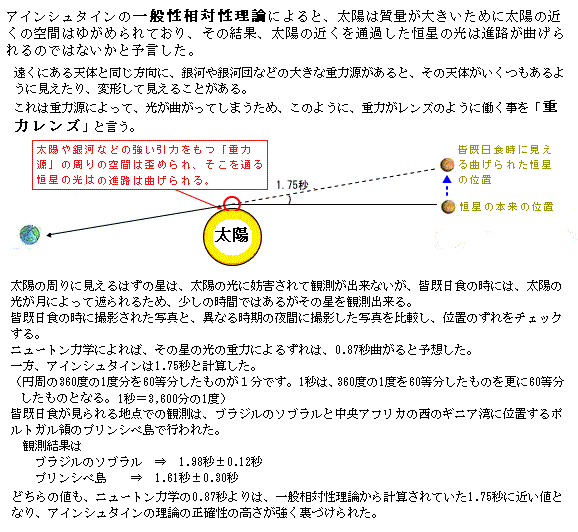 例えば、走りながら、あるいは新幹線や飛行機、ロケットなどに乗っていれば、懐中電灯の明かりを前方へ向ければ、その瞬間に光速を簡単に越えられるはず。しかしなぜか光速を超えられない。
例えば、走りながら、あるいは新幹線や飛行機、ロケットなどに乗っていれば、懐中電灯の明かりを前方へ向ければ、その瞬間に光速を簡単に越えられるはず。しかしなぜか光速を超えられない。それが相対性理論の基本原理「光速度不変の原理」であるが、実際は「真空中の光」に通用する原理で、地球上では、通常、諸々の物質を通過するたびに光の速度は減速している。しかし超えることはできない。
例えば、欧州原子核研究機構CERNにある大型ハドロン衝突型加速器LHCという装置では、陽子を光速の99.9999991%まで加速させている。陽子をそこまで加速させられるなら、もう少しエネルギーを加えれば光速を超えられはずが、実際には粒子が光速に近づけば近づくほど、加速に必要なエネルギーが大きくなっていき、光速は超えられないどころか、光速に達する速度を得るために無限大のエネルギーが必要になったため挫折した。相対性理論の妥当性は、実際の実験でも明らかになっている。
ただ物質の中を通過する際には、その物質の性質により速度が変わる。屈折率の大きい物質ほど、光の通過する速度が遅くなる。例えば、空気中や水中では、それらを構成する原子や分子が光の進みを邪魔するため、空気中の光の速度は、真空中の約99.97%と僅かに減速するが、水中になると秒速は約23万kmとかなり減じる。ダイヤモンドでは秒速は約12万kmと著しく減速する。
目次へ.

アインシュタインの一般相対性理論によれば、質量をもった物体が存在するだけで、周りの時空にゆがみが生じる。さらにその物体が運動をすると、周りの歪んだ時空が波のように宇宙空間に広がってゆく。これが重力波だと言う。この時空のゆがみが光速で伝わって行く。重力波はすべてを貫通し、減衰しないと考えられている。
「重力波」の発生源は宇宙の星としか考えられないと言われている。その代表的なものが、「中性子星同士の連星とその合体」や「超新星爆発」で、中性子星は、大質量星が進化の最終段階で、重力収縮が極限に達し超新星爆発を起こした際に作られる、超高密度な中性子からなる天体で、二つの中性子星から成る連星が形成されるためには、連星を作る二つの大質量星それぞれが超新星爆発を起こす必要がある。
その組になった連星は重力波を放つことで合体する。合体の際には中性子星の一部が吹き飛ばされて、金やプラチナなどの重元素になる。 超新星爆発は、星が一生を終えて爆発し、その質量の大部分を宇宙空間に一瞬にして解き放つ非常に劇的な現象である。
太陽のおよそ10倍以上の質量を持つ恒星は、その進化の最終段階に中心部に鉄のコアを生成する。この鉄コアが重力的に不安定になり崩壊を開始することが引き金となって生じる大爆発後には、中性子星もしくは「ブラックホール」が残される。重力崩壊を如何に爆発に転じさせるのか、その爆発のメカニズムは未だ完全には明らかになっていない。
一般相対性理論は、時空の歪みが極限にまで大きくなると、光さえも飲み込まれ二度と抜け出せない「ブラックホール」と言う特異な領域がつくられるとした。その表面では時間の流れも止まる不思議な能力に満ちた天体であったため、アインシュタインも「ブラックホール」は理論上の産物であって、さすがに実在しないと考えていたようだ。
アメリカの物理学者ジョン・ホイーラー(1911年- 2008年)は、量子論の創始者ニールス・ボーアの直弟子で、アインシュタインの友人でもあった。1960年代には、中性子星と重力崩壊の理論的分析を行ない、相対論的天体物理学の先駆者となった。1967年「ブラックホール」を命名した。
「はくちょう座 X-1」は、1964年に発見された地球に最も近いブラックホールの一つX線天体である。そのX線観測により、「ブラックホール」の存在が確実視された。
「中性子星」は宇宙に存在する最も高密度な天体であり、太陽質量の約10倍以上の大質量星の進化の最終段階で起こる超新星爆発により生まれると考えられている。
太陽ほどの質量を持ちながら、その半径が10km程度しかない天体であり、その主成分は中性子で、他には、5%程度の陽子やそれ以外のハドロンが混合していると考えられている。その中心部は1cm3あたり1兆kg(原子核密度の5~7倍)にも達する超高密度状態となっている。
中性子星の表面は原子核や電子からなり、内部に進むにつれて原子核が融けて中性子を主とする一様な高密度物質になると考えられているが、詳しい内部構造についてはよく分かっていない。一方で、昨今の重力波観測により、中性子星連星同士の合体の際には金やプラチナなどの重元素が合成されることが分かってきた。
「重力波」は「波動現象」であるが、「電磁波」の仲間とは大きく異なる特徴を持つ。その名が示すとおり、重力波は「重力」の発生起源である「質量」が運動することで発生する。アインシュタインが導き出した一般相対性理論から予測される物理現象である。重さを持つ物は、その重力で周りの時空を「歪(ゆが)めて」行く。その物体が運動をすると、周りの歪んだ時空が波のように宇宙空間に広がって行き、これを重力波と呼ぶ。
重力波が到来すると、自由落下している二つの物体の間の距離が伸び縮みする。しかも重力波による物体間距離の変化は、直交する二つの方向で、片方が伸びれば、もう片方が縮む、片方が縮めば、もう片方は伸びるという変化を繰り返す。その伸び縮みの量は、測っている長さが長いほど大きくなる。その伸び縮みの伸縮量は、物体間距離が離れているほどより大きくなる。
中性子星の合体などの天体現象が、通常は、地球が含まれる銀河系とは遠い銀河で発生する。その重力波の発生源までの距離は、地球から太陽までの距離の4000億倍あり、そこで発生した重力波による歪みの大きさは地球・太陽間程度の距離を、たかだか水素原子1個分動かす程度にすぎないほど小さ。
天体現象から発生する重力波は、全てのものを貫通してしまうため、なにかにぶつけてその反応をみるという方法がとれない。しかし光は重力波によって歪んだ空間に沿って走る性質があり、また直交方向で伸縮するという性質を利用して、現在の重力波検出器は、重力波の周波数 100Hzあたりの領域で歪の大きさが10-22~10-23という非常に小さなものまで検出できるように設計されている。
地球上の物体に働く引力には、地球の自転による遠心力が働く。その地球が左回転するため回転軸と直角方向の逆方向に遠心力が働くため、地球の引力と遠心力の、合力が重力の正体であるから、重力の測定値は時間や場所によって異なる。また、赤道は中心からの距離が一番大きいので引力は一番小さくなる。
遠心力fは、円運動している物体の質量m、円の半径r、運動の角速度ω(ラジアン・s-1)とすると、f=mrω2となる。地球の自転の角速度ωは、地球の自転=24時間(60×60×24秒)で2πラジアン(360°)なので、2πrad÷(60×60×24)s=7.3×10-5rad・s-1と一定である。つまり、地球の自転による遠心力は、自転軸からの距離に比例することになる。
しかも、地球を微小質量の集合体と考えると、重力は個々の微小質量がもたらす万有引力の総和と言えるが、ただその鉛直下にある微小質量が呼び込む万有引力のみが重力に寄与している
また、地球形状は自転軸方向でわずかに扁平であるため、地球重心から地表面までの距離は両極地で近く、赤道で遠くなっている。この影響で、万有引力は両極地で大きく、赤道で小さくなる。加えて、地球の遠心力は、自転軸から遠いほど大きくなる。すなわち、遠心力は両極地ではゼロとなりが、赤道では最大となる。自転軸からの距離が遠い低緯度ほど遠心力が大きくなるため、赤道上の重力は北極や南極よりも小さい。また、測定地の地下の密度構造の違いや、さらに、同じ場所であっても、動き続ける月や太陽の引力や地殻変動などにより時間的にも変化が生じる。それでも、区分けされた観測地ごとに重力測定は積み重ねられている。
重力の万有引力項g ≌ GM / R2 (G は万有引力定数、M は地球質量、R は地球の平均的な半径)
重力gravityは重力加速度gravitational accelerationに比例して変化する。地球上を1とした場合、月では6分の1、太陽では28倍の重力がかかり、「重さ」はその場所ごとに変化する。沖縄で1kgの金が、北海道に持っていくだけで約1g重くなるので、売るなら北海道の方が得である。
「重力加速度」は、物体が落下したとき、その物体の速度が単位時間当たりにどれだけ速くなるかを示した量である。地球の重力によって物体が自然落下する時の加速度であり、記号はGで表される。
質量が違うものでは、落ち方に違いはある。リンゴと鳥の羽根を、まずは空気中で落とす。リンゴはすぐに落ちるが、空気抵抗を受けやすい羽根はゆっくり落ちる。
これらを、真空ポンプで容器の中の空気を抜いて落としてみる。結果は、リンゴと羽根がほぼ同時に落下する。質量が違っても、落ちる速さは変わらない。木製の質量が違い形も違う3つの球形を真空中で同時に落としてみると、3つとも、ほぼ同時に落下する。
これらの自由落下の運動をグラフにすると、グラフは直線となり、等加速度直線運動になっている。速度増加が一定であることがわかる。
この自由落下のときの加速度を「重力加速度(gravitational acceleration)」と呼び、記号「g」を使って表す。
国土地理院による推定g値(自由落下方式による絶対重力計などを用いて測定の公称精度。単位は「m/s2」なので、加速度は「1秒あたりに速度がどれだけ変化するか」を表す量とも言える。)は、岐阜県庁付近で 9.7975 m/s2が計測された値である。このg値は、地球上の場所(北緯東経)と高さ(標高)によって変わるが、愛知県の場合でも 9.7970 で、小数点以下 4 桁目が場所によって変わるだけである。
地球の重力加速度は、平均すれば9.8 Gとなる。高校の物理では、地球の重力加速度をg=9.8m/s2(=980Gal)の定数として扱うことが多い。
重力(N)=質量(kg)×9.8(m/s2) (「重さ」とは、「重力」、この力を表す単位がN【ニュートン】。)
「質量」は物体そのものの量であれば、「場所」によって変化しない。「重さ」の方は、「その物体に働く重力の大きさ」ということになる。
実は、日常「1kgの重さ」とは、質量1kgの物体に作用する力(通常、9.8N)のことを示す。そのため無重力では重さが0となる。
地球上でも、赤道に近くなるほど、高度が高くなるほど重力加速度が小さくなる。例えば、札幌の重力加速度は9.805m/s2、沖縄の那覇の重力加速度は9.791m/s2の重力加速度になる。そのため沖縄は札幌の 99.86%の重力加速度となり、札幌で1kgの金塊は沖縄では998.6gで1.4gの差となる。
目次へ

ブラックホールの存在は、アインシュタインの一般相対性理論によって予知されていた。
地球の上空に、ボールを上に投げ上げても、そのボールの速さが、重力を振り切っるほどの速さでなければ、ボールは落ちてくる。重力を振り切る速さを脱出速度と言う。地球の脱出速度は秒速11kmである。
人工衛星を地球の衛星軌道にのせるために必要な速さは約7.9km/s、これを「宇宙第1速度」と呼ぶ。ただし、地球の自転を利用すると、この速さ以下でも軌道にのせることができる。自転を最大限に利用できるのは、重力が最小で、遠心力が最代に働く赤道上での打ち上げである。ここでは約0.5km/sの速さを減じることができる。赤道近傍で、しかも自転の慣性系を利用して、西から東へ回る静止軌道に乗せるため東へ向けて約7.4km/sの速さ以上で打ち上げれば地球の軌道に乗れる。
真西に打ち上げれば、人工衛星の質量は、真東に打ち上げる時のほぼ2分の1の物しか打ち上げられなくなる。それほど地球の自転速度は、打ち上げる人工衛星に影響を及ぼしている。
ただ、人工衛星が必ずしも東側に向けて打ち上げられているわけではなく、地球観測地図作成や地球観測衛星、偵察衛星、気象衛星などは、全地球を効果的に観測するために投入される軌道は、地球の北極と南極上空を通る、ほぼ縦に回る極軌道に投入される。この場合は、極地に向けてロケットを打ち上げるが、地球上の広範囲の地点を、常に上空から次々と観測できる大きな利点がある。
地球の衛星軌道にのせるのではなく地球からはるか遠くに離れるに必要な速さは約11.2km/sである。これを「宇宙第2速度」と呼ぶ。これも自転を利用するなら約10.7km/sで足りる。
ただし、宇宙第1速度や宇宙第2速度は、地球の引力だけを考慮した物理で、太陽の引力も考慮すると宇宙第2速度では太陽系外へ脱出することはできない。
ところが、脱出速度が光の速さより大きな天体がある。膨大な質量が極狭い領域に圧縮されたブラックホールと呼ばれる膨大な質量を持つ天体の周囲は、アインシュタインの一般相対性理論によると、時空は巨大な物質によって歪められ、その歪んだ軌道に沿って他の物体が流れていく。それが重力であるとアインシュタインは述べている。その近くを通ると、空間は物理の理論を超えた極大の歪みに飲み込まれ、その近くを通る光すら時空の歪みの影響を受けて曲げられ円を描きながら吸い込まれていく。そのため光による観測ができず、宇宙に空いた黒い穴のように見えることから、ブラックホールと呼ばれた。ブラックホールに飲み込まれ光は、その反対側から出てくることもなく、再び脱出することもない。光を吸収したブラックホールは、そのエネルギーを獲得しただけ質量が増える。ブラックホールの発見は、アインシュタインの一般相対性理論によって既に予言されていた。
光さえも出ては来られないブラックホールでも、間接的に観測することはできる。ブラックホールの強い重力に引き寄せられたガスなどの物質は、吸い込まれかけつつもブラックホールの周囲を高速で周回する「降着円盤(重力をおよぼす天体のまわりに形成された回転ガス円盤、ガスの主成分は電離した水素ガスすなわち水素プラズマで、ヘリウムの他、重元素も若干含まれている)」を形成する。その円盤の中心にはブラックホールが存在する。実際には幅の広い輪のような構造をしていると考えられている。この降着円盤が高温になって波長の短いX線や波長の長い0.1~1mmほどの「サブミリ波」などの電磁波を放つ。その様子を詳しく観測することで、ブラックホールの性質を調べることができる。
(1万度以上の高温になると、原子の中の原子核と電子が離れて勝手に動くようになる。この状態を「プラズマ」と言う。この高温で核融合反応をさせるときの燃料は重水素や三重水素など軽い原子核同士の融合で、より重い原子核に変える。その際に膨大なエネルギーが生じる。
太陽も核融合で燃えている。水素が核融合反応を起こしてヘリウム(He)となり、膨大なエネルギーの熱や光を放出する。太陽は地球の約33万倍もの質量を持つ巨大なガスの塊、核融合反応で水素を消尽するまでに50億年はかかる。)
ブラックホールはすべての物質を吸い込んでしまうだけでなく、物質の一部を巨大で最も強力な電波源の「ジェット(噴出物)」として放出している。これまでの技術では、十分に高い解像度が得られなかったことに加え、十分に高い周波数が観測できなかった」が、今では、超巨大ブラックホールから放出される、非常に巨大な電波ジェットが生まれ様子が、非常に鮮明な解像に解析されるようになった。
ジェットは電磁波を放つので、観測が可能になった。それにより膨大なエネルギーが放出されていることがわかった。
ハーバード&スミソニアン天体物理学センターの研究者マチェク・ヴィエルグスMaciek Wielgusは、「これまでの技術では、必要なレベルの解像度が得られなかったことと、余りに高い周波数は観測できなかった」と述べながら、ヴィエルグスはブラックホールから放出されたジェット(噴出物)が、そのブラックホールの非常に強い重力から逃れたものの、ブラックホールの中に閉じ込められることなく、数百万光年もの超大な帯となって放出されたまま、そこに留まる現象として観測された、と発表した。その画像から、ジェットの中心から遠くなった部分がなぜか明るくなっていることが解析された。つまり、ブラックホールの上に光が洩れたとしても、その光はブラックホールの重力で引き戻され、この天体から放出されることなく留まる現象として理解された。こういう天体がブラックホールであった。
この他にも、ブラックホールの性質を調べたり一般相対性理論の時空の歪みを検証したりするために、ブラックホールのすぐ近くを周回する恒星の動きが観測されている。
ブラックホールを相対性理論で説明すると、それは空間の歪みととらえる。例えば、広く張られた薄いゴムのシートの上に物質、たとえばビー玉を置いてみる。すると、ビー玉をおいたところが少しへこみ、そのへこみはビー玉のまわりに広がっている。これが空間の歪みである。ブラックホールであれば、強い重力で空間が歪み、まるで空間に穴があいているように見えるはずだ。穴の近くにさしかかつた天体は、その強い重力にとらえられて、この穴に落ちていく。光でさえも逃げ出すことができないほど強い重力でえぐられた穴、それがアインシュタインの相対性理論で言うブラックホールであった。
天体の表面での重力の大きさは、その天体の質量に比例しており、天体の質量が大きいほど大きくなる。また同時に、天体の大きさの二乗に反比例している。つまり、天体の質量が変わらなければ、小さければ小さいほど重力は大きくなる。そうすると、ある天体をぎゅっと押し縮めて、小さくすると、その表面の重力が極大化し、脱出速度が光の速さを上回ると、ブラックホールができる。太陽を押し縮めて、直径6kmの球にしたとすれば、太陽がブラックホールになる。
それは、太陽の数億倍に輝く超新星爆発は、太陽の8倍以上の質量を持つ重い天体で起きる。その天体の一生の最後に起きる大爆発である。中でも非常に重い天体の場合には、その芯の部分が爆発の反動で押し縮められ、非常に小さくまた高い密度の天体として残る。その強い磁場を持ち回転する中性子星をパルサーと呼ぶ。その残った芯の質量が大きければ、重力が強すぎてどんどん小さく縮んでいき、ついにはブラックホールとなる。
ブラックホールからは、光がでてこないので直接見ることはできない。しかし、ブラックホールに物質が落ち込むと、位置エネルギーが解放されて物質が光るのが見える。
ブラックホールのすぐそばにもう一つの星があり、お互いに回りあっている場合、すなわち、ブラックホールが連星同士にあるときは、相手の星から放出されたガスがブラックホールに落ち込む時、強いX線やγ線を出すので、これを観測することができる。また実際このようにして、連星の中にブラックホールが発見されている。
また、銀河の中心領域の非常に小さいところに、太陽の何百万倍もの質量が集中している天体がある。やがて近くの恒星のガスを剥ぎ取り飲みこむときがある。それらのガスは、ブラックホールの周りを高速で回転し、円盤を形成する。これが「降着円盤」で、その渦中のガス同士の摩擦熱により高温となり光輝く。かつてはその雲状のプラズマplasmaに覆われているため、多くの電磁波が遮られてブラックホールの近くは観測できなかった。今では、ここからの強いX線や電磁波を観測する技術の進化により、質量の大きなブラックホールが捉えられている。
(気体の温度が高温になると気体の分子は解離して原子になり、さらに太陽のように極めて高い温度になると、原子が電子と陽イオン【原子核など】に電離して飛び交う状態になる。この電離現象によって生じた荷電粒子を含む気体を「プラズマ」と呼ぶ。)
目次へ

一般相対性理論によって、空間は変化し続けるものであって、質量のある物は、その重力で周りの時空を歪(ゆが)め、その物体が運動をすると、周りの歪んだ時空が波のように宇宙空間に広がって行く。これが、アインシュタインが導き出した時空の一般相対性理論から予測される物理現象「重力波」である。
人類は、太古より可視光に頼り自然を観察して来た。しかし19世紀に入って電波やX線が発見されると、遠くに一瞬で情報を伝えたり、人体や物質の中の様子が観察できるようになった。今まで全く未知だった世界への扉が開かれた。その後も赤外線・紫外線やガンマ線など、次々と新しい「観測手段」が発見され、未知なる世界が広く開放されてきた。
「重力波」も、電磁波と同じ「波動現象」利用した自然観察である。しかも、重力波はすべてを貫通し、減衰しないと考えられている。新しい観測手段となり得る「重力波」の直接検出を行い、将来の「重力波による天体観測」の創生につなげていきたいと考えられている。「重力波」は「波動現象」でありながら、「電磁波」の仲間とは大きく異なる特徴を持つ。重力波は「重力」を発生する起源である「質量」が運動することで発生する。「重力波」を使った自然の観察が、「電磁波」の仲間を使った観察と根本的に異なる世界へも展望が開かれそうだ。
1922年、旧ソビエトの宇宙物理学者アレクサンドル・フリードマンA.Friedmann(1888年-1925年)は、一般相対性理論の方程式を参考に宇宙全体を解析し、宇宙空間全体が膨張あるいは収縮することを導き出した。
つまり、この宇宙空間は変化しうるもの、宇宙の誕生と進化、そしてその未来の宇宙が予測できる本格的な「宇宙論cosmology」が発表された。
現在の宇宙年齢は、138億年? 宇宙は時間も空間も存在しない「無」から生まれた。 この段階で一番重要な仮定は、宇宙が、その外界から完全に隔絶した、即ち、宇宙の外側との物質の出入りや、熱やエネルギーの交換がないという前提である。
宇宙誕生以前は、現在の宇宙の全エネルギーが圧縮され、光さえ脱出することができない状態であった。それを「宇宙のブラックホールblack hole」と表現する。
アインシュタインは、ブラックホールでは、重力は無限の密度を持つと説く。その初期の宇宙は全てのエネルギーが一点に集中していたことになり、誕生直後の宇宙は、想像を絶するほどの絶対温度約1028k(絶対温度Tとセ氏温度tとの関係はT=t+273.15 で与えられる)の超高温で、しかも高密度に凝縮されていたことになる。この状態からの爆発を、「インフレーション期」と呼ぶ。
ビッグバン直前の「宇宙のはじまりの瞬間」をとらえたのが「インフレーション理論inflationary cosmology」である。
1981年に、東京大学の佐藤勝彦名誉教授が発表したインフレーション理論は、宇宙誕生の初期、10-36秒後、宇宙は一瞬で10の何十乗にも巨大化し、その10-27秒後という瞬間に、極小だった宇宙が急膨張し、超高温・高密度の空間となった。この灼熱の宇宙誕生が「ビッグバン」である。米国のアラン・グース(A.H. Guth)が、ほぼ同時期に同じような理論を提唱している。 ビッグバン直後の0.00001秒後の原始宇宙の世界では、今ある原子のようなものはなく、バラバラのクォーク・電子・ニュートリノ・光子などの素粒子だけが飛び交う世界であった。クォークが集まり陽子と中性子が生まれた。
インフレーションが終了するとともに、インフレーションを惹き起こしていたエネルギーが【E=mc2】の物理原理をなぞるように、物質の元になる素粒子や光に姿をかえた。これが「物質と光の誕生」で、その後、宇宙は超高温・超高密度の空間となり、灼熱の宇宙の誕生「ビックバン」となる。
ニュートリノが最も多く作られたのは、宇宙の始まり「ビックバン」と言われている。つまり宇宙空間は、その誕生以来、ニュートリノで満たされていた。つまりニュートリノは、宇宙で一番多い、ありふれた粒子と言える。 突然現れて明るく輝き、やがて消えていく「超新星爆発」は、「新」と言う呼び名とは真逆で、広大な宇宙で度重なる太陽の何倍もある重い星の終末期の姿である。この爆発のエネルギーの99%は、ニュートリノとして放出され、大量の物質が超高温・超高密度になった時の情報を、そのまま地球に届けている。
それは太陽の中心部の核融合反応で作られたニュートリノが、殆ど何物にも遮られず、真っすぐ約8分後に地球に到達して、その中心部の情報を伝達していることでもある。
同じく核融合反応で作られる波長の短い光のγ線(ガンマ線;原子核の壊変によって原子核から放出される電磁波)は、数十万年費やして、ようやく太陽の表面にたどり着くまでに、電子などに何度も衝突して反応を繰り返すため、エネルギーを失って波長の長い可視光に変わっている。
宇宙マイクロ波cosmic microwaveは、宇宙の「最後の恒星の散乱面」から発せられている。ビッグバンが起こってから約37万年後、宇宙は低温になり、1個の陽子が1個電子と結びついて水素原子(原子核1個に電子1個が結合している水素原子の電子が、電離してイオン化した陽子をを中性水素原子と呼ぶ。この時の水素原子の束縛電子の電離エネルギーは、10〜20eVの範囲内にある。)ができた。それまで散乱する電子に進路を阻まれていた光子が、ようやくまっすぐに進めるようになり、宇宙の「晴れ上がりclear up of the Universe」となった。
宇宙マイクロ波は、この後に発せられた光と言われている。現在、この宇宙が誕生した「晴れ上がり」前の光「宇宙マイクロ波」をとらえることができないため、宇宙が誕生した瞬間の予測が極めて困難になっている。
その後、宇宙がだんだんと冷えていくに従って、陽子や中性子からなる原子核ができ、それが原始宇宙に漂う電子を捉え原子ができあがった。原子が重力により引き合い集まって星が生まれ、銀河が生まれ、今の宇宙ができ上がった。その過程でも、そもそもどのようにして重力が生み出されたかなど、多くの重要な疑問が解決されていない。
その後、宇宙はインフレーションと比べて緩やかな膨張が続き、その後長い時間を掛ける宇宙の拡大にともない次第に冷え込んでいく。その過程で原子がつくられ星が誕生する。約130億年前には、銀河は既に宇宙に存在したことが、観測されている。宇宙が誕生して3億年後頃に、最初の星が輝き、5億年後頃には、不規則な銀河が合体して、大きな銀河が作られた。しかし最初の星の誕生がいつ頃かについては、正確なことはわかっていない。
宇宙空間における銀河は、銀河が集まっている部分と殆ど存在していないボイドvoid(1-1.5億光年程度のスケールにわたって銀河が殆ど存在しない巨大な空間)と呼ばれる低密度の領域とが、疎密状態になっている。大部分の銀河は、銀河団と銀河団をつなぐフィラメント状構造に属しており、このフィラメントに囲まれるようにしてボイドと呼ばれる低密度の領域が存在する。この網の目を「宇宙の大規模構造large‐scale structure of the cosmos」と呼ぶ。
宇宙の最初の星たちは、太陽の数百倍程度の重さを持っていた。その巨大な星々は、自らの重力による核融合から様々な軽め元素を作り出した。その膨大なエネルギーの凝縮が超新星爆発を起こして、鉄より重い元素やウランより重い元素などを創生し宇宙に撒き散らした。それが、次の世代の星の種となった。
炭素より重い元素の起源は、恒星内部での核融合と超新星爆発が切っ掛けとなった。鉄より重い元素も、巨星の段階で一部は合成されるが、ウランより重い元素が合成されるのは超新星爆発のときのみである。膨大な質量を持つ中性子星の密度であっても、やがて「質量の運動はエネルギーに変わる」、加えて「質量には膨大なエネルギーが閉じ込められている」。
この物質と重力の関係を簡単に示すアインシュタインの公式
E=mc2 (エネルギー E = 質量 m × 光速度 c の2乗)
がその物理作用により、中性子星の驚異的な密度が起因する質量が重力となって働くため、膨大な質量を持つ巨星に働く重力による圧縮に抗するものもなく、やがてブラックホールとなり崩壊過程をたどる。超新星爆発の後の爆発噴出物は、星間空間に散乱する。
「原始宇宙」では、低エネルギーの電子とその反粒子である陽電子とが衝突して、消滅前の運動量を保存したまま複数個のγ線が放出される「電子対消滅」反応が頻発していたはずだ。その際に生じる対電子の質量が光に100%が変化する時の膨大なエネルギーは何に使われていたのだろうか。
たった5gの質量があれば、東京ドームを満たす水を沸騰させることができる。 特殊相対性理論の有名な公式
E=mc2
この公式の中のc2により、かつて別々に扱われていた質量mが、想像を絶したエネルギーEに変わる事を、この極めて単純なこの公式が教えてくれる。
逆に光子γ線(この放射性物質、ガンマ線の主な発生源は、宇宙の高エネルギー天体などである)が、十分なエネルギーをもつ原子核の周囲で急に曲げられると電子と陽電子の対がつくられる。この原子核の近傍で消滅すると同時に、陰陽電子の対が生成される。この「電子対生成」により、エネルギーが物質にかわる。
特殊相対性理論によって、時間や空間の物理学が急速に進化した。ただ特殊相対性理論は、観測者が静止しているか、等速直線運動(直線運動をしている物体の速さと方向が一定であれば等速度運動と呼ぶ。)している限定的な条件下で成り立つ理論であった。
人が走行するか車中であれば、通常、速度が変わるし、方向が時間とともに変化する加速度運動している。当然、重力もともなう。そうした日常的な条件下でも当てはまる一般的な相対論を完成させるためアインシュタインは、10年掛けて研究の進捗状況に合わせて、シリーズで論文を掲載し続けた。
「アインシュタイン方程式」と言われる重力場の方程式は、1915年に投稿され、次の1916年に出版されている。 太陽の横を光がかすめた時に方向が変わるなど、重力と光の物理について予言するなど、科学的に真正面から、今まで殆ど議論されることがなかった「この宇宙の始原」の領域に及ぶ物理を、アインシュタインは、再び衝撃的に「一般相対性理論」と名付けて発表した。しかも、「空間は絶対的なものではなく、質量のある物体があれば、歪みが生じる」ことを明らかにした。
そのアインシュタインの一般相対性理論の方程式を宇宙全体に適用し発表した「アインシュタイン方程式」には、宇宙項(宇宙定数)が付け加えられていた。その宇宙項は「アインシュタイン方程式」には、必然であったようで当初から導入されていた。その宇宙項によれば、空っぽの空間を満たし、宇宙の加速膨張を引き起こす謎のエネルギーの存在を示していた。
最初に提案した一相対性理論の基本方程式である「アインシュタイン方程式」に基づいて、一様で等方的な宇宙モデルを表す解をつくってみると、その解は必ず膨張、あるいは収縮を示した。
アインシュタインは、宇宙は静的な存在に違いない(膨張も収縮もしていない)と固く信じていた。宇宙は無限の過去から無限の未来まで変わらないという先入観が働いていた。それが、彼自身が構築した一般相対性理論の「アインシュタイン方程式」の宇宙項と矛盾してしまう。
1917 年、「宇宙は永遠不変である」という固い信念に基づき静止宇宙モデルとなる「アインシュタイン方程式」を発表した。自分の方程式に反発力を表す項を付け加えて時間的に変化しない有限な体積をもつ宇宙モデル(静止宇宙)を作り、この項を宇宙項と呼んだ。分かりにくいことに、その場しのぎの余分な宇宙項を付け加えることで、重力の効果を相殺する静的な解を導いたのである。つまり、宇宙は膨張するが、重力の働きでその膨張のスピードは衰えるとした。
ところが、いろんな人が宇宙を支配する重力について、アインシュタイン方程式で解いたところ、皮肉にも、宇宙は膨張や収縮をし続けて、とどまることはないということを発見していく。
アインシュタインの式を解いて最初に「宇宙が膨張している」という計算を示したのが、旧ソビエトの宇宙学者アレクサンドル・フリードマンA.Friedmann(1888年-1925年)である。1922年、論文をドイツの『Zeitschrift für Physik』という物理学会誌に投稿した。それを審査したのがアインシュタインであった。アインシュタインは、当初、フリードマンの論文を読んで、「計算が間違っている。自分が計算し直すとちゃんと静止宇宙になった」と、そのレポートを返した。
フリードマンは友人を介して自分の計算が正しいことをアインシュタインに説明し、その結果「計算としては正しい」ということで、有名なビッグバンの基礎になった論文が出版された。しかし、アインシュタインは「宇宙は膨張したり収縮したりしているものだ」ということを信じたわけではなく、単に数学の答えとしては認めただけで、現実は静止していると考えていた。
やがて、アインシュタインの一般相対性理論の方程式を宇宙全体に適用して新たに発見した、フリードマン方程式の解によって示される、宇宙の振る舞いの記述が事実である決定的な観測結果が示された。スライファーやハッブルがアインシュタインの「静止宇宙」の信念を突き崩す観測結果を公表した。
アインシュタインは、宇宙を静止させることができるように1917年に、既に方程式に宇宙項(宇宙定数)を付け加えていたが、やがてフリードマン方程式の解として直され定式化され、宇宙は膨張したり収縮したりすることを示した。
フリードマンモデルでは、宇宙は静止しているのではなく、時間とともに膨張あるいは膨張の後収縮する。そのどちらになるかは、宇宙にある物質密度によって決まるとした。
フリードマンの死後、1929年にエドウィン・ハッブルの観測によって宇宙膨張が発見されたことで高く評価されることとなった。
「宇宙が膨張している」ことを観測で示したアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルEdwin Hubble(1889年- 1953年)は、その正体は、宇宙項と同じく、単なる真空のエネルギーであるかもしれない、ととなえた。この結果は、宇宙が膨張しても密度の減らない未知の性質を持つエネルギーによって満たされていることを示唆する。この状態では宇宙が大きくなればなるほど宇宙の全エネルギーは大きくなるので、このエネルギーは負の圧力(強く引っ張られた物質の内部に発生する物質固有の抗力か?)をもっていることになる。これが暗黒エネルギーである。
1929年、遠方の銀河までの距離の測定から、「遠方の銀河ほど速く遠ざかってい る(後退している)」ことを発見した。これがハッブルの法則である。つまり、宇宙全体が膨張しているのであれば、逆に時間を遡れば、宇宙全体が小さくなり、ひいては「宇宙誕生の瞬間」があったことになる。
1998年の超新星の観測結果からも、過去50億年にわたって宇宙膨張は減速するどころか加速を続けてきたことが分かった。つまり、重力の効果を打ち消すような力が存在していた。
これが現在でいう宇宙定数で、量子論から予想される「真空のエネルギー」に相当するのではないかと考えられている。この未知のエネルギーを、ダークエネルギーdark energyと呼んでいる。アインシュタインが導入しその後撤回した宇宙項とは本質的に異なるが、ダークエネルギーは、宇宙の膨張を加速する元になる未知のエネルギーのことである。引力である重力によって宇宙が潰れずに静的状態を保つために、アインシュタインが導入した宇宙項とよく似た性質をもっている、なんらかのエネルギーによって宇宙は支配されているようだ。
宇宙が膨張しても密度の減らない未知のダークエネルギーによって満たされていることを示唆する。この状態では宇宙が大きくなればなるほど宇宙の全エネルギーは大きくなるので、このエネルギーは負の圧力をもっていることになる。
2013年までに発表されたプランクの観測結果からは、宇宙の質量とエネルギーに占める割合は、原子などの通常の物質が4.9%、ダークマター dark matterが26.8%、ダークエネルギーが68.3%と算出されていた。2021年の現在では、ダークエネルギーが、宇宙の平均エネルギー密度の約4分の3を占め、正体不明の物質ダークマターは、ほぼ4分の1の.27%を占める。通常の物質ordinary matterを構成する粒子バリオンbaryon(天文学では、この用語を使うことが多い)は、5%以下に過ぎない。
バリオンには、原子核を構成する陽子や中性子などのハドロンhadron(強い相互作用が働く粒子の総称)の基本構成要素の6種類のクオークquarkやグルーオン、またクォーク2個がグルーオンの働きによって結合したメソンmeson(中間子)などがある。それ以外に電子や電子ニュートリノと光子、そして反粒子などもある。
1970年代後半、質量があるため光が曲げられると言う「重力レンズ効果」により、大きな重力がある物質の存在、ダークマターが観測された。光やX線、赤外線などの電磁波により光学的に直接観測できないため暗黒darと呼ばれる、言わば仮説上の物質である。ニュートリノのように、宇宙に遍く存在し、電荷を持たないため他の物質とは殆ど相互作用しない、しかも質量を持ち安定しているなど、間接的にその存在を示す観測データは増えているものの、その正体は未だ不明である。
初期の宇宙では、僅かな揺らぎ.からダークマターの密度に差が生じ、密度の濃いものは重力によって、さらに周囲のダークマターを引き寄せていき、次第に目に見える物質であるチリやガスも引き寄せ、やがて星や銀河が形成されたようだ。
今では、我々の銀河系の外にも銀河が存在することや、それらの銀河からの光が宇宙膨張に伴って赤方偏移していることまで発見された。
一般に観測者に対して運動している物体から発せられる波には、ドップラー効果Doppler effectが生じる。発生源が近付ければ、波の波長が詰められて周波数が高くなり、逆に遠ざかる場合は波長が伸びて周波数が低くなる。それで、近づいてくる救急車のサイレンは通常より高くなり、遠ざかれば低く聞こえる。
つまり、一般的にドップラー効果で、波の振動数が低くなると波長が伸びる。光も波の1種なので、光源が観測者に対して遠ざかれば、このドップラー効果を受けて光の波長は伸びる。この伸びの現象を「赤方偏移」と呼ぶ。
つまり、見かけの明るさから超新星までの距離が分かり、その赤方偏移から超新星爆発が起こった時の宇宙の大きさと現在の大きさの比がわかる。赤方偏移が、天体までの距離の指標となる。やがて宇宙の始原からの膨張の経過が調べられる。
銀河の後退速度と銀河までの距離の間の比例定数がハッブル定数である。エドウィン・ハッブルは現代宇宙学の基礎を築いた。 すべての粒子に対しその反粒子がパートナーのように存在する。「反粒子」というのは、すべての粒子「電子・陽子・中性子・クォークなど」が、正負反対の粒子を持つことを言う。電子electronの反粒子は陽電子positronであり、陽子protonの反粒子は反陽子antiprotonと呼ばれる。
中性子にも反中性子antineutronがある。反中性子の質量は中性子と同じであり、電荷も中性子と同じでゼロである。ところが、中性子は2個のダウンクォークと1個のアップクォークと呼ばれる3個のクォークによって構成されている。反中性子は2個の反ダウンクォークと1個の反アップクォークから出来ている。
ニュートン力学は、光の速さに近いスピードで運動する物体には適合できないように、量子力学も、相対性理論との合体なくしては、高速で運動する電子を正しく扱うことができないことが明らかになり、こうした相対論的量子力学が予知していた陽電子が、既に実験で見つかっている。その後、創生期の宇宙の状態を探る目的の気球観測により、宇宙線の中に数多くの反陽子が観測されている。
反粒子は、確かに存在するが、この世界では、誕生した瞬間にパートナーとなる粒子と結合してすぐに消滅する。 陽電子は、質量・スピン(電子には空間的な三次元の運動のほかに、スピンとよばれる自転の自由度があり、これが電子の磁気モーメントの原因と考えられている)は電子と等しいが、正の電荷を持っている。陽電子が物質に入射すると、原子核や電子と衝突を繰り返し熱化され、電子と対消滅する。この現象は陽電子消滅positron annihilationと呼ばれる。電子対消滅annihilation of electron pairでは、物質がエネルギーに変わり、通常2本のγ線が放出され、そのエネルギー量はアインシュタインの式E=mc2で与えられる。
このとき放出されるγ線は通常2個で、運動量保存の法則law of momentum conservationにより、二つの物体がお互いに力を及ぼしあっているが、それ以外の力を受けないで運動している場合、全運動量は時間的に一定で変化しないため、正反対の方向に放出され、それぞれ1本のγ線のエネルギーは
mc 2 = 0.51 MeV (mは陰陽電子の静止質量、cは真空中の光速度) のエネルギーを持つ。
MeV《mega electron volt》1メガ電子ボルト =1ミリオン電子ボルト=106eV(100万電子ボルト)のこと。 電子ボルトelectron volt(記号eV)の1eVは、1個の電子が真空中で電位差1Vの電極の間で加速されるときに得られるエネルギーに等しい。
1eV ≒ 1.602×10-19J
(運動量保存の法則とは、物体と物体が衝突した時に、それぞれの物体が持つ運動量の総和に変化が生じないと言う法則である。この法則が成り立つためには、それぞれの物体に摩擦力や空気抵抗などの外力が働いていないことが条件であるが、通常、床や空気中の分子なども衝突の影響を受けるため、物体と物体の間だけに運動量が保存されているわけではない。)
目次へ
