| Top 車山お知らせ 車山の山菜 車山日記 車山ブログ 車山高原の野鳥 車山の紅葉 車山のすすき | |
| ☆早春のスミレ ☆車山高原の笹 ☆車山高原のシジュウカラ ☆諏訪の植生 ☆諏訪に生息する哺乳類 ☆諏訪の狐 ☆車山高原の狐 |
花粉の形成と受精
ブドウ糖とデンプン 植物の運動力 光合成と光阻害 チラコイド反応 植物のエネルギー生産 ストロマ反応
植物の窒素化合物 屈性と傾性(偏差成長) タンパク質 遺伝子が作るタンパク質 遺伝子の発現(1)
遺伝子の発現(2) 遺伝子発現の仕組み リボソーム コルチゾール 生物個体の発生 染色体と遺伝
減数分裂と受精 対立遺伝子と点変異 疾患とSNP 癌変異の集積 癌細胞の転移 大腸癌 細胞の生命化学
イオン結合 酸と塩基 細胞内の炭素化合物 細胞の中の単量体 糖(sugar) 糖の機能 脂肪酸
生物エネルギー 細胞内の巨大分子 化学結合エネルギー 植物の生活環 シグナル伝達 キク科植物
陸上植物の誕生 植物の進化史 植物の水収支 拡散と浸透 細胞壁と膜の特性 種子植物 馴化と適応
根による水吸収 稲・生命体 胞子体の発生 花粉の形成 雌ずい群 花粉管の先端成長 自殖と他殖
フキノトウ アポミクシス 生物間相互作用 バラ科 ナシ属 蜜蜂 ブドウ科 イネ科植物 細胞化学
ファンデルワールス力 タンパク質の生化学 呼吸鎖 生命の起源 量子化学 ニールス・ボーアとアインシュタイン
元素の周期表 デモクリトスの原子論 古代メソポタミア ヒッタイト古王国時代 ヒッタイトと古代エジプト
ヒクソス王朝 古代メソポタミア史 新アッシリア時代 ギリシア都市国家の興亡 古代マケドニア 古代文明の破綻
相対性理論「重力」 相対性理論「宇宙論」 相対性理論「光と電子」
 |
|
| 目次 | |
| 1)光電効果 | |
| 2)赤方偏移 | |
| 3)放射光 (☆シンクロトロン光 ☆大型ハドロンコライダー ☆強い相互作用 ) |
|
量子力学の創始者の一人であるドイツの理論物理学者マックス・プランクM. Planckは、最初は光子のエネルギー E と振動数νの間の比例関係から、光子はエネルギー量子hν を持った粒子と考える。光はこのような光子の集団であると言う。記号 h で表されるのがプランク定数Planck constantであるが、量子力学の基本定数の一つとなった。
E = hν
この式は、光の振動数νと波長λの関係(c=νλ)から、E=hc/λ(c は光速度)とも表された。
(量子とは、粒子と波の性質を合わせ持った、極小な物質やエネルギーの単位。物質を形成する原子や、原子を構成する電子・中性子・陽子や、光を粒子としてみたときの光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどといった素粒子も量子に含まれる。 量子の世界は、原子や分子といったナノサイズ nm(1mの10億分の110-9m;)、あるいはそれよりも小さい世界である。この極めて小さな世界では、日常的な物理法則【ニュートン力学や電磁気学】は当てはまらず、「量子力学」という新たな物理法則に従っている。)
光の強さは、単位時間に飛んでくるエネルギーhν を持つ光量子(光子)の数によってきまる。単色光(ν )が一定の場合の強さ(明るさ)は、光の波としての振動数の2乗に比例する。
この1900年のプランク法則の発表により量子論の幕が開き、1913 年に発表されたデンマークの理論物理学者ボーアNiels Bohr(1885-1962年)の原子物理学の理論を契機として、量子の研究に新たな展望が開かれ、加速度的に理論物理学が進化を遂げた。それを追うように、急速に実証実験に革新的な装置上の進化をもたらし、それが現代の壮大な実験物理学experimental physicsに繋がった。
光は波であるが、素粒子の光子でもある。光は電磁波としてよく知られているが、粒子の性質も合わせ持つ。
物質が光を放出したり吸収したりするのは、連続的な電磁波としてではなく、1個の光量子が振動数νに比例するhν(hは6.62607015×10-34J・s【ジュール秒】)のエネルギーで、その過程に関与するためである。振動数νの光が伝播するというのは、エネルギーhνの光量子が飛んでいき、その進行方向にhνの運動量が伝わるからである。これをアインシュタインの光量子仮説という。
プランクの導入した不連続を一歩進めたのが1905年のアインシュタインによる光電効果の理論であった。光電効果は、真空中で、アルカリ金属(周期表第1族の元素で、水素を除くリチウムLi・ナトリウムNa・カリウムK・ルビジウムRb・セシウムCs・フランシウムFrの6元素の総称。原子構造は外側に1個の電子を持ち、容易にその1個の電子を失って1個の陽イオンになる。)などに紫外線を照射すると金属から電子が放出されるのが観察される。出てくる電子の運動エネルギーは、いろいろな大きさのものがある、その中で最大の運動エネルギーは照射した光の振動数によって定まる。
光電効果の特徴の一つは、ある一定の振動数より小さな振動数(長波長)の光をいくら照射しても、電子が出てこないことである。日焼けの場合も、紫外線では日焼けをするのに、赤外線では日焼けはしない。光電効果でも同じで紫外線を照射すると、弱くても電子は出てくる。
しかし、どんなにつよい赤外線を照射しても、加熱して金属が溶けることはあっても電子が出てくることはない(これは、熱電子放出のことまで考えれいないが)。アインシュタインは、それに対して、光は、hνというエネルギーを持った粒子であると考えれば、光電効果を説明できることを指摘した。プランクは、単に波のエネルギー(振幅の自乗)がhνの整数倍に限られると言ったのに対して、アインシュタインは、波ではなく粒子であると考えるべきだと指摘した。
赤外の振動数νが小さい光ではhνの値は小さい。粒子としてのエネルギーが小さいわけで、それに対して、遥かに重く、同じ速度でも大きな運動エネルギーを持つ、振動数の高い短波長の光に相当する粒子をであれば、例え一個であっても、光電効果の概念的な説明がつく。
実際に光量子により電子がたたき出される場合にも、電子が直接外側に向かって飛び出すのではなく、任意の方向に進んで何かとぶち当たってから外に出てくることもあるだろう。その場合には、運動エネルギーの一部は衝突によって失われるので、出てくる電子の運動エネルギーは、照射した光量子のエネルギーより小さくなっている。最大の運動エネルギーとなるのは、内部でエネルギーを散逸することなく外に飛び出した場合のみである。
実は、光が波であるのか粒子であるのかはニュートンの時代から、物理の大問題であった。19世紀に、干渉や回折、さらには偏光が発見され、ついに光が波であることが決定した。それに対して、アインシュタインは改めて光の粒子性を主張する大胆な提案であった。アインシュタインが光の粒子性を主張したからといって、光の波動性が否定されたわけではない。古典的には、あるものが粒子であり波であるということはありえないけれども、量子論の枠組みでは、光は波動的な面と粒子的な面の両方を持ち合わせたものであった。
「アインシュタインの 光電効果に関する理論」は、1905年に、光電効果に関する仮説として提唱された。プランクの理論による光電効果の実験観察 と整合するものとして、光はプランクの式 E = hνで与えられるエネルギー量子を持つ粒子であると 提案した(光量子仮説)。アインシュタインは、プランクの理論を光にまで拡 張したのである。「光は粒子のように つぶつぶになって 空間内に存在している」と説く。
振動数が「ν 」の光は、hν のエネルギーの かたまりとなって金属内の電子に吸収され、電子がもらったエネルギー hνが、金属の内側から外側に電子を運ぶのに必要なエネルギー W より大きい場合には、電子は外側に放出される。したがって、出てくる光電子photoelectronのエネルギーの最大値は
E = hν - W
となるはずだ と言う。
1923 年、アーサー・コンプトン(1892 - 1962, 1927 年ノーベル物理学賞)は単色の X 線を黒鉛結晶に 照射し、その散乱角の増加とともに散乱 X 線の波 長が長波長側にシフトすることを見出した。こ れは光の粒子が結晶内の電子に衝突し、電子を弾 き飛ばすことで光子のエネルギーが低下したと考 ることにより説明可能な結果であった。その波長変化は 光量子仮説に基づく予測と定量性に一致した。これにより光子が実在のものであることが明確され、以降光は波動性と粒子性を合わせ持つとい う考えが定着してゆく。
その後、フランスの理論物理学者ルイ・ド・ブローイL. de Broglie((1892-1987年))が、光子に限らずすべての素粒子は粒子性と波動性の両者を併せ持つとして、運動量p を持つ粒子は波長 λ=h/p の波のように振る舞うことを示した。この波長を「ド・ブローイ波長」という。
1924年、ルイ・ド・ブロイは、光に二重性があるように、電子や陽子といった、それまで粒子と考えられてきた物質粒子一般にも拡大適用できりる、と発表した。これが後に「物質波」とか「ド・ブローイ波」と呼ばれる。
光子の運動量は、上記の波長の式から、p = h/λ になる。ド・ブロイは、あらゆる粒子においてもこの式は成り立つと考えた。
上式を変形するとλ = p /hとなり、p= mνを代入するとλ=h/mνとなり、このときの波を物質波あるいはド・ブロイ波と言い、特に電子の場合、電子波と呼ぶ。
アメリカのベル研究所のダヴィソンとジャーマーは、1927年、電子線をニッケル結晶に照射する実験をした。実験結果の示す波長は、・ブロイ理論による予想 1.67Å に極めて近かった。これによ り物質波の実在が証明され、ド・ブロイは 1929 年にノーベル物理学賞を受賞する。
アインシュタインは、空洞内の放射エネルギーは、常にゆらいでいる。そのゆらぎは、hνを単位として、 その整数倍となっているはずだ。つまり hνと言う決まった単位の光が空洞の壁から瞬間的に出たり入ったりしている。
金属など物質の表面に充分に振動数の大きな光が入射すると、そのエネルギーによって物質内の電子が外部に飛び出す(外部光電効果photoelectric effect)、一般に光電子と言う場合、この現象によって外部に飛び出した電子を指す場合が多い。この光電効果により、物質に光を照射した際に、電子が放出されたり電流が流れたりする。デジタルカメラや太陽光発電の動作原理として広く利用されている。
この光電子1個1個を捉えて増幅するのが高感度光センサの光電子増倍管である。この光電効果により放出された電子を増幅することにより、高い感度を実現する光センサである。光子1個まで検出可能な超高感度、高速動作・分光分析・高エネルギー物理学・天文学・医療診断(ガンマカメラ、PETなど)・血液分析・石油探査・環境測定・バイオテクノロジー・半導体製造・材料開発など用途は広がるばかりである。
また光電子の持つエネルギーは、物質の表面状態や内部のバンド(伝導体)の層構造などを反映するため、光電子分光法などを用いた分析にも応用されている。
結晶中の電子が取り得る、幅のあるエネルギー準位をエネルギーバンドと呼ぶ。金属や半導体の自由電子は、バンドの層構造を取っている。各原子には、陽子数の電子が存在するので、一定のエネルギーレベルまでを電子が水のように埋める。金属では、水面がバンド(伝導体)の途中にあると、電子は、そのバンド中を自由に移動できる。
半導体であれば、水面 がバンドとバンドの間の禁止帯にあると、埋まったバンドの電子は移動できないので、半導体の抵抗が大きくなる。
アインシュタインのこの理論は、1916年、アメリカの実験物理学者ロバート・アンドリューズ・ミリカンRobert Andrews Millikanによる実験で、見事に証明された。「電圧 V を十分高くして、光電効果により飛び出した電子(光電子)を全て陽極に集めると、流れる電流は陰極に照射した光の強さに比例する」
「どのような金属面に対しても、光電効果の起こすためには最小の振動数がいる。それ以下の 振動数の光では、どんなに強い光でも光電効果が起こらない」
「光電子のもつ最大の運動エネルギーは、光の振動数によって直線的に変化する。それは、アインシュタインの仮説
E = hν - W
に完全に一致する」
ミリカンは、1912-1915年にかけて光電効果の研究を進め、アインシュタインの光電子のエネルギーと振動数との間の関係式を実験的により証明した。
1914年、光電子効果によるプランク定数の最初の決定を行った。1915年、ミリカンは実験結果を発表した。彼の結果は、アインシュタインの理論を破るものでは決してなく、理論を見事に証明するものであった。ところが、ミリカンはそれでも、アインシュタインの理論に納得していなかった。
(実験の原理は、有名なミリカンの歴史的実験に基づくものであった。ミリカン電気素量測定実験は、平行極板間に油滴を噴霧し、このとき帯電した油滴粒子の電界中での運動を測定することにより電気素量【基本的物理定数の1つ】を求める。
油滴は顕微鏡テレビ装置により大型モニターで観察し、運動の時間測定にはコンピュータ計測を利用した。)
そのミリカンは1916年の段階では、「アインシュタインの光電方程式は、私の判断では今のところ満足できる理論的基礎を持たない」が、それでも光電効果の実験では「実際の現象を非常に正確に表している」と記している。
1921年、アインシュタインは光電効果の理論的業績によりノーベル物理学賞を受賞した。2年後の1923年、ミリカンは電気素量(電子の電荷量)の測定と光電効果の研究によりノーベル物理学賞を受賞した。
ミリカンは、1953年12月19日カリフォルニア州サン・マリノで死去したが、その後1958年に出版された本では、自らの実験結果では「アインシュタインの光の粒子論以外のいかなる解釈も不可能だ」と断定していた。
目次へ
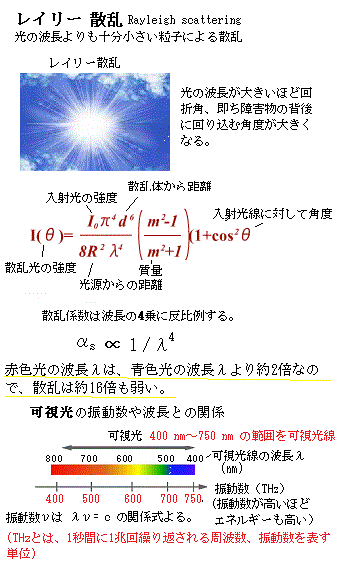 |
| 光とその仲間を総称して「電磁波」と言う。光とその仲間の正体は、空間を伝わる電気的な波である。電気的な波が起こると、必ず磁気的な波も同時に起こるので、電磁波と呼ばれている。 光とその仲間たちとの違いは、波長の違いである。波長とは、波の一番高い場所から次の山までの長さである。電磁波の中で、波長が最も長いのが電波である。それから赤外線・光(可視光)・紫外線・X線・ガンマ線の順に波長が短くなる。 太陽の光は、様々な波長の光の混合物で、赤い光が最も長く(約700nm)、最も波長が短いのが紫の光(約400nm)である。 光の波長の大きさに比べて、空気中の分子の大きさは、その1/1,000.程度しかない。光が分子のような非常に小さな物質に当たった時の散乱を「レイリー散乱Rayleigh scattering」と呼ぶ。 |
第一に天体が我々から遠ざかる運動をする場合に、音の場合のドップラー効果と同様に、光の波長が長くなる現象を運動学的赤方偏移と呼ぶ。天体が近づく場合には波長が短くなり青方偏移となる。
第二は、宇宙膨張により光が飛ぶ間に空間が伸び、結果、波長が伸びて観測される。これを宇宙論的赤方偏移と呼ぶ。
第三に、強い重力場をもつ天体からの影響を受ける光は、重力ポテンシャルがより深い場所から脱出するさいに、エネルギーを失い赤方偏移が生じる。これは一般相対性理論の効果で、重力赤方偏移と呼ばれる。
ここで「光」と表現をしているが、実際には電磁波に共通の現象で、いずれも相対性理論で理解できる。
どんな偉大な文明が形成されたとしても、そのテクノロジーをもってしても、速さに限界が生じる。その上限は光の速さである。
特殊相対性理論によると、物体は光速に近づくほど加速しづらくなる。つまり「質量が急激に増える」からであり、光速に近づけば近づくほど、質量は膨大になり加速ができなくなる。
実際、静止した電子に加速器(電気のエネルギーで電子を光速近くまで加速する装置)で、電子にエネルギーEを与えて、電子の速さを光速の86.6%まで加速できたとすると、質量は静止時の2倍になる。
さらに同じエネルギーEを追加し、エネルギーの総投入量を2Eとすると、質量は静止時の3倍となるが、速さの増加量は光速の7.7%しか増えず、電子の速さは光速の94.3%にとどまる。さらに、エネルギーの総投入量を3Eとすると、質量は静止時の4倍となるが、速さの増加量は光速の2.5%しか増えず、電子の速さは光速の96.8%にとどまる。さらにエネルギーの総投入量を4Eとすると、質量は静止時の5倍となり、速さの増加量は光速の1.2%、電子の速さは光速の98%になる。
この場合加速に使われたエネルギーの多くは、質量の増加に転じるため「エネルギーの効果は、増加する質量で打ち消される」ことになる。
質量が増えると言うことは、加速された物体が大きくなることではない。例えば、100万個の原子でできた物体が加速された質量が2倍になるということは、原子の数が200万個になるのではなく、100万個の原子1つ1つの質量が2倍になることである。
質量とは物質の動きにくさの度合い、つまり慣性の大きさのことである。そのため、慣性質量とも呼ぶ。慣性質量は単に質量と呼ばれることが多いが、万有引力の法則にでてくる質量(重力質量)とは原理的には異なった量である。質量は運動に関係なく普遍であり、そのため、宇宙飛行士が船外に出て人工衛星を簡単に手で掴んで移動させたりはできない。物質の質量は地球上でも、宇宙空間でも、月面でも変わらない。質量の単位はkgである。
「重量」は、重力によって2つの物体の間に働く力と定義されている。ニュートンnewton(記号: N)が重量の単位でもある。場所によって10分の数パーセントの差異があるが、地球表面において質量1kgの物体の重量は約9.81ニュートンNである。
国土地理院では「 重力の大きさは時間や場所によって異なります。例えば、遠心力は自転軸からの距離が遠くなるほど大きくなることから、赤道上の重力は北極や南極よりも約0.5%小さくなります。また、地下の密度構造(鉱床など密度の高い物体が地下にあったり、活断層などによる地層の不連続性や、また断層の両側で密度の差による)の違いでも変わります。さらに、同じ場所であっても、月や太陽の引力(潮汐)、地殻変動等により時間的にも変化します。」、「実は物の重さは重力の大きさによって変わります。地球の遠心力は高緯度ほど小さくなるので、北海道と沖縄を比べると北海道の方が少しだけ(約0.15%)重力が大きくなり、同じ物でもその分重くなります。例えば、沖縄で1kgの金が、北海道に持っていくだけで約1g重くなるのでとてもお得に感じます。」と教えてくれる。
ニュートンI.Newtonの万有引力の法則における質量は、重力質量である。重力質量のある2つの物体は互いに引き合うが、その引き合う力の大きさは、それぞれの物体の重力質量に比例して、互いの間の距離の2乗に反比例する。
師のプラトンから「学校の精神」と評されたアリストテレス(BC384 – BC322年)ですら、その著書「自然学」の中で、「重いものが速く落ちる」と、その学説はなんとその後2000年近くも信じられていた。それは重さではなく、空気抵抗(形状)や密度(空気による浮力)の影響である。実生活においては、空気が存在する以上、環境次第で、それは正しい観測であるのも否定はできない。
ただ、重い石と軽い石を二階の窓から落としてみれば、結果は、「ほぼ同時に落ちる」。
物体はその質量や組成によらず重力場中で同じ加速度で落下するという観測事実は質量と重力質量が等価であることを示している。これらの2つの質量が等しいということを主張するのが等価原理である。
『新科学対話』は、ガリレオ・ガリレイGalileo Galileiの晩年の1638年に出版された本で、登場人物のサルヴィアーティが、
「同じ大きさであるが、たとえば鉛の球と樫の球のように、一方が他方より10倍ないし12倍も重い2つの球が、150あるいは200ブラッチョの高さから落下するとき、両者はほぼ同じ速さで地面に到達することが実験により示されますから…」と話している。
このように本書では、ガリレオ自身の実験とは書かれていないまでも、異なる重さの2つの物体を同時に落とすことが実験されたことを物語っている。その中で、「真空中では、すべての物体は同時に落ちるはずだ」と記している。
アインシュタインは、1907年、等価原理に基づいて一般相対性理論の土台となる生涯最高のアイディア、「落下する箱の中では重力は消える」、つまり「慣性と重力は同じ」、「無重力空間でも、宇宙船が加速すれば、慣性力により見かけの重力が生まれる」、「その宇宙船の中の人にとって天体の重力なのか、慣性力なのか区別はできない」と考えた。
つまり、重力を受けていない宇宙船の中と、落下する箱の中は、本質的に同じ無重力状態で「慣性力と重力は区別できない」、「重力と慣性力が等価なら、落下する箱の中では、両者は完全に打ち消し合い、本質的に重力は消えている」と説く。
落下する箱の中にリンゴがあれば、「落体の法則」、両方とも同じ速さで落下する。では、同じように落下する箱の中で、人が球を横に押すと、地上にいる人が見れば球は放物線を描いて落下する。しかし、箱の中の人は自分も落下しているので、球の運動のうち、重力による落下運動の分は差し引かれて見える。
「放物線運動」―「自由落下運動(加速度運動)」=「等速直線運動(等加速度直線運動)」となり、箱の中の人は、真っすぐに同じ速さで進む「等速直線運動」をする球の軌跡を見ることになる。 つまり落下する箱の中の人は、重力の影響のない宇宙船の中に居る状況と全く同じになる。
(加速度が一定の運動を等加速度運動と言う。このうち、直線上の運動である場合を等速直線運動(等加速度直線運動)と言う。『等速直線運動』のうち、もっともシンプルな運動が自由落下運動であり、手に持った鉄球を初速度 0 でそっと放して重力にまかせて真下に落下させるような運動である。地表において物体が落下するときの加速度が重力加速度であり、その値は g = 9.8[m/s2] である。)
重力は物体の質量に関わらず、全ての物体に同じ自由落下運動(加速度運動)をさせるが、落下する箱の中は、重力の影響を受けない宇宙船と同様、「重力の影響のない慣性系と同等」とみなせる。それは特殊相対性理論の領域である。
アインシュタインの特殊相対性理論では、時間と空間が一体となる四次元時空では「すべての慣性系同士で、物理法則が同じように成り立つ(相対性原理)」と考えた。さらにアインシュタインは、慣性系を含む加速度系でも成り立つ相対性原理を研究し、慣性力と重力が同じであるという等価原理を基本として、重力理論でもある一般相対性理論を構築した。
落下する箱の中や重力の影響を受けない宇宙船の光源から発せられた光は、その瞬間の速度は0であっても、光は直進する。それを地上から見れば、その軌跡は放物線を描いている。つまり重力によって光も曲げられたことになる。
速度が0から加速を始めた宇宙船の中から、宇宙船の光源から発せられた光を見た場合、加速する方向とは逆の慣性力が働き、光は宇宙船の運動による影響を受けないので、取り残されて光は曲がって見える。結果、「慣性力(重力)が光を曲げた」ことになる。言わば、重力と慣性力は、共に光を曲げる、つまり両者が「等価」であることの証明となる。
1922年、ロシアのフリードマンA. Friedmannがアインシュタインの一般相対性理論の方程式を宇宙全体に適用して発見した解によって、宇宙は静止しているのではなく、時間とともに膨張あるいは膨張の後収縮する。そのどちらになるかは、宇宙にある物質密度によって決まると唱えた。
この解の発見当時は、宇宙は静止していると考えられていたので、アインシュタインですらフリードマンの計算は間違いと思っていた。その後、計算は正しいが、フリードマンの宇宙方程式は、現実の宇宙とは関わりないとして重要視されなかった。
1929年にエドゥイン・ハッブルE. Hubbleにより、遠い銀河の赤方偏移から宇宙が膨張していることを明らかにした。アインシュタインは、「宇宙は静止している」という先入観で、宇宙項を導入したことを大変後悔したと言う。
近年では、宇宙背景放射の観測が、宇宙背景放射探査機COBEやウィルキンソン・マイクロ波異方性探査機WMAP、プランクPlanck衛星などで、総合的に現在の宇宙像が明らかにされ、宇宙の加速膨張が幾度も確認され、宇宙項を含めた宇宙モデルが復活した。
(このWMAPの打ち上げ後の2002年に、このミッションの科学研究チームの一員で、宇宙背景放射の研究においてパイオニアでもあった天文学者デビッド・ウィルキンソンが亡くなったため、その功績を讃えてその名を冠にした。
ウィルキンソンは、現代宇宙論、特にビッグバンで生じた宇宙マイクロ波背景放射CMBの研究で、大きな功績を残したが、その一方、特に数多くの大型CMBによる実験に.よる解析研究の成果を公表した。
プランクPlanck衛星は、ヨーロッパ宇宙機関ESAが打ち上げた宇宙マイクロ波背景放射を観測するための人工衛星である。そのプランクの名は1918年にノーベル物理学賞を受賞したドイツの科学者マックス・プランクM. Planckにちなんでいる。
プランクは、量子論の創始者の一人であり、光のエネルギーに関する方程式は、E=hc/λ特における定数、プランク定数と名づけられ、物理学における基礎定数の一つになっている。)
その宇宙の膨張の仕方がハッブルの法則と一致していた。科学者たちは、宇宙がビッグバンの直後に急速に膨張したことを確認した。その後、不可解で目に見えない暗黒物質の重力によって膨張は一時減速したとも言われた。
科学者たちは何十年もの間、宇宙の膨張速度を測定しようと試みてきた。約138億年前のビッグバンの名残である宇宙マイクロ波背景放射(CMB)研究により、宇宙の歴史を解明しようとしてきた。ただ、CMBを研究する科学者たちは、約138億年前の想像を絶する過去の、遥か彼方の宇宙を見ていることになる。
ただ、その測定結果は、これまで考えられてきたモデルの予測よりもはるかに速く膨張していた。しかも、宇宙はCMBの観測に基づく計算で予測された値よりも、9%速い速度で膨張していると考えられてもいる。 その原因は、宇宙の約68%を占めるが、未だ不可解なダークエネルギーかもしれない。このエネルギーは、暗黒物質の重力を圧倒しながら、膨張を加速させているようだ。
宇宙は光速よりも速く膨張している。これは相対性理論と矛盾してはいない。宇宙全体が一様の速度で膨張することはではない。膨張宇宙では、遠くの天体はそこまでの距離に比例した速度で遠ざかる。結果、138億光年と言う遠い天体が遠ざかる速度は、光速を超えることになる。 しかし、全く静止した状態の宇宙空間から、銀河が光速を越えて遠ざかるなら、アインシュタインの相対論と矛盾するのであるが、膨張宇宙とは、空間自体が膨張する。単に銀河が地球から遠ざかる速さではなく、宇宙空間そのものが膨張するということとの間には大きな違いがあり、空間の膨張の場合、距離の膨張率が光速を越えてしまうことを意味する。
光速を越えて膨張する宇宙の遥か彼方の背後からは、光の信号が届くことがないため、今の段階では全く観測不可能なっている。そのため、物理学の基本原理である相対論とは、矛盾しないが、その想像を絶する宇宙を膨張させる膨大なエネルギー源は何なのか、しかも、人々が時代を超えて問い掛ける宇宙の果てはあるのか、我々が生きる世界とは別の宇宙自体存在するのではと、その答えは依然として、明確な理論が確立されていないばかりか、逆に混迷を深めている。
光速を超えるものは存在しない、という論理は物体に適用されても、空間の膨張には当てはまらない。正確に言えば、光速を超える情報は、伝わっては来ない、という言い方の方がより正しいようだ。固定された空間の中で物体が光速を超えてしまえば、必然的にその情報を物体が放つ光に頼るため、宇宙空間自体が光速を超えて膨張するとなれば、光の情報に頼る現代の観測手段では永遠に入手することは不可能となる。
そのため、光速という速度とは、別次元の原理が働く宇宙空間の膨張となれば、相対論を適用することは困難なのか?
アインシュタインが示した有名なE=mc2という式は、質量m(kg)の物質はそれに光速c=30万km/secの自乗を掛けただけのエネルギーを持つ、という意味である。cが大きいのでかなり巨大な数字になる。実際原子力エネルギーは原子核(ウランやプルトニウム)の分裂反応で余った質量をエネルギーとして取り出してる。例えば1ccの水の質量をすべてエネルギーに変えることが出来るとすると、20万トンの0度の水を一瞬に沸騰させることが可能となる。
目次へ
イオンionとは、電気的に中性の原子や原子団(複数個の原子が集合して一つの化学単位をつくる。化合物中の基を形成する官能基も原子団で、それら集団を概括的に原子団と言う。)または分子が、1個または数個の電子を失うか、逆に過剰の電子を得て電荷をもつ状態になったもの言う。電子を失って正電荷を帯びたものを陽イオン(カチオン)、取り込んで負電荷を帯びたものを陰イオン(アニオン)と呼ぶ。最外殻に1個の電子を持つ周期表1族のアルカリ金属は1価に、第17族元素に属するハロゲンhalogen(第17族に属する5元素の総称)と呼ばれるフッ素F・塩素Cl・臭素B・ヨウ素IおよびアスタチンAtの5元素は、反応性非金属としての性質がありマイナス1価になりやすい。電子の授受を経てイオンになることをイオン化または電離と呼ぶ。つまり、アルカリ金属は電荷数+1のイオンに、ハロゲンは電荷数-1のイオンになる。
ヨウ素やアスタチンはハロゲン族だが、常温の固体では金属光沢を持つ。ハロゲンは、陽性の強いアルカリ金属元素とイオン結合してイオン性結晶を作り典型的な塩類(イオン性化合物)となる。それで、ギリシア語のháls(塩)とgennáō(つくる)を合わせてハロゲンと呼ばれた。
価電子valence electronとは、原子核の周囲に束縛されている電子のうち、最外殻に存在する電子のことで、原子核からの引力が弱いため、原子核から離れやすく不安定である。 しかも、最外殻にある電子が、最もエネルギーが高い。価電子は、原子間のイオン結合などにおいても重要な役割を果たしていることが多いが、加えて、物理的な特性を持つため素粒子としての主要な役目を担っている。
電子や陽子などの荷電粒子が加速・減速したり曲がったりすると、光(電磁波)が放射される。これが「放射光Synchrotron Radiation(Synchrotronは、電子・陽子などの加速装置)」である。この放射光は、通常、全方位に球状に放射される。さらに速度の速い電子が曲げられると、前方向だけに偏って放射される。次に光速に近い速度まで加速された電子が曲げられると、放射光が極く狭い範囲に絞られる。荷電粒子のスピードが上げれば上げるほど、放射される方向の進行方向が極めて細い領域に狭まる現象である。
その細い領域に平行性の高い放射光が集中し、しかも加速された分エネルギーが高くなり、それだけ光は明るくなる。しかも、電子の進行方向の変化の大きさによって、様々な波長の電磁波を取り出すことができる。
放射される光の方向の変化は、「アインシュタイン」の重力による現象など、特殊相対性理論で説かれるが、現代の物理学では、可視放射による物体の色の区別、赤外放射による温くなる熱効果など、光の波長域は、周辺環境条件に応じて物理的に異なり、それぞれの現象とその効果の間には一見全く関連が無いようにも思えたが、これらの各種現象全体については、物質を構成する各種原子核と電子や分子群と、電磁波との相互作用の結果として統一的に論じることがでる。
実際、「先端材料の原子・電子の構造」、「触媒反応の動的挙動」、「原子・分子分光」、「超微量元素分析」・「地球深部物質の構造と状態」・「映像法による呼吸器系疾患の観察」など多岐にわたる。
広島県・岡山県・兵庫県など広範囲にわたる吉備高原の東端部、兵庫県南西部の丘陵地帯を切り開いて造成した学術公園都市(播磨科学公園都市)にある「SPring-8」は、世界最高性能の放射光を生み出すことができる大型放射光施設Large radiation facilityである。
ミクロの世界を観測するには非常に強いX線が必要であるため、電子ビームの加速エネルギーがおよそ50億電子ボルト(5GeV;通常、ギガエレクトロンボルトと読む)以上の加速器を装備する施設である必要がある。2003年7月、米物理学会速報誌『Physical Review Letters』で発表された「5クオークの発見」は、この電子ビームラインを用いた研究における特筆すべき成果であった。陽子や中性子は3つのクオークからできている。しかし、理論物理で予言されていた4個以上のクオークから成る粒子が、高輝度ビームのパワーにより、世界で初めて「5個のクォーク」からなる粒子が発見された。
現在では、クォークには、アップ(u)、ダウン(d)、ストレンジ(s)、チャーム(c)、ボトム(b)、トップ(t)の6種類があることが判っている。ただ地球上で安定しているのはuクォークとdクォークのみであるし、それ以外の複数のクォークからなる複合粒子「ハドロン」は、SPring-8の実験で観測されているだけである。
2010年、SPring-8には、ビーム強度、エネルギーともに世界最高のレーザー電子光ビームラインと、より測定波長領域が広くなる高分解能スペクトロメーターを備えた施設の建設が始まろうとしていた。ここで「5クォーク粒子発見」のより確かな証拠が得るための実験が開始された。
SPring-8では、極めて明るく品質の良い放射光を用い、光と物質の様々な相互作用を利用した精度の高い分析を行なっている。例えば、物質に一定以上のエネルギーを持つX線を照射すると、物質中の原子の内殻電子が励起され、それによって生じた空孔(ホール)に外殻電子が移る際に内殻と外殻のエネルギー差に対応したX線が放出される。このX線を蛍光X線と呼ぶ。
原子核のまわりに有る電子の内殻と外殻のエネルギー状態は、原子特有の値であるため、そのエネルギー差は原子ごとに固有である。そのため、蛍光X線のエネルギーも原子ごとに固有となる。電子が存在できる軌道はいちばん内側からK殻・L殻・M殻・N殻と呼ばれ、内側ほど強く原子核に結合している。つまり、もっともエネルギーが低い状態にある。それぞれの殻には何個の電子が入れるかが決まっているため、いちばんエネルギーの低い状態から電子が詰まっていく。もし電子が外側の軌道にいて、それより内側の軌道に電子が入れる空孔があったとすると、電子はエネルギーの高い状態から低い状態に移り、そのときに余分なエネルギーを光として放出する(発光)。電子がL殻からK殻へ遷移する時に放出される蛍光X線をKα線、M殻からK殻へ遷移する時に放出される蛍光X線をKβ線と言う。
「蛍光X線分析」という分析手法では、X線を物質にあてると、物質に含まれる原子に応じた波長のX線が放出される作用を利用して、その放出されたX線の波長を測定することで、その物質の原子の種類と比率を解析し、考古学や地球科学などの幅広い分野にデーターを提供をしている。
原子核を構成する陽子と中性子は、どちらもクォークとグルーオンと呼ばれる素粒子から構成されている。陽子がクォークとグルーオンからどのように作られているかを解明するために、これまで世界中で多くの研究が行われてきたが、未だ多くの謎が残されている。 特に、陽子にはコマの回転に似た「スピン」と呼ばれる向きを表す性質があるが、スピンの向きにクォークやグルーオンが、それぞれどのように作用しているのかが分からない。陽子のスピンの一部は、グルーオンが陽子のスピン軸の周りを回転して生み出していると考えられているが、その割合がどれくらいかは全く分かっていない。
原子核を構成する陽子や電荷をもたない中性子は、それぞれ、陽子は2個のアップクォークと1個のダウンクォーク、中性子は1個のアップクォークと2個のダウンクォークからなる。そのクォーク3つからなる陽子や中性子とその他の核子を「バリオンbaryon」と呼ぶ。字句の意味は質量を持った重い粒子、天文学では「ダークマター」ではない通常の物質を構成する粒子という意味で用いられる。
バリオンには、ハイペロンhyperonと呼ばれる質量の小さな粒子を含んだ原子核(ハイパー核)がある。ハイペロンは不安定で約10-10秒程度で崩壊するハイパー核は我々の身の回りには存在しない。ハイペロンは、λ粒子(ラムダー;u,d,s)、Σ粒子(シグマ;uus,uds,dds)、ξ粒子(グザイ;uss,dss)といった粒子で、いずれもストレンジクォーク(s)を含む。
水素を除くあらゆる元素の原子核は、複数の陽子と中性子が「パイ中間子π-meson」の媒介する強い力で結びついている。原子核内で、同じ正の電荷を持つ陽子同士の間には電磁気力による反発力が生じるが、陽子の間を飛ぶパイ中間子が伝達する強い力が、その電磁気力をはるかに上回っている。これはパイ中間子の質量が極めて軽いからこそ成り立つ。またパイ中間子が重すぎたなら、陽子や中性子の間で強い力が届かなくなり、陽子1つで原子核をつくる水素以外の元素は存在できなかった。この中間子の一種、陽子間の電気的斥力を抑えて原子核を安定化させる核力【強い相互作用】を媒介する粒子のように、クォーク2個から構成される「メソンmeson」などがある。これらバリオンやメソンの強い相互作用を行う重粒子を総称して「ハドロンhadron」と呼ぶ。「ハドロン」とは「強い相互作用」で結合した複合粒子」という意味である。
グルーオンは、クォーク間の「強い力」を媒介する粒子である。その「強い力」は、クォークを結びつけて、陽子や中性子などの核子を作り、さらに、それら核子から原子核を作る力となる。その核子を結びつける力(核力)の粒子が、パイ 中間子であり、パイ中間子自体はクォークと反クォークの対からなり、それを結びつけているのもグルーオンである。つまりは、原子核はグルーオンによる核力の引力効果で結合している。
2つの核子の間でパイ中間子が交換されることで、核子を結びつける核力が生じる。それもグルーオンによる力に頼る。「強い力」の到達距離は、重力や光子のようにグルーオン自体、質量を持たないにもかかわらず極めて短い。そのため日常では感じることができない。
高いエネルギーを持った光は、粒子として振る舞い、光子と呼ばれる。光子は陽子同士の衝突反応からも生成される。そのほとんどは、反応で生じたパイ中間子などが崩壊して間接的に生成される。これに対して、陽子内のクォークやグルーオンの衝突反応から直接生成される光子を「直接光子」と呼ぶ。
高エネルギーの陽子同士の衝突では、中性パイ中間子などの粒子が多く発生する。中性パイ中間子は、発生後すぐに2個の光子に崩壊する。粒子の崩壊から生じる「崩壊光子」の量は直接光子の何倍もあるため、直接光子の観測・測定を妨げる雑音となるため、直接光子の信号を崩壊光子の雑音から分離する必要が生じる。
約138億年前の「ビッグバン」直後の宇宙は、極めて高温で、クォーク対やグルーオン・光子・電子などが、プラズマ状態で乱雑に動き回っていた。この状態の宇宙をクォーク・グルーオンプラズマ Quark Gluon Plasma(QGP) と呼ぶ。その後、宇宙膨張とともに宇宙の温度は冷え、クォーク対やグルーオンから、陽子や中性子がつくられ、ヘリウム Heやリチウム Liなどと軽い元素の原子核が生成された。ビッグバンから37万年経過すると、今度は陽子や軽い原子核が 電子を捉えるようになり中性原子となる。この時点から、これまで電子の散乱よって遮られていた 光子が直進ができるようになり「宇宙は晴れ渡った」。その宇宙空間は、やがて重力の働きにより様々な物質が形作られ、膨大な天体と銀河が形成された。
(一般的に物質の温度を上げると固体から液体・気体へと状態が変化する。気体の温度をさらに上げたり、電界をかけると「電離」が起こり、電荷を持たない中性子と陽イオン、電子が混在した非常に活性化した状態になる。これが固体・液体・気体に次ぐ物質の第4状態「プラズマ」である。)
宇宙空間に自由電子が殆どなくなると、トムソン散乱Thomson scattering(可視光などの低周波の電磁波が自由荷電粒子と衝突して、進行方向を変えるがエネルギーを失なわない弾性散乱。つまり、散乱後も波長に変化が生じない。これに対して波長の変化を伴うX線やガンマ線など短波長の電磁波の散乱をコンプトン散乱Compton scattering【X線を結晶に照射すると、 X 線が結晶中の電子に衝突して散乱される。散乱により光子のエネルギーの一部が反跳電子に移るので、散乱光子は入射光子よりエネルギーが小さくなる】 と呼ぶ。)が起こりにくくなる。これ以降、光子は自由電子に行てを遮られず宇宙空間を基本的に直進する。この時代を「宇宙晴れ上がり」、または再結合期と呼ぶ。
この時代の光子が、約138億年をかけて地球に到達する。地球に到達した頃には、宇宙の膨張により、温度が約3K(ケルビン;-270℃ )まで下がっている。この非常に低温な放射は、マイクロ波と呼ばれる波長で観測されるので、この光子のことを宇宙マイクロ波背景放射と呼ぶ。 1964年、ペンジャスとウィルソンが宇宙マイクロ波背景放射Cosmic Microwave Background(CMB)を初めて観測する。その後、1989年にNASAによって打ち上げられた宇宙背景放射探査衛星Cosmic Background Explorer(COBE)が行った観測で、宇宙マイクロ波背景放射はほぼプランク分布と一致するものと判明した。これは、「宇宙晴れ上がり」以後の宇宙は、熱平衡状態にあること、また、その温度が全方向でほぼ一定であったことを意味した。
ドイツの物理学者マックス・プランクMax Planck(1858年-1947年)は、宇宙空間全体では、相互にエネルギーをやりとりする時間が経過しても、それぞれの熱力学状態が変化しないという(熱平衡)。また、放射場と熱平衡状態にある物体が放出する電磁波を黒体放射と呼ぶが、その放射エネルギー密度分布(その放射輝度radianceの分布を表す法則プランク分布)は、宇宙の等方性を証明するものであった。さらに、約10万分の1の大きさの温度の揺らぎがあることも明らかになりなった。この温度の揺らぎが、後の宇宙を創造する種となり、密度の揺らぎの存在を裏付けるものとなった。
(1905年、アインシュタインが特殊相対性理論を発表した。プランクは、当時無名だったアインシュタインの論文をいち早く評価し、同年から翌1906年にかけてのゼミナールで、この理論を検証して相対性理論を擁護し、この理論が科学者の間に伝播する契機となった。
プランクは、1913年、アインシュタインをベルリンで研究させるため、後年1920年に熱力学第三法則の功績によりノーベル化学賞を受賞するヴァルター・ネルンストと一緒にチューリッヒを訪れた。プランクらは、新しく設立されたカイザー・ヴィルヘルム物理学研究所の研究主任や、ベルリン大学での講義の義務が無い研究職といった地位までも用意してアインシュタインを招聘し、その承諾を得ることに成功した。
1921年、アインシュタインは、「光量子仮説に基づく光電効果の理論的解明」によってノーベル物理学賞を受賞した。)
マイクロ波帯域の宇宙背景放射は、宇宙開闢の1つの名残である。LHC加速器の内部には、長さ15mの超伝導双極電磁石が連なっている。宇宙赤外線背景放射は、ビッグバン後にに形成された星や銀河によるものと考えられている。宇宙X線背景放射の方は、遠方の銀河の中心にある活動銀河核によるものと考えられている。これらはいずれも宇宙初期の天体や銀河形成の軌跡や、宇宙年齢や背景放射の起源を探る重要な研究となっている。
銀河の中心で激しく活動している天体があり、このような天体を「活動銀河核」と呼んでいる。その中心には、太陽の何百万倍以上もの質量がありながら、光を発しないため天体望遠鏡では観測できない大規模な天体がある。それがブラックホールである。その周りではいろいろな重要な物理現象が起きているが観測しずらい天体である。しかしなぜ、銀河の中心に存在するのか?
ブラックホールでは、100万光年以上の長大な高エネルギーのジェットが噴出している。このジェッの正体や、その一方では、ガスや塵などの物質が回転しながらブラックホールに吸い込まれて行く。その正体は、円盤状のもの(降着円盤)として、ブラックホール周辺で観測されている。しかしながら構造自体は不明である。
シンクロトロン光
Synchrotronとは、「荷電粒子の加速装置の一種」で、十分に速く走る電子が方向を変えるとき、エネルギーを放出する。その放出されるエネルギーがX線波長である。シンクロトロンはその非常に強力なX線源となり、そのX線は、シンクロトロンの周りを循環する高エネルギー電子によって生成される。
現在では、電子や陽子など電気を帯びた粒子を電場や磁場を用いて加速・制御し、高速で高い運動エネルギーを持った粒子を発生させるため、電子を80億電子ボルトeV(速度は光の速度の99.9999998%に相当)にまで加速し、これを蓄積リングと称する周長約1.5kmの装置に導き放射光synchrotron radiationを発生させている。
(ギガエレクトロンボルトGeVは、109eV、高エネルギー物理学や放射線治療において、加速器から照射される光子や電子、原子などの荷電粒子のエネルギーの大きさを表すのに用いられる。例えば、可視光線域での光子1個のエネルギーは数eVで、波長620 nmの赤い光の光子1個のエネルギーは2 eVである。)
シンクロトロン光 Synchrotron Lightとは、電子加速蓄積リングと呼ばれる加速器particle acceleratorを用いて、真空中で光速に近い速度で直進する電子を、磁石によって進行方向を曲げた時に発生する、細く強力な電磁波である「放射光」のことである。また、シンクロトロン光は、電子の進行方向の変化の大きさによって、分光装置で必要に応じた光を選択できるため様々な波長の電磁波を取り出す。赤外線から硬 X 線までの広い波長領域をカバーすることができる。しかも、エネルギーが高いため、同じ X 線と比較しても、その明るさは、医療用のレントゲンや CT 装置といった従来の装置から発生する X 線に比べて 10000 倍以上も明るくなる。
「SPring-8」では、この放射光を使い、ナノテクノロジーやバイオテクノロジー、その他の産業利用まで幅広い研究が行われている。「SPring-8」の名前はSuper Photon ring-8 GeV(80億電子ボルト)に由来する。
サイクロトロンでは、一様な磁場を発生させる電磁石とその磁場の中に入れられた加速電極から構成される装置である。さらに高いエネルギーを得るためには、加速用の高周波電場を作る周波数も磁場も一定であるため、粒子の軌道半径を何倍も大きくしなければならない。
そうしたとき、従来のサイクロトロンでは、粒子軌道がらせん状であるため、巨大な磁石が必要となる。これを避けるために、円形軌道の半径を大きくし一定にするかわりに、粒子が加速されるとともに、磁場を強くして行く方式がとられた。これがシンクロトロンである。
大型のシンクロトロンは、加速粒子を円形軌道に乗せるための多数の偏向電磁石と粒子を加速するための電極に相当する高周波加速空洞から構成されている。
加速粒子をイオン源からビームとして取出し、線形加速器を使って、あるエネルギーにまで加速した後、円形軌道に打ち込む。このとき、円形軌道上の偏向電磁石の磁場の強さは、最小にする。ビーム粒子は、円形軌道を周回するたびに、加速空洞を通過し、その度に、加速されエネルギーが増加していく。それに合わせて、磁場も増加させ、同じ円軌道を周回するように調整する。そして、最高エネルギーに達した時、円形軌道から離脱させ、その外部でビームとして取り出す。
ブースターbooster(増幅器)シンクロトロンは、円軌道の半径を大きくすることで、より高いエネルギーにまで粒子を加速することができる。しかし、一つの円軌道のシンクロトロンでは到達エネルギーに限界がある。そこで、何段かの線型加速器で、次々とエネルギーを上げる、ブースターシンクロトロンと蓄積リングから構成され世界最大の放射光施設が造られた。「SPring-8」は線型加速器、ブースターシンクロトロンそして蓄積リングの3つの加速器施設から成る。
1997年初頭、蓄積リングに電子ビームが入射された。その後順調に電子ビームが蓄積され同年1997年10月から放射光利用が開始され、非常に安定な蓄積リングとして今日までに多くの利用者が実験を実施し、多くの成果が発表されている。
兵庫県の「SPring-8」は、電子を光速の99.9999998%まで加速することができる。この電子の進行方向を電磁気の力で曲げると、持っていた運動エネルギーの一部が放射光として放射される。この光の波長は非常に短い「X線」で、強さは太陽の100億倍に相当する。
光でものを見る時、どれだけ細かいものが見られるかは、光の波長で決まる。可視光の波長は360~830㎚(ナノメートル; 10-9m)ほどであるため、髪の毛は見えても、10µm以下の細胞・ウイルス・タンパク質・原子など、到底、見ることはできない。ただそれも、可視光よりも1000倍ほど波長の短いX線であれば、100pm(ピコメートル; 10-12m)の原子の1つ1つまでも見分けられる。
可視光を使う光学顕微鏡では、100㎚あたりのウイルスはもとよりタンパク質や原子も観察はできない。一方、X線の波長は、1 pmから10㎚であるので、原子を見分けることもできる。
一般に単色光の強さや明るさは、光の波としての振幅(波長は、電磁波の1振動の長さと定義され、周期の長さとも呼ばれる。メートルmの単位で表される。振動の強さ、または高さを振幅と呼ぶ)の2乗に比例する。「SPring-8」は、太陽の100億倍の明るさに相当する光を作り出す。電子は外から磁力をかけられると進行方向が曲がる。その際に放射光を発する。電子が加速されて光速に近くなると、相対論的効果によって、放射される光の領域が非常に狭くなり、非常に明るい光となる。
放射光Synchrotron Radiationとは、相対論的な荷電粒子(電子や陽電子・イオン)が磁場で曲げられるとき、その進行方向に放射される光(電磁波)である。放射光は明るく、指向性が高く、また光の偏光特性を自由に変えられるなどの優れた特徴を持っている。
「SPring-8」は、電子以外の陽子・重イオンの加速にも用いられる。 荷電粒子のエネルギーに応じて磁場を強くすることで、粒子に半径一定の円軌道をとらせ、その回転周期に同期した高周波加速電場を加えて粒子を更に加速させる。
従来の線源に比べ10000 倍以上の明るい光を発生させることができるため、従来では見えなかったものが見えるようになる。ナノ秒 (10億分の1 秒) 単位の短い時間間隔で、次々と放出される光であるため、時間とともに変化する現象を研究することが可能となり、試料の分析に要する時間が大幅に短縮された。
シンクロトロン光を物質に照射すると、シンクロトロン光の一部が吸収され、物質表面から電子や X 線が放出されたり、シンクロトロン光自身が物質により散乱や回折されたりするなど、様々な現象が起こる。物質表面から放出される電子を光電子、X線を蛍光 X 線と呼んでいる。
SPring-8の放射光を用いると、物質の構造や働き、材料の組成をナノの世界の原子レベルで観察・計測・解析できることから、広く学術分野や産業分野での研究開発のために利用されている。SPring-8でも素粒子の研究を目的としたビームラインがある。大阪大学が整備したレーザー電子光ビームラインでは、紫外線のレーザーをSPring-8の加速電子に正面衝突させて跳ね返ってくる極めてエネルギーが高く、波長の短いガンマ線を使い、主にクオークの研究を行っている。
一方、大型ハドロン衝突型加速器LHC(Large Hadron Colliderの略称)は、陽子を加速し、正面衝突させることによって、その時に起こる現象を調べることができる施設である。この施設では、「ヒッグス粒子」の発見など、素粒子研究で成果を挙げている。
大型ハドロンコライダー
Large Hadron Collider(LHC)とSPring-8は、どちらも加速器を使った施設であるが、加速する粒子も、施設の利用目的も異なる。LHCは、CERN(セルン)が建設した世界最大の大型ハドロン衝突型加速器である(Collider;衝突型加速器)。CERN という名称は、本機構の開設準備のために設けられた組織のフランス語名称であるConseil Européen pour la Recherche Nucléaire (欧州原子核研究機構)の頭字語である。
LHCの建設には日本も貢献している。CERNはメンバー国の共同出資で運営されているが、1995年日本政府とCERNの間で協定が交わされ、オブザーバ国として、LHC建設に日本は138億円出資している。
LHCは、スイスとフランスの国境を跨ぐ周長27 kmにも及ぶ地下100mに設置された巨大な装置である。遠方にレマン湖やジュネーブ市街が眺められ、その先にはモンブランをはじめとするアルプスの山々が見える。1994年に計画が承認され、地下約100mの環状トンネルに、15年以上かけて建設され、2010年春から本格的に始動した。LHC加速器の内部には、長さ15mの超伝導双極電磁石が連なっている。
それらの超伝導電磁石は、超伝導状態で動作する特殊な電気ケーブルのコイルで構築され、抵抗やエネルギーの損失なしに完全に電気を伝導している。これら磁石は、宇宙空間より寒い温度-271.3°Cに冷却する必要がある。このため、加速器の多くは、磁石を冷却する液体ヘリウムの流通システムや他の供給サービスと接続・管理されている。
この周上4か所に巨大な検出器が設置され、素粒子反応の観測など高エネルギー物理実験が行われている。
2010年3月39日には、陽子同士を衝突させて、電子より約1,800倍重い陽子を7兆電子ボルト(速度は光速の99.9999999997%に相当)にまで加速するほどの能力に達成し、研究者は祝杯をあげて祝っている。早くも、2012年7月には、ヒッグス粒子の発見に成功した。
2021年7月26日から開催された欧州物理学会の「高エネルギー物理に関するオンライン会議」では、2個のチャームクォークおよび反アップクォークと反ダウンクォークから構成される異種のハドロン粒子の発見など、研究成果が報告されている。
強い相互作用
強い相互作用は、電磁相互作用・弱い相互作用・重力相互作用と並んで、宇宙に存在する4種の基本相互作用の一つである。原子核内の核子である陽子や中性子を束縛する極めて短い距離で働く「強い力strong force」である。それはクォークとグルーオンの間で最も強力に作用している。強い力を媒介する力の素粒子グルーオンは、8種類あり、そのグルーオン粒子の交換によって作用する。 光子や重力と同様、グルーオン粒子いずれもが質量を持たないはずなのに、短い距離しか伝わらないが、原子核内であれば電磁気力の100倍程の強さで作用するので、この名前がつけられた。
グルーオンは、クォークを結びつけ、陽子や中性子を作り、また陽子同士が電気的に反発する斥力に勝る強い力で、中性子とともに100種類以上原子核を構成する。
(質量が陽子の約90倍と非常に大きいウイークボソンは、β崩壊やπ中間子の崩壊などを引き起こすが、素粒子間の弱い相互作用を媒介する粒子である。正・負のWボソンと中性のZボソンの3種がある。
β崩壊とは、原子核中の中性子が電子と反電子ニュートリノを放出して陽子に変わるβ-崩壊、陽子が陽電子と電子ニュートリノを放出して中性子になるβ+崩壊、陽子が原子軌道上の電子を捕獲して中性子に変わり、その際、電子ニュートリノと特性X線を放つ軌道電子を捕獲するなどが主な作用である。)
陽子proton は、その個数によってあらゆるを原子の種類を定めており、中性子や電子とともに、物質を形作る最も中核となる基本粒子である。その内部ではクォーク・反クォーク・グルーオンと言う素粒子(パートン)が核子を作る。
これら素粒子が陽子の要素、つまり「パートpart」であるから、核子の構成要素の粒子と言う意味で「パートンparton」と呼ばれた。
原子の中心にある正の電荷をもつ粒子は、陽子と呼ばれる。しかし、その陽子は部分的に反物質でもあることが知られている。 クオークは、物質を構成する素粒子であるため、反クォークは反粒子となる。また、グルーオンは、強い相互作用を媒介する粒子である。
強い相互作用は、クオークのフレーバーflavor(種類)に関わらず、等しく働くと考えられている。例えば、陽子のグルーオンによりクオークと反クオークが対生成する過程では、アップクオークの対と、ダウンクオークの対が生成する確率は、ほぼ等しいと考えられていた。これを「フレバー対称性」と呼ぶ。
(同じ数の陽子を持つ、つまり同じ原子番号の原子atomsが、同じ元素chemical elementsとなる。元素は、地球上では118種の存在が確定している。
異なる数の陽子を持つ原子は異なる元素であるが、質量数235のウラン【U235】と238のウラン【U238】のように、質量数が違っても陽子の数が同じであれば、ウランの同位体であり、つまり原子番号92番で括られる同じ元素である【放射性同位元素】。 U-235は、核内に92個の陽子と143個の中性子があり、U-238は、核内に92個の陽子と146個の中性子がある。元素は、ある特定の原子番号をもつ原子によって代表される。
同じ元素でも中性子の数が異なる場合
例えば、①水素原子の殆どの原子核は、陽子1個だけである(軽水素とも呼ばれる;1H)。中性子は存在していない。
②中性子の数が1個のもの(重水素; 2H )。
③中性子の数が2個のもの(三重水素またはトリチウムと呼ばれる;3H)。
これら①~③はどれも同じ水素原子であり、性質は変わらない。②と③は水素の安定同位体と呼ばれ質量は少しずつ大きくなる。このように陽子の数は同じで、同じ元素に属しながら、中性子の数の違いで質量数が異なる原子を、互いに同位体isotopeと呼ぶ。名称の由来はギリシア語のisos(同じ)とtopos(場所)からきている。同位体には水素のように安定したものと、ウランの不安定なもの(放射性同位体)があ る。原子はこのように1個1個の粒なので、本来は中性子の数が異なれば区別する必要がある。
元素は、原子の種類を表す用語である。元素名が同一でも、まったく同じ粒なのかと言われると違うこともある。地球上の水素全体における、それぞれの存在割合は、軽水素が99.985%、二重水素が0.015%、三重水素にいたってはごく僅かである。
同一種類の元素で出来ているのに原子数が異な る物質オゾンO3と酸素O2は、同素体と呼ばれる。
元素を原子番号順に並べると、化学的な性質が似ている元素が繰り返しあらわれる。似た性質を持つ元素が縦の列に並ぶように元素を配置した表が周期表periodic tableである。例えば、周期表1(ⅠA)族の、水素を除くリチウム・ナトリウム・カリウム・ルビジウム・セシウム・フランシウムの6元素はアルカリ金属元素と総称される。いずれも価電子を1つ持ち、典型元素の単体においては周期が小さいほど共有結合性が強く、周期が大きいほど強い結合力が発生する金属結合性が強くなる傾向がある【金属は展性や延性が高い】。このため反応性が高く、簡単に酸化されるため、天然には単体として存在しない。)
かつて、陽子はクォークquarkと呼ばれる3つの素粒子でできているように見え、陽子の中にあるクオークの殆どが「アップ」と「ダウン」であるかのように‥‥。そのうちの2つが「アップu-」クォーク、1が「ダウンd-」クォークで、それらの電荷は、「アップ」2個でプラス3分の2と、「ダウン」1個でマイナス3分の1が組み合わさって、陽子はプラス1の電荷を持っている。つまり、陽子内では、u-quarkが正偏極で、 d-quarkが負偏極である、と考えられている。
実際には、陽子の内部では数が変動する6種類のクォークと、それらと反対の電荷を担う反物質(反クォーク)、さらには「グルーオン」と呼ばれる粒子がかなりの数で渦巻いている。
遠くから眺めると、陽子はクォークと呼ばれる3つの粒子からできているように見えるが、陽子の中では常にクォークの総数が変動し続けていると考えられている。つまり、3個のクォークとは別のクォークが、陽子内部で、強い相互作用を媒介するグルーオンにより、間断なくクォークと反クォーク対生成されては対消滅していると考えられている。その状況から、反クォークの存在量を測定することができれば、陽子の中で極めて短い時間で変化し続ける様子をとらえることができると期待されている。
粒子の海が現れたり消えたりする。これが30年前(1990年以降)に発見された、「陽子の海proton sea」の驚くべき特徴である。
「陽子の海」は、物理学者が未だ解明出来ずにいる、6種類の「Up」・「Down」・「Top」・「Botton」・「Charm」・「Strong」がそれぞれ数多くのクオークと反クオークがペアとなって陽子の海に渦巻いている。その一方、あらゆる粒子と結合できるグルーオンは、ほかの粒子と結びつき、グルーオンに変形させている。グルーオンは、常にその機会を狙い、その多くは海の中に漂っている。
そのグルーオンの強い相互作用は、クォークのフレーバーに関わらず、いずれにも等しく働くと考えられており、そのことが「フレーバー対称性」と呼ばれている。たとえば陽子の中でクォークと反クォークが対生成する過程においては、アップの対とダウンの対が生成する確率は等しくなるという。ダウンの方がアップのほぼ倍の質量があるため、厳密にはほんの極わずかだが生成確率が異なるものの、両者の質量自体が極めて小さく、その差は微小でもあり、等しいとされても影響は小さいとみられていた。
その「フレーバー対称性の破れ」が確認された。
物理学者たちは20年前、陽子の海に存在するミステリアスな「非対称性」を発見して以来、反物質にあらためて注目した。
研究者たちはこの「陽子の海」がもつ驚くべき特徴を発見した。理論上は異なるタイプの反物質が均等に分布していると考えられていたが、実際には反ダウンクォークの数が反アップクォークの数を大きく上回っていたのだ。それから10年後に、別の研究グループが、反クォーク比が不思議とダウングオーク側に優勢に傾く理由のヒントを見つける。しかし従来の実験方法の性能では、それ以上の成果は挙げられなかった。
グルーオンには、ほかの粒子と結びつき、グルーオンに変形させ、その数を難なく増やす能力がある。ところがどういうわけか、あまたの粒子からなるこの「陽子の海」の大渦は完全に安定していて、表面的にはあたかもそこに3つのクォークだけが並んでいるだけの、とても単純な形に思えた。
なぜそれが可能なのか、イリノイ州アルゴンヌ国立研究所で核物理学を研究していたドナルド・ジーサマンが観測を開始した。それで20年前、ジーサマンと彼の同僚であるポール・リーマーが新しい実験を始めた。その研究は「シークエストSea Quest」と名付けられた。
陽子の内部では、グルーオンの放射からクオーク・反クオークの対生成が間断なく起きている。そのクオークと反クオークの様子は、海になぞらえて「海クオークsea quark」と呼ばれた。「Sea Quest」とは、反クオークを含むSeaを探索Questするという意味である。その実験がついに終わったとき、その結果を『ネイチャー』で発表した。彼らはかつてなかったほどに陽子内の反物質を詳細に測り、1つの反アップクォークにつき平均して1.4個の反ダウンクォークがある事実を突き止めた。
バリオン陽子の質量・半径・スピンなどの基本的な性質は測定されているが、しかし、そうした様々な性質が、どの素粒子からどのような作用で働いているかは未だ判明していない。ただ、極小な時間の尺度で観測すると、その内部構造は、強い相互作用として働くグルーオンの放射やクォーク・反クォークの対生成による複合体となっている。
特に陽子の中の反クォークは、物質中の反物質粒子であるため、クォークと反クォークの対として短時間で生成し、即時に消滅する。それで、反クォークの存在量を測定することにより、陽子の中で短時間に変化していく様子を捉えようとした。
陽子の中の素粒子パートンは、高速で運動しており、様々な大きさの運動量を持つ。陽子全体の運動量に対する 比=【パートンの運動量】 /【 陽子の運動量】 を使って、パートンの状態を予想する。この比率を、提唱者の名をとって「ブヨルケンのスケーリング変数」と呼ぶ。
海クオークの運動量の大きい領域では、反ダウンクオークは、反アップクオークより50%も多く陽子の中に存在するが、その仕組みの解明にまで至らなかった。
東京工業大学 理学院 物理学系の中野健一助教、柴田利明名誉教授(日本大学特任教授)、山形大学学術研究院の宮地義之教授、理化学研究所 仁科加速器科学研究センターの後藤雄二先任研究員、高エネルギー加速器研究機構(KEK) 素粒子原子核研究所の澤田真也教授らは、陽子の内部において、反クォークの運動量が大きい領域でそのフレーバー対称性が大きく破られていることを、陽子ビーム実験によって明らかにした。
本研究では、米国フェルミ国立加速器研究所FNALでの日本・アメリカ合衆国・台湾の研究チームによる国際共同実験(SeaQuest実験)によって陽子の中の反クォークのフレーバー対称性を検証した。
(KEKは大学共同利用機関法人として、加速器科学の最先端の研究や、関連分野の研究を発展させる目的で、国内外の研究者のために高エネルギー加速器の共同利用の場を提供している。自然界に働く法則や物質の基本構造を探求するために素粒子や原子核に関して、また、生命体を含む物質の構造や機能に関して実験的研究や、理論的研究を推進している。)
その結果、反クォークの運動量が大きい領域では、反ダウンクォークが反アップクォークより50%も多く存在し、フレーバー対称性が破れていることを突き止めた。この結果は、陽子の中に、「フレーバー対称性を大きく破る」何らかの仕組みがある、それを探究することにあった。
その成果は、英国時間2021年2月24日公開の学術誌「Nature」に掲載された。
アメリカ合衆国のFNALにおいて日本・アメリカ合衆国・台湾の研究者の国際共同実験(実験名称 SeaQuest)を実施した。この実験では、FNALによる高エネルギーの大強度の陽子ビームを液体水素の陽子と液体重水素の重陽子(三重水素の原子核、陽子1個と中性子の2個の核子で構成されている)を標的に照射し、標的中の陽子と中性子で起こるドレル・ヤン反応Drell–Yan processを測定した。
陽子-中性子の Drell–Yan processの終状態のミューオン(6種類のレプトンの1つ)対を測定することにより、大きな範囲で陽子中の反クォーク分布のフレーバー非対称度を観測することを目的としている。フレーバー非対称度は、陽子のパートン構造の解明に 役立つほか、強い相互作用を示す非摂動論的な性質の研究にも用いることができる。
レプトンleptonは、弱い相互作用や電磁相互作用をする素粒子である。バリオンに対して、質量が軽いことから軽粒子と呼ばれる。それらは電子、ミューオン、タウとそれと対をなす電子ニュートリノ、ミューオン・ニュートリノとタウ・ニュートリノ6粒子とそれらの反粒子が知られている。
ミューオンは20世紀の初頭に宇宙線の中で発見された。クォークは単独で取りだした形では見つかっていないが、その存在は、加速された高エネルギーのレプトンで陽子を激しくたたく非弾性散乱実験(原子・イオン・電子などの荷電粒子が、入射する時にエネルギーの移動が生じ、周波数が変化する反応を非弾性散乱と言う。)により、陽子の中に存在する点状粒子(パートン)として確認されている。
FNALの研究者たちは、2021年4月7日のセミナーで、2018年に始まった「ミューオンg-2実験」の最初の結果を発表した。この実験ではミューオンという素粒子を測定している。ミューオンは1930年代に発見された電子の仲間の素粒子で、電子よりも重い。
(摂動perturbationとは、物理学や天文学では、主要部分は正確に解けているが、これに小さい付加項が加わわると全体の問題が正確には解けない現象が生じる。それは他の副次的な力の撹乱(摂動項)によって乱されたとみる。この場合、主要部分に付加項による小さい補正が加わったとして、全体的な観点からを近似的に解き、その付加項を摂動といい、その解法を摂動論と呼ぶ。
量子力学では、解の求められている運動をする系に、さらに想定外の比較的小さな力が作用した場合、わずかに変化が生じたと見なす。その小さな力の作用を摂動という。)
その計数の比から、反アップクォークと反ダウンクォークの存在量の比(=d /u )を抽出した。このd /u が 1 ならば反アップクォークと反ダウンクォークの存在量がフレーバー対称であることを意味する。 このSeaQuest実験では、反クォークの運動量の大きい領域までd /u を測定した。その結果、運動量が大きい領域では反ダウンクォークが反アップクォークより50%も多く存在しており、全測定領域においても反クォークのフレーバー対称性が大きく破れていることがわかった。
これは、陽子の全領域に、フレーバー対称性を大きく破るこれまでに明らかになっていない、何らかの仕組みの存在をうかがわせる。以後の観測に大きな期待が寄せられている。
目次へ